
さらなる DX 推進に向けた、アクティオの Google 活用法とはアクティオの Google Workspace 導入事例
株式会社アクティオホールディングス様
記事を見る
網走市役所

北海道北東部に位置する網走市は、オホーツク海の流氷や雄大な自然、網走監獄で知られる観光都市です。古くから水産業や農業が盛んで、スポーツ合宿地としても注目を集めています。
人口減少という課題を抱える一方で、市民・団体・行政が一体となり、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進。2025年2月の新庁舎への移転を機に、スマートワークによる働きやすい環境づくりを目的として、Google Workspace と Chromebook を導入しました。さらに、デジタルサイネージを使った市民向けの情報発信も始めました。
課題


対策


効果
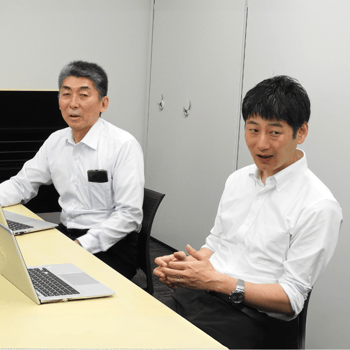
コロナ禍を経て働き方が変化する中、網走市では従来の働き方が続いていました。「社会とのギャップが広がっただけでなく、業務効率化を阻むさまざまな課題があった」とDXを担当する山縣氏は話します。
例えば、網走市では「α(アルファ)モデル」(*1)による三層分離を採用していたため、外部データを取り込む際の無害化処理に手間と時間がかかっていました。また、全端末が有線接続だったため、自席以外での作業が困難でした。さらに、職員間でスケジュール管理ツールが統一されていないことにより、日程調整に手間がかかるという課題もありました。
「臨時で会議を開きたくても、参加者のスケジュール調整に時間がかかってしまい、開催が翌々週になることもありました。その結果、迅速な意思決定ができない場面も多くありました」(小松氏)
こうした中、転機となったのが新庁舎の建設です。移転の決定をきっかけに、若手職員を中心としたICT研究グループが立ち上がり、『利便性・効率性・省力化・次世代育成』をキーワードに、場所にとらわれない働き方の検証がスタートしました。
「また別のDX研究グループに参加していた外部の有識者から、Google Workspace と Chromebook の導入が提案されました。まずは実証実験として、2022年7月からグループのメンバーと外出の多い観光課を対象に、あわせて16ライセンスで利用がスタートしました」(山縣氏)
(*1) セキュリティ対策として、自治体のネットワークを「マイナンバー利用事務系」「LGWAN接続系」「インターネット接続系」の3つに分離するモデル
すでに市内の小中学校では、GIGAスクール構想のもとで Google Workspace for Education が導入されており、庁内でも Google Workspace に対する一定の知見がありました。
「 Google 製品は政府のセキュリティ評価制度であるISMAPに登録されており、信頼があります。当市としても、インターネット接続後、クラウド上のセキュリティは Google に任せられる点が大きな魅力でした」(小松氏)
「一時期、出向先で他社のクラウド製品を使っていたことがありますが、普段使っているものと大差ないという印象があり、働き方が変わるイメージが掴めませんでした。その点、Google Workspace には、Google カレンダーやチャットといったクラウドネイティブなコラボレーションツールが備わっており、導入を決断する後押しとなりました」(山縣氏)
導入にあたっては、電算システムによるサポートも高く評価されました。
「私たちが実現したいシステム要件を伝えると、すぐに技術的な実現方式について的確な回答が返ってきます。通信技術に関する知見も豊富で、非常に心強い存在でした」(小松氏)

2024年1月末に全職員に Chromebook を配布、全庁展開にあたっては、2月に全職員440名に対し、習熟度別に「基礎編」「中級編」「管理職編」の3講座を10回に分けて実施し、4ヶ月の検証期間を経て、6月からポータルを開設して正式に Google Workspace をグループウェアとして切り替え2025年2月には新庁舎への移転を完了しています。
「研修の様子やアプリケーションの使い方動画を、Google サイトで作ったポータルサイトからいつでも視聴できるようにしています。これにより、わからないことがあっても自分で学べる環境を整備。新人職員も、初期設定マニュアルを見ながら自ら設定を進められるようになりました」(山縣氏)
導入後は、電子決裁などの基本業務も Google Workspace 上で行うようにし、新しい働き方の定着を図っています。また、職員向けに専用チャットスペースを設け、質問に答えられるフォロー体制も整えています。
「一人の質問に回答することで、全員がそのやりとりを共有できるため、同様の質問が繰り返されにくくなり、非常に効率的です」(山縣氏)
導入後の効果について、定量的な評価は難しいものの、現場では確かな手応えがあるといいます。
「導入後、紙の使用量は約3割削減できました。印刷・編纂・廃棄にかかる時間も減り、業務効率が向上しました。会議時も Google カレンダーで資料を共有し、皆が Chromebook を持参するようになり、働き方の変化を実感しています」(小松氏)
「内線電話に代わり、チャットが主流になりました。チャットは、相手の作業を中断させることなく、都合の良いタイミングで返信できるため、不在時でも内容が残り便利です。イベントの出欠確認は、紙から共有ファイルへの移行で、記入後の回収・集計の手間がなくなり、スピーディーな運用ができています。さらに、共用の車両や備品などの予約も Google カレンダーでリアルタイムに確認・予約でき、無駄な調整が減り、稼働効率が向上しました」(山縣氏)
一方で、すべての業務が完全に Google Workspace に移行されたわけではありません。過去の資料を参照する場面などでは従来のソフトウェアが必要になることもあるため、引き続き併用できる環境を整備しています。
今後の展望について、山縣氏は次のように語ります。
「最終的な目的は、職員の『スキマ時間』をつくり、その時間を活用して新しいアイデアを生み出してもらうことです。そのためにも、Google Workspace with Gemini の活用は重要だと考えています。現時点では、全職員の約85%が何らかの形で Google Workspace with Gemini を利用しています。資料を要約したり、サイドパネルで簡単な問いかけをする程度ですが、それでも業務の効率化に貢献しており、働き方の改善につながると期待しています」(山縣氏)
小松氏は他自治体へのアドバイスとして『段階的な導入の重要性』を強調します。
「導入は、一気に進めるのではなく、段階を踏み、進めるべきです。新たな手法が確立されない場合は、既存のやり方を担保することも大切で、職場のストレスにも配慮が必要です。
また、導入前後の予期せぬ事態に備え、アジャイルを基本とした柔軟な方針見直しが不可欠です。『三層分離』からどのように移行するのか制約があり難しいと思いますが、どの方式であれば実現できるかを、前向きに検討してみるとよいと思います」(小松氏)
さらに、小松氏は、AIの活用がもたらす可能性について次のように展望を語ります。
「AIの業務導入は働き方の『パラダイムシフト』となります。クラウドにデータがあるからこそ、Google Workspace with Gemini のようなツールが活用できます。当市では今年度からAI活用の研究を始めていますが、最終的には市民と職員のウェルビーイング向上にもつながるものと期待しています」(小松氏)


さらなる DX 推進に向けた、アクティオの Google 活用法とはアクティオの Google Workspace 導入事例
記事を見る

10 年前から Google へ。エイベックスがスムーズにテレワークへ移行できた理由
記事を見る

社内プラットフォームを G Suite™ に刷新!Google 製品を軸にしたリモートワークの課題解決と社内業務の効率化を実現
記事を見る


Google Workspace , Google Workspace with Gemini , Gemini Enterprise , Google Meet , Appsheet , Notebook LM , Google Cloud , Google Cloud Platform, Chrome , Chrome Enterprise , Chrome OS , Chromebook , Google Maps , Google Meet ハードウェア, Google for Education , Google Workspace for Education , Google Classroom , および Google ドライブ は Google LLC の商標です。