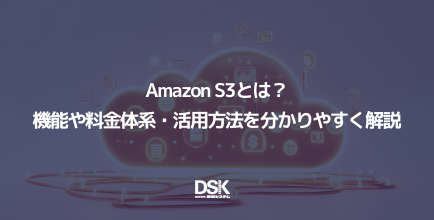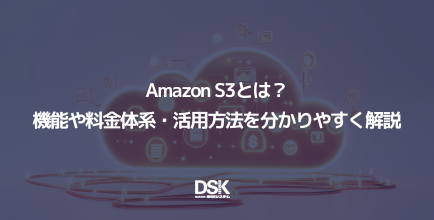ビッグデータを管理するには、データ分析基盤の整備が欠かせません。データの保管が不十分だと、運用負担が増し、情報管理のリスクも高まります。
本記事では、データ分析の基盤となるデータウェアハウス、データマート、データレイクの違いをわかりやすく解説します。
それぞれの目的や活用例、選び方を紹介し、導入時の注意点についても説明します。データ管理の方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
データレイク・データウェアハウス・データマートの概要と特徴
データ分析の基盤は、構成方法により以下の3種類に分けられます。
- データレイク
- データウェアハウス
- データマート
それぞれ保存するデータの種類や活用法が異なるため、目的に応じた使い分けが必要です。
あらゆるデータを保存できるデータレイク
データレイクは、未加工のデータをそのまま保存できる仕組みで、用途が決まっていない生データを保管できる点が特徴です。
データの種類を問わず、画像・動画・テキスト・ログデータなどの非構造化データに加え、Webサービスやアプリで使われるJSONや、文書管理で利用されるXMLのような半構造化データも保存できます。
蓄積したデータは、必要に応じて抽出・加工・分析が可能で、大規模なデータ環境に適した設計になっています。
ビジネス分析に特化したデータウェアハウス
データウェアハウスは、構造化データを集約・整理して保存する仕組みで、ビジネス向けのデータ分析に適している点が特徴です。
データレイクに保存された未加工のデータとは異なり、データウェアハウスでは「受注」「出荷」「配送」といったテーマごとにデータが整理されているため、分析を効率的に行えます。
蓄積されたデータは、集計や分析の処理を最適化した形で管理されており、大量のデータ処理や複雑なクエリにも対応可能です。ビジネスの意思決定を支援するデータ環境として設計されています。
特定部門に最適化されたデータマート
データマートは、特定の部門や用途に最適化されたデータを保存する仕組みです。部門ごとの分析ニーズに対応し、マーケティングや営業などの部門では、限られたリソースで効果的なデータ分析が可能となります。業務ごとに必要なデータを迅速に活用できる点が特徴です。
比較的低コストで導入でき、構築にかかる時間も短縮できます。さらに、シンプルな構造を持つため、導入が容易であり、データの追加や変更にも柔軟に対応できるのが利点です。特定の業務ニーズに応じたデータ環境として、業務の効率化を促進します。
データレイク・データウェアハウス・データマートの違い
「データレイク」「データウェアハウス」「データマート」の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | データレイク | データウェアハウス | データマート |
| 利用目的 | あらゆるデータを蓄積し、後から分析可能 | ビジネス分析のために整理されたデータを保存 | 特定の部門向けに最適化されたデータを提供 |
| 保存方法 | 未加工のデータをそのまま保存 | 構造化されたデータを整理して保存 | データウェアハウスの一部を抽出・加工して保存 |
| 対象ユーザー | データを扱う専門職(データ分析担当者、エンジニアなど) | 意思決定を行う立場の人(経営者、ビジネス分析担当者など) | 各部門の実務担当者(部門責任者、マーケティング担当者など) |
| コストと管理負担 | 低コストで大量データを保存できるが、管理・活用には専門知識が必要 | 費用は高めだが、データの検索や活用が容易 | 比較的低コストで導入可能 |
利用目的の違い
- データレイク
収集時点で特定の目的がなくても、後から新たな活用方法を見つけられる仕組みです。AIやビッグデータ解析など、大量の生データを必要とする用途に適しています。例えば、ECサイトの行動ログをすべて記録し、後から購買行動の分析に活用できます。また、SNSの投稿データを蓄積し、トレンドや感情の分析に応用することも可能です。
- データウェアハウス
ビジネス分析向けに整理されたデータを保存し、レポート作成やデータの推移を把握できます。営業、財務、人事など、企業全体で統一されたデータを使用することができ、売上データの統合や週次・月次の業績分析に役立ちます。
- データマート
部門ごとに特化したデータを保存し、マーケティング分析や営業戦略の立案に活用します。迅速な分析結果が求められる業務に適しており、広告効果の測定や購買データの分析などの利用が可能です。
データの保存方法と構造の違い
- データレイク
あらゆる種類のデータを加工せずに保存し、一元管理できます。拡張性が非常に高く、用途が決まっていないデータも保存できるため、長期的な活用に適しています。
- データウェアハウス
階層的な構造によってデータの整合性を保つ仕組みです。一定の拡張性はあるものの、事前に設計されたデータモデルに基づいているため、新しいデータを追加する際には調整が必要です。
- データマート
データウェアハウスの一部を抽出・加工し、部門ごとに最適化して保存するため、シンプルな構造を持っています。新しいデータソースを統合する場合、データウェアハウスの変更が必要になるなど、小規模なデータ環境には適しているものの、大規模な拡張には適していません。
対象ユーザーの違い
- データレイクの利用者:データの取り扱いに精通した専門家
主な対象ユーザー
- データサイエンティスト:機械学習モデルの開発や高度な分析を行う
- データエンジニア:データの収集・整理・前処理を行う
- システムエンジニア:データ基盤の設計やインフラ管理を担う
- データウェアハウスの利用者:意思決定を担う立場の人
主な対象ユーザー
- 経営者・役員:会社全体の売上や業績を分析し、経営戦略を決定する
- 財務・会計担当者:損益データや売上データをもとに財務分析を行う
- アナリスト:市場データや財務データを分析し、事業計画を策定する
- データマートの利用者:各部門の実務担当者
主な対象ユーザー
- マーケティング担当者:広告効果測定や顧客データ分析を行う
- 営業マネージャー:営業活動の成果を分析し、戦略を立案する
- カスタマーサポート担当者:顧客対応履歴を分析し、サービス改善を行う
コストと運用負担の違い
- データレイク
クラウドストレージを活用することで、データ容量に応じた従量課金で運用できます。比較的低コストで導入できますが、検索や活用には適切なデータ処理が必要です。また、データ分析時には大量の計算処理が発生し、分析用のクラウドサービスに追加コストが発生するケースがあります。
- データウェアハウス
データの整理や統合にかかる費用が高額になる傾向があります。しかし、データが整備されているため、検索や分析の手間が減り、運用後の負担は軽減されます。
- データマート
データウェアハウスの一部を活用するため、導入コストを抑えることが可能です。部門ごとに必要なデータのみを保存できるため、利用者は容易に情報へアクセスできます。ただし、各部門が独自のデータマートを増やしすぎると、データの整合性が損なわれる可能性があります。
データレイク・データウェアハウス・データマートの活用事例
データ管理の仕組みを理解し、活用することで業務改善につながります。ここでは、データレイク、データウェアハウス、データマートの活用事例を紹介します。
あらゆるデータを柔軟に活用できるデータレイク
データレイクは、センサーやIoTデバイスからの非構造化データをリアルタイムで収集し、予測分析に活用できます。例えば、製造業では、機器の稼働状況をリアルタイムで計測し、データレイクに蓄積します。データをAIが分析することで、設備の故障予測に役立てることが可能です。
また、動画配信サービスでは、ユーザーがどのタイミングで視聴をやめるのかを分析し、コンテンツの最適化やおすすめ機能の改善に活用されています。さらに、ログデータを解析することで、ユーザーの行動パターンを可視化し、パーソナライズ機能の強化やUX向上にも貢献します。
AIの開発には、多様なデータを大量に集め、正確で汎用性の高いモデルを構築することが不可欠です。データレイクは、機械学習のプラットフォームやフレームワークと連携し、AIモデルのトレーニングや展開を効果的に管理できます。
高速なデータ分析を実現するデータウェアハウス
データウェアハウスは、大量の売上データや在庫データの集約・分析に活用されます。
例えば、全国の店舗ごとの売上データを統合し、月ごとの売上推移を集計することで、「どの地域でどの商品が売れているのか」を把握できます。売上データをもとに各部門のパフォーマンスを視覚的に分析し、経営判断の材料として活用することも可能です。
また、在庫管理システムとの連携により、常に在庫状況を確認できます。欠品や過剰在庫を防ぐだけでなく、経営層に迅速に情報を提供し、適正在庫の維持や発注戦略の最適化にもつながります。
さらに、データウェアハウスはBI(ビジネスインテリジェンス)ツールと連携し、視覚的なダッシュボードを活用したデータ分析が可能です。グラフやヒートマップを使うことで、膨大なデータを直感的に理解しやすくなり、迅速な意思決定を支援します。
部門ごとの効率化を支えるデータマート
データマートは、各部門でデータを簡単に扱えるようにし、業務の効率化を促進します。
例えば、マーケティング部門では、キャンペーンごとの顧客反応データを蓄積し、次回の戦略立案に活用可能です。オンライン広告のクリック率や購入率を分析することで、「どの広告が最も効果があったか」を明確にし、次のキャンペーンに反映できます。
営業部門では、地域別の売上データを分析し、ターゲット顧客の選定に役立てられます。特定の地域の売上データをもとに、「このエリアではSUVがよく売れている」といった傾向を把握し、営業戦略の調整に活かせるでしょう。
また、データマートは新規事業の立ち上げにも適しています。例えば、新製品の市場調査を行う際、「特定の地域や特定の年齢層のデータだけを分析したい」といったニーズにも対応でき、スピーディーに情報を取得できます。
自社に合ったデータレイク・データウェアハウス・データマートの選び方
データを管理し、活用するためには、自社のニーズに合った方法を選ぶことが重要です。保存するデータの種類や企業の規模、目的によって、適した方法が異なります。
大量データを柔軟に活用するならデータレイク
データレイクは、将来的なデータ活用を検討している企業に適しています。特に、AIや機械学習を用いた高度な分析を予定している企業に向いているでしょう。
例えば、大規模なECサイトでは、ユーザーの閲覧履歴や購買データ、口コミのテキストなど、多様な情報が蓄積されます。これらのデータには、数値データだけでなく、画像や動画、ログデータといった非構造化データも含まれています。これらのデータにAIや機械学習を組み合わせることで、レコメンデーションやパーソナライズされた商品提案など、より精度の高いマーケティングが可能になります。この仕組みにより、離脱率の低下や売上の向上が期待できるでしょう。
また、データウェアハウスとの併用を検討する企業にも適しています。データウェアハウスは構造化データの整理や管理に特化しているのに対し、データレイクは未加工データをそのまま保存できる仕組みです。それぞれの特性を生かして統合的に活用することで、多角的なデータ分析が可能となります。
さらに、社内システムと連携すれば、業務の効率化も期待できます。手作業で行われていた業務を自動化し、業務負担を軽減できるでしょう。
高速な分析で意思決定を支えるならデータウェアハウス
データウェアハウスは、整理された大量のデータを活用し、意思決定を行う企業に適しています。継続的なデータ分析が求められるプロジェクトにも有効でしょう。
例えば、金融機関では、大量の取引データを迅速に分析する必要があります。不正利用の検知や顧客の利用傾向を把握し、リスク対策を講じる際に活用されています。このような信頼性の高いデータに基づいた分析が求められる企業には、データウェアハウスが最適です。
また、大量のデータを効率的に管理し、複雑な分析をスムーズかつ継続的に行えるため、マーケティングや販売管理の分野でも広く活用されています。特に、顧客データや売上データを活用した推移分析に適しており、意思決定の精度向上に役立つでしょう。
さらに、各部門のデータを一元管理することで、組織全体で統一された情報に基づく戦略立案が可能となるでしょう。
部門ごとのニーズに応えるならデータマート
データマートは、特定の部門やプロジェクト単位での分析ニーズに対応したい企業に適しています。コストを抑えながら柔軟にデータを活用したい中小企業にも向いているでしょう。
例えば、限られた予算の中で、部門ごとの売上分析を行いたい場合に有効です。データウェアハウスと比べて小規模な導入が可能であり、必要なデータのみを対象とするため、システム構築や運用の負担を最小限に抑えられます。
また、データ処理の負担軽減によって、分析にかかる時間を短縮でき、リアルタイムでのデータ活用がしやすくなります。さらに、不要なデータ処理を省くことで、システムの維持管理コストが削減されるだけでなく、クラウドサービスの活用でインフラ整備の負担も軽減できます。
データ管理に必要な人的リソースも最小限に抑えられるため、IT部門の専任担当がいない企業でも運用できるのは大きな利点です。
データレイク・データウェアハウス・データマート導入時の注意点
データ管理システムを導入する際は、管理の難易度や費用など、考慮すべき点があります。自社に適した運用を行うために、想定される課題と対応策を事前に把握しておきましょう。
データレイクは運用管理がポイント
データレイクは、適正な運用管理がポイントとなります。多様なデータを保存できる柔軟な仕組みですが、運用計画が不十分だと「データの沼」となり、十分に活用できなくなります。特に、複数の部署が無秩序にデータを追加すると、検索が困難になり、必要な情報を見つけるのに時間がかかります。
これを防ぐには、データの分類とラベル付けを徹底し、検索しやすくすることです。また、データを定期的に見直し、不要なものを削除することで、運用コストの増加を防げます。さらに、データの活用目的を明確にし、必要以上のデータの蓄積を抑える運用ルールを設けることも重要です。
データウェアハウスは設計とコスト高に要注意
データウェアハウスの導入には、設計とコストの負担に注意が必要です。特に、初期構築に時間がかかるため、業務の繁忙期と重なるとスムーズな導入が難しくなります。計画的に進めなければ、予想以上にコストがかかる可能性があります。
対策として、段階的な導入を検討し、スモールスタートで運用を始めるのが有効です。最初は特定のデータセットのみを対象とし、運用しながら徐々に拡張することで、負担を軽減できます。
また、拡張性を考慮したデータ設計を行うことで、変更が発生しても柔軟に対応できるでしょう。さらに、データの更新頻度が高い場合は、データマートと組み合わせることで、より効率的な運用が可能です。
データマートは運用ルールが不可欠
データマートの円滑な運用には、統一されたルールの策定が不可欠です。部門ごとに独自のデータを運用すると、全社的なデータの統一性が損なわれ、分析の精度や意思決定に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、データの整合性を確保し、全社レベルで一貫した情報活用ができるようにすることが重要です。さらに、データウェアハウスを基盤とし、必要なデータをデータマートへ適切に展開することで、部門ごとの最適化を図りながらも、全社的なデータ統制を維持できます。
データレイク・データウェアハウス・データマートの違いを理解してビジネスの成果を高めよう
データ分析を有効活用するには、その基盤となるデータレイク、データウェアハウス、データマートの違いを理解することが重要です。それぞれの構成、利用目的、活用法、費用、拡張性は異なります。これらのポイントを把握することで、データ管理の精度が向上し、ビジネスの成果につなげることができるでしょう。
データレイクは専門的な管理体制が求められ、データウェアハウスは導入にかかる時間と費用のバランスを考慮する必要があります。ただ、クラウド型のデータウェアハウスを利用すれば、初期費用を抑えながら、段階的に拡張できるのが利点です。一方、データマートを利用する場合は、部門間のデータ連携を適正に管理することが求められます。
クラウド型のデータウェアハウスを導入する場合は、Google のBigQuery がおすすめです。安価に導入でき、高速なデータ処理が可能なため、コストを抑えながら効果的にデータを活用できます。
データ分析をスムーズに進めたい方は、ぜひ以下の資料をチェックしてみてください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- データウェアハウス データレイク 違い