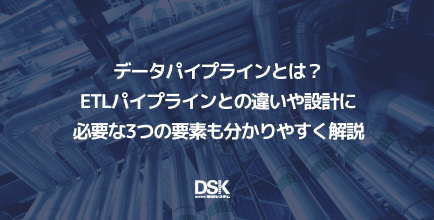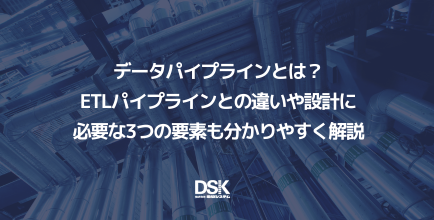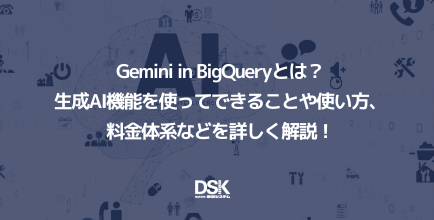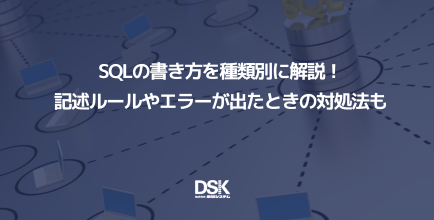最近は、ビジネスシーンでAI技術を積極的に活用するケースが増えています。データ分析や需要予測、商品やサービスの提案、チャットボットによる問い合わせ対応など、AIを活用すればさまざまな分野での業務効率化やタスクの自動化が可能です。
AIを活用する際に押さえておくべきなのが、今回紹介する機械学習です。AIを稼働させるための根幹となる技術なので、その仕組みをしっかりと頭に入れておく必要があります。学習方法やアルゴリズムの種類などを押さえておくと、独自のAIモデルを開発する際にも役立つでしょう。
本記事では、機械学習の仕組みや学習方法、活用する際の注意点などを解説します。機械学習を使って実際にどのようなことができるのか、その活用例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
機械学習とはコンピュータが自ら学習してデータを分析する技術
機械学習とは、コンピュータが自ら学習してデータを分析する技術です。特定の分野に焦点を当てて、大量のデータをアルゴリズムで解析し、そのなかから法則性や相関関係を見つけ出します。
すべてのパターンや関係性をコンピュータが自動的に発見するわけではなく、どのデータに着目すべきかは人間があらかじめ判断し、設定しておく必要があります。従来のプログラムとの違いは、開発者が事前にすべての動作を細かく定義しなくても良いという点です。
機械学習の仕組み
機械学習では、コンピューターに大量のデータを取り込ませ、それをさまざまなアルゴリズムにもとづいて解析させる仕組みです。コンピューターが繰り返し学習を行うことで、データ内に潜むパターンや規則性を見つけ出すことができます。ここで用いるアルゴリズムは、読み込ませるデータの種類や目的に応じて異なり、それぞれの用途に適したものを選定することが求められます。
AIと機械学習の違い
AI(Artificial Intelligence)とは、人間が行う認識や思考といった知的な活動をコンピュータ上で再現するための技術です。現在では、柔軟なデータ分析や文章生成といった機能を備えた、さまざまなAIシステムが開発・実用化されています。
一方で、機械学習とは、あらかじめ用意されたサンプルデータにもとづいて、コンピュータが自ら試行錯誤を行いながら学習する技術です。AIモデルを構築するうえで重要な技術の一つであり、AIの精度向上を目的として広く活用されています。
機械学習とディープラーニングの違い
機械学習とディープラーニングは、どちらもコンピュータが自らデータを分析して、そのパターンを探る技術だが、学習方法や仕組みに大きな違いがあります。ディープラーニングでは、従来の機械学習で必要とされていた特徴量の手動設計を行う必要がありません。人の手を介さず、データをディープラーニングのアルゴリズムに入力することで、AIが自動的にデータ出力に役立つ特徴量を習得します。
この高度な学習が可能なのは、人間の神経細胞の仕組みを模したニューラルネットワークが活用されているためです。多層構造のニューラルネットワークを用いた学習によってAIモデル(機械学習モデル)の精度を向上させ、人間では気付きにくい特徴を見つけ出せます。
また、データの特徴をコンピュータ自らが見つけ出せるのも、ディープラーニングの大きな強みです。従来の機械学習では、どこに注目してデータを分類すれば良いかを人間があらかじめ指示する必要がありましたが、ディープラーニングでは、注目すべき特徴をコンピューターが自動的に学習します。
機械学習の3種類の学習方法
機械学習には、教師あり学習と教師なし学習、強化学習の3種類の学習方法が存在します。学習方法によってAIモデルの仕様に違いが現れ、活用手段にも差が生まれます。そのため、それぞれの特徴を理解したうえで、目的に合わせて適切なタイプを選ぶことが重要です。
教師あり学習
教師あり学習とは、あらかじめ正解が与えられたデータを用いて学習を行う手法です。トレーニングデータや教師データと呼ばれる正解付きの学習データを活用する点に特徴があるため、正誤がはっきりしている課題の解決に適した学習手法だといえます。例えば、不正行為の検出やユーザーに合わせた製品のレコメンドといった場面での活用が可能です。
教師あり学習を導入する目的は、データに実用的な価値を持たせることにあります。具体的には、機械の温度が60度を超えると異常とみなすような基準を設定して学習させれば、AIは人間と同様に自動で判断できるようになります。
温度や稼働時間といった情報だけであれば、人が一つひとつ確認することも可能ですが、チェック項目や機械の台数が増えてくると対応に手間やコストがかかります。こうした状況において教師あり学習を活用すれば、AIが判断精度を高めていくことで効率化が図れ、結果としてコスト削減にもつながります。
教師なし学習
教師なし学習とは、学習データに正解ラベルを与えずに行う手法です。これは、正解データを付与して学習させる教師あり学習とは対照的な機械学習のアプローチです。教師なし学習では、予測や判断の基準となる正解が存在しないため、教師あり学習のように回帰や分類といった課題(株価予測やデータのカテゴリ分けなど)には直接対応できません。
教師なし学習の主な目的は、データ内に隠れた未知のパターンや構造を発見することにあります。現実の問題には、明確に正解が定義できないケースが多く存在します。教師なし学習は、そうした状況に対応するための手法として用いられます。
例えば、これまでに販売実績のない新商品について、どの市場をターゲットにすべきかを検討する際、参考となる正解データが存在しないことがあります。つまり、どの顧客層がターゲットになるのかという正解が得られないことから、教師あり学習ではアルゴリズムを訓練することができず、このような場合に教師なし学習が効果を発揮します。教師なし学習では、既存の情報をもとにクラスタリングや次元削減の手法を用いてターゲット層を予測し、データに潜む未知のパターンを見出すことが可能です。
強化学習
強化学習とは、コンピュータが自ら試行錯誤を繰り返すことで、最適な制御方法を学習していく手法です。あらかじめ学習データを用意して行う教師あり学習や教師なし学習に対し、強化学習ではそのようなデータを直接利用するわけではありません。
強化学習では、プログラムが与えられた環境を観測し、そこで得られた一連の行動とその結果を通じて、より価値の高い行動を学びます。そして、その行動に対する評価もプログラム自身で更新していく点が特徴です。多様な行動を試しながら、より望ましい選択を見つけていくというプロセスは、人間の行動パターンにも近いものといえるでしょう。
近年では、AI研究の進展とともに、囲碁ソフトや自動運転といった実用的な分野にも強化学習が応用されており、今後のAI活用において欠かせない技術の一つとなっています。
機械学習に用いられる代表的なアルゴリズム
機械学習を進める際は、次のようなアルゴリズムを活用できます。
- 線形回帰
- ロジスティック回帰
- k近傍法
- 決定木・ランダムフォレスト
- サポートベクターマシン
アルゴリズムとは、特定の問題を解決するための計算方法や手順のことです。各アルゴリズムの特徴を解説します。
線形回帰
線形回帰とは、目的変数と説明変数との関係を直線的なモデルを用いて表すアルゴリズムです。目的変数とは予測や分析の対象となる変数であり、説明変数はその目的変数に影響を及ぼす変数を指します。線形回帰を用いることで、説明変数の値から目的変数を推定することが可能です。
線形回帰を用いて機械学習を行うことで、小売業やオンラインショップ、金融業界など、さまざまな分野で売上や需要の予測として活用できます。想定される要因となるデータを入力して予測モデルを構築し、将来的な数値を見積もることで、売上向上に寄与する要因を洗い出したり、需要に応じた対策を講じたりできるのが特徴です。また、製造業では、製造条件のデータをもとに線形回帰を適用し、異常値として現れる故障や不良品の原因を特定するために活用されています。
ロジスティック回帰
ロジスティック回帰とは、複数の説明変数をもとに、2つの選択肢からなる目的変数の発生確率を予測するためのアルゴリズムです。ここでいう2つの選択肢とは、「合格・不合格」や「採用・不採用」といったように、答えが2つに限定されるケースを指します。
ロジスティック回帰は、特定の事象が起こる確率をもとに2つの分類に分ける回帰分析の一種です。この手法を用いることで、マーケティングにおける売上拡大や業務の効率化といった場面で、確率にもとづいた意思決定を行うことが可能になります。
さらに、ロジスティック回帰を活用することで、予測分析に必要な洞察を得ることができ、実用的な機械学習モデルの構築につながります。こうしたモデルを導入することで、業務効率の向上や運用コストの削減といった効果が期待できます。
k近傍法
k近傍法とは、データ間の類似性を距離という概念で評価するアルゴリズムです。機械学習の分野では、教師あり学習の手法としてよく用いられます。
一般的に、データは複数の特徴量で表現されます。例えば、果物の場合、色や重さといった特徴量があげられますが、k近傍法では、これらの特徴量を数値化し、座標として扱えるのがポイントです。
事前に用意された正解データの座標を記憶し、新たに入力されたデータとの距離を計算するのがk近傍法の基本的な仕組みです。正解データのなかから距離が近いものをいくつか数え、その結果にもとづいて入力データがどのカテゴリに属するかを判定します。そのため、複数のデータを特定のジャンルに分類する際に役立ちます。
決定木・ランダムフォレスト
決定木とは、複数の二者択一の条件を用いてデータを分類し、予測や判別などの結果を導き出すアルゴリズムです。条件分岐をフローチャートの形で表すと、枝分かれした木の形に似ていることから「決定木」と呼ばれています。
例えば、自社の商品を購入した顧客データを決定木で機械学習する場合、性別や年齢、購入回数が一定以上かどうかといった条件にもとづいて分類を行います。こうして分類されたデータから購入金額の高いグループの特徴を特定し、優良顧客の属性や傾向を把握することが可能です。
ただし、決定木単独では学習データの偏りや条件設定の誤りにより、判別ミスが発生する場合があります。こうした弱点を補い、精度を向上させるために考案されたのがランダムフォレストです。ランダムフォレストは、複数の決定木の結果を多数決のように集約し、より高精度な学習モデルを作りあげます。
サポートベクターマシン
サポートベクターマシンとは、2つのクラスに分類されたデータセットを分ける境界線や超平面を決定することで、分類や回帰などの課題に対応できるアルゴリズムです。分類問題において非常に高い精度を実現できるよう、マージン最大化という考え方を採用しています。
マージン最大化とは、2つのサポートベクトル間で最も広い距離を持つ位置に境界線を引くことを指し、サポートベクターマシンの核心的な技術です。この手法によって、サポートベクターマシンはニューラルネットワークなどの深層学習モデルと比較して、少ないデータ量でも高い汎用性を発揮できます。
機械学習の活用例5選
機械学習を発展させると、予測やレコメンデーション、異常検知など、さまざまな分野での活用が可能です。実際にビジネスに導入する際は、それぞれの活用例や活用方法を理解しておくことが重要です。
予測
機械学習において、最も重要なタスクの一つが予測といえるでしょう。過去のデータを蓄積することで、高精度な分析や予測が可能になります。
その代表例として、需要予測があげられます。需要予測とは、蓄積されたデータを分析し、在庫の最適化や収益の最大化を目指す方法です。
高い精度で需要予測を行うためには、まず現状の業務内容を把握するためのヒアリングが欠かせません。そのうえで、過去の実績データや天候の影響などを加味し、需要予測モデルを構築することで、より精度の高いシステムを作り上げることが可能です。
したがって、最初に実施するヒアリングは、結果的に業務負担を大幅に軽減するための非常に重要な工程となります。また、適切なデータ活用を継続するためには、定期的なデータの検証と改善も不可欠です。こうした作業を継続的に行うことで、在庫切れによる機会損失や過剰在庫による廃棄リスクを抑制でき、結果として収益の最大化につなげられます。
レコメンデーション
インターネット上でのショッピング時によく見られるレコメンデーション(おすすめの商品やサービスの提案)にも、アイテム間の類似度を算出するために機械学習が活用されています。この場合、コンピュータはデータから特徴や傾向を自動で抽出するため、教師なし学習が用いられるのが一般的です。
レコメンデーションは、大きく分けてユーザーベースとアイテムベースの二種類に分類されます。ユーザーベースでは、似た特徴を持つユーザー同士をグループ化し、そのグループ内で高評価の商品を提案します。一方、アイテムベースでは、対象の商品に類似した商品や、よく一緒に購入される商品をおすすめするのが特徴です。
異常検知
異常検知とは、大量のデータのなかから通常とは異なるデータ(異常)を見つけ出す技術です。データマイニングと呼ばれる、大量のデータからパターンや傾向を抽出する技術を活用し、ほかのデータとの比較を通じて一致しないデータを識別します。
異常検知は、用途に応じて「故障検知」や「不正使用検知」といった名称で呼ばれる場合もあります。しかし、これらは別物ではなく、いずれも膨大なデータのなかから異なる挙動を示すデータを抽出する技術であることに変わりはありません。
近年では、メールや文書、画像、動画、Webサイトのアクセスログなどといった、非構造化データを用いた異常検知が増加しています。そのため、ビジネスの現場で実際に活用していくには、データ分析に関する知識やスキルが求められます。
異常検知は膨大なデータから傾向や規則性を学習する必要があるため、機械学習との相性が良い点も大きな特徴だといえます。
顔認証システム
機械学習の活用例として代表的なのは、不審者を検知する顔認証システムです。教師あり学習を用いて、従業員や関係者といった入退室を許可されている人物の画像を正解データとして学習させます。監視カメラに映った顔が登録データと一致しない場合、不審者の可能性があるとして検出される仕組みです。
顔認証システムは、入退室管理システムに標準機能として備わっていたり、入退室管理システムと別々に販売されている場合でも、それぞれのシステムを連携できたりと、互いに相性が良い関係にあります。入退室管理システムと同時に利用すると、顔認証とIDカードの認証を組み合わせて、オフィスの安全性をより向上できます。
音声認識
音声認識とは、人間の話す言葉をコンピュータが理解する技術のことです。音声信号を解析し、それを文字情報に変換できます。
例えば、スマートフォンに搭載されている音声アシスタント(GoogleアシスタントやSiriなど)は、音声による操作を可能にしており、「明日の天気は」と話しかけるだけで天気予報を教えてくれます。また、車載のナビゲーションシステムでは、音声で目的地を設定したり、音声案内を受け取ったりすることも可能です。ビジネスシーンでは、電話の自動応答システムとして活用が可能で、コールセンター業務の効率化・自動化を図れます。
機械学習を活用する際の注意点
機械学習を活用するにあたっては、次のような点に注意が必要です。
- 過学習や未学習が発生する恐れがある
- 出力結果の根拠を探るのが難しい
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
過学習や未学習が発生する恐れがある
機械学習の分野では、「訓練誤差」と「汎化誤差」の2種類の誤差が発生する可能性があります。訓練誤差とは、モデルの学習に用いたデータに対する誤差のことを指し、汎化誤差とは、未知の新しいデータに対してどれだけ誤差があるかを示すものです。
たとえ訓練誤差が小さくても、汎化誤差が大きい場合には、そのモデルが訓練データに過学習している(オーバーフィッティング)と判断されます。過学習では、特定の訓練データに関しては最適化されていますが、そのほかの問題には対応しにくく、一般的な課題やタスクを処理できるほどの汎用性はありません。
一方で、訓練誤差も汎化誤差も両方とも大きいままである場合、そのモデルが訓練データを十分に学習できていない(アンダーフィッティング/未学習)と判断されます。未学習は、コンピュータが訓練データに対して表面的にその解決法を学んだにすぎず、過学習と同様、実用的なモデルを構築するには不十分な状態だといえます。
このような点から、機械学習を行う際は、過学習や未学習が起きないように学習方法を検討する必要があります。
出力結果の根拠を探るのが難しい
機械学習モデルの予測結果について、その根拠を説明するのは非常に困難です。特に、ニューラルネットワークのように構造が複雑なモデルでは、予測の理由を人間にとってわかりやすく説明するのが難しいケースも少なくありません。
2015年には、Googleフォトがアフリカ系の女性をゴリラとタグ付けしたことで大きな問題となりました。このとき、機械学習モデルがどのような部分からゴリラと判別したのか、明確に説明することができず、単純なアルゴリズムの修正では問題解決に至りませんでした。
画像認識のほかにも、データ分析や需要予測、顧客のセグメンテーションなど、出力結果の根拠が求められるケースは数多く存在します。このような場面で出力結果がブラックボックス化しやすいのは、機械学習が抱える重要な課題の一つだといえるでしょう。
機械学習の仕組みを理解してさまざまな業務で活用しよう
機械学習の仕組みを理解することで、自社独自のAIモデルの開発を促進できます。そのAIモデルは、予測やレコメンデーション、異常検知など、さまざまな分野へと発展可能です。結果として、経営判断やマーケティング、生産活動などの効率性を高められるメリットがあります。
ただし、機械学習には、過学習や未学習に陥ったり、出力結果の根拠がわかりにくかったりと、いくつかの課題も存在します。このような課題を理解したうえで、正しい活用方法を習得し、目的に合わせて導入を検討しましょう。
機械学習の仕組みや活用方法については、こちらの資料でも詳しく解説しています。無料でダウンロードできるので、機械学習を使って業務効率化やコスト削減を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- 機械学習 とは