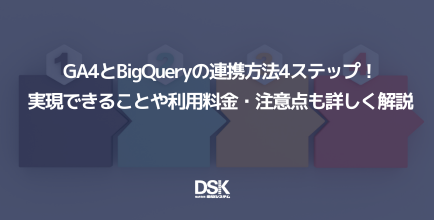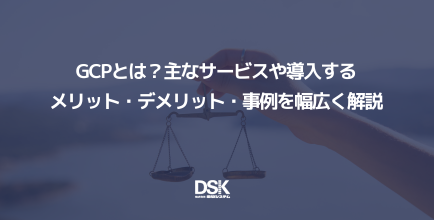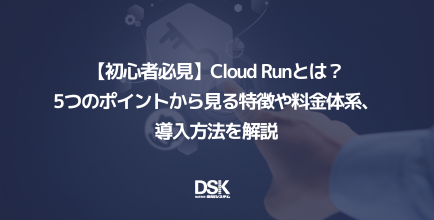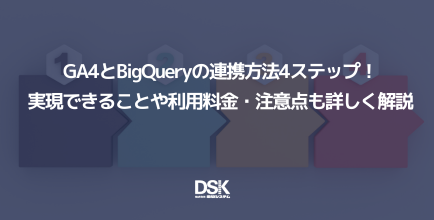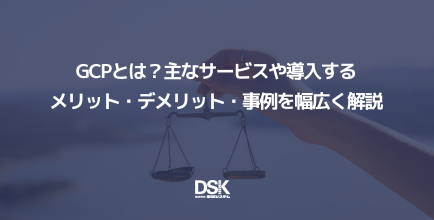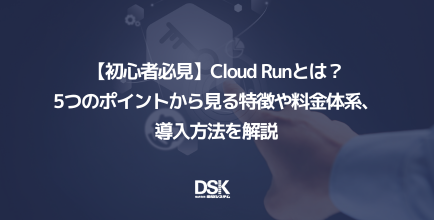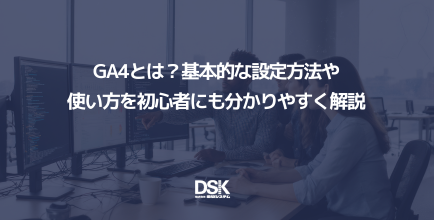最近では、企業のホームページなどでチャットボットを見かける機会も多いのではないでしょうか。画面端にあるチャット部分に質問を書き込むことで、機械が自動的に返信してくれるため、電話やメールで問い合わせる手間を抑えられます。
ユーザーにとって利便性や満足度の向上につながる点から、カスタマーサポートやマーケティングでチャットボットを活用するケースも珍しくありません。ただし、チャットボットを導入する場合は、その仕組みや成果、活用方法をしっかりと理解する必要があります。
本記事では、チャットボットの仕組みや機能、メリットなどを詳しく解説します。チャットボットの活用例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
チャットボットとはチャット上の質問に自動返答するプログラム
チャットボットとは、「チャット(chat)」と「ボット(bot)」を組み合わせた言葉で、ユーザーからの問い合わせや質問に対して、自動的に会話を行い、応答してくれるプログラムのことです。チャットボットを導入することで、問い合わせ対応にかかる業務負担を軽減できるほか、24時間365日対応が可能になるといった利点があります。
そのため、近年では多くの企業や団体で導入が進んでいます。また、Webサイト上での問い合わせ対応が可能なWeb接客向けのチャットボットに加え、LINEやFacebookといったメッセージングアプリに組み込まれるケースも増えており、カスタマーサポートを目的としたチャットボットへの関心が高まっています。
チャットボットの種類
チャットボットには、ルールベース型とAI型の2つの種類があります。それぞれシナリオの設計方法や運用方法が異なるため、目的に沿って選び分けることが重要です。
ルールベース型
ルールベース型は、あらかじめ定めた「シナリオ」と呼ばれる会話の流れに従って対話を進めるタイプのチャットボットです。「シナリオ型」と呼ばれることもあります。想定される質問とその回答をセットで用意し、そのシナリオにもとづいて会話が分岐する仕組みです。
AI型と比較すると、導入や運用が比較的容易で、コストも抑えやすいメリットがあります。ただし、あらかじめ設定されたシナリオ内の質問には正確に応答できる一方で、想定外の質問には対応しにくく、複雑な問いかけを苦手とする傾向があります。
また、ルールベース型は次のように、シナリオの構築方法によってさらに細かく種類が分かれます。
- ログ型:ユーザーとの会話ログをもとに回答を提示する
- 選択肢型:明確な回答ではなく複数の選択肢を提示する
- 辞書型:特定の単語とそれに対する回答を登録して質問に対応する
- ハイブリッド型:「選択肢型&辞書型」のように複数のタイプを組み合わせて活用する
ルールベース型は、質問と回答のパターンがある程度決まっているケースに向いています。例えば、「解約する際に手数料はかかりますか」「発送までにどの程度の時間がかかりますか」といった定型的な質問に答える場合、FAQのような形で容易にシナリオの構築が可能です。
AI型
AI型は、初期設定時に読み込ませた大量のデータと、運用を通じてAIが学習した情報をもとに、ユーザーの質問に対して最適と判断された回答を選び出すチャットボットです。
AIには機械学習と呼ばれる技術が活用されており、大量の学習データをインプットすることで、データ同士の関連性や法則性を自ら学び取れます。例えば、FAQやマニュアル、トークスクリプト、営業資料などを学習データとしてインプットすると、自社の商品やサービス、問い合わせ時の対応方法に関するノウハウをAIが習得し、関連する質問に対して的確な回答を行えるようになります。
機械学習の特性上、保有・蓄積されているデータが多いほど応答の精度が向上し、ユーザーに寄り添った自然な会話が実現できます。逆に、データの量や質が不足している場合には、回答の精度が低下することも少なくありません。また、導入時に多くのデータが必要となり、運用中も適宜調整を加える必要があるため、ルールベース型に比べて運用の手間がかかりやすい点には注意が必要です。
問い合わせのなかでも定型化されていない内容が多い、あるいはよりスムーズで自然な会話体験をユーザーに提供したい場合は、ルールベース型よりもAI型が向いているでしょう。
チャットボットの代表的な機能
製品によって異なりますが、チャットボットには自動応答や有人対応など、幅広い機能が搭載されていることも多いものです。チャットボットに搭載されている代表的な機能を紹介します。
自動応答
自動応答とは、ユーザーの質問に対し、人間の指示なしで自動的に的確な回答を行えることです。AIを搭載したチャットボットであれば、蓄積されたデータをもとにAIが継続的に学習するため、問い合わせの回数が増えるに連れて自動応答の精度が向上します。
ルールベース型の場合、ユーザーの質問を一つひとつ人間が想定し、それに応じたシナリオを設計しなければなりません。取扱品目やユーザー数が多い場合は、その分、想定される質問の種類や数も多くなるため、シナリオ設計に時間がかかることもあります。
一方で、AI型の自動応答に対応したチャットボットなら、学習を進めるうちに回答精度が高まります。そのため、プログラムを再構築する手間が徐々に軽減されるため、長期的に見るとAI型のほうが費用対効果が向上する可能性も考えられます。
有人対応
AIを搭載したチャットボットであっても、すべての問い合わせに自動で対応できるわけではありません。問い合わせ対応では単純な質問に限らず、多様な内容の質問が寄せられることもあり、特に複雑かつ高度な問い合わせには、過去に蓄積されたデータだけでは適切な回答を行えないケースもあります。
その対策として、近年では有人オペレーター対応へ切り替え可能な機能を備えたチャットボットも登場しています。チャットボットで対応できない問い合わせについては、オペレーターが対応する体制を整えることで、AIと人間の業務を適切に分担できます。また、オペレーターの負担を軽減しつつ、スムーズな顧客対応を実現できるのも利点です。
FAQ連携
FAQと連携することでオペレーターの負担を軽減できるチャットボットも存在します。ユーザーから寄せられる質問に備えて、あらかじめFAQを整備しておくことで、関係部署との連携もより円滑に行えるようになります。
また、よくある質問やリクエストに対する回答をテンプレート化できるのも特徴です。結果としてユーザーは素早く疑問を解消できるため、顧客満足度の向上にもつながります。ただし、ユーザーのニーズは常に変化するため、FAQそのものの見直しやシナリオの定期的なメンテナンス作業が欠かせない点には注意が必要です。
外部システム連携
チャットボットのなかには、外部システムと連携できるものもあります。連携可能な外部システムは製品によって異なりますが、SNSや問い合わせ管理システム、予約システム、顧客管理システムなどが代表的です。
例えば、LINEとチャットボットを連携すると、LINEのトークルーム上でユーザーからの質問に自動で回答ができます。最近ではLINEを顧客とのコミュニケーションやマーケティング、販売促進などに活用するケースが増えており、チャットボットによってやり取りを効率化することで生産性の向上につながります。
外部システムとの連携方法は、APIを活用したり、アプリケーション上に直接設置したりと、さまざまな手段があります。そのため、チャットボットの連携範囲に加え、連携方法についても事前にしっかりとチェックすることが大切です。
チャットボットを導入する4つのメリット
チャットボットを導入すると次のようなメリットが生まれます。
- より効率的に問い合わせ対応業務を行える
- 顧客満足度の向上につながる
- コンバージョン率を改善できる可能性がある
- VOC分析を行いやすい
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
より効率的に問い合わせ対応業務を行える
チャットボットを導入することで、問い合わせ対応にかかる時間を削減できるため、業務の効率化につながります。従業員がほかの業務と並行して問い合わせに対応しているような場合でも、チャットボットが代わりに対応することで、従業員は本来取り組むべき生産的な業務に集中できます。また、コールセンターにおいても、定型的な質問をチャットボットに任せることで、応答率の向上やオペレーター数の削減が可能です。
顧客満足度の向上につながる
チャットボットを導入することで、より丁寧で柔軟な問い合わせ対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
仮に問い合わせ対応をコールセンターのみに依存しており、その対応時間が9~17時までに限られている場合、17時以降にしか時間を取れないユーザーは問い合わせができず、不便を感じることがあります。一方でチャットボットを活用すれば、ユーザーがどの時間にサイトを訪れても、必要な回答を即座に得られます。
ユーザーが思い立ったときに即座に問い合わせられる環境を構築することで、顧客満足度が高まり、商品やサービスの利用促進にもつながります。
コンバージョン率を改善できる可能性がある
チャットボットを導入することで、Webサイトからのユーザー離脱を防ぎ、コンバージョン率の向上が期待できます。
ユーザーがWebサイトを離れてしまう大きな要因の一つは、疑問や不明点をその場で解決できないことです。問い合わせの手段が電話やメールしかなく、手続きが面倒だと感じた場合、そのままページを離れてしまう可能性も考えられます。
その点、Webサイト上にチャットボットが設置されていれば、容易に質問ができ、その場で疑問を解消できます。このように手軽にサポートを受けられる環境があることで、ユーザーの不安を軽減し、結果としてコンバージョン率の向上にも寄与します。
VOC分析を行いやすい
チャットボットを導入することで、VOC(Voice of Customer:顧客の声)を分析し、マーケティングや製品開発に活用できます。
チャットボットでは、顧客とのやり取りがデータとして自動的に蓄積されます。蓄積されたデータを分析することで、顧客が疑問を抱きやすいポイントや、商品・サービスに対するニーズなどの傾向がわかります。
分析データを活用すれば、製品の改良やサービス品質の改善、Webサイトの見直しなどが可能です。従来は見落とされがちだった顧客の声をデータとして可視化できる点は、チャットボットを活用する大きな利点だといえるでしょう。
チャットボットを導入する3つのデメリット
さまざまなメリットがあるチャットボットですが、次のようなデメリットも存在します。
- 完全に自動化できるとは限らない
- 準備作業や運用に手間がかかりやすい
- 費用対効果が見合わない可能性がある
チャットボットを利用するうえでの注意点にもあたるため、事前に適切な対策を講じましょう。
完全に自動化できるとは限らない
多くの企業が業務の効率化や顧客満足度の向上を目的としてチャットボットを導入する傾向にありますが、すべての問い合わせに対して自動対応が可能というわけではありません。
例えば、ルールベース型の場合、文章が長かったり内容が複雑であったりする問い合わせには、チャットボットだけでは対応が難しい場合があります。そのため、有人対応やFAQ連携などの機能を活用し、チャットボット以外のリソースも有効活用するのが理想です。
AI型の場合でも、ときには誤った回答を出力するケースがあります。誤りやミスを防ぐには学習データやアルゴリズムを見直す必要がありますが、完全にゼロにするのは困難です。そのため、できるだけ精度を高めるために定期的なメンテナンスが欠かせず、人間の手で作業を行う必要があります。
準備作業や運用に手間がかかりやすい
チャットボットを導入・運用するにあたっては、事前の準備や継続的なメンテナンスにある程度の労力が必要です。導入時には、FAQの整備やシナリオ設計が欠かせません。さらに運用が始まった後も、定期的にメンテナンスを行い、回答の精度向上に努める必要があります。
こうした作業にかかる負担を軽視せず、導入時の準備内容や運用後の体制についてあらかじめ計画を立てておくことが重要です。適切な計画と運用体制の整備こそが、チャットボットの導入効果を最大限に引き出す鍵となります。
費用対効果が見合わない可能性がある
チャットボットを活用するには、初期費用に加えて、運用にかかる継続的なコストも発生します。特に、コスト削減を目的として導入する場合には、削減できる費用と新たに必要となる支出とのバランスを慎重に見極めることが重要です。新しいツールが導入直後から期待通りの費用対効果を発揮するとは限らないため、その点にも注意が必要です。
まずは自社の課題や導入目的を明確にしたうえで、それらにマッチした機能や特性を持つチャットボットを選定しましょう。中長期的な予算計画を立て、どの時点で投資回収が見込めるかを見通すことで、安定した運用が可能になります。
チャットボットの活用例4選
チャットボットには次のような活用方法があります。
- カスタマーサポート
- 社内ヘルプデスク
- ナレッジ共有
- マーケティング支援
さまざまな領域でチャットボットを活用することで、組織全体での業務効率化や生産性向上が見込めます。具体的な活用例を紹介します。
カスタマーサポート
チャットボットは、ユーザーからの問い合わせ対応に広く活用されています。ルールベース型でもAI型でも、内容がシンプルな問い合わせであれば十分に対応可能です。
カスタマーサポートを実施するには、ユーザー対応のために大規模なコールセンターを設置したり、多数の人員を確保したりするケースもあります。チャットボットを活用すると、施設設置や人員確保のコスト・手間を軽減できます。限られたコストやリソースのなかでも、チャットボットが問い合わせ対応の一部を担ってくれるため、うまく活用すればコールセンターや組織の規模縮小にもつなげられます。
社内ヘルプデスク
社内ヘルプデスクとは、社内のIT機器や業務システムを利用する従業員を支援する専門部署です。「インターネットにつながらない」「パソコンが起動しない」といったIT関連の問い合わせを受け付け、迅速かつ的確に問題解決を図る役割があります。
社内ヘルプデスクへの問い合わせ内容は、カスタマーサポートよりもパターン化しやすい傾向があります。そのため、チャットボットによる対応が可能なケースも珍しくありません。
ただし、社内ヘルプデスクではチャットボットや有人チャットに加え、遠隔サポートなどの手段を併用するケースもあります。遠隔サポートとは、オペレーターが相談者のパソコンやスマートフォンを遠隔操作し、画面を通じて操作方法を実演したり、トラブルの原因を視覚的に示して解決へ導いたりするサービスです。チャットボットだけでは対応が難しい複雑なケースに備えて、遠隔サポートのような仕組みを導入しておくのも効果的です。
ナレッジ共有
社内の情報をチャットボットに集約することで、ナレッジ共有ツールとしても活用が可能です。従来、社内ナレッジはマニュアルやイントラサイトで管理されるのが一般的ですが、必ずしも検索性に優れているとは限りません。そのため、従業員が必要な情報を探すのに時間を要し、生産性が低下する恐れもあります。
チャットボットを導入すれば、知りたい情報や資料についてチャットで問いかけるだけで、自動的に該当する情報・資料を的確に提示してくれます。結果、資料収集の効率性が向上したり、より効果的な社員教育を行えるようになったりと、さまざまなメリットが生まれます。
マーケティング支援
チャットボットに寄せられた顧客からの問い合わせ内容を分析することで、マーケティング施策への活用も可能です。チャットボットには、日々さまざまな質問や相談が寄せられますが、なかには商品やサービスに関する些細な疑問やフィードバックなども多く含まれています。こうした声を拾うことで、これまで見落としていた顧客ニーズを把握できます。
マーケティング領域でチャットボットを活用する際は、顧客管理システムや問い合わせ管理システムと連携するのも一案です。システム連携により、顧客の属性や行動履歴、問い合わせ履歴などのデータを活用できるため、チャットボットを用いたデータ分析にも役立ちます。
チャットボットを効果的に活用する4つのポイント
チャットボットを効果的に運用するには、次のポイントを意識することが重要です。
- チャットボットの導入目的を明確にする
- 事前に必要なデータを準備する
- 回答後のステップを用意しておく
- 定期的にPDCAを行う
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
チャットボットの導入目的を明確にする
チャットボットを導入する際は、その導入目的と活用シーンを明確にすることが重要です。目的に沿ったチャットボットを選ぶことで、ユーザーの具体的なニーズや課題に対して、的確に対応できます。反対に、目的が曖昧なまま導入を進めてしまうと、ユーザーの問題解決に結び付かず、効果を実感できない可能性が高くなります。
顧客対応の質を向上させる目的であれば、問い合わせ対応に特化したチャットボットが適しています。一方、社内の業務効率化が目的の場合、従業員からの問い合わせに迅速に対応できるチャットボットが求められます。このように、チャットボット導入の目的を明確にしておくことで、必要な機能を備えた最適なツールを選定でき、ユーザーの課題に対して効果的な解決策を提供することが可能です。
事前に必要なデータを準備する
ルールベース型とAI型を問わず、チャットボットを運用するにはある程度のデータが必要です。
ルールベース型の場合は、シナリオを構築するためのデータが必要で、FAQや問い合わせ履歴、業務マニュアルなどがそれに該当します。そのため、あらかじめ必要な資料を準備しておくことが重要です。
AI型の場合、商品やサービスに関する質疑応答をチャットボットに担わせるには、そのサービスに関する質問とその回答例をしっかりと学習させる必要があります。十分なデータを蓄積すればするほど、より高性能なAIを構築でき、実用性の高いチャットボットとして活用が可能です。
回答後のステップを用意しておく
チャットボットによって疑問が解消されたとしても、それだけでユーザーが完全に満足するとは限りません。
例えば、「商品が壊れて動かない」という問い合わせに対して、「修理が必要です」と返答したとします。確かに質問には答えているものの、ユーザーの抱える問題が本当に解決されたとはいえません。相手が本当に求めているのは、不具合が発生した原因や理由よりも根本的な解決策です。
そのため、修理が必要であれば担当部署を案内するといった形で、回答後のステップへとつなげる導線を用意することが大切です。こうした丁寧なフォローがあってこそ満足度の向上へとつながります。
定期的にPDCAを行う
チャットボットを導入した後は、その効果を最大限に引き出すために、定期的な分析と改善を行うことが不可欠です。継続的に運用しながら評価を重ねることで、長期的にチャットボットのパフォーマンスを最適な状態に保てます。
また、ユーザーの反応やフィードバックを分析し、それをもとにチャットボットの設定や応答パターンを見直すことで、より質の高いサービス提供が可能です。ユーザーからの質問に対する回答率や解決率、満足度といった指標を活用し、チャットボットの効果を定期的にチェックしましょう。さらに質問の傾向や頻度などを分析することで、不足している情報や改善すべきポイントを把握できます。
このような継続的な分析と改善のプロセスを通じて、チャットボットの性能を着実に向上させ、ユーザーにとってさらに役立つ存在へと育てていけます。
チャットボットを活用して業務効率化や生産性向上を図ろう
「問い合わせ対応に時間や手間がかかる」「従業員が不足しており応対品質がなかなか向上しない」といった悩みを抱えている場合は、チャットボットの導入がおすすめです。チャットボットであれば、問い合わせの一部に対して自動的に対応が可能なので、少ない人員で効率良く業務を進められます。
なかでもAIを搭載したチャットボットは、機械学習を通じてユーザーの質問の意図を読み取り、的確な回答が可能です。定期的なメンテナンスを行うことで精度向上にもつながります。
電算システムでは、Google Cloudのスターターパックサービスや技術コンサルティングサービスなどを提供しています。Google Cloudには「Vertex AI Studio」や「AutoML」など、さまざまなAI関連サービスが搭載されており、独自のAIモデルを開発したり、既存のAI技術を活用したりできるのが特徴です。Google Cloudの活用方法については以下の資料で紹介しており、無料でダウンロードできるので、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- チャットボット とは/チャット ボット ai