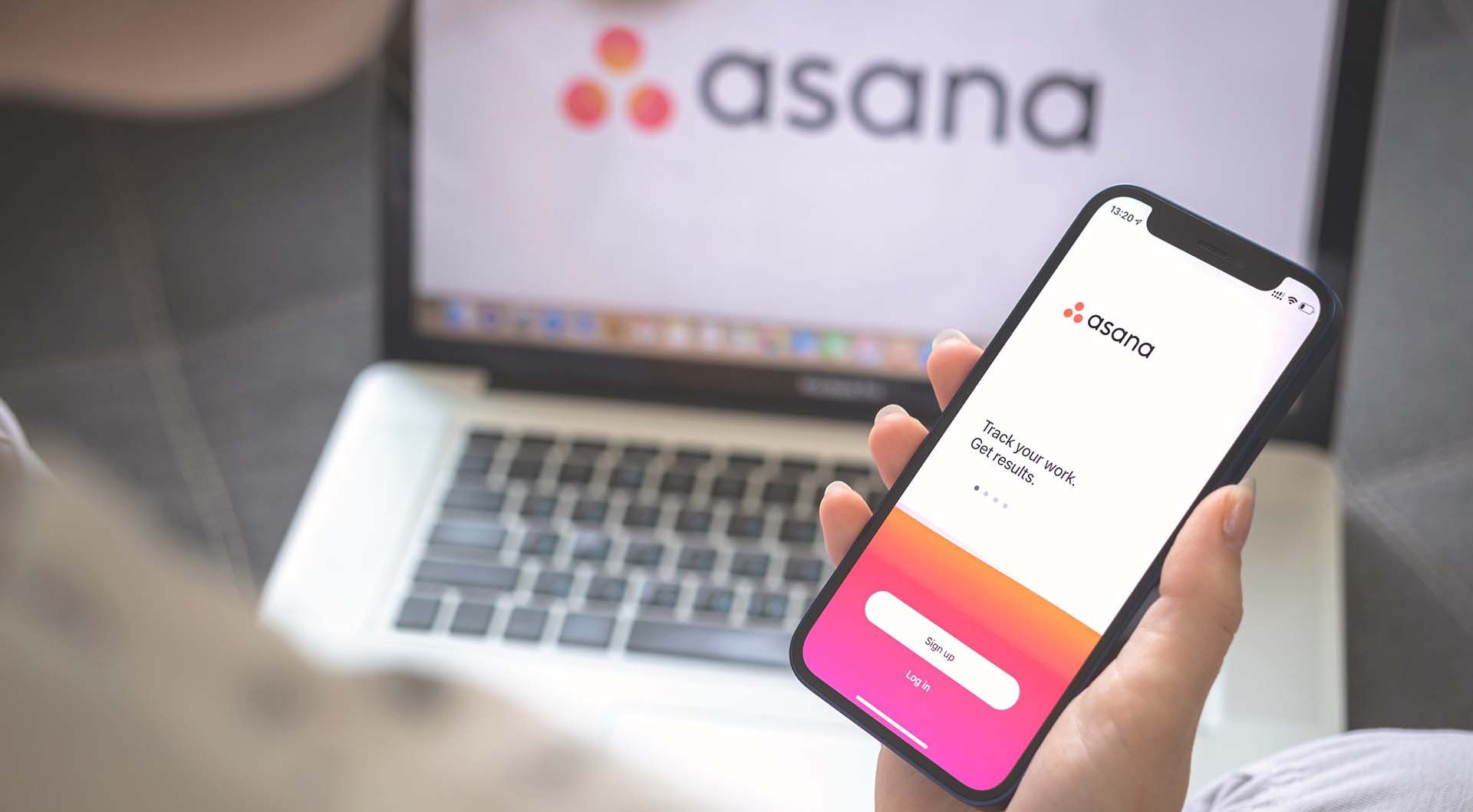プロジェクトをスムーズに進めるには、プロジェクト管理に関する知識が不可欠です。管理手法や知識を身につければ、滞りなくプロジェクトを進行でき、成功へと導けるでしょう。本記事では、プロジェクト管理の手法を学ぶ必要性や、具体的な管理の手法について解説します。知識と手法を習得し、今後のプロジェクト管理に活かしましょう。

なぜプロジェクト管理の手法を学ぶのか?
スムーズなプロジェクト管理を実現するには、知識や手法を学ぶことが重要です。プロジェクト管理において、絶対にこうしなくてはならない、といった明確なルールはありませんが、手法を知らないと非効率な管理になってしまうおそれがあるからです。
詳しくは後述しますが、プロジェクト管理にはさまざまな手法があります。これらの手法を学ぶことにより、具体的な取り組み方や注意点を把握でき、効率のよいプロジェクト管理を実行できるのです。
プロジェクト管理の手法を知りたいのであれば、PMBOKを学んでみましょう。PMBOKは、プロジェクト管理のグローバルスタンダードともいわれる手法です。プロジェクト管理の手法やノウハウを体系立てたもので、プロジェクトマネジメントを理解するうえで役立ちます。
プロジェクト管理の主な12の手法
プロジェクト管理の手法としては、WBSやガントチャート、タイムライン、マインドマップなど、さまざまです。それぞれ、取り組み方やできることが異なりますが、プロジェクト管理に役立つことは間違いありません。ここからは、代表的な12の手法について解説します。
WBS
WBSは、Work Breakdown Structureの略で、日本語では、作業分解構成図と訳され、プロジェクトの全体像を構成図化できる手法です。
プロジェクト達成に向けた過程では、さまざまな作業が発生します。具体的に、どのような作業が発生するのかを抽出できないと、タスクの割り振りもできません。
WBSを用いれば、作業を段階的に細分化でき、それぞれの工程において、どのような作業があるのかを明確にできるでしょう。
ガントチャート
ガントチャートは、もっともポピュラーなプロジェクト管理手法のひとつです。プロジェクトの作業工程や進捗状況を、表形式にしたもので、現状をひと目で把握できるのが特徴です。
ガントチャートは、縦軸と横軸で構成されます。縦軸には、作業内容や担当者などを、横軸には日にち、時間を設定します。これにより、誰のタスクがどれだけ進んでいるのか、または滞っているのか、期限まであとどれくらい猶予があるのか、といった情報をまとめて把握できるのです。
なお、ガントチャートが単体で用いられるケースはそこまで多くありません。一般的には、WBSでタスクを細かく抽出したうえで、ガントチャートを用いてグラフ化します。
タイムライン
時系列でタスクを表示し、管理を行う手法です。一般的には、日にちを横並びに配置し、タスクの開始日と終了予定日を横線で示します。これにより、いつまでに何をやるべきかを、正確に把握できるのです。
一方で、タスクの進捗状況を把握するのには、あまり適していません。そのため、近年ではタイムラインより、ガントチャートを用いるケースが多く見受けられます。
タイムラインは、Excelでも作成できますが、専用のツールもリリースされています。オンラインで入手できる、無料のツールもあるので、気になる方はチェックしてみましょう。
マインドマップ
マインドマップは、思考整理の手法として広く知られています。アイデア出しの手法としても用いられており、ひとつのテーマから連想できることを次々と派生させていきます。
プロジェクト管理で用いるときは、プロジェクトのゴールから逆算するように、各タスクを分解します。複雑なプロジェクトであっても、小さなタスクに分解して表せるため、課題の抽出や分析が可能です。
マインドマップで抽出したタスクを、WBSでグラフ化すれば、より視認性を向上させられるでしょう。マインドマップ作成に適した専用ツールもリリースされています。
ウォーターフォール
ウォーターフォールは、システム開発で用いられる手法です。クリアすべきフェーズを複数設定し、スケジュールを組み立てたうえで順番に着手します。
プロジェクト開始前に、やるべきことをすべて抽出し、順番に進めていくため、頭の中を整理しながらプロジェクトの進行が可能です。ひとつのフェーズが完了しないと、次のフェーズへは進めないため、管理がしやすいのも特徴です。
一方で、ウォーターフォールは計画段階で入念に作業工程やスケジュールを組み立て、その通りに進めていく手法であるため、融通がききにくい面があります。仕様や作業内容に変更が生じたときに対応しにくく、余計な手間が発生してしまいます。
アジャイル
従来、ソフトウェアやシステム開発の現場では、ウォーターフォールによる管理手法が用いられてきました。しかし、先述した通りウォーターフォールは変更に対応しにくいというデメリットがあります。そこで、ウォーターフォールに代わり注目を集めたのが、アジャイルと呼ばれる手法です。
アジャイルでは、プロジェクトを一定の期間に区切り、管理を実行します。1~4週間単位の期間にわけ、期間ごとに計画や目標を打ち出すのです。たとえば、Webサイトの作成であれば、1週間目はトップページを、2週間目にはメインのコンテンツを、3週間目にはFAQを、といった具合です。
それぞれの期間にわけて管理を行うため、急な変更が起きても柔軟に対応できることが特徴です。ただ、長期のプロジェクトとなると、それだけ区切られた期間が多くなり、全体の管理が難しくなるデメリットがあります。
QFD
quality function deploymentの略で、日本語では品質機能展開と訳されます。顧客のニーズを正確に把握し、品質を保ちつつ、ニーズを満たすために何が必要なのかを考える手法です。
QFDにおいては、顧客のニーズを整理し、要求された品質を実現するための要素を考えるため、満足度の高い製品開発が可能です。なお、QFDを可視化するには、一般的に顧客の要求をヒアリングしたうえで品質機能展開表を作成します。
CCPM
Critical Chain Project Managementの略です。各タスクの完遂に必要な時間を短縮し、プロジェクト全体に余裕をもたせる手法です。
AとB、C3つのタスクがあり、それぞれ余裕をもたせて20分の所要時間を設定するとします。この場合、担当者は時間いっぱい使って作業を進めようとするかもしれません。余裕を省いて15分に設定すれば、各タスクで5分浮くため、5×3=15分の余裕が生まれます。
仮に、何らかのトラブルが発生して作業が遅れたとしても、余裕をもたせてあるため納期に影響しません。これがCCPMのメリットです。
PERT
各タスクの関係性を図に示し、所要時間や重要工程を把握する手法です。タスクを図に示し、矢印でつなぐことで、取り掛かる順番や重要性などを把握できます。
複雑なプロジェクトでも、全体像を把握しやすくなるのがメリットです。視覚的に、プロジェクトの完遂に必要な工程を確認でき、優先すべき作業も抽出できるため、最短のスケジュールを組むことも可能です。
PPM
Project Portfolio Managementの略で、複数プロジェクトの管理によく用いられる手法です。問題児と花形事業、金の成る木、負け犬など4つの概念があり、これらをプロダクトにあてはめます。
これにより、各プロダクトにおけるライフサイクルや需要を把握できます。成長期なのか、それとも撤退期なのかといった情報の把握、管理を行うことで、利益の最大化と損失の最小化を目指します。
P2M
プログラムマネジメントの要素を加えた、プロジェクト管理の手法です。日本で誕生した手法であり、経済産業省が2001年に、プロジェクト&プログラムマネジメント標準ガイドブックとして発行しました。
PMBOKでは、複数のプロジェクトの統合が難しいといわれていましたが、P2Mではその課題をクリアしています。なお、P2MにはPMCやPMS、PMR、PMAと4つの資格が存在するのも特徴といえるでしょう。
EVM
EVMは、客観的にプロジェクトを把握できる手法として知られています。プロジェクトが当初の予定通り進んでいるのかを、予算額(PV)、進捗(EV)、実コスト(AC)3つの数値を用いて可視化します。
スケジュールはもちろん、コストが計画通りであるかどうかを、確認できるのが特徴です。現状把握に留まらず、このまま進めることで将来的にどうなるのかといった分析できます。
まとめ
プロジェクト管理にはさまざまな手法がありますが、アナログで実行するのは非常に非効率です。効率的なプロジェクト管理を実現するには、ツールの利用がおすすめです。
Asanaなら、タスクやプロジェクトの可視化ができ、スムーズな情報共有が実現できるプロジェクト管理ツールです。操作が簡単なうえに、リアルタイムで業務進捗状況を管理できるため、滞りなくプロジェクトを進行できるでしょう。
なお、DSKではAsanaの導入および、運用のサポートサービスも提供しています。Asana認定プロ資格の保有者が、サポート対応してくれるため、安心して導入、運用を始められます。