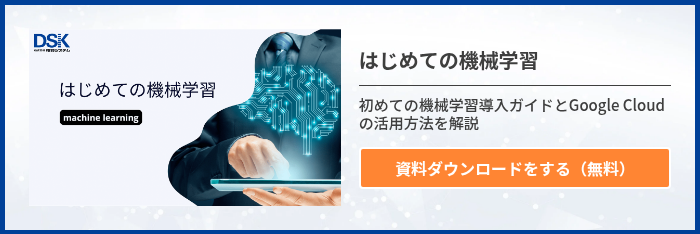AIと機械学習は、高度なデータ分析に利用されており、さまざまな業界や目的で活用されています。AIと機械学習の活躍によって、以前はできなかったビッグデータの解析や自動運転も可能になり、社会の発展やビジネスの成長に大きく貢献しています。
AI技術を効果的に活用するには、AIや機械学習、深層学習(ディープラーニング)に関する基礎知識が必要です。それぞれの用語や違いを学んで、AI技術を自社に導入する際に役立てましょう。
この記事では、機械学習の定義や、AI、深層学習(ディープラーニング)との違い、機械学習の種類やできることなどを解説しています。AIと機械学習についてわかりやすくまとめた内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。
機械学習とは?AI・深層学習との違いも解説
機械学習を正確に理解するために、まずは機械学習の定義や、AI(人工知能)、深層学習(ディープラーニング)との違いを把握しておきましょう。
機械学習の定義
機械学習とは、コンピューターが膨大な量のデータを学習し、アルゴリズムに基づいて情報を分析する手法のことです。主にデータの識別や物事の予測を目的として、取り込んだデータからルールやパターンを発見します。
機械学習が近年注目されている理由の1つは、若年層の労働者不足です。日本の労働人口は年々減少しており、限られた人材でいかに効率良く働くかが求められている今、業務効率化による労働者不足の解消に役立つ方法として、機械学習が注目を集めています。
機械学習を活用すれば、人が手動で行っていたあらゆる業務を自動化でき、業務の効率化が可能です。例えば、クレジットカードの不正取引を機械学習によって検知すれば、従業員の負担を大幅に軽減でき、迅速に不正を見つけ出せます。
コンピューターの処理技術が向上した現代では、機械学習はあらゆる業界・用途に活用されており、マーケティングや医療、金融などの専門性の高い分野でも活躍しています。
機械学習とAI (人工知能)の違い
AI(人工知能)とは、明確な定義はありませんが、一般的に人間の知的行動をコンピューターが学習して再現するシステムの総称です。Artificial Intelligenceの頭文字を取ってAIと呼ばれており、人間のように計画を立てたり、特定の問題を解決したりできます。
機械学習は、AIを実現する技術の中核であり、AI技術の一種です。現代のAIは、機械学習を基盤としているものが多くあり、ビッグデータの解析や自動翻訳、自動運転などの高度な機能や技術の実現に貢献しています。AIの登場によって、業務のサポートはもちろん、人間の手だけでは難しかったことも実現できるようになりました。
機械学習と深層学習(ディープラーニング)の違い
機械学習と深層学習では、ニューラルネットワークの構造が異なります。ニューラルネットワークとは、人間の脳にある神経細胞の仕組みをモデルにした技術です。
機械学習では、ニューラルネットワークが「入力層・1〜2層の隠れ層・出力層」という構造になっている場合が多いですが、深層学習は「隠れ層」が何十層にもなっています。(機械学習にも「隠れ層」が2層より大幅に多いものもあります)深層学習は、ニューラルネットワークの構造が何層にも分かれているため、機械学習よりもさらに複雑なデータ処理が可能です。
また、機械学習と深層学習では、データの特徴量の扱い方も異なります。データの特徴量とは、特定のデータの特徴を定量的な数値で示したもので、AIが物事の意思決定や予測を行うために必要不可欠な要素です。
機械学習では、人間が特徴量を設定しますが、深層学習では、コンピューターが自らデータの特徴量を見つけ出します。この違いが、深層学習がより複雑なデータ処理を可能にする理由の一つです。特徴量の設定工程がないため、特徴量を設計しにくい分野では、深層学習の活用が有効です。
AI(人工知能)の4つのレベル
AIには、1〜4のレベルがあります。レベルごとの特徴を確認して、AIの理解を深めましょう。
レベル1:単純な制御プログラムを持つAI
レベル1のAIは、事前に設定されたルールに従って処理を実行するため、人工知能としての機能は極めて低いものです。条件分岐によって構成された制御プログラムは、ほとんどが単純な出力のみ実行できるように作られており、特定のタスクを実行するためにのみ動作します。
レベル1のAIは、身近な生活で多く活用されており、洗濯機の自動的に重さを測定できる機能や、家庭用エアコンの自動温度調節機能が例として挙げられます。販売されている家電製品に「AI搭載」と表記されている場合は、ほとんどがレベル1のAIです。
レベル2:最適な行動パターンを選択するAI
レベル2のAIは、複数の行動パターンから最適なものを自ら選択できるAIです。自身で学習はできないため、あらかじめ行動パターンのデータを与える必要があります。
レベル2のAIの代表的な例は、質疑応答システムや掃除ロボットです。質疑応答システムは、自然な言語で質問や回答を自動で実行でき、掃除ロボットは、物や壁などの障害物を認識して移動しながら自動で掃除ができます。
レベル3:機械学習を取り入れたAI
レベル3のAIは、大量のデータから自動でルールやパターンを学習できるAIです。自ら考え学習して、適切な行動を選択できます。学習データの用意やデータの特徴量の設定は人間が実行しなければなりませんが、レベル1〜2のAIと比較して、より多様な出力が可能です。ただし、AIの出力品質は学習データの種類や数に依存するため、慎重なデータの品質管理が求められます。
レベル3のAIの代表的な例は、Googleをはじめとした検索エンジンです。検索エンジンは、ビックデータから抽出したコンテンツの質を判別して、質の高いコンテンツを優先的にユーザーへ表示し、有用な情報を提供できます。
レベル4:ディープラーニングを取り入れたAI
レベル4のAIは、人間による指示なしで自動でルールやパターンを学習するだけでなく、学習データを自ら収集できます。機械学習よりもさらに多くのデータ処理ができ、AI自ら学習パターンを学ぶため、処理を重ねるごとに出力品質が向上します。
レベル4のAIの代表的な例は、自動運転です。自動運転に搭載されたAIは、安全な運転を実現するために、車を運転する際に注意すべきところを自ら学習し、自動かつ安全な運転を実現します。
機械学習の3つの種類
機械学習には、3つの学習方法があります。機械学習における学習方法の種類は、以下の通りです。
| 機械学習における学習方法の種類 | 概要 |
| 教師あり学習 | コンピューターにデータに併せて正解を示し、コンピューター自ら正解を見つけ出せるようにする学習方法 |
| 教師なし学習 | コンピューターに正解を示さないままデータのパターンやルール、特徴を学習させる方法 |
| 強化学習 | 教師あり学習の過程でコンピューターが出力した結果に点数をつけて評価し、より優れたものを学習させる方法 |
それぞれの種類の特徴を詳しく確認して、機械学習の基礎知識を身につけましょう。
教師あり学習
教師あり学習では、正解となる教師データを事前に読み込み学習させて、正解となる結果を提示できるようにする学習方法です。正解が明確にある場合に有効な学習方法で、教師データの質と量が充実するほど精度が向上します。
十分に学習が進めば、正解の無いデータが与えられても、コンピューター自身が正解を見つけ出して提示できます。教師あり学習は、売上などの予測や、オブジェクトの識別などに使われる学習方法です。
教師なし学習
教師なし学習は、正解となる教師データを与えず、コンピューターが自らデータの特徴量を学習する方法です。与えられたデータからコンピューター自身がパターンやルールを見つけるため、未知のデータを与えても対応できます。教師なし学習は、異常の検出や、データを分類したいときによく使われる学習方法です。
強化学習
強化学習は、教師あり学習の過程でコンピューターが出力した結果に点数をつけて評価する工程を繰り返し、試行錯誤を促して出力の精度向上を図る学習方法です。出力の結果と評価を紐付けて学習し、点数が最大になる行動パターンを導き出します。強化学習は、自動運転やロボット制御、囲碁や将棋といったボードゲームのAIなどに使われている学習方法です。
機械学習ができる5つのこと
機械学習はさまざまな用途に活用できる優れた技術で、大きく分けると以下の5つのことを実行できます。
- データの分類
- データの圧縮・可視化
- データのグループ化
- データに基づいた予測
- ニーズの予測・推薦
機械学習ができることを把握して、自社で導入した場合にどのように活用するかを具体的にイメージしましょう。
データの分類
機械学習は、分析対象のデータをカテゴリー別に分類する「クラス分類」を実行可能です。機械学習のクラス分類によって、具体的には以下のようなことができます。
- 任意の画像を識別して分類する
- 過去の天候データを分類して天気を予測する
- 受信したメールがスパムメールや迷惑メールではないか判断する
データの圧縮・可視化
機械学習は、データの圧縮・可視化をして、不必要な情報をなくす「次元削減」という処理を実行可能です。データの圧縮・可視化により情報が整理されて、機械学習の出力品質を向上できます。次元削減は、主にデータ量が多くなりやすい顔認識で活用されている技術です。
データのグループ化
機械学習では、一定のルールに基づいてデータをグループ化する「クラスタリング」を実行できます。機械学習の学習方法である「教師なし学習」にあたる手法で、クラスタリングにも以下のような種類があります。
- 階層クラスタリング:1つのデータ群から、最も類似性の高い組み合わせのものを順に抽出して、グループ化する手法
- 非階層クラスタリング:異なる性質のものが集まったデータ群から、類似性の高いものを見つけて階層を構築せずにグループ化する手法
データに基づいた予測
機械学習は、実績データに基づいて、新規の数値を予測する「回帰」という処理を実行可能です。回帰を行う主な目的は、「相関関係と因果関係に関する分析」と「将来の数値予測」です。回帰は、教師あり学習にあたるもので「線形回帰」「ロジスティック回帰」といったアルゴリズムがあります。
ニーズの予測・推薦
機械学習は、データをもとに顧客のニーズや嗜好を予測しておすすめを提示する「レコメンデーション」ができます。顧客の購入履歴や閲覧しているものと類似した商品の情報が活用されて、顧客のニーズに合った商品を表示します。オンラインショッピングにおける売上の向上につながるため、ECサイトには欠かせないシステムです。
レコメンデーションには、関連商品を表示して追加購入を促す「クロスセル」や、さらに高いグレードの商品を表示して購入単価をアップさせる「アップセル」といった方法があります。
ビジネスにおける機械学習の活用事例
機械学習の活用事例を、以下の3つ紹介します。
- 需要・売上を予測する
- 機器の故障を予測する
- 顧客をグループ化する
機械学習は、汎用性が高く幅広い分野で活用されています。活用事例を詳しく確認して、機械学習を活用する際の参考にしましょう。
需要・売上を予測する
需要と売上の予測は、機械学習の代表的な活用方法です。過去の在庫情報や売上実績のデータをもとに、将来の需要と売上を予測できます。機械学習の予測に従って仕入れや生産を最適化すれば、売上向上だけでなく、コスト削減にもつながります。
機械学習の需要と売上の予測は、顧客属性やキャンペーン情報、天候データなどの情報も組み合わせることで、精度の向上が実現可能です。
機器の故障を予測する
機械学習は、製造業での故障診断にも活用されている技術です。コンピューターが過去の修理実績に関するデータを学習して、最適な部品を提示できます。機械学習による故障診断を活用すれば、故障が起きる前に対処でき、機器の停止時間短縮や製造業務の安定化につながります。
また、修理サービスを提供している企業の場合は、業務効率化や品質向上、属人化の解消などのメリットも得られるでしょう。
顧客をグループ化する
機械学習は、マーケティングの分野でも活用されています。購買実績をはじめとしたデータをもとに顧客をグループ分けして、以下のような分析結果が得られます。
- 特定の商品を購入している顧客の属性はどういうものか
- ECサイトの再利用が多い顧客の特徴はどういうものか
- サービスの解約が多い顧客はどういうグループか
上記のような分析結果が把握できれば、顧客満足度や売上向上につながる効果的なマーケティング施策の実行に役立つでしょう。
以下の記事では、機械学習の活用事例をより詳しく解説しています。機械学習に興味のある方は、以下の記事も併せてご覧ください
機械学習を活用して業務効率化を実現しよう
機械学習とは、AIやコンピューターに膨大な量のデータを与えて、学習させる技術です。AIを実現するための中核と言える技術で、汎用性が高いため、製造業や運送業、小売業、アパレル業などのあらゆる業界で活用されています。
機械学習には、教師あり学習と教師なし学習、強化学習の3つの種類があり、目的によって異なる学習方法が採用されます。例えば、売上予測やオブジェクトの識別には教師あり学習が適しており、異常検知やデータ分類には、教師なし学習が最適です。目的に合わせた機械学習の学習方法とアルゴリズムを活用することにより、業務効率化やコスト削減、人手不足解消などのさまざまなメリットが得られます。
現代のAIは、機械学習を活用しているものが多く、ビッグデータの解析や自動運転などの高度な機能や技術はAIが支えています。AI技術を業務に活用したい方は、機械学習の導入を検討すると良いでしょう。
機械学習は、深層学習(ディープラーニング)よりも低コストかつ短期間で導入できるため、社内の業務効率化やコスト削減に取り組みたい方におすすめです。電算システムでは、機械学習についてわかりやすく解説した資料を無料で提供しています。機械学習に興味のある方や、より知識を深めたい方は、以下のページからダウンロードできる資料をぜひご覧ください。
監修者

<保有資格>
・Professional Data Engineer
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- ai 機械学習 ai 学習