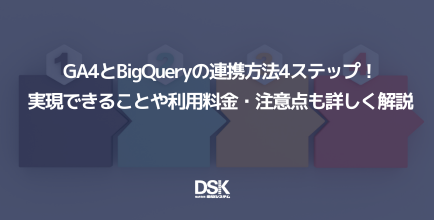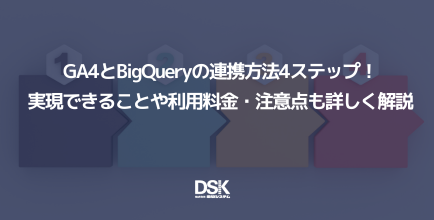社内に蓄積されたビッグデータを活用したいものの、どのような手段を採用すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。このような際は、今回紹介するデータウェアハウス(DWH)を導入するのがおすすめです。
データウェアハウスとは、ビッグデータをはじめとする膨大な量のデータを一元管理するためのシステムです。基幹システムや顧客管理システム、販売管理システムなどからデータを集約できます。また、BIツールと連携してデータの分析や可視化もできるため、本格的なデータ活用を行う場合に欠かせないツールだといえるでしょう。
本記事では、データウェアハウスの特徴や機能、導入メリットを詳しく解説します。さまざまな活用例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
データウェアハウス(DWH)とはデータ分析に特化したデータベース
データウェアハウス(Data Ware House/DWH)は、直訳すると「データの倉庫」という意味で、大量のデータを蓄積・管理するシステムを指します。
データウェアハウスを導入することで、さまざまなデータソースから収集した情報を一元的に管理し、整理することが可能になります。これによりデータ分析の効率や精度が向上し、部門やシステムを横断したデータ活用が実現します。結果としてデータドリブン経営の基盤構築が可能です。
データベースとの違い
データウェアハウスと同様、データベースも大量のデータを蓄積・管理するためのシステムです。ただし、同じような役割がある両者にもいくつか違いが存在します。
最大の違いは、データウェアハウスは分析に最適化されているという点です。一般的に別々のシステム同士ではデータの保存形式が異なるため、一方のシステムからもう一方へとデータを転送する際に大きな負荷がかかります。データベースはこのような処理に膨大な時間を要することがありますが、データウェアハウスはより迅速に処理が可能で、データ収集から分析へとスムーズに移行できます。
また、DWHの特徴として、大容量のストレージを備えている点もあげられます。通常のデータベースでは、データ量が増加すると容量の制限を超えるため、詳細データではなく集計済みのサマリデータとして保存する必要が生じます。その結果、長期間にわたる顧客動向や売上推移といった分析が困難になりがちです。
データレイクとの違い
データレイクとは、異なるソースから収集したデータを一元的に管理し、蓄積できるリポジトリ(貯蔵庫・収納庫)のことです。さまざまなデータを蓄積できるデータウェアハウスと似ていますが、役割や仕組みが異なります。
データウェアハウスは、社内に点在するデータを集約するためのツールであり、各種アプリケーションやデータベースから情報を収集します。データの保存形式や項目名が統一されているため、ユーザーにとって閲覧しやすい形で表示され、必要なデータを簡単に検索できるのが特徴です。
一方、データレイクは、テキストやGPSデータなど、多様なデータをそのままの形式で保存・管理するツールです。保存されたデータは未処理の状態のため、用途に応じた柔軟な活用が可能ですが、その分データウェアハウスよりも大容量のストレージが必要になり、データの統一的な管理が難しい点が課題となります。
データマートとの違い
データマートとは、企業の情報システムに記録・蓄積されたデータのなかから、利用部門や用途、目的に応じて必要な情報を抽出・集計し、使いやすい形で格納したデータベースのことです。
データウェアハウスは、基幹システムなど複数のシステムから必要なデータを収集し、目的別に整理して時系列で蓄積した統合データベースです。データマートは、このデータウェアハウスのなかから、特定の目的に応じて抽出されたデータの集合体を指します。
そのため、データウェアハウスよりもデータマートのほうが、分析対象が絞り込まれます。より小規模なストレージで済むため、比較的安価に初期構築できるのが利点です。
BIツールとの違い
BIツールとは、企業が保有するさまざまなデータを分析し可視化することで、経営や業務の改善に活用するためのソフトウェアです。データウェアハウスはデータ分析に強みを持つデータベースでもあることから、BIツールと役割が似ているようにも思えますが、両者には違いがあります。
データウェアハウスの役割は、社内の複数のシステムからデータをエクスポートし、一元管理できるように最適な形式で集約・蓄積することです。一方、BIツールの役割は、データウェアハウスに蓄積されたデータを取り出し、分析やグラフ化を行い、視覚的に分かりやすく可視化することにあります。
そのため、データウェアハウスはBIツールの一部と捉えることもできます。いい換えれば、BIを実現するために企業内に点在するデータを大規模なデータ倉庫として整理・保管するのがデータウェアハウスであり、そのデータを活用するためのツールがBIツールです。BIツールにはさまざまな種類があり、データの集計、分析、マイニング、加工など、それぞれの用途に応じたツールが存在します。
データウェアハウスでできること
データウェアハウスには次のような機能があります。
- サブジェクトの整理
- データ統合
- データの整理
- データの永続的な保管
それぞれの機能を理解することでデータウェアハウスでできることをイメージしやすくなります。機能ごとの特徴を解説します。
サブジェクトの整理
サブジェクトとはデータの内容を指し、「商品」や「顧客」といった項目が該当します。データウェアハウスに蓄積されるデータは、さまざまな基幹系システムから集約されたものですが、システムごとに整理されている状態では、せっかく集約しても十分に活用できません。
そのため、システム単位ではなく、サブジェクトごとにデータを整理する機能が求められます。これにより、分散していたデータを統合し、一つのまとまったデータとして扱えるようになります。例えば、「商品」単位で整理する場合、各システムに存在する商品データが統合され、システムを横断した高度な分析を行えます。
データ統合
データウェアハウスは、複数のシステムから収集された異なるフォーマットのデータを、統一されたスキーマに変換して保管します。
例えば、会員ID一つを取っても、システムによってはメールアドレスとして扱われる場合や、文字列や整数として保存される場合があります。このような違いがあると、同じ会員であっても別の会員として認識されてしまい、正確な分析ができなくなる可能性があります。その点、データウェアハウスを活用すれば、こうしたデータの不一致を防ぎ、整合性を高めることが可能です。
この処理には、一般的に「ETL(Extraction・Transformation・Loading)」と呼ばれるツールが使用されます。ETLは、各システムからソースデータを抽出し、統一されたスキーマに変換したうえで、データウェアハウスへと自動的に書き出す役割を担います。
データの整理
データウェアハウスでは、現在のデータだけでなく過去のデータも時系列で整理されます。
一般的なデータベースは最新の情報を優先します。例えば、ある会員が自身の保有ポイントを調べる際は、現在のポイントが画面上に表示されるのが一般的です。過去のデータまで参照すると処理時間が増えてしまうため、最新の情報を優先的に表示します。
一方、上記の例をデータウェアハウスにあてはめると、その顧客が会員になってから現在に至るまでのポイントの推移をすべて保存します。これにより、現在の情報だけでなく時系列の流れを把握できるため、ビジネス上の意思決定に活かしやすくなります。
データの永続的な保管
データウェアハウスでは、一度格納されたデータは更新・削除されることなく長期間保管されます。時系列で整理された膨大なデータを対象にすることがデータウェアハウスを活用した分析の目的です。
ただし、データウェアハウスはあくまで一つのストレージに過ぎないため、無限にデータを保存し続けることはできません。容量やコストの制約から限界を迎えることがあり、その際には優先度の低いデータをアーカイブしたり、削除したりといったメンテナンスが必要となる場合もあります。
データウェアハウスを導入する3つのメリット
データウェアハウスを導入すると、データ活用の効率性向上やセキュリティ強化など、さまざまなメリットが生まれます。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
データを加工・統合する際の手間を省ける
データウェアハウスを導入する最大の利点は、データ統合や加工の手間を省けることです。従来のシステムでは、どこにどのようなデータがあるのかがわかりにくく、収集や集計に時間がかかるなど、さまざまな課題が存在していましたが、データウェアハウスを用いることでこれらの問題を解決できます。
データウェアハウスは、面倒な処理を行うことなく、複数のデータを一元化して集約することが可能です。さらに、複数のデータをサブジェクトごとに自動分類するなど、迅速なデータ処理や高度な検索が実現できます。また、データは時系列で保管されるため、「誤って上書きしてしまった」「どのデータが最新か分からない」といった不安も解消されます。
セキュリティやコンプライアンスの強化につながる
企業ではさまざまなシステムが個別に運用されていますが、データウェアハウスを活用することで、各システムの履歴や実績、ログなどを効率的に保存し、セキュリティを確保しながら迅速かつ簡単に集計・分析できるようになります。
例えば、システムへのログイン・ログアウト情報をもとに業務状況を把握したり、個人情報へのアクセスログを収集したりすることで、情報漏洩の防止や緊急時の原因追及に役立ちます。業務状況の可視化や不正行為のリスク軽減といった点で、データウェアハウスは健全な業務運営をサポートします。
部門を超えたデータ活用が可能になる
データウェアハウスは複数の部門からデータを集約して整理しているため、部門を超えたデータ活用が可能です。
例えば、小売店の接客担当者が顧客の動向を把握するために、顧客情報や商品情報を分析したいというニーズがあったとします。販売管理システムのデータベースからデータを抽出し加工して分析することはできますが、時間がかかるのが難点です。
その点、データウェアハウスでデータが整理されていれば、すぐに分析を始められます。大量のデータを扱うこともできるため、より長期間にわたるデータをもとに分析することも可能です。
データウェアハウスの活用例4選
データウェアハウスは、内部に蓄積されたデータの活用方法次第で、さまざまなケースへと発展できます。具体的にどのようなケースでデータウェアハウスが活用されているのか、複数の例を紹介します。
CRMツールと連携した顧客分析
CRMツールとは、システム上で顧客情報を一元管理するためのツールです。顧客の属性や問い合わせ情報、行動履歴、購買履歴など、顧客に関するあらゆるデータを1ヶ所に集約できます。CRMツールに蓄積された顧客情報をデータウェアハウスに統合することで、より質の高い顧客分析が可能になります。
例えば、Webサービスやアプリケーションを運営している小売業の場合、顧客の属性や購買情報と、Webやアプリケーション内での行動データを結び付けることで、より詳細なデータ分析を行えます。このような分析により、パーソナライズされたマーケティング施策の実施や、個別対応したサービスの提供につながります。
在庫管理
データウェアハウスを活用することで、効率的な在庫管理システムを構築できます。販売データや仕入れ情報、倉庫の在庫状況、市場トレンドなどのデータを統合し、リアルタイムで分析できるためです。
これにより需要予測の精度が向上し、適正在庫を維持しやすくなります。さらに、サプライチェーン全体の可視化が可能になることで、リードタイムの短縮やコスト削減にも効果を発揮するでしょう。
不正検知
金融業界や電子商取引を行う企業でもデータウェアハウスが活用されています。データウェアハウスを利用すると、取引データや顧客情報、デバイス情報、位置情報などのデータを統合し、リアルタイムで分析を行えます。通常と異なる取引パターンや不審な行動を迅速に検出できるため、不正行為を未然に防げるのが利点です。
IoTデータ分析
データウェアハウスは、生産設備の稼働状況やモノ・人の動きといったIoTデータの分析にも役立ちます。例えば、ファシリティ事業の強化に向けて、ビルの設備管理に特有のノウハウを活かし、圧縮率が高く高速なデータ分析環境を構築することが可能です。
さらに、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)の推進にもデータウェアハウスの活用が欠かせません。データウェアハウスを活用することで、公共交通機関のデータや利用者の決済情報など、多様なデータを一元的に管理できるようになります。
データウェアハウスを導入するならBigQueryがおすすめ
データウェアハウスにはさまざまな製品がありますが、なかでもGoogleが提供するBigQueryの導入を検討してみてはいかがでしょうか。BigQueryとは、Google Cloud上で提供されているデータウェアハウスで、大量のデータを高速に処理できる特徴があります。
ビッグデータが多様な分野で活用されるなか、大量のデータを処理する必要がある場面が増えています。通常、数TBや数PBに達するデータを処理するには時間を要しますが、BigQueryを使用すれば、これらの処理を数十秒で完了させることが可能です。そのため、データのリアルタイム分析や大規模なログ解析などのケースでも、BigQueryは大いに役立ちます。
Google CloudにはBigQueryのほかにも、GoogleのITインフラを利活用できるCompute Engineや、容量無制限のストレージサービスであるCloud Storage、API管理に特化したCloud Endpointsなど、さまざまなサービスが用意されています。それらのサービスを自由に組み合わせて活用できるのもメリットです。
データウェアハウスを導入して効率的なデータ活用を
データウェアハウスを利用することで、さまざまなデータソースから取得したデータを効率的・一元的に管理できます。また、格納したデータはETLツールを使って加工したり、BIツールに移行して分析・可視化を行ったりと、最終的なデータ活用へと発展できるのが特徴です。データウェアハウスにはさまざまな製品がありますが、初めて導入するならBigQueryを活用するのがおすすめです。
従来の方式とは異なり、BigQueryはサーバーを使用せず、チューニングの必要もなく利用できるという大きな特徴があります。データベース管理において必要だったインデックス作業もいらず、誰でも簡単に大容量のデータ分析を行えるのが利点です。また、Googleが提供するほかのサービスとのシームレスな連携が可能で、Googleのデータ分析プラットフォームLookerと連携することで、データの統合や分析、変換に加え、レポート作成や可視化も行えます。
BigQueryの特徴や機能、活用方法については、こちらの資料で詳しく紹介しています。無料でダウンロードできるため、データウェアハウスの導入を検討している方は参考にしてください。
監修者

<保有資格>
・Professional Data Engineer
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- データ ウェア ハウス