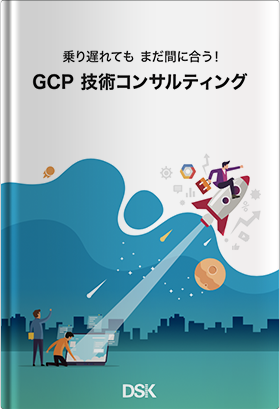データベースを利用している方のなかには、データ管理をより効率化したいという方がいらっしゃるのではないでしょうか。データベースにおけるデータ管理の効率化は、業務全体の効率アップにつながります。データベースでの管理を効率化するには「DBMS」の導入がおすすめです。DBMSは、安全性の高いセキュリティ環境のなかでデータ管理を効率化できるシステムです。
そこでこの記事では、DBMSの概要、DBMSとデータベースとの関係性や表計算ソフトとの違い、DBMSの主な機能、DBMSの種類、DBMSを活用するメリットなどを解説します。DBMSについて網羅的に理解できる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。
DBMSとはデータベースの機能を提供するソフトウェア
DBMSの概要について、以下の内容に沿って詳しく解説します。
- データベースとは
- DBMSとは
概要を確認して、DBMSを理解するために必要な基礎知識を身につけましょう。
データベースとは
データベースは、あらゆるデータを整理・保管して、効率的なデータ利用を可能にするデータの集合体です。データベースを活用すれば、膨大なデータ量であっても高速で処理できるため、在庫管理や顧客管理におけるさまざまなデータを取り扱う際に使用されています。データベースに備わっている主な機能は、以下の通りです。
- データの蓄積
- データの読み込み
- データの作成
- データの更新
- データの削除
データベースは、顧客管理や予約管理、業務管理、在庫管理などに多く活用されており、企業や組織の業務をサポートしています。
DBMSとは
DBMSは、データベースを運用・管理して、外部のソフトウェアからのリクエストに応じてデータベースを操作するシステムです。「Database Management System」の頭文字を取っており「データベース管理システム」を意味します。
DBMSを利用すれば、ユーザーはアプリケーションを通じて必要なデータを出力でき、データの追加や更新、削除なども効率的に行えます。DBMSは、多くの企業や組織でデータベースを効率的に管理する方法として導入されているシステムです。
DBMSと表計算ソフトの違いを解説
企業のなかには、データ管理の方法としてDBMSではなく、表計算ソフトを利用している場合もあります。表計算ソフトは、さまざまなデータの計算・分析を可能にするアプリケーションソフトウェアです。代表的なソフトウェアには、ExcelやGoogleスプレッドシートがあり、データを入力して簡単に一覧表を作成できます。
表計算ソフトは、本来計算を目的としたソフトウェアであるため、計算と異なる用途で使うには、限界があります。データ抽出ができる「フィルター」機能やデータの並び順を一定の条件で変更できる「並べ替え」機能を使えば、データベースに近い処理が可能ですが、データベースほどの処理速度や機能性は発揮できません。
また、表計算ソフトは膨大なデータ入力を想定したソフトウェアではないため、一定のデータ量を超えた場合は、起動や動作が遅くなります。データ量が多ければ、画面をスクロールするだけでも手間がかかり、データ管理や分析に多くの時間を要します。数万件を超えるデータを管理する場合は、膨大なデータ量をすばやく処理できるDBMSがおすすめです。
DBMSの主な5つの機能
DBMSの主な機能は、以下の5つです。
- データベースの定義
- データベースの操作
- データベースの制御
- 排他制御
- 障害回復
機能を確認して、DBMSの理解を深めましょう。
データベースの定義
「データベース定義機能」は、DDL(データ定義言語)という言語でスキーマを定義する機能です。スキーマは、データベースの構造を表す概念を意味します。「スキーマを定義する」とは、データベースを利用するための準備として、データの格納形式やデータベースの構造を定義することを表します。DDLは「Data Definition Language」の頭文字を取った用語で、SQL(※1)の一種です。
※1. SQL:データベースを操作するために使用される言語のこと
データベースの操作
「データベース操作機能」は、日々の業務で利用するデータベースでのデータ更新や情報検索をするための機能です。ユーザーは、DMLという言語を使用して、必要なデータの更新や検索を実行します。DMLは「Data Manipulation Language」の頭文字を取った用語で、日本語では「データ操作言語」と訳されます。
データベースの制御
「データベース制御機能」は、データベースにおけるユーザーのアクセスを制御して、安全に保護する機能です。「データベース制御機能」を利用すれば、細かいレベルでユーザーのアクセスを制御でき、データベース内のデータを安全に管理できます。
「データベース制御機能」では、DCLという言語を使用して、不正なユーザー認証やアクセスの防止、障害や同時更新が発生した際のアクセス制御によるデータの保護が可能です。DCLは「Data Control Language」の頭文字を取った用語で、日本語では「データ制御言語」と訳されます。
排他制御
「排他制御機能」は、データ更新を実行する前に、対象のデータをロックして、自分以外のユーザーがデータの読み込みや書き込みなどの更新ができないようにする機能です。「排他制御機能」を利用すれば、在庫管理や顧客管理などにおけるデータ更新のエラーを防止できます。
ユーザーがデータ更新をする際は、データがロックされていないかどうかを確認してから実行します。データがロックされている場合は、ほかのユーザーが行っているデータ更新が終わってから、処理を実行しなければなりません。
障害回復
「障害回復機能」は、プログラムやシステムの障害が発生した際に、自動でデータベースを復旧できる機能です。データベースに障害が発生した際の復旧方法には、以下の2つがあります。
- ロールフォワード(前進復帰):バックアップファイルをもとにデータを復旧して、バックアップファイル以降の更新データを再現する方法
- ロールバック(後退復帰):途中だった処理を停止して、障害が発生する前の状態まで戻す方法
DBMSには4種類ある
データベースにはいくつかの種類があり、DBMSにもそれぞれの機能を提供するための専用システムが複数あります。DBMSの種類は、以下の4つです。
- リレーショナル型
- 階層型
- ネットワーク型
- NoSQL
それぞれのメリットとデメリットは、以下の表にまとめています。
| DBMSの種類 | メリット | デメリット |
| リレーショナル型 |
|
|
| 階層型 |
|
|
| ネットワーク型 |
|
|
| NoSQL |
|
|
DBMSの種類を確認しながら、それぞれの特徴を詳しく把握しましょう。
リレーショナル型
リレーショナル型は、表(テーブル)という概念を使ってデータの一覧を整理できるDBMSです。関連のあるデータを表(テーブル)の形でまとめて、行単位でデータを操作します。業務システムにおいては、リレーショナル型が主流になっています。
リレーショナル型のメリットは、データの重複登録を防止でき、簡単かつ柔軟にデータを取り出せる点です。複数の表でデータベースを構成しており、データの追加や削除などの処理に伴う負担を低減して、効率的に実行できます。リレーショナル型のデメリットは、膨大なデータ量を取り扱う際や、データを管理するプログラムが複雑な場合に処理速度が遅くなる点です。
階層型
階層型は、ツリー構造でデータを蓄積するDBMSです。上層から下層に分岐する構造になっており、親データと子データで関連づけてデータが保管されています。1つの親データに対して複数の子データの関連づけが可能です。
階層型は、特定のデータへアクセスする手順が1通りしかありませんが、ほかの種類と比較してデータ検索の処理速度が速いというメリットがあります。階層型のデメリットは「多対一」や「多対多」の形式でデータを管理した場合に、データの重複登録が発生して、冗長化しやすい点です。
ネットワーク型
ネットワーク型は、階層型と同じく、関連性のあるデータを結びつけてツリー構造でデータを蓄積するDBMSです。階層型は1つの親データに対して複数の子データを関連づけできますが、ネットワーク型では、複数の親データに対して複数の子データを関連づけられます。
ネットワーク型のメリットは「多対一」もしくは「多対多」のデータ構造をとって、重複したデータの登録・管理が防止できる点です。「多対多」の構造によって、データ管理が複雑化しやすいデメリットがあるため、適切に運用するには、専門知識やプログラム開発スキルを要します。データ構造を正しく理解していなければ、必要なデータへのアクセスも難しく、システムの導入にはIT人材のサポートが必要不可欠です。
NoSQL
NoSQLは、あらゆる形式でデータを蓄積できるDBMSです。SQLを使用しないため、データの一貫性を保証できませんが、膨大なデータ量でも高速で処理できるメリットがあります。また、NoSQLは、サーバーの数を増やさなくても、システム全体の処理能力を上げられます。
NoSQLのデメリットは、SQLを使用しないため、データの検索精度が低下したり、複雑な検索がしづらかったりする点です。
DBMSを活用する2つのメリット
DBMSを活用するメリットは、以下の2つです。
- データベースの運用を効率化できる
- データを安全に管理できる
メリットを確認して、DBMSのビジネスにおける役割を把握しましょう。
データベースの運用を効率化できる
DBMSを活用すれば、効率的なデータベースの運用が可能です。企業や団体は、扱うデータが増え続けても、システムのパフォーマンス低下や事業継続性とコンプライアンスへの悪影響を防止しながら、適切にデータベースを管理しなければなりません。
DBMSでは、データベース上のデータを適切にコントロールしながら、必要なデータの読み取りや作成、更新、削除ができます。データへのアクセスと整理が円滑にでき、設定次第でエンドユーザーもデータベースへのアクセスが可能です。組織内のエンドユーザーは、データへのアクセスや共有が簡単にできます。エンドユーザーは必要なデータにアクセスできるため、より迅速な販売と意思決定ができます。
データを安全に管理できる
DBMSを導入すれば、データベースへの不正アクセス防止に役立つアクセス制限や権限設定が可能です。DBMSの利用と併せて、組織内のプライバシーポリシーやデータセキュリティにおけるルールを整備すれば、情報漏えいのリスクも低減できます。
DBMSには、データのバックアップ機能もあるため、操作ミスやシステムの誤動作でデータが破損・紛失しても、バックアップデータから復元可能です。DBMSでデータを安全に管理すれば、安定した企業運営が維持でき、顧客や取引先からの信頼獲得につながります。
DBMSの2つの選び方
DBMSの選び方は、以下の2つです。
- 自社の目的や課題に合わせる
- セキュリティ対策
選び方を確認して、自社に合ったDBMSを見つけましょう。
自社の目的や課題に合わせる
DBMSを選ぶ際は、自社の目的や課題を事前に整理しましょう。組織体制や事業形態によって、最適なITシステムは異なるため、自社の目的や課題に応じたシステム選びが大切です。例えば、リレーショナル型は、精度の高いデータ検索ができる点で、生産管理や人事管理などのマネジメント領域に向いています。また、ビッグデータ分析やリソースを拡張したい場合は、NoSQLが最適です。
セキュリティ対策
DBMSを選ぶ際は、システムのセキュリティ対策も大切です。データベースには、事業活動を通じて収集された多くのデータが保管され、データのなかには機密情報も含まれます。機密情報の漏えいは、企業の社会的信頼を大きく損なう事態になるため、企業規模に応じた適切なセキュリティ対策が求められます。
DBMSを導入する際は、適切な運用・管理体制を整えて、強固なセキュリティ体制を構築しなければなりません。データを安全に保護するために、より安全性の高いセキュリティ対策が構築できるシステムを選びましょう。
ビッグデータの活用は「電算システム」にお任せください
ビッグデータの活用を検討している方は「株式会社電算システム」によるサポートの利用をおすすめします。電算システムでは、Googleの資格取得者を有する専用チームが作られており、Googleシステムの豊富な導入実績を活かして、企業様の目的や課題に合わせたサービス提供が可能です。
Google Cloud は、ビッグデータの分析・活用に便利なクラウド型サービスです。Google Cloud では「Cloud SQL」をはじめとした複数のデータベースサービスを提供しています。Cloud SQLでは、データベースの設定や管理、データベースインスタンス(※1)の拡張、自動フェイルオーバー(※2)の設定など、通常は管理者が行うべきタスクの自動化が可能です。
また、以下のような高度なセキュリティ機能も提供されています。
- データや通信経路の自動暗号化
- 物理的なセキュリティ対策
- 不正アクセスの防止
- 定期的なデータバックアップ
Google Cloud に興味のある方は、Google Cloud の導入によって自社の課題解決に成功した以下の事例をご覧ください。
データを効果的に活用したい方は、無料でダウンロードできる「データ活用」についてまとめた以下の資料をご覧ください。データベースの管理や活用にお困りの方は、Googleシステムの導入実績が豊富な「電算システム」によるサポートの利用をおすすめします。
資料ダウンロード
※1. データベースインスタンス:データベースを管理するメモリー構造のこと
※2. 自動フェイルオーバー:稼働しているシステムやサーバーが停止した際に、待機システムへ自動で切り替える仕組みのこと
DBMSで自社のデータベース管理を効率化しよう
DBMS(Database Management System)は、データベースを運用・管理して、外部からのリクエストに応じてデータベースを操作するシステムです。DBMSを活用するメリットは、大きく2つあります。
- データベースの運用を効率化できる
- データを安全に管理できる
DBMSでは、データベース上のデータを適切にコントロールしながら、必要なデータの読み取りや作成、更新、削除ができます。また、データベースへの不正アクセス防止に役立つアクセス制限や権限設定が可能です。データのバックアップ機能もあるため、操作ミスやシステムの誤動作でデータが破損・紛失しても、バックアップデータから復元できます。
電算システムでは、これからデータを効果的に活用したい企業様に向けて「データ活用」についてまとめた資料を無料で提供しています。資料では、データ収集や加工に加えて、分析を行う体制構築の方法などについても解説しています。社内のデータを有効活用したい企業様は、ぜひご覧ください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- dbms