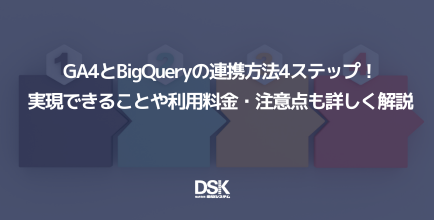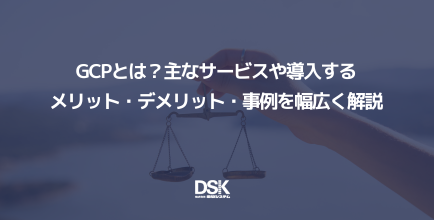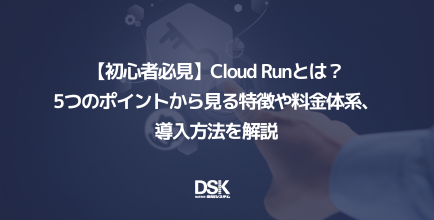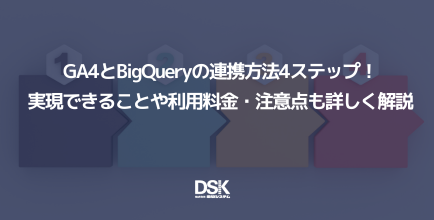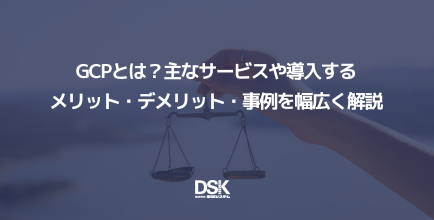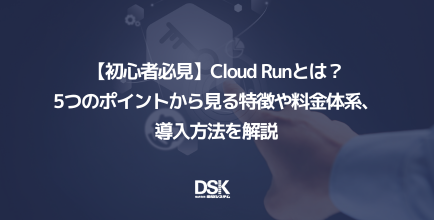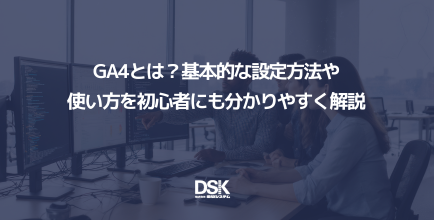企業活動において、データの活用はますます重要になっています。近年はインターネットやSNSの発展もあり、企業が得られるデータの量も種類もこれまでにないほど増えてきました。ただ、社内のデータを効果的に活用できていないとお悩みの方もいるのではないでしょうか。
また、データ管理が不十分で顧客データ流出などのセキュリティインシデントが発生すると、企業の信頼が低下して場合によっては経営にも影響が出る恐れがあります。
こうした背景から注目されている概念が「データガバナンス」です。「データガバナンス」を的確に構築して、正しく運用することで、データをビジネスに有効活用しやすくなる上に、データ活用におけるリスクも軽減できます。
そこで、本記事ではデータガバナンスの意味や役立つフレームワーク、成功させるポイントなどを解説します。企業でのデータ活用やセキュリティに関する悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
データガバナンスとはデータの品質やセキュリティを確保する取り組み
データガバナンスとは、企業が有するデータの品質やセキュリティを確保する取り組みです。以下に示すとおり、幅広い内容をカバーしています。
▼データガバナンスがカバーする範囲(一例)
- インフラ構築
- テクノロジー構築
- プロセスセットアップ
- ポリシーセットアップ
- プロセス更新
- ポリシー更新
- データ処理権限
- データ保護権限
- 組織内責任者の特定
- データの取り扱いに関する組織体制
データガバナンスは企業のコンプライアンスにおいて重要な概念で、企業の正しいデータ活用の促進が策定の目的です。データの保存・処理・セキュリティ管理はシステムが担いますが、システムを的確に運用してデータを保護するには、データガバナンスの構築と遵守が求められます。
データガバナンスとデータマネジメントなどの用語との違い
データガバナンスには、混同しがちな類語が複数存在します。これらの類語とデータガバナンスの違いを理解することで、より深くデータガバナンスを理解することが可能です。ここでは、以下の3つのデータガバナンスの類語との違いを解説します。
- データマネジメント
- マスタデータ管理
- データスチュワードシップ
データマネジメントとの違い
データマネジメントは、データ全体におけるライフサイクルを管理するものです。データガバナンスにおいてはデータ管理の枠組みが着目されますが、データマネジメントにおいては活動・行動が着目されます。ただ、両者とも対象範囲は似通っています。
マスタデータ管理との違い
マスタデータは、企業・組織にとって基盤となるデータです。例えば顧客データであれば「年齢」や「性別」などがマスタデータで、個別の顧客に「年齢」=「30」といったデータが与えられます。
マスタデータ管理は、このマスタデータを一元管理するプロセスで、データマネジメントの一領域です。これにより、データの信頼性や一貫性を担保します。
データスチュワードシップとの違い
データ管理の品質を向上させ、データ資産にアクセスできる状態にするプロセスがデータスチュワードシップです。データスチュワードシップはデータガバナンスより実務的な内容に踏み込んでいます。
データガバナンスを徹底する3つのメリット
ここでは、データガバナンスを徹底するメリットについて3つ解説します。
- データ管理に関するリスクの軽減
- 意思決定の高速化
- データの一貫性の確保
それぞれのメリットを把握し、データガバナンスの重要性を再確認しましょう。
データ管理に関するリスクの軽減
データガバナンスでは、役職や部署ごとに閲覧・編集権限を適切に設定し、データの取り扱いルールを明確にすることで、管理リスクを軽減できます。
また、データの不正利用や情報漏えいを防ぐだけでなく、万が一インシデントが発生した際も、迅速かつ適切な対応が可能になります。
意思決定の高速化
データガバナンスを徹底することで、データの取り扱いルールが全社で明確に統一されます。その結果、情報活用やデータ分析の効率化が可能です。これにより、市場動向や需要分析がスムーズに行え、データに基づく意思決定のスピードが加速します。
データの一貫性の確保
部署・部門ごとにシステムが統一されていないと、情報のサイロ化が発生して情報共有が思うように進みません。この場合、データの取り扱いも部署・部門ごとにバラバラになり、データの一貫性を保つことが困難です。
しかし、データガバナンスで社内システムやデータ管理方法が全社的に統一されれば、データの一貫性が保たれ部門を横断してのデータ活用が可能になります。データ品質を確保しやすくなる上に、データ整理の手間を省いて効率的にデータ分析・活用が可能です。
データガバナンスを構築する手順5ステップ
これからデータガバナンスを構築したい方に向けて、構築手順を5ステップで解説します。
- データ管理における現状把握
- 組織の立案
- 組織設計
- ガイドライン作成
- 施策の実行と改善
一つひとつ手順を踏んで進めることが、成功のポイントです。
データ管理における現状把握
まずは、自社のデータ管理における現状把握を行います。そもそもデータガバナンスは、データの適切な管理・運用につなげることが最大の目的です。現状把握を通じて、データガバナンスで解決したい課題を明確化することで、後述のとおり具体的な施策や管理すべきデータを洗い出せます。
施策の立案
現状から導き出したデータガバナンス上の課題について、その解決策となる施策を立案します。その際には、ルールだけでなく管理すべきデータの決定も必要です。また、全データに共通するルールの設定に加えて、データ管理やデータ分析など個別のルールも合わせて設定する必要があります。
組織設計
全社的にデータガバナンスを構築・運用するためには、チームで進めることが欠かせません。まずは、社内データの取り扱い状況を監視するメンバーが必要です。また、今後のデータガバナンス体制の改善も見据え、データやセキュリティに関しても知見がある人材が求められます。
ガイドライン作成
データガバナンスのルールが明確化しなければ、社内への普及が困難です。そのため、あらかじめデータガバナンスのガイドラインを作成し、それを全社各部門に向けて公表する必要があります。
その際には、ガイドラインを単に公表するだけに留めず、従業員が積極的にデータガバナンスに向けた取り組みを行ってくれるよう促すことが必須です。そのためには、データガバナンスの意義やガイドラインの必要性などについても、十分に説明することが欠かせません。
施策の実行と改善
データガバナンスは、構築したら終わりではありません。運用の過程で新たな課題や改善点が見つかることも多いため、その都度修正が必要です。これにより何度も軌道修正を繰り返すことで、自社に合ったデータガバナンスの方法を模索し、より大きな効果を得られます。
データガバナンスの策定・運用に役立つフレームワーク3選
データガバナンスの策定・運用を進める際には、必要に応じたフレームワークの活用がおすすめです。ここでは、データガバナンスに関する代表的なフレームワークを3つ紹介します。
DMBOKホイール
「DAMA International」が提唱しているフレームワークです。データマネジメントに関して、以下のとおりさまざまな切り口で体系的にまとめています。
▼DMBOKホイールでまとめられている内容の例
- データガバナンス
- データアーキテクチャ
- データモデリングとデザイン
- データストレージとオペレーション
- データセキュリティ
- データ統合と相互運用性
- ドキュメントとコンテンツ管理
- 参照データとマスターデータ
- DWH
- BI
- メタデータ管理
- データ品質
これにより、データガバナンス以外でも、データマネジメント全般で必要な知識と作業内容を把握できます。
データガバナンス成熟度モデル
アメリカのガートナー社が提唱しているフレームワークです。以下6つの成熟度に応じ、各フェーズにおいてデータガバナンスで重要になる考え方やアクションをまとめています。
▼データガバナンス成熟度モデルの成熟度6段階
- unaware(気付かない)
- Aware(気付いている)
- Reactive(反応)
- proactive(積極的)
- Managed(管理)
- Effective(効果的)
これにより、データマネジメントを進める過程で、どのようなアクションを取ればよいかわかります。
データマネジメント成熟度モデル
アメリカのカーネギーメロン大学が提唱しているフレームワークです。以下6カテゴリより、データマネジメントの成熟度を判定でき、そのうち1つにデータガバナンスがあります。
▼データマネジメント成熟度モデルのカテゴリ
- データ管理戦略
- データガバナンス
- データ品質
- データオペレーション
- プラットフォームとアーキテクチャ
- 補助プロセス
これにより、自社で行っているデータマネジメントの強み・弱みを可視化できます。
データガバナンスでよくある3つの課題
ここまでデータガバナンスのメリットや手順などを解説してきましたが、思うようにデータガバナンスを進められていない企業も存在します。その要因は多種多様ですが、よくある課題は以下の3つです。
- 旗振り役の不在でチームがまとまらない
- リソース不足で施策を実行できない
- サイロ化しているデータの一元管理に苦労する
ここでは上記のよくある課題について解説します。
旗振り役の不在でチームがまとまらない
データガバナンスを実行する過程では、部署ごとで意見が対立するといったトラブルが十分想定されます。そのため、データガバナンスを成功させるには旗振り役となるリーダーが必要です。
裏を返せば、リーダーシップをとって指示出しやメンバーとのコミュニケーションを取れる人材を確保できないと、チームがまとまらずデータガバナンスは実行できません。
リソース不足で施策を実行できない
データガバナンスの推進には、ツールの導入や従業員教育など、それに伴う各種施策の実行が必須です。しかし、各種施策を実行するには予算や人員などのリソースが必要になるため、それらのリソースが不足しているとデータガバナンスに関する施策を実行できません。
サイロ化しているデータの一元管理に苦労する
部署や部門ごとに情報が点在している「サイロ化」が発生すると、「同じ情報が別の部署で別々に管理される」「同じ情報が一部の部署では更新されていない」など、情報管理に支障が生じます。そのため、データガバナンスを成功させるにはデータの一元管理でサイロ化を是正しなければなりません。
しかし、データのサイロ化が発生している段階では、どこにどの情報があるか不明瞭であるためデータの一元管理は容易ではありません。
データガバナンスに役立つツール6選
ここでは、データガバナンスに役立つツールを6つ解説します。自社のデータガバナンスで課題を感じている場合、これらのツールを活用することで解決できる可能性があります。
データの統合管理:マスタデータ管理
マスタデータは企業データベースにおいて、基本的な情報・データを意味します。例えば、顧客のマスタデータであれば、住所や性別などが代表例です。マスタデータ管理では、このマスタデータについて統合管理を行います。これにより、データの同期やバージョン管理に役立ちます。
データの解釈や利用:メタデータ管理
メタデータは、各種データについての属性・情報を示します。
▼メタデータの一例
- 作成日時
- 更新日時
- 作成者
- ファイルサイズ
メタデータ管理を行うことで、メタデータの検索や分類をしやすくなります。また、データの品質確保にも役立ち、データの一元管理やデータ活用の効率化に貢献します。
データ分析の頻度を確保:品質管理
データガバナンスの過程では、データの品質管理も欠かせません。なぜなら、品質が高いデータを使わないとデータ分析精度が向上しないためです。データの品質管理を行うため、データ品質管理ツールでは、以下の処理に対応できます。
▼データ品質管理ツールでできる処理
- データプロファイリング
- データマッチング
- データ統合
- データ修正
- データクレンジング
- データ充実化
データ取得・変更のプロセスを追跡:データリネージ管理
データリネージ管理は、データ取得・変更などのプロセスについて、それらの追跡情報を可視化することです。これにより、データを取り扱う中で問題が発生した際に、役立つ判断材料がもたらされます。
データの意味を正しく解釈:用語集
ビジネス用語集は、その組織で用いられている標準的な用語についてまとめたものです。これにより、ユーザーはデータの意味を正しく理解でき、データ資産の共同利用を行いやすくなります。データガバナンスの過程で、用語集のメンテナンスや更新が行われます。
データの概要や保存場所などが一目でわかる:データカタログ管理
データカタログは、社内で取り扱う各種データについて概要・保存場所・使用方法などをまとめたものです。これにより、必要なデータをいち早く発見できる上に、内容を速やかに理解できます。
データカタログ管理を用いることで、メタデータや属性情報の検索などがしやすくなり、データカタログを一層使いこなせます。最近では、AIを活用してより効率的にデータカタログ管理ができるツールも登場しています。
データガバナンスを成功させる2つのポイント
最後に、データガバナンスのポイントについて2つ解説します。ポイントを抑えることで、より全社的にデータの活用が進められます。
最初は無理なくスモールスタートで始める
データガバナンスを実行するには、データの取り扱いに関するさまざまなルール設定を行わなければなりません。そのため、大規模なデータガバナンスをいきなり始めると、取り扱うデータが多い上にルール設定にも手間がかかります。
そのようなことがないよう、まずは一部署や特定のデータなど狭い範囲からスモールスタートすることがおすすめです。
データガバナンスを行う目的の明確化
データガバナンスの目的が明確化していないと、収集・管理すべきデータの種類や保存方法を決定できません。そのため、自社の現状や課題からデータの収集・活用目的を明確にしてから、データガバナンスを行うことが重要です。
データガバナンスで企業のデータを安心かつ効率的に活用
データガバナンスは企業が有するデータの品質やセキュリティを確保する取り組みで、インフラ構築やポリシー更新など幅広い内容が対象です。データガバナンスを正しく構築すれば、データ管理に関するリスク軽減や意思決定の高速化などのメリットを得られます。
データガバナンスを構築するには、データ管理における現状把握から施策の実行と改善までの手順を、1つずつ実施していくことが必要です。DMBOKホイールをはじめ、必要に応じてフレームワークを活用するとより効率的に実行できます。
ただ、旗振り役の不在やリソース不足などの要因があると、データガバナンスを成功させることは困難です。反対に、データガバナンスの構築目的を事前に明確にし、スモールスタートで行うと成功の確率を高められます。
なお、データガバナンスの構築にはデータ基盤の構築が必要で、おすすめツールの1つがLookerです。電算システムでは、Lookerの基本情報をまとめたホワイトペーパー「初めてのLooker」を作成していますので、興味がある方はぜひダウンロードしてみてください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- データ ガバナンス