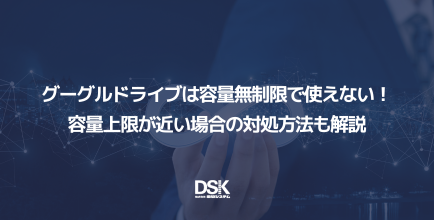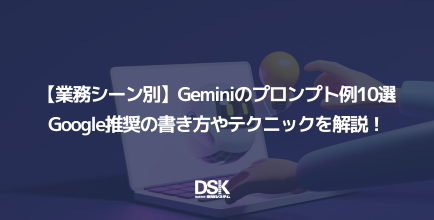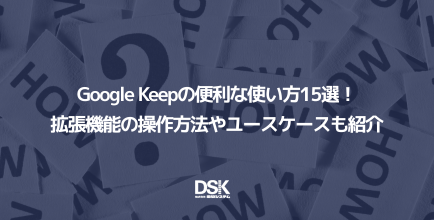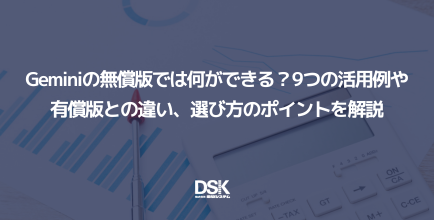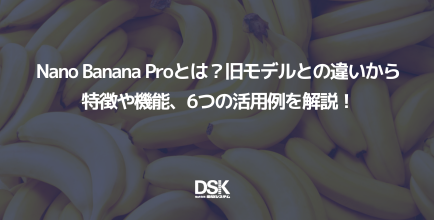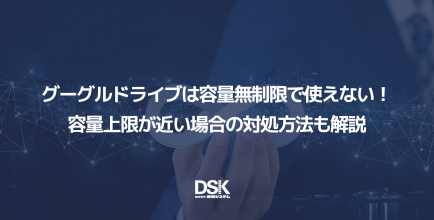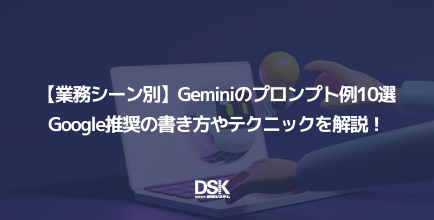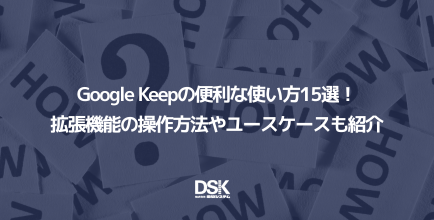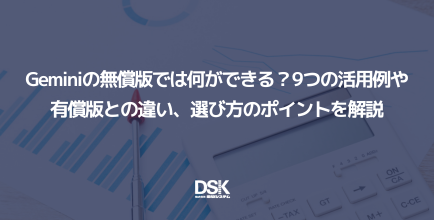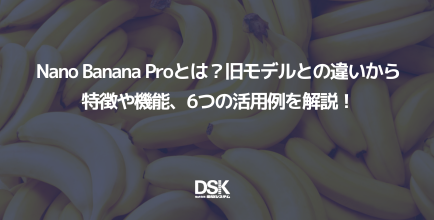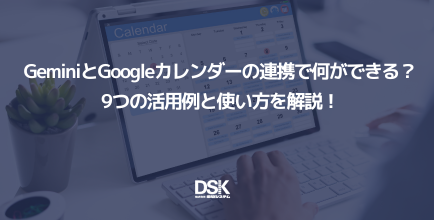社内コミュニケーションとは、従業員同士で日常的に行われる情報交換や交流、雑談などの行為を指します。円滑な社内コミュニケーションは情報共有の質を高め、組織の業務効率や生産性を向上させる大きな要因となります。
しかし、社内コミュニケーション活性化に向けた施策にはさまざまな種類があるため、「どのような施策を展開して良いかわからない」「現状の課題を把握できていない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。社内コミュニケーションを円滑にするには、まず現状の課題を認識し、どのような施策が向いているかを客観的に判断する必要があります。
本記事では、社内コミュニケーションを活性化させるメリットや7種類の施策について解説します。また、他社の事例も紹介しているので、具体的なアクションプランを策定したい方は参考にしてください。

社内コミュニケーションを活性化させる4つのメリット
社内コミュニケーションを活性化させると、業務効率の向上やモチベーションアップなど、さまざまなメリットをもたらします。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
業務効率化や生産性向上につながる
社内コミュニケーションが活発になると、従業員が意見や相談をしやすい環境が整います。これにより従業員が積極的に発言できるようになるだけでなく、自分の言動に対して上司から叱られたり、同僚から否定的な視線を向けられたりすることへの不安も減少します。自然に上司や同僚とコミュニケーションが取れるようになると、従業員はより働きやすさを感じるようになるでしょう。
さらに、報告・連絡・相談がしやすくなり、仕事に対するモチベーションが高まりやすくなるため、結果的に業務の効率化や生産性向上が期待できます。トラブルが発生した際でも、普段から円滑なコミュニケーションを取っていると迅速な対応が可能です。
従業員の離職を防げる
従業員が退職する理由はいくつかありますが、そのなかでも大きな要因の一つが人間関係です。従業員同士のコミュニケーションがうまくいかない場合、人間関係が悪化し、それが精神的なストレスとなり、離職率が高くなる傾向があります。
社内コミュニケーションを活発にすることは、人間関係の悪化を防ぎ、離職率を低減させるために非常に重要です。特に、さまざまな年齢層の従業員がいる企業では、若い従業員が周囲とのコミュニケーションが取れず孤立してしまうケースも少なくありません。したがって、社内コミュニケーションを促進して孤立を防ぐことは、離職率を下げるために重要なポイントとなります。
収益力の向上につながる
円滑なコミュニケーションは従業員エンゲージメントにも良い影響を与えます。エンゲージメントとは、自社に対する愛着や関心を意味します。社内でのコミュニケーションを活性化させることで、従業員同士の関係を強化したり、担当する業務の目的をより深く理解したりすることが可能です。また、企業の目指す方向性も把握しやすくなり、従業員の「この会社に貢献したい」という気持ちを高められます。
エンゲージメントが高い従業員が増えると、日々の業務に対してより高いモチベーションで取り組むため、成果が上がりやすくなります。その結果、企業の収益向上にもつながります。
新しいアイデアが生まれやすくなる
社内コミュニケーションを促進し、企業全体で風通しの良い環境を作ることで、これまで交流のなかった従業員や部門同士が連携する機会が増えます。これにより、新しいアイデアが生まれやすい雰囲気が醸成されます。また、新しいアイデアを持ち寄ってディスカッションすることで、さらなるイノベーションの創出にもつながるでしょう。
社内コミュニケーション活性化につながる施策7選
社内コミュニケーション活性化に向けた施策には、次のような種類があります。
- 社内イベント
- 社内報
- 1on1ミーティング
- フリーアドレス制度
- コミュニケーションツールの活用
- サンクスカード
- 社員食堂の開設
それぞれ単独で活用するのはもちろん、複数を組み合わせることも可能です。施策ごとの特徴を理解し、社内コミュニケーション活性化に向けて積極的に取り組んでいきましょう。
社内イベント
社内イベントとは、従業員同士が集まり、業務時間外にお互いのコミュニケーションを深める機会を指します。
社内イベントの種類は、運動会や社員旅行などの大規模なものから、ボウリング大会のように有志で短時間で開催されるものまでさまざまです。また、サークル活動やお花見、誕生日会、忘年会なども社内イベントの一部として捉えられます。さらに、業務時間内に行われる創立記念パーティや社員研修も、広い意味で社内イベントに含まれることがあります。
いずれにせよ、社員同士が共通の目的で集まり交流を深める場として、社内イベントは社内コミュニケーションの促進に役立ちます。また、イベント中の社長メッセージや従業員の発表を動画で撮影し配信することで、欠席者への情報共有やイベント内容の記録として活用することも可能です。
社内報
社内報とは、社内での出来事や連絡事項を従業員向けに伝えるための広報媒体です。
かつては冊子や新聞形式で従業員に配布されていましたが、最近ではイントラネットや社内SNSで公開されることが増え、メールマガジンのような形で配信されることもあります。また、テキストだけでなく動画を活用する企業も増えており、これにより従業員同士の人柄や温かみを伝えられます。主な内容は社内のニュースや従業員紹介、最新の業績などさまざまで、企業や従業員をより深く理解することを目的に作成されるため、定期的に発行されるのが一般的です。
企業の規模が大きくなるほど従業員同士の面識が薄くなります。特に新入社員は、ほかの部署でどのような人がどのような仕事をしているのか、まったく把握していない場合もあります。社内報を通じてこのような情報を得ることで、コミュニケーションの円滑化や、組織への帰属意識の向上など、さまざまな効果が期待できます。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で行う個人面談のことです。部下の成長を促すことを目的とし、上司は部下の話を引き出しながらフィードバックを行います。週に1回や月に1回など、定期的に実施されるのが特徴です。
このミーティングを行うことで、双方の理解が深まり、信頼関係を築けます。また、困ったことを相談しやすくなったり、日常的なコミュニケーションが円滑になったりと、社内コミュニケーションを活性化する役割も期待できます。
フリーアドレス制度
フリーアドレスとは、特定の席を固定せずに、自由に好きな座席で仕事ができる仕組みを指します。この制度は、社内のコミュニケーションを活性化させるうえで高い効果を発揮します。
従来、企業では同じ部門の従業員がまとまって座るのが一般的でした。フリーアドレスを導入することで、異なる部門の従業員が垣根を越えて同じ空間で仕事をすることが可能になります。それまで交流のなかった社員同士が隣り合って座ることで、新たなアイデアが生まれることも期待できるため、フリーアドレスの導入は有効な施策だといえるでしょう。
サンクスカード
サンクスカードとは、従業員が互いの努力や成果を評価・賞賛・承認するための制度です。企業ではなく従業員同士で評価を行うことで、コミュニケーションが活発になり、職場環境が改善されます。また、お互いを褒め合うことにより、仕事へのモチベーションを高める効果も期待できます。
サンクスカードは自社で作成することもできますが、外部企業が提供しているサービスを活用するのも一案です。なかにはポイント制度が組み込まれているサービスもあり、サンクスカードを使って従業員同士が評価し合うことで独自のポイントが加算されます。溜まったポイントはギフトと交換できるため、福利厚生の一環として活用が可能です。
社員食堂の開設
社員食堂とは、従業員が昼食や夕食を取るために利用できる食堂です。一般的には、企業の敷地内に設置されており、食堂の形式ではなくカフェやバーとして運営されることもあります。
社員食堂は、食事をしながら、またはコーヒーやお酒を楽しみながら、従業員同士が気軽に交流できる場として活用されています。福利厚生としても効果的なことから、採用時に有利に働くこともあります。
コミュニケーションツールの活用
社内コミュニケーションを活性化させるために、ITツールを活用するのも良いでしょう。従来のアナログな手法に比べ、デジタル技術を駆使したコミュニケーションは、より円滑な情報共有や情報交換を可能にします。
代表的なコミュニケーションツールは次の通りです。
- メーラー:Gmail、Yahoo!メールなど
- ビジネスチャットツール:Slack、Chatwork、Googleチャットなど
- SNS:X、Facebook、LINEなど
- Web会議システム:Zoom、Google Meetなど
- グループウェア:kintone、Google Workspace、Microsoft 365など
- スケジュール共有ツール:Googleカレンダー、Backlog、Asanaなど
このようなツールは基本的に導入コストや運用コストが発生します。そのため、社内コミュニケーションで発生している課題を特定し、明確な目的なもとで適切なツールを検討することが大切です。定着率を高めるために、業務マニュアルや研修制度を用意するのもおすすめです。
社内コミュニケーション活性化に成功した事例6選
社内コミュニケーション活性化の施策を考える際は、他社の事例を参考にするのがおすすめです。社内コミュニケーション活性化に成功した6社の事例を紹介します。
株式会社三喜
株式会社三喜は、全国で婦人服や紳士服などのアパレル商品を展開する小売企業です。同社では売り場での情報共有を促進するため、社内チャット機能に強みを持つコミュニケーションツールを導入しました。
具体的には、チャット上で在庫確認用のトークグループを設置して社内コミュニケーションを行っています。顧客から在庫に関する問い合わせが来ると、店舗間であらかじめ撮影しておいた商品写真やタグを使って在庫数を確認し、グループ上で情報を交換し合う仕組みです。また、各店舗の売り場に設置している商品ディスプレイや展示方法を店舗同士で共有することで、販売方法の最適化にも効果を発揮しています。
参考:【WowTalk AI】使い慣れているコミュニケーションツールからシームレスに活用!シャドーITの防止にも繋がる|WowTalk
株式会社西武ライオンズ
株式会社西武ライオンズは、プロ野球球団の埼玉西武ライオンズを運営する企業です。同社は多岐にわたる情報発信業務を担う広報部で、タスク管理ツールを使った施策を展開しています。
広報部の業務は、イベントの開催やゲストへの対応、グッズの販売促進などがあり、繁忙期になると200以上のタスクを同時に進行しなくてはなりません。アナログな手法では確認漏れや属人化などのリスクが高まるため、タスク管理ツールを使って情報の一元管理を行っています。
タスク管理ツールを活用すると、「誰が、いつ、どのような業務を行っており、いつまでに完了すべきか」といった情報が可視化されます。チーム内での情報共有が促進された結果、業務が滞留するリスクを最小限に抑えられています。
参考:西武ライオンズの業務をBacklogで見える化!最大200件のタスクを同時進行しつつ進捗共有がスムーズに|Backlog
株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズ
株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズは、通信インフラに関する基地局の設置交渉から設計、工事までを一貫して担う企業です。同社は現場作業員とのコミュニケーションを円滑にするため、法人向けのWeb会議システムを導入しました。
基地局での工事は多いときに20ヶ所以上の現場を回る必要があり、対応スピードを早めたり事故のリスクを抑えたりするには、現場作業員との迅速な情報交換が欠かせません。Web会議システムであれば、オフィスから離れた現場でも直接工事の様子を見ながら会話を行えます。作業一つひとつを注意喚起しながら進めることもできるため、円滑な社内コミュニケーションだけでなく現場の安全確保にもつながっています。
参考:導入事例 株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズ様|LiveOn
株式会社ロッテ
株式会社ロッテは、2024年3月8日の国際女性デーにあわせて、従業員向けのDEI(Diversity,
Equity & Inclusion)推進の取り組みを強化しました。持続的な成長を実現すべく、従業員一人ひとりがその能力を発揮することが目的です。
具体的には女性管理職によるパネルディスカッションの配信や、出産・育児といったライフイベントのサポートなどの施策を展開しています。そのなかで社内コミュニケーションを活性化させるための施策も展開されています。例えば、従業員の多様性を尊重して柔軟な発想を育む「服装の自由化」や、コミュニケーション促進のための「フリーアドレス制」や「多目的スペース」の導入などが代表的です。
参考:3月8日国際女性デーにあわせてロッテの従業員に向けたDEI推進の取り組みを紹介|株式会社ロッテ
キリンホールディングス株式会社
キリンホールディングス株式会社は、1958年から「きりん」という社内報を発行しており、社内コミュニケーション向けの施策の一環として活用しています。そのなかでは社長からのメッセージや、グループ内での新たな動きを伝える特集などが紹介されており、企業規模の大きい同社でも社内報を読むことで社内のリアルタイムの状況を知ることができます。
また、「写心館」という独自のコーナーを掲載しているのも特徴です。写心館では、グループ会社やバックオフィスなど、普段表に出る機会が少ない従業員に焦点をあて、仕事に対する想いや活躍する姿を紹介しています。従業員の人となりを知るきっかけにもなるため、社内報を通じて新たなコミュニケーションの機会を生み出しています。
参考:「一緒に働く誇らしい従業員を知ってもらいたい!」社内報の編集部が語る、その役割と可能性|note KIRIN公式アカウント
清水建設株式会社
清水建設株式会社は、2024年7月に「コミュニケーションHUB」というコンセプトのもと、38年ぶりに名古屋支店を丸の内の新オフィスへと移転しました。同コンセプトを掲げたのは、日頃から従業員がコミュニケーションの仕方に課題を抱えており、コミュニケーションを加速させて支店としての一体感を育む必要があったためです。
新オフィスでは10階と11階が吹き抜けでつながっており、風通しの良い雰囲気に仕上がっています。また、仕事内容に合わせて働く場所を選択できる「ABW(Activity Based Working)」や、従業員の健康やストレス軽減に配慮した「リラクゼーションWELL」など、独自性の高い施策を展開しているのもポイントです。
参考:【清水建設株式会社】人と人がつながる「コミュニケーションHUB」を目指して|hataraku
社内コミュニケーションを活性化するためのポイント3つ
社内コミュニケーションを活性化させるためのポイントは次の通りです。
- 現状の課題を明らかにする
- 目的や成果を従業員と共有する
- 長期的な視点で取り組む
それぞれのポイントを意識して施策を展開することで、円滑な社内コミュニケーションの実現に近付けます。
現状の課題を明らかにする
一概に社内コミュニケーションの活性化といっても、取り組み方は企業によって大きな違いがあります。むやみに施策を展開しても成果は見込めないため、あらかじめ現状の課題を明確にしたうえで、その解消に向けたピンポイントの施策を検討することが大切です。
現状の課題を洗い出す際は、まずボトルネックとなっている階層を明らかにすると良いでしょう。社内コミュニケーションの階層は、主に上司と部下、経営陣と従業員、同じ部門・チーム内、異なる部門同士といった形で分けられます。そのなかで慢性的な課題が生じている箇所を特定し、アプローチ方法を決定しましょう。
課題や階層が明らかになれば、必要な施策が見えてきます。例えば、上司と部下との間でコミュニケーションの課題が生じているなら、1on1ミーティングやメンター制度といった施策が効果的です。
目的や成果を現場担当者と共有する
社内コミュニケーション活性化の取り組みは、上層部や管理者が旗振り役となって推進するケースも珍しくありません。しかし、実際にコミュニケーションの課題を抱えているのは現場担当者であることが多いものです。そのため、現場の意見を尊重せず無理に施策を推進しようとすると、反発を招いたり、制度やツールが組織に浸透しなかったりと、さまざまな問題を抱える可能性があります。
このような問題に発展しないためにも、社内コミュニケーション活性化の目的や想定される成果を現場担当者と共有することが大切です。現場の声をヒアリングしつつ、アクションプランに反映させることも重要だといえるでしょう。
長期的な視点で取り組む
社内コミュニケーション活性化の取り組みは、実施したからといってすぐに効果が出るものではありません。特に慢性的なコミュニケーションの課題を抱えている組織では、従業員が前向きに施策に取り組むまでに時間がかかることもあれば、日常業務に忙殺されて時間が取れないことも考えられます。
そのため、長期的な視点のもとで施策に取り組む姿勢が求められます。短期的な施策を数回実施しただけで満足せず、効果検証を繰り返しながら継続的に施策を展開することが重要です。そのためには長期的なゴールやマイルストーンを設定し、目指すべき姿を明確にする必要があります。
Google Workspaceで円滑な社内コミュニケーションを実現
社内コミュニケーションを活性化するにはコミュニケーションツールが効果を発揮しますが、なかでもグループウェアの導入を検討してみてはいかがでしょうか。グループウェアとは、スケジュール共有やチャット、社内SNSなど、さまざまなコミュニケーション機能が統合されたツールです。
グループウェアにはさまざまな種類がありますが、Google Workspaceは導入ハードルが低く、誰でも手軽に扱えるメリットがあります。Google Workspaceに搭載されているコミュニケーションツールは、GmailやGoogleドライブ、Google Meetなど、普段から使用する機会が多いものばかりなので、一から操作方法に慣れる必要がありません。
具体的な活用方法としては、Googleサイトで社内ポータルサイトを作成できるほか、Googleカレンダーを使ってチーム内でのスケジュールを共有するといった形です。そのほか、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートでは、複数人で共同編集する際にコメントを添付できるため、よりスムーズなコミュニケーションにつながります。また、Google Workspaceに登録すると、それぞれのツールが有料版にアップグレードされ、ストレージ容量の拡張や充実したセキュリティ・サポートを利用できます。
Google Workspaceの特徴や機能、メリットなどに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
社内コミュニケーションを活性化させて業務効率化や生産性向上につなげよう
社内コミュニケーションを活性化させる施策は、社内イベントや社内報、フリーアドレス制度など、さまざまな種類があります。それぞれ想定される効果や取り組み方が異なるため、現状の課題や目的を明確にし、適切な施策を採り入れることが大切です。
施策の一環としてコミュニケーションツールを採用する場合は、Google Workspaceの導入を検討してみてはいかがでしょうか。Google Workspaceには、有料版のGmailやGoogleドライブといったさまざまなコミュニケーションツールが搭載されており、社内コミュニケーションの活性化に役立ちます。
電算システムでは、環境構築やコンサルティングなど、Googleサービスの導入支援サービスを提供しています。GmailやGoogleドライブといった個別のサービスはもちろん、Google Workspaceのサポートにも対応しています。専門領域に精通した数多くのエンジニアが在籍しているので、スピーディかつ質の高いサポートを行えるのが強みです。「Googleサービスを活用したいが具体的なイメージが湧かない」といったお悩みを抱える方は、ぜひ電算システムへと気軽にお問い合わせください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- 社内コミュニケーション 活性化