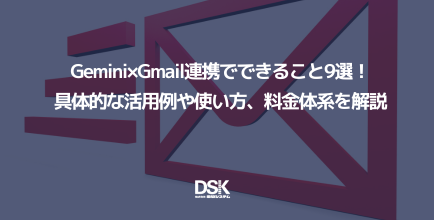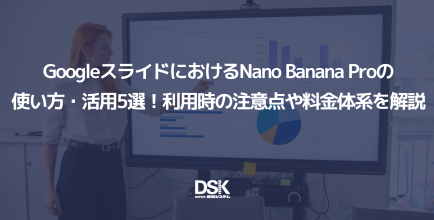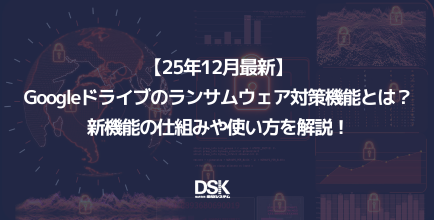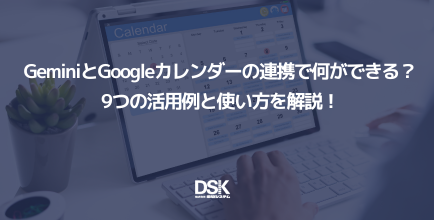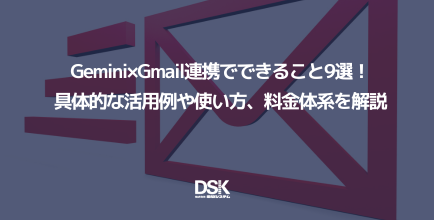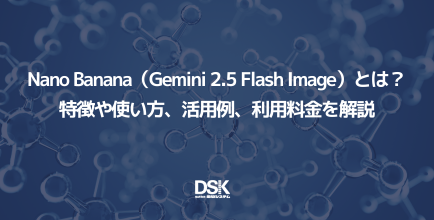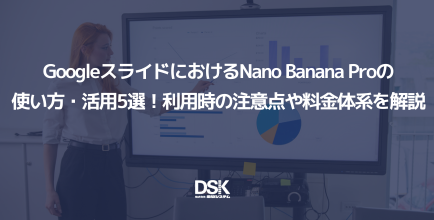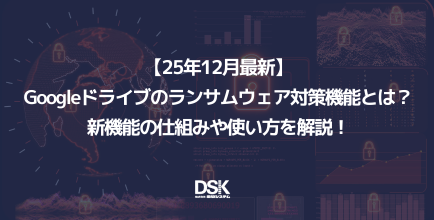生成AIとは、テキストや画像などで指示を与えることで、AIが自動的にコンテンツを作成してくれる技術です。なかでも、動画コンテンツの作成に長けたものを「動画生成AI」といいます。簡易的な指示だけで、高精細かつハイクオリティな動画を短時間で作成できるのがメリットです。
ただし、一概に動画生成AIといっても、さまざまなサービスの種類があります。そのため、導入目的や選定基準などを明らかにし、さらにサービスごとの特徴や強みを理解することが、適切なサービス選びへとつながります。
本記事では、動画生成AIの特徴や活用方法などを詳しく解説します。また、おすすめのサービスや選び方のポイントも紹介しているので、ビジネスに動画生成AIを活用したい方は参考にしてください。
動画生成AIとは指示通りのオリジナル動画を自動作成できる技術
動画生成AIとは、AIの技術を用いて動画コンテンツを自動で生成する技術です。この技術により、これまで手作業で行っていた動画の編集や制作工程を大幅に効率化し、短時間で高品質な動画を作成することが可能になります。
動画生成AIの学習(機械学習)には、大量の画像・動画データが必要です。これらのデータは、ジグソーパズルの完成図に例えられ、一つひとつを細かいピースとして分解し、ピース同士のつながりや関係性をAIが学習します。このようにして蓄積された情報をもとに、指定された内容に応じてピースを組み合わせ、完全オリジナルな動画を生成する仕組みです。
動画生成AIでできること
一概に動画生成AIといっても、テキストの指示をもとに動画を生成したり、アップロードした画像から動画を生み出したりと、サービスごとにできることが異なります。そのため、まずはどのような作業方法が良いか、あらかじめ決めておくことが大切です。
動画生成AIでできることを4つの種類に分けて解説します。
プロンプトから動画を生成する
動画生成AIサービスの最も代表的な作業方法は、プロンプトから動画を生成することです。プロンプトはテキストによる指示のことを表します。
例えば、「空に浮かぶ雲」と入力すると、青空のなかで動く雲の様子をAIが動画へと落とし込んでくれます。この「空に浮かぶ雲」というテキスト状の指示がプロンプトにあたります。プロンプトはほかにも、「太陽」や「飛行機」など、自由に言葉を組み合わせて設定できます。また、画像のイメージだけでなく、構図やサイズ比、ズームイン・ズームアウトといったカメラワークの指定、動きの強弱などをプロンプトとして入力することも可能です。
生成された動画はすぐにプレビューでき、仕上がりに満足できない場合は、指示を変更して再度生成できます。なお、利用するサービスによって生成される動画のクオリティや対応機能、動画の長さなどに違いがあります。
アップロードした画像をもとに動画を生成する
動画生成AIサービスによっては、1枚または複数枚の静止画から動画を生成できます。あらかじめ用意した画像をアップロードするだけで、その内容によく似た動画をAIが自動的に作成してくれる仕組みです。
例えば、風景写真のなかに車が写った画像をアップロードした場合、その車が動き出すような動画を生成可能です。そのほか、画像内のキャラクターの表情や手足が動かすこともできます。静止画から動きのある映像コンテンツを効率良く作成できるのがメリットです。
また、複数の画像をアップロードした場合は、それらを組み合わせたアニメーション動画を作成できます。
画像と音楽を組み合わせて動画を生成する
画像と音声データをもとに自動で動画を生成できるサービスもあります。画像ファイルと音声ファイルをアップロードするだけで作業が完了します。また、ファイルのアップロードとあわせて、プロンプトによる指示や既存映像のスタイル変換に対応したサービスも存在します。
この方法は、自社商品・サービスのプロモーション映像や広告用の動画、ミュージックビデオなどを作成する際に効果的です。面倒な編集作業は一切不要で、まるでプロの映像作家が制作したかのようなクオリティの高い映像を容易に作成できます。
ニュースやSNSの情報をもとに動画を生成する
動画生成AIサービスのなかには、Web上に掲載されているニュース記事やSNS投稿、スポーツイベントの結果、統計情報など、さまざまなテキストコンテンツをもとに動画を自動で生成できるものもあります。使い方は非常にシンプルで、ユーザーが対象のWebページのURLを入力するだけで済みます。AIがそのテキスト内容を解析し、内容に沿った動画を自動で作成する仕組みです。
質の高い動画生成AIサービスであれば、単なる映像だけでなく、ナレーションや効果音、BGMまで、包括的な要素を組み合わせて完成度の高い動画を生成できることもあります。自社のブログやニュースリリースの情報も参照できるため、マーケティング用の動画コンテンツを作成する際にも役立つでしょう。
動画生成AIサービスを導入する3つのメリット
動画生成AIサービスを導入すると、次のようなメリットが生まれます。
- 動画制作の手間や時間を抑えられる
- 専門知識がなくても質の高い動画を作成できる
- 動画制作におけるアイデアのヒントを得られる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
動画制作の手間や時間を抑えられる
動画生成AIサービスを活用することで、これまでに比べて制作の手間や時間を大幅に削減できます。従来は撮影から編集までを含めると、動画の完成までに数週間以上かかることもあります。しかし、動画生成AIを用いれば、指示を入力する、あるいは必要なデータをアップロードするだけで、スピーディーに動画を作成できます。
ただし、AIに希望通りの動画を生成させるためには、プロンプトの内容が非常に重要です。不適切なプロンプトを入力すると、期待通りの出力結果は得られません。
プロンプトを作成する際、最初に明確にしておくべきなのは目的です。何を伝えたいのか、どのような情報を引き出したいのかをはっきりさせることで、AIもその意図に沿った動画をより的確に生成できるようになります。また、コンテキスト(制作意図や背景)や出力方法など、条件を具体的に指示することも重要です。
専門知識がなくても質の高い動画を作成できる
本来、動画を制作・編集するには専門的な知識やスキルが求められます。企業紹介や商品PRといった動画を作る際には、これまでは制作会社に依頼するのが一般的でしたが、動画生成AIを活用すれば、初心者でも簡単に動画を作成することが可能です。
動画生成AIを利用することで、知識や経験に関係なく、高品質な動画を手軽に作成できる点は大きな利点です。ターゲットやニーズに合わせた映像を、誰でもスムーズに作ることができ、さらにクリエイティブな発想を自分で一から考える必要もありません。
社内に動画制作のノウハウが不足している場合でも、動画生成AIサービスだけで作業が完結することもあるため、結果として制作会社に外注するコストや、専門人材を採用・育成するコストを抑えられる可能性があります。
動画制作におけるアイデアのヒントを得られる
動画生成AIサービスをクリエイティブ業務のサポートとして活用するのも一つの方法です。例えば、動画制作において明確な企画やアイデアが思い浮かばない際に、AIにラフ案を作ってもらうことで、それがヒントになり得ることも考えられます。機械が独自にコンテンツを作成するからこそ、人間ではなかなか考え付かなかったアイデアが見つかる可能性もあります。
このように、動画生成AIサービスは、使い方次第でクリエイティブ業務の効率性や生産性を高めてくれます。
動画生成AIサービスを選ぶ際の5つのポイント
動画生成AIサービスにはさまざまな種類があるため、サービスを選定する際の基準を明確にすることが大切です。動画生成AIサービスを選ぶ際のポイントを複数の観点から解説します。
目的に応じたサービスを選ぶ
動画生成AIサービスのなかには、プロモーション動画や製品紹介に特化したものもあれば、非常に高精細でリアルな映像表現を得意とするツールもあります。それぞれのサービスが持つ特性を把握し、目的に合致したものを選ぶことが重要です。
例えば、プロモーション用の動画を制作する場合には、ブランドや商品・サービスの魅力を引き立てるテンプレートやナレーション機能が充実しているツールが適しています。社内研修やEラーニングに活用するのであれば、教育向けの素材が豊富で、操作が簡単なツールが向いているでしょう。
このように、サービスを選定する際は、サービスごとの強みや活用手段をしっかりと把握することが大切です。また、目的を達成するために必要な機能が揃っているかも必ず確認しましょう。
日本語対応の可否を確認する
動画生成AIサービスを選ぶ際に意外と見落とされがちなのが、日本語対応が可能であるかどうかです。特にプロンプト入力やテキストベースの操作を行う場合、対応言語が限られていると、思った通りの指示が伝わらず、期待した結果が得られない可能性があります。そのため、当該サービスが日本語に対応しているかどうかは、選定時の重要なチェックポイントとなります。
なお、プロンプトに日本語を使用できても、英語のユーザーインターフェースを採用している場合もあります。日本語対応の可否を確認するには、無料トライアルや無料プランを活用し、少なくとも1回はそのサービスを実際に触れてみることをおすすめします。操作性や機能性もあわせて検証できるため、サービス選定の効率性が向上します。
商用利用の可否を確認する
AIによって生成された動画をビジネス用途で活用する際には、あらかじめ商用利用に関する利用規約を確認する必要があります。規約に反した形でビジネスに使用してしまうと、法的なトラブルに発展する恐れがあるため、細心の注意が求められます。
多くの場合、利用規約のなかに商用利用に関する項目が明記されています。「商用利用可能」や「商用利用不可」といった記載のほか、「有料プランのみ商用利用可」といった条件付きのケースも存在します。
セキュリティレベルの高いサービスを選ぶ
動画生成AIサービスの導入にあたっては、情報漏えいや著作権侵害といったリスクを伴うため、十分なセキュリティ対策が講じられているかどうかを確認する必要があります。
サービスのなかには、ユーザーが入力したデータがAIモデルの学習に利用されるものがあります。仮に社内の機密情報や顧客の個人情報などを入力した場合、その情報が出力結果として一般公開され、外部に流出してしまう恐れも懸念されます。また、他者の権利を侵害するような動画を生成するリスクにも注意が必要です。
このようなリスクを防ぐためには、サービスを選定する段階で、入力データが学習に使用されないかどうか、その設定が可能かを確認しましょう。あわせて、データの暗号化に関する設定やプライバシーポリシーを確認することも大切です。セキュリティレベルの高いサービスを選ぶことで、情報漏えいや権利侵害のリスクを抑えられます。
サポート体制にも着目する
動画生成AIサービスの導入を検討する際には、サポート体制が整っているかどうかを事前に確認することが重要です。サービスの操作方法や疑問点が生じた場合に、適切なサポートを受けられるかどうかが、導入後の円滑な運用に大きく影響します。
特に技術的な支援が必要となるケースでは、サポート内容が充実しているサービスを選ぶことで、トラブル対応のスピード向上や業務の効率化が見込めます。すべてのサービスに十分なサポートが備わっているとは限らないため、事前のチェックが欠かせません。
動画生成AIサービスのおすすめ5選
動画生成AIサービスには、特徴や強みが異なるさまざまな種類があります。特におすすめのサービスを紹介するので、目的や用途に合わせて最適なものを選択しましょう。
Sora
Soraは、テキスト生成AIサービスのChatGPTを開発したOpenAI社が、2024年2月に発表した動画生成AIサービスです。プロンプトを入力するだけで、10~20秒程度のHD・フルHD画質の動画を自動生成できます。
高品質な動画生成を実現するために、拡散モデル(Diffusion Model)と呼ばれるAI技術が採用されています。拡散モデルとは、画像・テキスト・音声などのコンテンツに大量のランダムノイズを加えたうえで、徐々にノイズを取り除きつつ最終的に求められる高品質な映像に近付ける仕組みです。
このプロセスを経ることで、細かいプロンプトにも柔軟に対応できます。緻密なシーン構成や多様な登場キャラクター、カメラの動きといった複雑な要素も繊細に再現可能です。すでに数十本ものサンプル動画が公開されており、ドローン撮影や本物のカメラワークと見分けがつかないほどの高い完成度を誇っています。
Veo 2
Veo 2は、Google社が開発した動画生成AIサービスです。プロンプトから最大4Kの高解像度映像や、数分にも及ぶ長編動画を生成できます。フルHD画質かつ数十秒程度の動画生成に対応していた旧モデルのVeoに比べ、性能が大幅に向上しています。
Veo 2の特徴は、ユーザーが入力したテキストの内容を正確に理解し、それにもとづいて動画を生成できる点です。現実世界の物理法則を理解し、それを映像内に自然に落とし込めるほか、多様な視覚的スタイルを再現できるため、プロンプトに含まれる微妙なニュアンスやトーンまでも忠実に反映できます。
また、数分に及ぶ長尺の映像生成に対応しているのもポイントです。従来の動画生成AIサービスでは、数秒~数十秒程度の短編動画しか作成できないケースが一般的でしたが、長編ストーリーの表現が可能になったことで、映像制作の可能性がさらに広がります。
Veoを利用するにはGoogle Cloudへの登録が必要でしたが、Googleが提供しているテキスト生成AIサービスのGeminiにVeo 2が搭載されたことで、Geminiのインターフェース内でテキスト生成と動画生成を同時に行えるようになります。さらに、Google Labs内の生成AIプロジェクトWhiskでもVeo 2を体験できます。
2025年5月26日には、次世代モデルのVeo 3が日本でも提供開始されました。Veo 3は、Veo 2よりも映像品質が向上しており、音声付きの動画を生成できるのが特徴です。
Adobe Firefly Video Model
Adobe Fireflyは、Adobe社が提供する生成AIを活用した画像生成サービスです。AIによって独自の画像を生成できるほか、生成したグラフィックの編集や3Dモデルの作成にも対応しています。
このAdobe Fireflyでは、2025年4月時点において、Adobe Firefly Video Model(ベータ版)が提供されています。Adobe Firefly Video Modelは、生成AIのなかでも動画生成に特化したサービスです。現時点ではベータ版ではありますが、すでにAdobe Fireflyを通じて世界中で180億以上の動画コンテンツが生成されています。
Adobe Firefly Video Modelは、商用利用における安全性に優れる特徴があります。同サービスで使用される素材は、すべてAdobeが所有権またはライセンスを有するデータに限定されており、著作権を侵害するリスクを気にせずに商用コンテンツとして利用できます。
また、動画内の不要なオブジェクトの除去や、トランジションの調整、カメラのアングル・ズームの制御といった、AIによる多彩な編集機能が備わっているのもポイントです。そのため、これまで手間のかかっていた動画編集作業の大幅な効率化につながります。
Canva
Canvaは、オンライン上で利用可能なグラフィックデザインツールです。直感的に操作できるドラッグ&ドロップ形式を採用しており、ポスターやSNS用の投稿画像、ロゴなど、さまざまなデザインを手軽に作成できます。デザインに不慣れな方でも安心して使えるよう、多数のテンプレートや素材が用意されており、短時間で高品質なグラフィックを制作できるのが特徴です。
Canvaには複数の生成AI機能が搭載されており、これらは総称して「Canva AI」と呼ばれています。代表的なCanva AIの機能としては、テキストから画像や動画を自動生成する「マジック生成」や、AIによる文章作成を行う「マジック作文」などがあります。
なかでも、マジック生成の動画作成機能は、テキストの入力だけで高品質な動画を手軽に制作できるのが魅力です。さらに、アニメーションやフォント、配色などの要素も自由にカスタマイズできるため、個性豊かな動画を短時間で作成できます。
Dream Machine
Dream Machineは、米国のAIスタートアップ企業Luma AI社が提供する動画生成AIサービスです。プロンプトや画像を入力することで、最大120フレーム(24fps×5秒)の動画を生成できます。
従来の動画編集ツールでは、クリエイターが1フレームずつ映像を調整する必要があり、多くの手間と時間がかかっていました。しかし、Dream Machineではあらかじめ構築された高度なアルゴリズムにより、その作業が自動で処理されます。その結果、動画制作にかかる時間が大幅に短縮されるだけでなく、作品全体のクオリティの向上にもつながります。
Dream Machineには、Ray2と呼ばれる高性能な動画生成モデルが搭載されています。プロンプトの内容を正確に理解し、自然で一貫性のあるリアルな動きを持つ動画を生成できるのが特徴です。細かな動画生成処理は自動化されている一方で、必要に応じて映像の内容を自由にカスタマイズすることも可能です。
動画生成AIサービスを活用する際の注意点
動画生成AIサービスを利用する際は、次のような点に注意が必要です。
- 出力される情報が正しいとは限らない
- 使い方を誤ると権利侵害に発展する恐れがある
- 生成AI技術を活用するには適切なノウハウが必要
サービスを導入する前に以下の注意点をよく理解し、社内で対応策を検討しておきましょう。
出力される情報が正しいとは限らない
現在の生成AIは、誤った情報を含むコンテンツを生成してしまう可能性があるため、一般に公開する際には細心の注意が求められます。生成AIの精度は年々向上していますが、依然として発展途上の技術であり、情報の正確性については課題が残っています。正しくない情報を選別せずに学習を続けると、不正確なコンテンツが生成されてしまうことも考えられるでしょう。
例えば、動画生成AIの場合、映像とともに生成したナレーションや登場人物のセリフなどに誤情報が含まれてしまうリスクがあります。誤った情報を世の中に発信すると、混乱を招く危険性があるため、現時点ではコンテンツの事実確認(ファクトチェック)は人の手で行うことが望ましいといえます。
使い方を誤ると権利侵害に発展する恐れがある
動画生成AIサービスによって作成されたコンテンツが、他人の著作物と酷似している場合、トラブルの原因となるため、権利関係には十分な注意が必要です。AIに学習させるデータに他者のコンテンツが含まれていると、類似した作品が生成される可能性があります。特に類似性や依拠性が高い場合には、著作権侵害と見なされる恐れがあるため、他人のコンテンツを無断で使用することは避けましょう。
また、他者の著作物を直接使用していない場合でも、生成されたコンテンツが権利侵害に該当しないよう配慮が必要です。有名なキャラクターや著名人に似た人物が映像のなかに登場している、ナレーションの内容が他社のCMの内容と酷似しているといったケースでは、権利侵害に発展する可能性が高いので特に配慮が求められます。
生成AI技術を活用するには適切なノウハウが必要
組織内のすべての従業員が、動画生成AIサービスを正しく使いこなせるとは限りません。そのため、生成AIには利便性だけでなくリスクも存在することを、従業員に十分理解してもらうことが重要です。
このような点から、社内への周知に加えて利用時のルールも明確にしておきましょう。仮に企業の機密情報が漏洩した場合、社会的な責任を問われる可能性も否定できません。したがって、生成AIサービスを利用する際には、顧客の個人情報や社内の研究データなどの入力を禁止し、加えて管理者による入力内容の確認を行う体制を整えることが望ましいでしょう。
また、従業員への意識改革を目的とした教育も欠かせない要素です。単に生成AIサービスの使い方といった表面的な知識にとどまらず、機械学習やディープラーニングといった基礎技術も含め、AIに関する包括的な理解を深めることが求められます。
生成AIを活用して動画制作の効率性や生産性を高めよう
動画生成AIサービスを導入すると、プロンプトに従ってAIが自動で動画を作成してくれます。サービスによっては、高精細かつ長尺の動画を短時間で生成できたり、生成した動画をその場で編集したりできるものもあります。このようなサービスをうまく活用すれば、動画制作の工数を大幅に削減できるでしょう。
ただし、動画生成AIサービスには数多くの種類があるため、あらかじめ目的や用途を明確にしたうえで適切なものを選ぶことが大切です。価格や機能だけでなく、セキュリティやサポート、日本語対応の可否なども視野に入れて複数のサービスを比較するのが良いでしょう。
動画生成AIサービスにはさまざまな種類がありますが、普段からGoogleサービスを利用する方には、Google Workspaceがおすすめです。Google Workspaceには、「Google Workspace with Gemini」の機能が搭載されており、GmailやGoogleドライブ、Googleドキュメントなどの各種サービスに、生成AIのGeminiの機能を組み込むことが可能です。以下の資料でGoogle Workspace with Geminiの特徴や使い方を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- 生成 ai 動画