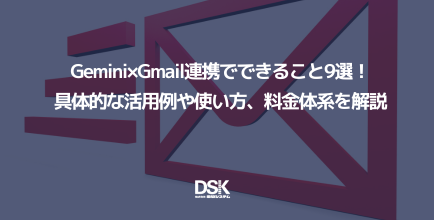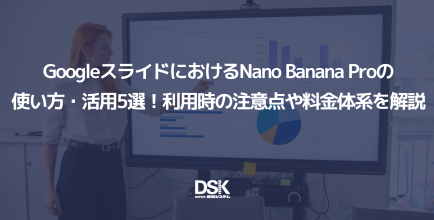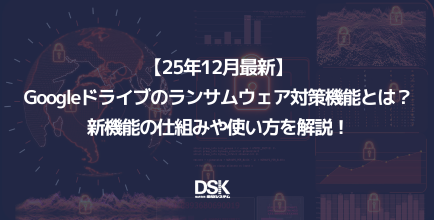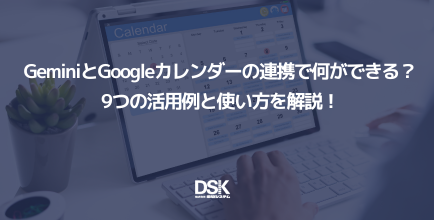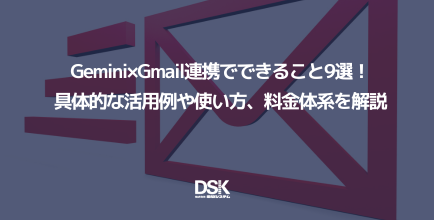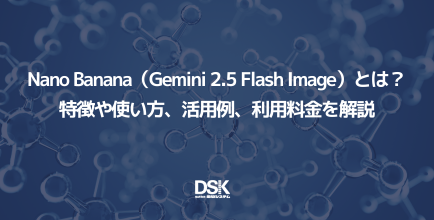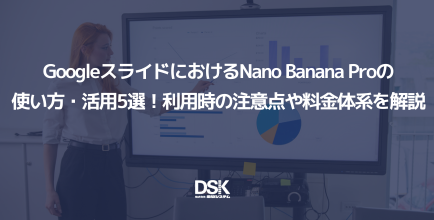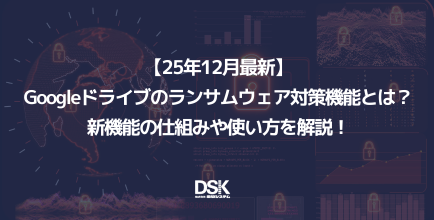社内に蓄積されたデータを一元管理する際はファイルサーバーを活用するのが一般的ですが、「導入コストが高額で実装が難しい」「ノウハウ不足でどのように導入すれば良いかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。このような際は、まずNASサーバーから導入を検討するのがおすすめです。
NASサーバーは、ネットワークで接続するストレージデバイスで、複数の端末から一度に必要なデータへとアクセスできるメリットがあります。ファイルサーバーと似たような機能を持っていますが、導入時のコストや手間がかかりにくいため、初心者の方でも安心して利用できます。
本記事では、NASサーバーの特徴や種類、ファイルサーバーとの違いについて詳しく解説します。手軽にデータ管理の環境を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
NASサーバーとはネットワークで接続するストレージデバイス
NAS(Network Attached Storage)サーバーとは、ネットワークで接続するストレージデバイスです。USBメモリや外付けHDDといった一般的なストレージデバイスと同様、端末内にデジタル文書や画像、動画などのデータを保存できます。
また、一般的なストレージデバイスがパソコンなどの端末に直接接続するのに対し、NASサーバーはネットワークにアクセスすることでデータのインポートやエクスポートが可能です。そのため、異なる部署同士でデータを共有するなど、ネットワークに接続されているどの端末からでも必要なデータにアクセスできます。
NASサーバーにデータを保管すれば、端末のストレージ容量の削減につながります。加えて、端末とNASサーバーに分散してデータを保存することで、バックアップとしても活用できます。
NASサーバーの4つの特徴
NASサーバーの特徴は次の通りです。
- 複数の端末から同時にアクセスできる
- ストレージ容量を柔軟に調整できる
- 導入時のコストや手間を抑えやすい
- セキュリティの強化につながる
それぞれの特徴について詳しく解説します。
複数の端末から同時にアクセスできる
NASサーバーは常時ネットワークに接続された状態でデータを保存できます。そのため、同じネットワーク内にいるメンバーであれば、たとえ部署が異なったとしても、いつでも必要なデータへとアクセスが可能です。複数端末からアクセスも可能なので、業務効率化にも効果を発揮します。
USBメモリや外付けHDDといった一般的なストレージデバイスの場合、データを共有するには、その都度デバイスを端末から取り外したり、別の場所に持ち運んだりする必要があります。一方、NASサーバーであれば、デバイスを移動することなく端末上の操作のみでデータ共有を行えます。
このような特徴があることから、NASサーバーはチーム内での情報共有やコミュニケーションを促進する手段として効果的です。社内だけでなく、テレワーク中や外出時のデータアクセスにも対応できるため、働き方改革を推進する際にも役立つでしょう。
ストレージ容量を柔軟に調整できる
データを保管するストレージを運用する場合は、容量の問題が常に付きまといます。容量が不足すればスケールを拡張しなければなりませんし、反対に容量が大きすぎてダウンスケールを検討するケースもあるでしょう。
例えば、一般的なストレージデバイスであれば、容量不足の問題を解消するために新たな機器を購入しなければなりません。ファイルサーバーの場合はさらに大がかりな手続きが必要で、ハードウェアの増設やOSのアップグレードといった処理が必要です。
一方のNASサーバーは、専用の拡張ユニットが用意されており、スケーリング時のコストや手間を抑えられます。容量を拡張したい場合はデバイスに拡張ユニットを接続するだけで済みます。また、ネットワーク上で複数のデバイス同士を連携させて容量を拡張することもできるため、柔軟性に優れるのもメリットです。
導入時のコストや手間を抑えやすい
データを管理する際、どのような手段を利用するかによって費用が大きく異なります。ファイルサーバーの場合は、サーバー購入費やネットワーク構築費、ライセンス購入費などが必要で、クラウドストレージを利用する場合でも継続的なサービス利用料が発生します。
その点、NASサーバーは、デバイスを購入すれば追加費用をかけることなく利用できます。また、サーバーやネットワークといったハードウェアを構築する必要がないため、ファイルサーバーに比べて初期費用を抑えられるのも利点です。大がかりな設置工事も求められず、コストだけでなく導入時の手間も削減できます。
セキュリティの強化につながる
従業員や顧客の個人情報、社内の機密情報など、さまざまなデータを扱う場合は、セキュリティが重要な要素となります。もしサーバーやストレージデバイスのセキュリティレベルが低いと、外部からの攻撃や侵入、マルウェア感染などのリスクが高まり、情報漏えいへと発展しかねません。
NASサーバーにはさまざまなセキュリティ機能が搭載されており、データを安全に管理できます。例えば、アクセス時の権限を設定できるアカウント管理や、送受信時のデータを変換する暗号化、ネットワークへの不審な侵入を防ぐファイアウォールなどが代表的です。
NASサーバーの種類
NASサーバーは、「HDD内蔵タイプ」と「NASキット」の2種類に分類できます。それぞれの特徴やメリットについて解説します。
HDD内臓タイプ
HDD内臓タイプとは、NASサーバーのデバイス自体にHDDが搭載されている製品です。デバイスとは別にHDDを用意する必要がなく、容易に初期設定を行えるため、NASサーバーの扱い方に慣れていない方に向いています。
ただし、柔軟性に欠ける点には注意が必要です。NASキットとは違い、内部のHDDを自由に入れ替えられないため、容量のアップグレードやダウングレードに対応しにくいデメリットがあります。
NASキット
NASキットとは、NASサーバーのデバイスとHDDが別々に販売されている製品です。利用するには、まずNASキットと呼ばれる筐体にHDDを組み込む必要があります。そのため、HDD内臓タイプに比べて導入時に手間がかかりやすい傾向にあります。
その代わり、目的や用途に応じて自由にHDDを入れ替えられるのがメリットです。HDDを組み込む際は本体のベイという箇所に実装します。ベイの数が多いほど、たくさんのHDDを実装でき、容量拡張にも対応しやすいため、NASキットを選択する際はHDDの搭載可能数をしっかりと検証することが大切です。
NASサーバーとファイルサーバーの違い
NASサーバーとファイルサーバーは基本的な機能がよく似ており、役割を混同するケースも多いものです。しかし、両者には細かい違いがあり、向き・不向きも異なるため、それぞれの違いを理解することが大切です。NASサーバーとファイルサーバーには次のような違いがあります。
定義・用途
ストレージデバイスそのものにネットワーク機能を有したNASサーバーに対し、ファイルサーバーはネットワークを経由してファイルを共有するためのシステムです。そのため、NASサーバーはデバイスを購入すれば即座に利用できますが、ファイルサーバーはネットワーク接続のためにさまざまなハードウェアやソフトウェアを組み合わせなければならないため、導入時に複雑な設定や工事が必要です。
主な用途としては、導入ハードルが低いNASサーバーは、規模の小さい企業で活用されるのが一般的です。また、家族内での写真共有やテレビの録画など、家庭内で利用するケースも珍しくありません。一方、要件を柔軟にシステムへと反映できるファイルサーバーは、要求が厳しい大規模な企業でよく用いられています。
導入コスト
システムの構築が容易なNASサーバーは、その分コストも安く抑えられます。必要な初期費用はデバイスの購入費程度で、容量を拡張しない限りは追加費用もかかりません。
一方、ファイルサーバーは導入時のコストが高額になりやすい傾向があります。ファイルサーバーのシステムを構築するには、複数のハードウェアやミドルウェア、ソフトウェアを組み込む必要があり、さらには設置するための工事も欠かせません。また、サーバー内に含まれるOSを定期的に更新する必要があるため、メンテナンスコストも発生します。
カスタマイズ性
NASサーバーは、購入した段階である程度の初期設定が可能ですが、ファイルサーバーほど柔軟にシステムをカスタマイズできるわけではありません。ファイルサーバーは、さまざまなハードウェアやソフトウェアを組み合わせてシステムを構築する分、細かい要件でもシステムに反映しやすいメリットがあります。そのため、システムそのものに柔軟性が生まれ、大規模な組織でも活用しやすくなります。
セキュリティの高さもファイルサーバーに軍配があがります。システムの細かい仕様だけでなく、自社のセキュリティポリシーや要件を柔軟に適用できるため、より安全にデータ管理を行うならファイルサーバーがおすすめです。
NASサーバーとファイルサーバーのどちらを選ぶべきか
ここまでに紹介した通り、NASサーバーとファイルサーバーにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、両者の違いを理解して選び分けることが重要です。以下で選択基準の一例を紹介しているので、参考にしてください。
NASサーバーが向いているケース
次のようなケースに該当する場合は、NASサーバーを導入するのがおすすめです。
- サーバーやネットワークの運用ノウハウが少なく、手軽にストレージ環境を構築したい
- 導入コストや運用コストを最小限に抑えたい
- USBメモリや外付けHDDでデータを管理する際の紛失や盗難のリスクを回避したい
現状、USBメモリや外付けHDDといった一般的なストレージデバイスでデータ管理を行っている場合は、まずスモールスタートとしてNASサーバーから導入するのが良いでしょう。専門的な知識や大がかりな手続きが必要になるファイルサーバーに比べ、NASサーバーは導入時の手軽さが魅力です。コストや手間を最小限に抑えつつ、いままで使っていたストレージデバイスよりも利便性や安全性を高められるメリットがあります。
ファイルサーバーが向いているケース
次のようなケースに該当する場合は、ファイルサーバーを導入するのがおすすめです。
- データ管理に対するニーズが細分化しており、NASサーバーだけで補完するのが難しい
- 機密情報の漏えいリスクが高く、よりセキュアなデータ管理の環境が必要
- 多くの部署をまたいで大多数のユーザー同士でデータを共有しなければならない
NASサーバーの難点としては、ユーザー数やデータ量が増大すると対応しにくい、対策できるセキュリティの内容が限定されるといった点があげられます。そのため、システムの仕様やセキュリティに関する要件が厳しく、情報共有すべき従業員の数が多いような場合には、カスタマイズ性と拡張性に優れるファイルサーバーが向いています。
大規模な組織で無理にNASサーバーを利用すると、デバイスへのトラフィックが増加するとともに負荷が高まり、処理速度が大きく低下する恐れがあります。一方のファイルサーバーは、システムの規模に応じて柔軟に増設や容量拡張を行えるため、常に高い処理性能を発揮できます。
クラウドストレージでデータを保管するのも手段の一つ
データ管理の手段としては、NASサーバーやファイルサーバーに加え、クラウドストレージも選択肢にあがります。クラウドストレージとは、サービス提供事業者が運用するサーバーでデータを管理できるサービスです。WebブラウザからIDとパスワードを使ってログインするだけで、クラウド上にデジタル文書や画像、動画などのファイルをアップロードできるため、ハードウェアやソフトウェアを用意する必要がありません。
クラウドストレージにはさまざまな種類がありますが、まずは無料で利用できるGoogleドライブを活用してみてはいかがでしょうか。Googleドライブはその名称の通り、世界トップレベルの安全性を誇るGoogleのサーバーを利用できます。ExcelやWord、PDFに加え、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートなどのファイルをまとめて管理できるのが特徴です。
無料版のGoogleドライブは、1ユーザーあたり15GBまでデータを保存できます。さらに容量が必要な場合は有料版にアップグレードすることで、1ユーザーあたり30GB~5TBまで拡張が可能です。
Googleドライブの特徴や機能、導入方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
自社にとって最適なデータ管理体制を築こう
今回はNASサーバーの特徴やメリットを紹介しましたが、データ管理の手段はそのほかにもさまざまな選択肢があります。USBメモリや外付けHDD、ファイルサーバー、クラウドストレージなど、それぞれのメリットとデメリットを理解し、適切な環境を構築することが重要です。
NASサーバーとファイルサーバーを比較した場合は、事業規模や業務環境、予算の範囲によって選択すると良いでしょう。事業規模が比較的小さく、取り扱うデータ量も限られている場合は、導入ハードルの低いNASサーバーが向いています。一方、ファイルサーバーは、大規模な組織で従業員数も多く、大容量のデータを管理する場合に役立ちます。
また、NASサーバーやファイルサーバーではなく、クラウド上でデータを一元管理したい場合は、手軽に導入できるGoogleドライブを活用するのがおすすめです。Googleドライブでは、クラウド上でファイルを一元管理できるため、オンプレミス環境のように物理的なサーバーを用意する必要がありません。ファイルサーバーとしてGoogleドライブを活用するメリットや方法に関しては、こちらの資料で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- NASサーバ