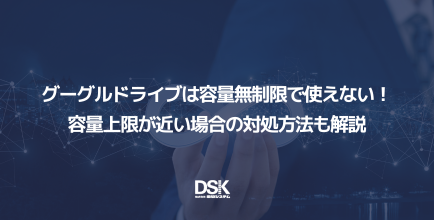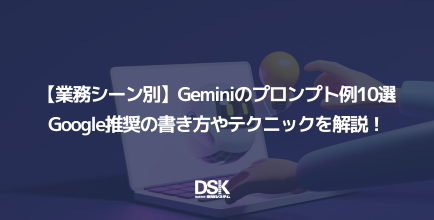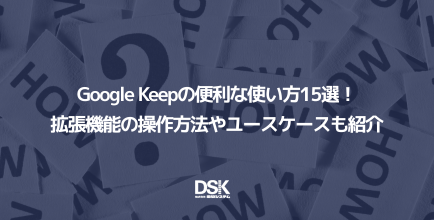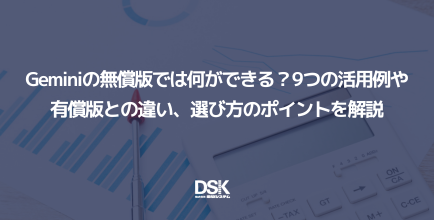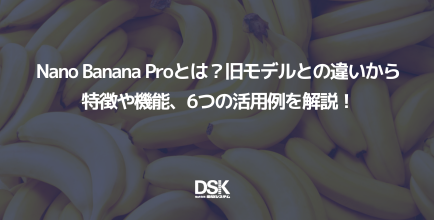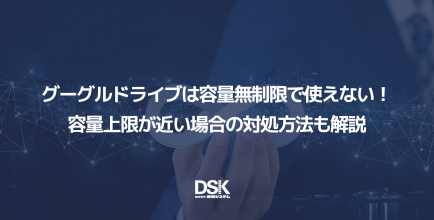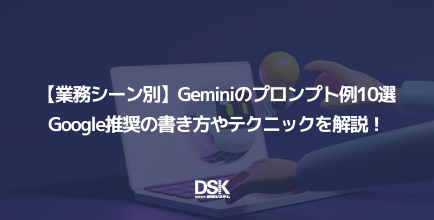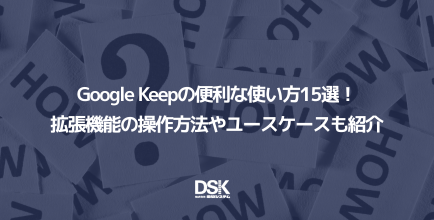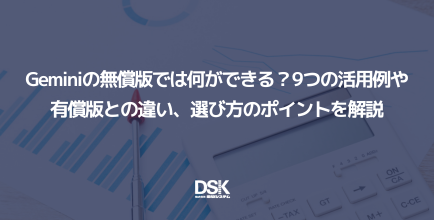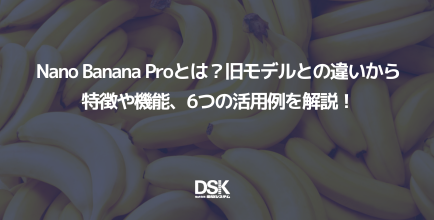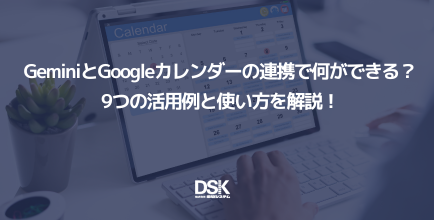サーバーとは何か問われた際に、説明が難しいと感じる方は多いのではないでしょうか。サーバーは、あらゆるサービスやシステムを支える重要なコンピュータです。サーバーの種類や役割を知れば、サーバーの移行や導入の際に役立ち、普段利用しているメールソフトやWebサイトがどのように成り立っているのかを理解できます。
この記事では、サーバーの概要や仕組み、種類などを詳しく解説しています。IT初心者の方にもわかりやすいように内容をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
サーバーとはネットワークを通じて利用者にサービスを提供するコンピュータのこと
サーバーとは、利用者にネットワークを介して何らかのデータを提供するコンピュータのことです。英語では「Server」と表記され、日本語に直訳した場合「提供する側」という意味になります。サーバーは、あらゆるシステムに必ず存在しており、メールの送受信やSNSへの投稿なども、サーバーの活躍によって実現しています。
例えば、インターネット上にあるWebサイトも、サーバーが利用されているシステムの1つです。検索エンジンに表示された検索結果の中から、利用者がページタイトルをクリックした際に、Webサイトデータが保管されたサーバーからリクエストされたページ情報が提供されます。サーバーは、データの保管やリクエストに応じた適切な情報提供の役割を担っており、すべてのシステムに欠かせない存在です。
サーバーの仕組み
サーバーの仕組みは、一般的なパソコンと基本的に同じです。パソコンがソフトウェアをインストールして画像編集や文書作成、インターネット検索などができるのと同様に、サーバーもソフトウェアやOSをインストールしてはじめて機能します。
サーバーに必要なソフトウェアやOSがインストールされていなければ、利用者からリクエストがあっても情報を提供できず、サーバーとして機能しません。サーバーを運用するには、メールの送受信やWebサイトの管理など、用途に応じたソフトウェアやOSのインストールが必要です。
サーバーは、パソコンと同様にCPUやドライブなどの部品によって構成されています。サーバーを構成する代表的な部品は、以下の通りです。
- CPU:さまざまな処理を行う中央処理装置
- マザーボード:CPUやグラフィックボードなどのパーツを設置して、電源を供給する電子回路基板
- サウンドボード:音声を出力する部品
- グラフィックボード:映像を画面に出力する部品
- メモリ:一時的にデータを保存するメインの記憶装置
- ドライブ:データを保存する記憶装置
- 電源
サーバーは、仕組みや代表的な構成部品がパソコンと同じですが、用途の違いから、パソコンよりも以下の点が重視されています。
- 安定性
- 耐久性
- セキュリティ
サーバーは複数人が同時に利用するため、優れた安定性と処理能力が必要です。安定性と処理能力が高いサーバーを用意すれば、多くの利用者が同時にシステムを使用しても、問題なく処理を実行できます。
【利用環境別】サーバーの種類
サーバーの種類は、利用環境や用途によって分類されます。IT技術の発展により、今では多くの種類があるサーバーですが、利用環境で大きく分類した場合は、以下のように分けられます。
| 利用環境の大別 | 分類 | 概要 | 特徴 |
| 物理サーバー | 共用サーバー | 複数人で1台のサーバーを使用するもの |
|
| 専用サーバー | 1台のサーバーを自社専用で使用するもの |
|
|
| 仮想サーバー | VPS | 自分専用のサーバーを仮想上で使用できるもの |
|
| クラウドサーバー | 複数の物理サーバーが構築した仮想上にあるサーバーを使用できるもの |
|
利用環境別に分類した際のそれぞれのサーバーの特徴は、以下の通りです。
物理サーバー
物理サーバーとは、物理的に設置・運用されている1台のサーバーです。一般的にサーバーと呼ばれるものは「物理サーバー」を指している場合が多くあります。物理サーバーは、以下の2種類に分けられます。
- 共用サーバー
- 専用サーバー
それぞれのサーバーの特徴は、以下の通りです。
共用サーバー
共用サーバーとは、複数人で1台のサーバーを使用することです。共用サーバーの代表的なものである「レンタルサーバー」では、複数の契約者が1つのサーバーを共有して使用します。共用サーバーを利用するメリットは、以下の2つです。
- 低コストでサーバーを使用できる
- 自社でサーバーを運用・保守する必要がない
共用サーバーの場合は、複数人で1台のサーバーを共有するため、後ほど解説する「専用サーバー」と比較して、低コストでサーバーを使用できます。また、サーバーの運用・保守はサービス事業者が行うため、自社のリソースを大幅に削減可能です。一方で、共用サーバーにも以下のようなデメリットがあります。
- カスタマイズの自由度が低い
- 処理速度が遅くなる場合がある
共用サーバーでは、自社専用にサーバーをカスタマイズできません。また、他の利用者と使用するタイミングが重なり、サーバーへの負荷が大きくなれば、処理速度が遅くなる場合もあります。そのため、共用サーバーは、小規模のサービスや個人利用の際におすすめです。
専用サーバー
専用サーバーとは、1台のサーバーを自社専用で使用することです。専用サーバーには、以下のようなメリットがあります。
- カスタマイズの自由度が高い
- セキュリティを強化できる
専用サーバーは、自社に合わせて自由にOSやアプリケーションを変更・設定できます。また、機密情報を安全に保護するために、独自のセキュリティシステムも構築・実装可能です。カスタマイズの自由度やセキュリティの高さを重視したい方は、専用サーバーの利用がおすすめです。専用サーバーの導入を検討する際は、以下の点に注意しましょう。
- 運用・保守を自社で行わなければならない
- 費用が高額になる
専用サーバーでは、サーバーの運用・保守をすべて自社で行わなければなりません。サーバーの運用・保守を行う管理者を決めて、24時間365日稼働するサーバーを管理し、問題が起きれば、自社で対処する必要があります。そのため、サーバーの運用・保守に高額な費用がかかり、自社独自のシステムを構築・実装する場合は、さらに多くの費用がかかります。専用サーバーは、大規模なサービスに対して企業がまとまった予算を確保できる場合におすすめです。
仮想サーバー
仮想サーバーとは、複数のOSを1台の物理サーバーの中で稼働させて、物理サーバーが複数あるかのように機能したサーバーのことです。仮想サーバーは、以下の2種類に分けられます。
- VPS
- クラウドサーバー
それぞれのサーバーの特徴は、以下の通りです。
VPS
VPSとは、自分専用のサーバーを仮想上で使用できるシステムです。Virtual Private Serverの頭文字を取って、VPSと呼ばれています。VPSは、レンタルサーバーのように1台の高性能なサーバーが稼働しており、複数の利用者が使用します。VPSを利用するメリットは、以下の通りです。
- コストが抑えられる
- カスタマイズの自由度が高い
VPSは、それぞれの利用者に仮想上にあるサーバーが構築・提供されるため、専用サーバーのように自社でサーバーを購入・運用・保守する必要がなく、コストを抑えられます。また、レンタルサーバーよりも自由にサーバーのカスタマイズが可能です。
クラウドサーバー
クラウドサーバーとは、複数の物理サーバーが構築した仮想上にあるサーバーを使用できるシステムです。クラウドサーバーを提供するサービス事業者は、複数のデータセンターに設置した物理サーバーを運用しており、利用者に合ったスペックの仮想サーバーが用意される仕組みになっています。クラウドサーバーを利用するメリットは、以下の通りです。
- 導入する手間が少ない
- カスタマイズの自由度が高い
クラウドサーバーは、インターネット上の手続きで簡単に利用を開始でき、低コストで導入できます。また、VPSよりもカスタマイズの自由度や性能が高い点も特徴です。クラウドサーバーは、従量制のサービスが多いため、利用条件によっては、コストが高くなる場合があります。
【用途別】サーバーの7つの分類
サーバーの種類を用途別に分類した場合は、以下のように分けられます。
| 用途別のサーバーの種類 | 概要 |
| Webサーバー | Webサイトのデータを保管し、リクエストがあった際にWebブラウザに情報を送るサーバー |
| メールサーバー | メールの送受信を管理するサーバー |
| データベースサーバー | データをまとめて管理し、データの保存や検索、更新、バックアップをするサーバー |
| ファイルサーバー | ネットワーク上にデータを保管し、複数人での使用・共有を可能にするサーバー |
| アプリケーションサーバー | プログラミング言語で構築されたプログラムを動作させるサーバー |
| FTPサーバー | 利用者とWebサーバーの間で行われるファイル送受信を管理するサーバー |
| DNSサーバー | ドメインとIPアドレスを管理・照合する役割を担うサーバー |
用途別に分類した際のそれぞれのサーバーの特徴は、以下の通りです。
Webサーバー
Webサーバーとは、Webサイトのデータを保管し、リクエストがあった際にWebブラウザに情報を送るサーバーのことです。Webサイトの運営に無くてはならない存在で、HTMLファイルやCSSファイル、画像、動画などのデータを保管しています。Webブラウザでリクエストされたサイトページを表示させるために、必要なデータを送ってくれます。
メールサーバー
メールサーバーとは、メールの送受信を管理するサーバーのことです。メールサーバーは、以下の複数のサーバーによって成り立っています。
- DNSサーバー
- SMTPサーバー
- IMAPサーバー
- POPサーバー
メールの送信はSMTPサーバーが行い、受信はIMAPサーバーもしくはPOPサーバーによって管理されます。DNSサーバーは、メールのドメイン名とIPアドレスを管理・照合する役割を担うサーバーです。メールサーバーについては、以下の記事でより詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひご覧ください。
データベースサーバー
データベースサーバーとは、データをまとめて管理し、データの保存や検索、更新、バックアップをするサーバーのことです。利用者は、プログラム言語を使ってデータベースサーバーにリクエストを送り、必要なデータの検索、新しいデータの保存、既存データの削除などを行います。
データベースサーバーは、他のサーバーと連携して活用される場合が多くあります。例えば、Webサーバーとの連携によって、Webサイト上で検索条件に該当する商品情報の表示が可能です。
ファイルサーバー
ファイルサーバーとは、ネットワーク上にデータを保管し、複数人での使用・共有を可能にするサーバーのことです。ファイルサーバーには、以下の2種類があります。
- オンプレミス型:自社に設置して運用・管理するファイルサーバー
- クラウド型:クラウド上に構築されたファイルサーバー
オンプレミス型とクラウド型では、コスト面やカスタマイズの自由度などが大きく異なります。ファイルサーバーについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
アプリケーションサーバー
アプリケーションサーバーとは、Ruby、Java、PHPなどのプログラミング言語で構築されたプログラムを動作させるサーバーのことです。複数人がアプリケーションを利用する場合は、プログラムを動作させるためにアプリケーションサーバーが必要です。アプリケーションサーバーは、Webサーバーとデータベースサーバーの2つのサーバーと連携してアプリケーションを動作させます。
FTPサーバー
FTPサーバーとは、利用者とWebサーバーの間で行われるファイル送受信を管理するサーバーのことです。FTPは、File Transfer Protocolの頭文字を取っており、日本語ではファイル転送プロトコルと訳されます。
FTPサーバーは、Webサイト作成に必要不可欠なサーバーの1つです。FTPサーバーがあってはじめて、利用者はWebサーバーへのファイルアップロードが可能になります。Webサイトを作成する際にFTPサーバーがなければ、サイトを構成するHTMLファイルやCSSファイルなどのデータをWebサーバーにアップロードできません。
DNSサーバー
DNSサーバーとは、ドメインとIPアドレスを管理・照合する役割を担うサーバーのことです。DNSは、Domain Name Systemの頭文字を取っています。IPアドレスは、インターネット上の住所のようなもので、コンピュータが理解できるよう数字の羅列で構成されているため、人間が判別しやすいようドメインと紐づけてDNSサーバーが管理しています。
DNSサーバーは、Webサイトの表示に欠かせないサーバーの1つです。DNSサーバーによって、入力されたWebサイトのドメインから該当するIPアドレスが割り出されて、表示リクエストのあったサイトページが表示されます。
サーバーに不可欠な保守とは
サーバーを利用する際には、保守業務が必要不可欠です。サーバーは24時間365日の稼働が基本になり、万が一トラブルによって停止すれば、サービスや業務の遅延・停止を招きます。以下の解説を読んで、サーバーにおける保守業務の重要性を把握しましょう。
サーバーの保守業務とは
サーバーにおける保守業務とは、具体的には以下のような業務を指します。
- トラブルの発生を想定して対策を行い、サーバーが常に安定して稼働するよう準備すること
- トラブルが発生した際に素早く復旧作業を行うこと
サーバーの保守業務は、運用管理と混同されがちですが、厳密には異なります。サーバーの運用管理にあたる業務は、サーバーの安定した稼働を目的とした点検とアップデートです。保守業務はトラブル対応が軸になっているのに対して、運用管理では日常的に安定した稼働を維持することが軸になっています。
サーバーは、購入の際に利用できるメーカーの保守サービスに加入してサポートを受ける場合が一般的ですが、サポート期間が終了した後は、自社のみで保守業務を行わなければなりません。第三者保守業者のサービスも利用しながら、サーバーの保守業務を徹底して万全な状態を維持しましょう。
サーバー保守が必要な理由を解説
サーバーに保守が必要なのは、物理サーバーが寿命のある部品で構成されていることが大きな理由です。保守業務を行わなければ、部品の老朽化が進み、いずれサーバーが正常に稼働しなくなります。サーバーの停止は、サービスや業務の遅延もしくは停止を招き、金銭的な損失に加え顧客や取引先からの信用低下につながります。
サーバーの停止を防ぐには、日頃の徹底した保守業務とトラブルに備えた対策が必要です。トラブル対策の具体例としては、素早く復旧作業ができる人材で構成された保守チームを設置すれば、トラブルが発生しても、被害を最小限に抑えられます。
Google Workspaceを契約するとレンタルサーバーは不要
サーバーの移行や導入を検討している方には、クラウドサービスのGoogle Workspace(旧G Suite)がおすすめです。Google Workspaceは、メールや資料作成、スケジュール管理、ストレージなどのさまざまなツールをまとめて利用できるグループウェアです。
Google Workspaceを導入すれば、メールサーバーやファイルサーバーを別々に契約する必要がなく、レンタルサーバーも必要ありません。また、サーバーの運用・管理・保守もすべてサービス事業者が行ってくれるため、コストや手間を削減でき、自社の業務に集中できます。
Google Workspaceでは、導入の際に独自ドメインを取得できます。自社の独自ドメインを取得して、スムーズに従業員ごとのメールアドレスも作成でき、メールサービスを素早く導入可能です。加えて、メール転送やメーリングリスト、スパムメールフィルタなどの豊富な機能も利用できます。他にも、Google Workspaceには以下のような優れた特徴があります。
- インターネット環境があれば、場所にかかわらずツールを利用できる
- Googleのツールと連携して、シームレスに情報共有ができる
- 1つのファイルを複数人で同時編集できる
Google Workspaceについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
サーバーの導入で自社に合ったサービスを活用しよう
サーバーとは、利用者にネットワークを介してデータを提供するコンピュータのことです。サーバーにはいくつかの種類があり、利用環境で大別した場合は「物理サーバー」と「仮想サーバー」に分類されます。サーバーは種類が変わっても、リクエストされた情報をメモリから探して送るという基本的な役割は変わりません。メールの送受信やWebサイトの閲覧など、目的に応じてサーバーがデータを管理する役割を担います。
サーバーの運用には、保守業務が必要不可欠です。保守業務が徹底されていなければ、サーバーの停止を招き、サービスや業務の停止につながります。保守業務には、人件費や機器購入費などさまざまなコストがかかりますが、Google Workspaceを導入すれば、コストや手間を大幅に削減可能です。サーバーの保守業務はサービス事業者が行い、サイバー攻撃や自然災害に備えた安全な環境でサーバーが管理されているため、自社のサービスや業務が停止するリスクを低減できます。
サーバーの移行や導入を検討している方は、Google Workspaceの導入をぜひ検討してみてください。以下のページでは、サーバーの移行やGoogle Workspaceについてわかりやすく解説した資料を無料でダウンロードできます。興味のある方は、ぜひご覧ください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- サーバーとは