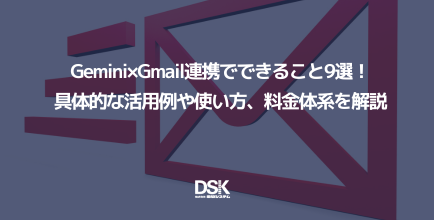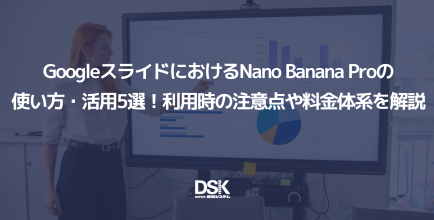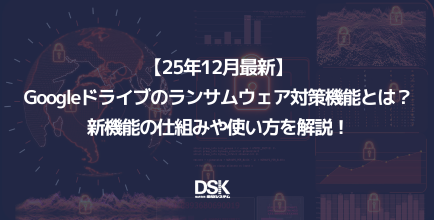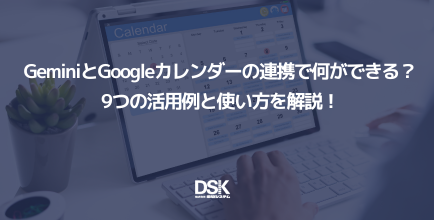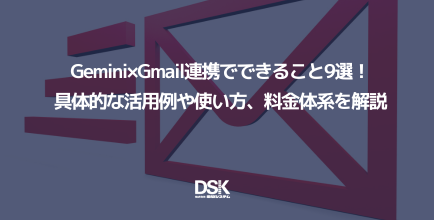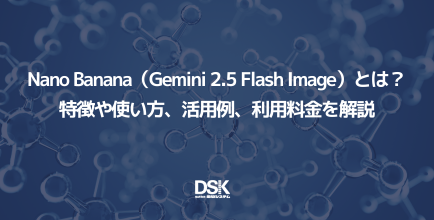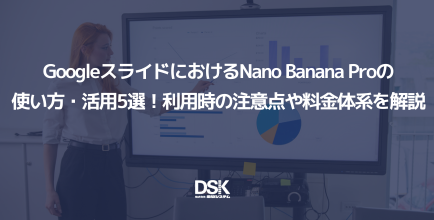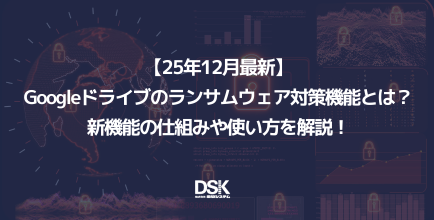Googleフォームはパソコンだけでなく、スマホでも作成することが可能です。スマホであれば場所を問わずに利用できるため、外出中や出張中などでも気軽にフォームを作成できるのが利点です。
ただし、スマホ版はパソコン版とレイアウトが異なるため、スマホ特有の使い方やフォームの作り方を理解しておく必要があります。パソコンとスマホの両方の使い方を押さえることで、Googleフォームの活用の幅が広がるでしょう。
本記事では、スマホを使ったGoogleフォームの作り方を詳しく解説します。また、細かいテクニックを使った応用や、作成時のポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
スマホでGoogleフォームを作成する際の注意点
Googleフォームには、iOSやAndroid用のアプリがありません。そのため、スマホでGoogleフォームを作成するには、Google ChromeやSafariといったWebブラウザを利用する必要があります。
アクセス方法は単純で、Webブラウザの検索エンジンで「Googleフォーム」と検索し、上位に表示された公式サイトにアクセスするだけです。または、Googleフォーム公式サイトのURLに直接アクセスするのでも構いません。
また、Googleフォームを利用するには、Googleアカウントが必要です。以下で登録方法を紹介しているので、Googleアカウントを保有していない場合は、事前に作成しておきましょう。
スマホを使ったGoogleフォームの作り方(iOS・Android共通)
スマホでGoogleフォームを作成する手順は次の通りです。
- フォームの新規作成
- テーマをカスタマイズ
- タイトルと概要を記載
- 質問項目の作成
- 質問項目の設定
- 画像・動画の挿入
- 共有設定
- プレビュー・公開
- 回答結果の確認
それぞれの手順に沿って、フォームの作り方や設定方法を解説します。
1. フォームの新規作成
スマホのWebブラウザからGoogleフォームの公式サイトにアクセスし、画面上の[ログイン]をタップします。

Googleアカウントのログイン画面に移行するので、Gmailアドレスとパスワードを入力します。なお、Google Chromeを利用している際にGoogleアカウントにログイン済みの場合は、[ログイン]をタップすると即座にGoogleフォームの画面が開きます。
ログイン手続きが完了すると、Googleフォームの新規フォーム画面が現れます。

なお、新規作成ではなく、作成済みのフォームを開く場合は、画面下部のツールバーから[質問をインポート]のアイコンをタップしましょう。

すると、Googleドライブに保存された既存のフォームが表示されます。

[最新使用したアイテム]や[マイドライブ]、[共有アイテム]などのタブを切り替えつつ、編集したいフォームを選択しましょう。
2. テーマをカスタマイズ
新規のフォームを作成する場合は、まず全体のレイアウトを調整します。画面上部のパレット([テーマをカスタマイズ]の)アイコンをタップしましょう。

すると、次のような編集画面が表示されます。

それぞれの項目では次のような設定が可能です。
- テキストスタイル:
ヘッダー、質問項目、テキストごとにフォントの種類とサイズを変更できる - ヘッダー:
ヘッダーに表示するサムネイル画像を任意で追加できる - 色:
フォームの背景色を変更できる
設定が完了すれば、画面上部の[適用]をタップします。設定した内容はフォーム全体に反映されます。
3. タイトルと概要を記載
次に、フォームのタイトルを決めます。フォームの最上部にタイトルの入力項目が用意されているため、任意のテキストを記載しましょう。

また、タイトルの下側に概要を入力するスペースもあります。概要欄の入力は任意ですが、フォームの内容や回答にあたっての注意点などを記載しておくことで、フォームの目的が明確になります。
4. 質問項目の作成
続いて、質問項目を作成します。新規フォームには、デフォルトで一つだけ新規の質問項目が用意されているため、そのなかに直接質問内容を入力しましょう。まずは、タイトルの枠内に質問の内容を記載します。

そして、回答方法をプルダウンリストから選択します。回答方法はラジオボタンやチェックボックス、記述式などの種類がありますが、それぞれの使い方や詳細は後ほど詳しく解説します。

最後に、回答の選択肢を設定します。それぞれの選択肢をタップすると、回答のテキストを編集できます。回答を消去する場合は[×]マークを、追加する場合は[選択肢を追加]の欄に回答テキストを入力しましょう。

なお、質問項目を追加する場合は、画面最下部のツールバーから[質問を追加]のアイコンをタップします。

5. 質問項目の設定
質問項目を作成した後は、必要に応じて細かな設定を行いましょう。
質問項目の下部にある[必須]のトグルボタンをオンにすると、必須項目に変更できます。必須項目は、必ず回答を選択あるいは入力しなければなりません。回答者の氏名や連絡先をヒアリングしたり、どうしても回答してほしい質問を行ったりする場合は、必須項目に変えておくのがおすすめです。

また、質問項目に説明(概要文)を記載することも可能です。説明は質問の補足や注釈を入れる際に役立ちます。例えば、「メールアドレスを入力してください」という質問に対して、「GmailやYahoo!メールなどのフリーメールアドレスは入力できません」といった補足を付け加える場合に便利です。
説明を追加する場合は、下部の三点リーダをタップし、そのなかから[説明]を選択します。

さらに、選択肢形式の質問を行う場合のみ、[選択肢の順序をシャッフルする]をタップすると、回答の度に選択肢がランダムで表示されるようになります。

選択肢のシャッフルは、テスト形式でフォームを作成する際に役立ちます。テストでは、回答の順番を覚えて不正に回答を行うケースもありますが、選択肢をシャッフルすることでその行為を未然に防ぐことが可能です。
6. 画像・動画の挿入
Googleフォームには、質問項目だけでなく画像や動画も挿入できます。
画像を挿入するには、画面最下部のツールバーから[画像挿入]のアイコンをタップします。

すると、画像の選択画面が表示されます。ローカルストレージから画像をアップロードできる[アップロード]や、挿入する画像のURLを入力する[URL]などのタブを切り替え、目的の画像を選択しましょう。また、GoogleドライブやGoogleフォトに保存された画像も選択できます。

動画を挿入する場合は、ツールバーから[動画を挿入]のアイコンをタップします。

挿入できるのはYouTubeの動画に限定されます。検索窓にキーワードを入力すると、YouTube内の関連する動画がヒットします。また、YouTube動画のURLを貼り付けて指定することも可能です。

7. 共有設定
フォームを公開する前に共有設定を行いましょう。画面上部のメニューバーにある人型のアイコンをタップすることで、共有設定画面が開きます。

この画面では、同フォームに対するアクセス権限を設定できます。[ユーザー、グループ、カレンダーの予定を追加]の欄にGoogleアカウントを記載すると、そのアカウントを保有するユーザーを招待できます。招待したユーザーに対しては、編集者または回答者の権限を付与できる仕組みです。

また、[一般的なアクセス]の編集者ビューと回答者ビューを変更することもできます。

編集者ビューはデフォルトで「制限付き」の状態になっているため、ほかのユーザーにアクセス権限を与えない限り、フォームの作成者以外は閲覧や編集ができません。そこで、「制限付き」を「リンクを知っている全員」に変更することで、共有リンクを付与されたすべてのユーザーがフォームを閲覧・編集できるようになります。
回答者ビューはデフォルトで「リンクを知っている全員」の状態になっています。そのため、共有リンクをメールやチャットなどで回答者に送付することで、その人がフォームにアクセスして回答を行えます。反対に「制限付き」に変更すると、招待したGoogleアカウントのユーザーしか回答できなくなるので注意が必要です。
設定が完了すれば、画面下部の[完了]をタップしましょう。
8. プレビュー・公開
ここまでの設定が完了すればフォームを公開できますが、その前にプレビューを行いましょう。プレビューでは、本番環境と同様のレイアウトでフォームを確認でき、一つひとつの質問項目に対して回答することも可能です。「テキストに誤りがないか」「回答ボタンは正常に動作するか」といった点を確認しておくことで、本番でのミスやエラーを防げます。
プレビュー機能を使用するには、画面上部のメニューバーから三点リーダをタップします。

そして、[プレビュー]を選択しましょう。

プレビューでフォームを確認し、問題がなければ公開手続きを行います。画面上部のツールバーから紙飛行機([公開]の)アイコンをタップしましょう。

なお、フォームの公開後は共有リンクをコピーできるようになります。共有リンクは、ツールバーの[共有リンク]のアイコンをタップすると表示されます。

取得した共有リンクは、共同編集者や回答者にメールやチャットなどで送信します。共有リンクを受け取ったユーザーは、そのURLにアクセスすることで閲覧や編集、回答が可能になります。
9. 回答結果の確認
フォームを公開した後は、回答者からのすべての回答を待つことになります。すべての回答が終了すれば、再びフォームの編集画面にアクセスし、画面上部のタブを[回答]に切り替えましょう。すると、回答結果を確認できます。

Googleフォームでは、回答結果は自動的に集計され、グラフや表によってわかりやすく可視化されます。ただし、Googleフォーム内では、グラフや表などの要素を自由にカスタマイズすることはできません。
そこで、回答結果を分析レポートなどにカスタマイズしたい場合は、Googleスプレッドシートと連携するのがおすすめです。画面上のGoogleスプレッドシートのアイコンをタップしましょう。

Googleスプレッドシートと連携する際は、新しくスプレッドシートを作成するか、既存のスプレッドシートに情報を反映させるかを選択できます。いずれの場合でも、シート内に回答結果の内容やグラフなどが出力されるため、Googleスプレッドシートの機能を使って自由にカスタマイズが可能です。
応用テクニックを使ったスマホでのGoogleフォームの作り方
スマホでGoogleフォームを作成する際は、便利な機能を使用することも可能です。便利な機能を使用することで、主に次のようなことが可能になります。
- セクションの追加
- 条件分岐
- 進行状況バーの表示
- メールの通知設定
- メールアドレス収集用の項目を自動生成
- テスト形式への変更
それぞれ、設定方法や機能の使い方を解説します。
セクションの追加
セクションとは、複数の質問項目をテーマ別に分割できる機能です。例えば、回答者の氏名や連絡先を質問する項目はセクション1へ、アンケートなどのメインの質問項目はセクション2へといった形で、セクションごとに共通の質問項目を配置できます。
セクションを追加するには、画面最下部のツールバーから[セクションを追加]のアイコンをタップします。

追加したセクションの下部には、質問や画像、動画など、自由に項目を配置できます。また、既存の項目をセクションの下部に移動させる場合は、項目の上部をタップしたまま、ドラッグ&ドロップで任意の箇所まで移動させましょう。

条件分岐
セクションの機能を活用することで、質問項目を条件分岐させることが可能です。例えば、「参加の可否をお選びください」の質問に対して、「参加可能」と答えた人のみセクション1の質問項目へ、「参加不可」と答えた人にはセクション2の質問項目へと、それぞれ分岐するようなイメージです。
条件分岐を設定するには、まず一つ目の選択肢で分岐するセクションと、二つ目の選択肢で分岐するセクションを作成します。それぞれのセクションにはタイトルを設定しましょう。

そして、セクションの下部に新たな設問項目を追加します。

これで、「参加可能」と回答した人に対してのみ、「連絡先を入力してください」という質問項目が表示されるようになります。
続けて、条件分岐の設定を行います。分岐前の質問項目に移動し、三点リーダをタップしてから[回答に応じてセクションに移動]を選択しましょう。

すると、回答の選択肢のなかにセクションを選択できる項目が現れます。それぞれの選択肢が適切なセクションに分岐するよう、プルダウンのなかからセクションを選択してください。

これで条件分岐の設定は完了です。
進行状況バーの表示
複数のセクションを追加すると、その分、フォームのページ数が増えます。例えば、回答者としてフォームにアクセスした場合、初めにセクション1のページが表示され、その後にセクション2、セクション3へと順番にページが移行していきます。
このような点から、セクションを増やしすぎるとページ数が多くなり、回答者が疲労感やストレスを感じてしまう恐れがあります。そこで、各ページに進行状況バーを表示することで、回答の進捗状況が一目でわかるようになるため、回答者の負担軽減につながります。
進行状況バーを表示するには、まず編集画面上部のタブを[設定]に切り替えます。

そして、[表示設定]の項目をタップして開き、[進行状況バー]のトグルボタンをオンにします。

これで、回答時の各ページに進行状況バーが表示されるようになります。

メールの通知設定
メールの通知設定を行っておくと、回答後にフォームが送信される度に通知を受け取れるようになります。設定するには、編集画面上部のタブを[回答]に切り替え、三点リーダをタップします。そのなかにある[新しい回答についてのメール通知を受け取る]を選択しましょう。

これでメール通知の設定は完了です。なお、回答の通知は、フォーム作成者のGoogleアカウントに紐付くGmailに届きます。
メールアドレス収集用の項目を自動生成
アンケートや問い合わせフォームなどでは、回答者の連絡先としてメールアドレスを聴取するケースも珍しくありません。このような場合は、メールアドレス収集用の質問項目を作成することもできますが、Googleフォームの機能を使って自動生成することも可能です。
設定を行うには、まず編集画面上部のタブを[設定]に切り替えます。

そして、[回答]の項目をタップして開き、[メールアドレスを収集する]のプルダウンリストから目的のものを選択します。

[確認済み]を選択した場合、回答者がGoogleアカウントにログインの後、メールアドレスが自動入力されます。[回答者からの入力]を選択した場合は、Googleアカウントへのログインは必要なく、回答者が手動でメールアドレスを入力する形となります。
テスト形式への変更
テスト用のフォームを作成する場合は、テスト形式に変更するのがおすすめです。テスト形式にすると、点数の割り当てや解答の設定などが可能になり、テスト専用のフォームへと容易にカスタマイズすることができます。
テスト形式へと変更するには、まず編集画面上部のタブを[設定]に切り替えます。

そして、設定画面上部の[テストにする]のトグルボタンをオンにしましょう。

設定後は、質問項目の編集画面に[解答集を作成]の項目が現れます。それをクリックすると、設問ごとの正しい解答を設定したり、設問ごとに点数を割り当てたりできます。その状態でフォームを公開した場合、割り当てた点数に応じて自動採点が行われるため、作業の効率化につながります。
スマホでGoogleフォームを作成する際の3つのポイント
スマホでGoogleフォームを作成する場合、いくつか押さえておくべきポイントが存在します。それぞれのポイントについて詳しく解説します。
通信環境が良い場所でフォームを作成する
場所を選ばずに作業を行えるのはスマホの大きなメリットです。しかし、だからこそ公衆Wi-Fiといった不安定なインターネット環境下で作業をする機会も少なくありません。
Googleフォームには自動保存機能が搭載されており、作成した質問や回答内容、設定内容、共有情報などは、特別な作業を行うことなくリアルタイムで保存されます。しかし、自動保存が機能するのは、あくまでインターネットに接続している間のみです。そのため、インターネット接続が不安定な環境でフォームの作成作業をしていると、自動保存機能が働かず、作業内容が消えてしまうリスクも想定されます。
このような問題を防ぐには、通信環境が良い場所で作業を行うことが大切です。作業中はキャリア通信を使ったり、Wi-Fiを使用する場合でも信頼できる通信元を選んだりと、スマホならではの配慮が欠かせません。
回答方法の種類や使い方を押さえる
Googleフォームの質問項目を作成する際は、さまざまな回答方法を選択できます。ラジオボタンやチェックボックスなど、種類ごとに特徴があり、用途も異なるため、それぞれの違いや使い方を押さえることが重要です。
回答方法には次のような選択肢があります。
- ラジオボタン:複数の選択肢から一つだけ回答を選べる
- チェックボックス:複数の選択肢から複数の回答を選べる
- プルダウン:リスト形式の選択肢から一つだけ回答を選べる
- 均等目盛:1~5といった段階から一つの回答を選べる
- 選択式(グリッド):複数のラジオボタンを設置できる
- チェックボックス(グリッド):複数のチェックボックスを配置できる
- 記述式:短文の回答を入力できる
- 段落:改行可能な長文の回答を入力できる
- 日付:カレンダーから日付を選択して回答できる
- 時刻:特定の時刻を選択して回答できる
例えば、「はい・いいえ」といった複数の回答が成り立たない場合はラジオボタンが向いています。一方で、「自社商品を選んだ理由」など、複数の回答が成り立つ場合は、チェックボックスを使うのが効果的です。
適切な回答方法を選ぶには、事前に質問の内容を入念に検討しておくと良いでしょう。
状況に応じてパソコンと併用して作業を行う
スマホでGoogleフォームを作る場合は、アイコンや文字が小さくて見えないことも考えられます。また、ドラッグ&ドロップ中の画面スクロールが難しいこともあり、質問項目の配置変換がうまくいかないなど、操作性に不満を感じることもあるでしょう。
このような点から、無理にスマホだけで作業を行おうとせず、状況に応じてパソコンでの作業に切り替えることも大切です。パソコンであれば画面が大きくて文字の可読性が高く、操作性にも優れるので、フォーム作成中のヒューマンエラーの抑制にもつながります。
また、フォームの見え方はスマホとパソコンで大きな差があります。作成済みのフォームは、スマホとパソコンの両方でプレビューしてレイアウトを確認しておくと良いでしょう。
Googleフォームを活用するならGoogle Workspaceを導入するのがおすすめ
Googleフォームを最大限に活用する際は、Google Workspaceを導入するのがおすすめです。Google Workspaceとは、GoogleフォームやGmail、Googleドライブ、Google Meetなど、有料版のGoogleサービスが搭載されたツールです。
Google Workspaceを導入することで、無料で使っていたGoogleサービスが有料版へとアップグレードされます。それによりストレージ容量が拡張されるのが特徴です。本来、Googleアカウントのストレージ容量は1ユーザーあたり15GBに設定されていますが、有料版になると30GB~5TBにまで拡張されるため、Googleフォームはもちろん、GmailやGoogleドライブ、Googleフォトなどで保存できるデータ量も増えます。
また、Google Workspaceでは、エンドポイント管理の機能を利用できます。モバイル端末の利用状況や傾向をレポート化したり、業務用データをリモートワイプしたり、インストール可能なアプリを管理できたりと、エンドポイント管理には、スマホで作業を行う際に役立つ幅広い機能が備わっています。
スマホの利便性を活かしてGoogleフォーム制作の効率化を
どこにでも持ち運べるスマホだからこそ、場所を選ばずに作業を行える利点があります。この利点を活かすことで、外出先や出張中、テレワーク中などでも、スマホで効率良くGoogleフォームを作成できます。ただし、通信環境が悪いと自動保存機能が働かない恐れがあるため、インターネットを安定して利用できる場所で作業を行いましょう。
ビジネスシーンでGoogleフォームを利用するなら、無料版よりも大きな容量を確保できるGoogle Workspaceがおすすめです。Google Workspaceを導入することで、Googleフォームだけでなく、GmailやGoogleドライブといった20種類以上のGoogleサービスを有料版へとアップグレードできます。
電算システムでは、環境構築やコンサルティングなど、Googleサービスの導入支援サービスを提供しています。GoogleフォームやGmailいった個別のサービスはもちろん、Google Workspaceのサポートにも対応しています。専門領域に精通した数多くのエンジニアが在籍しているので、スピーディかつ質の高いサポートを行えるのが強みです。「Google Workspaceを活用したいが具体的なイメージが湧かない」といったお悩みを抱える方は、ぜひ電算システムへと気軽にお問い合わせください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- googleフォーム 作り方 スマホ