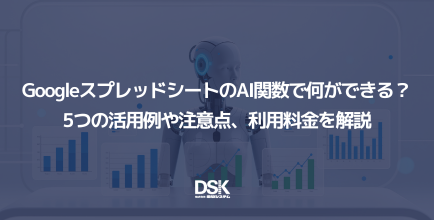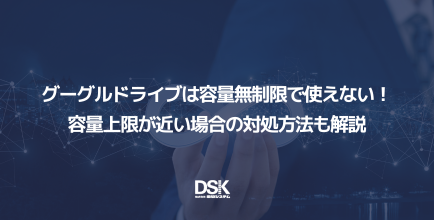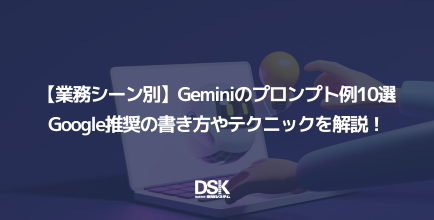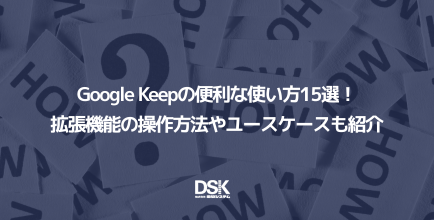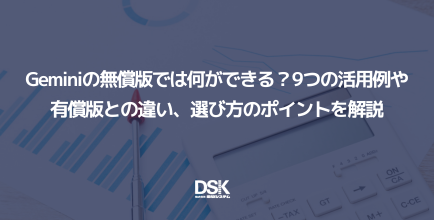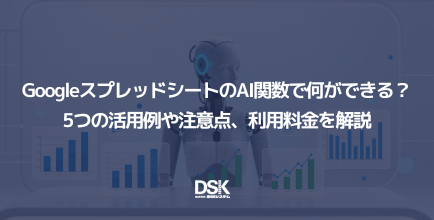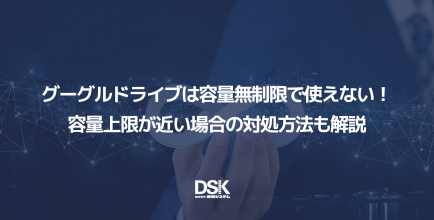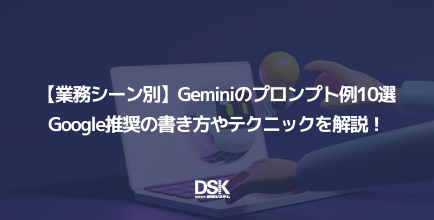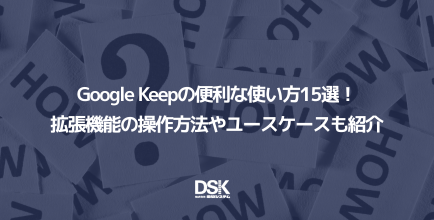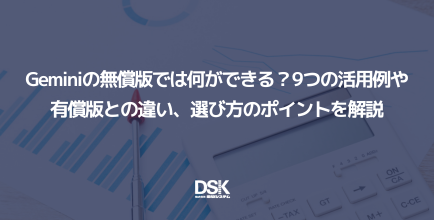Googleスライドは、無料で手軽に始められるクラウド型のスライド作成ツールです。ビジネスシーンでの資料作成やプレゼンテーションに活用され、アニメーションやプレゼンテーション中の質問受付など、優れた機能が豊富に備わっています。また、現在はGeminiを活用した資料作成を効率化する機能も利用可能です。
本記事では、Googleスライドでプレゼンテーション資料を作成する方法や編集方法、プレゼンテーションのクオリティを高める機能などについて解説しています。ツールの使い方やメリットまでわかりやすく紹介した内容になっているので、Googleスライドでプレゼンテーション資料を作成したいと考えている方は、ぜひご覧ください。
Googleスライドとは?概要を解説
Googleスライドとは、Googleドライブ上でプレゼンテーション資料をはじめとしたスライドショーを作成・編集できるクラウド型ツールです。Webブラウザから利用できるため、ソフトウェアのダウンロードは不要で、手持ちのデバイスからすぐにアクセスできます。
代表的な類似ツールにはPowerPoint(Microsoft 365)がよく挙げられます。PowerPointとは異なるGoogleスライドの特徴は、以下の通りです。
- 他のGoogleツールとスムーズに連携できる
- 無料で利用できる
- デバイスごとにソフトウェアをダウンロードする必要がない
- さまざまなデバイスから素早くファイルにアクセスできる
特に、Googleスライドの大きな強みは、他のGoogleツールと連携性です。例えば、Googleドキュメントで作成した表や文章をプレゼンテーション資料に反映させたり、Google Meet中に特定のプレゼンテーション資料を画面共有させたりできます。
こうした連携機能によって、資料の作成からプレゼンテーション実施までを効率良く進められる点が、Googleスライドの大きな魅力です。
Googleスライドでプレゼンテーション資料を作成する4つのメリット
Googleスライドを活用したプレゼンテーション資料の作成には、以下のような4つのメリットがあります。
- 同時編集が可能
- 外出先でも編集・閲覧が可能
- テンプレートが豊富
- 他のファイルからの移行が簡単
メリットを確認して、Googleスライドの特徴を把握しましょう。
同時編集が可能
Googleスライドでは、1つのファイルを複数人で同時に編集できます。部署やチームのメンバーで協力してプレゼンテーション資料を作成する場合や、上司に資料作成のアドバイスを仰ぐときなどに便利な機能です編集中は、自分以外のユーザーの編集箇所がリアルタイムでカーソルで表示され、誰がどこを編集しようとしているのかを把握できます。
また、Googleスライドにはチャット機能やコメント機能があり、リアルタイムでの会話や指示出しが可能です。ファイル上でやりとりをしながら作業を進められるため、チームでの資料作成がスムーズに進行します。
外出先でも編集・閲覧が可能
Googleスライドは、パソコンやタブレット、スマートフォンなど、複数のデバイスで利用できるマルチデバイス対応のツールです。インターネット環境があれば、どこからでもアクセス・編集が可能です。例えば、移動中にタブレットやスマートフォンでプレゼンテーション資料を確認したり、リモートワーク中は自宅のパソコンで資料を作成したりと、場所を選ばず業務を効率化できます。
また、Googleスライドでは、ファイルの編集履歴が自動で保存され、誰がいつどのような変更をしたのかを簡単に確認できます。チームメンバーと直接コミュニケーションを取らなくても進捗を把握できるため、共同作業の効率化にもつながります。
さらに、編集履歴を活用すれば、過去の状態へデータを復元することも可能です。万が一、誤って編集・削除してしまった場合も、編集履歴からデータを復旧できるため被害を最小限に抑えられます。
テンプレートが豊富
Googleスライドでは、新しいプレゼンテーション資料を作成する際に、テンプレートギャラリー(アプリ版では「テンプレート」と表記)から好きなデザインのテンプレートを選んで、活用できます。無料でさまざまなテンプレートを利用できるため、プレゼンテーション資料作成に不慣れな方や、デザインに自信のない方でも安心してクオリティの高い資料を作成可能です。
テンプレートの活用は、デザイン性の向上だけでなく、資料作成の時間短縮にもつながります。テンプレートをベースに作成するだけで、一から文字や画像を配置する手間やデザインを考える時間を削減でき、効率良くプレゼンテーション資料を作成できます。


他のツール・ファイルからの移行が簡単
Googleスライドは、プレゼンテーション資料をPowerPoint形式「.pptx」やPDF形式「.pdf」で出力できます。また、Googleスライドが対応しているファイル形式であれば、他のツールで作成された資料の読み込みも可能です。既存のツールで作成した資料をそのまま活用でき、ファイル変換の手間なくGoogleスライドへ移行できます。
ただし、他のツール独自のフォントがファイル内に使用されている場合、文字化けが発生する可能性があります。移行前に問題なくファイルを読み込めるかどうか、事前確認をおすすめします。
Googleスライドでプレゼンテーション資料を作成する方法
Googleスライドでプレゼンテーション資料を作成するには、基本的な操作方法を押さえることが重要です。ここでは初めての方でもスムーズに使えるよう、資料作成から共有までの基本操作を以下の7つに分けて解説します。
- 新しいスライドを準備する
- タイトル・サブタイトルを設定する
- スライドを追加する
- 作成したプレゼンテーション資料をダウンロード・共有する
- 資料をダウンロードする場合
- 特定の人にだけ資料を共有する場合
- リンクを知っている人全員に資料を共有する場合
新しいスライドを準備する
Googleスライドで新しいスライドを準備する手順は、以下の通りです。
- 任意のGoogleアカウントにログインする
- Googleの検索画面右上にあるメニューボタンをクリックする
- Googleスライドのアイコンをクリックする
- 「Googleスライドを使ってみる」をクリックし、アカウント情報を入力する
- Googleスライドのトップ画面にある「空白のプレゼンテーション」をクリックする
上記の手順で、新しいプレゼンテーション用のスライドを作成できます。テンプレートを使って資料を作成したい場合は、Googleスライドのトップ画面右上にある「テンプレートギャラリー」をクリックした後、好みのテンプレートをクリックしましょう。
タイトル・サブタイトルを設定する
Googleスライドで新しいスライドのタイトルを設定する手順は、以下の通りです。
- Googleスライドのトップ画面にある「空白のプレゼンテーション」をクリックする
- 「クリックしてタイトルを追加」と表示されている部分をクリックする
- 任意のタイトルを入力する
サブタイトルを設定したい場合は、同様に「クリックしてサブタイトルを追加」と表示されている部分をクリックして入力します。サブタイトルが不要な場合は、以下の手順で削除可能です。
- サブタイトルのテキストボックスにカーソルを合わせる
- 右クリックし、「削除」を選択する
スライド右側に表示されている「テーマ」から、プレゼンテーション資料に使用したいデザインを選べば、フォントや配色、背景、レイアウトが自動で設定されます。テーマの変更はいつでも可能ですが、スライドを多く作成した後ではレイアウトが崩れる恐れがあるため、できるだけ作成初期に設定しましょう。
スライドを追加する
Googleスライドで2枚目以降のスライドを追加するには、以下の操作を行います。
- スライドの編集画面左上にある「+」をクリックする
- 新しいスライドが末尾に追加される
特定の位置に新しいスライドを挿入したい場合は、以下の手順で操作します。
- 左側のスライド一覧から、追加したい位置(2枚のスライドの間)をクリックする
- スライドを追加したい箇所に青い横線が表示されたことを確認する
- 画面左上にある「+」をクリックする
- 指定位置に新しいスライドが追加される
Googleスライドでは、あらかじめ複数のレイアウトが用意されており、用途に応じて選択可能です。例えば以下のようなパターンがあります。
- タイトルと本文がスライド上部に配置されたレイアウト
- 本文のテキストボックスが2列で構成されたレイアウト
- 画像とテキストが左右に分かれた視覚的に整理しやすいレイアウト など
用途に応じてレイアウトを使い分けることで、作業の効率化が可能です。レイアウトを指定してスライドを追加する手順は、以下の通りです。
- 任意のファイルを開く
- スライドの編集画面左上にある「▼」をクリックする
- 希望のスライドレイアウトをクリックする
スライドを追加した後でもレイアウト変更は可能です。既存のスライドに対して別のレイアウトを適用したい場合は、以下の手順で行えます。
- 任意のファイルを開く
- レイアウトを変更したいスライドを選択する
- スライドの編集画面上部のツールバーにある「レイアウト」をクリックする
- 表示された一覧から希望のスライドをクリックする
作成したプレゼンテーション資料をダウンロード・共有する
作成したプレゼンテーション資料は、目的に応じてダウンロードしたり、社内外の関係者に共有したりできます。ここでは、その方法やコメント機能の活用方法を紹介します。
資料をダウンロードする場合
資料をローカル環境に保存したい場合、以下の手順でダウンロードします。
- スライドの編集画面左上にある「ファイル」をクリックする
- 「ダウンロード」にカーソルを合わせる
- 表示されたプルダウンから希望のデータ形式を選んでクリックする
Googleスライドでは、以下のデータ形式で資料をダウンロードできます。
- 「.pptx」(Microsoft PowerPoint)
- 「.odp」(ODPドキュメント)
- 「.pdf」(PDFドキュメント)
- 「.txt」(書式なしテキスト)
- 「.jpg」(JPEG画像)
- 「.png」(PNG画像)
- 「.svg」(Scalable Vector Graphics)
最新のファイルがわかりにくくなったり、ファイルが増えすぎて管理しにくくなったりするのを防ぐために、資料作成が完了した時点でダウンロードするのがおすすめです。
社内に資料を共有する場合
社内メンバーとの情報共有や共同作業を行うには、特定のアカウントに対して直接共有設定を行います。
- スライドの編集画面右上にある「共有」をクリックする
- 資料を共有したい人のメールアドレスを入力する
- 共有相手のアクセス権限を設定する(閲覧者・閲覧者(コメント可)・編集者から選択可能)
- 通知メールの送信設定を行う(通知しない場合はチェックを外す)
- 「送信」をクリックする
Googleスライドの共有機能は、セキュリティを保ちつつ、権限を柔軟にコントロールできます。
社外に資料を共有する場合
リンクを使って、不特定多数の社外関係者に資料を共有することも可能です。
- スライドの編集画面右上にある「共有」をクリックする
- 「一般的なアクセス」の下にある「制限付き」をクリックする
- 「リンクを知っている全員」をクリックする
- 共有相手のアクセス権限を設定する(閲覧者・閲覧者(コメント可)・編集者から選択可能)
- 「リンクをコピー」でURLを取得し、共有したい人にメールやチャットなどで送る
複数人で資料を共同編集する際は、Googleスライドのコメント機能が便利です。個々のスライドに対してコメントを入力でき、共同編集のメンバーへ効率的にフィードバックを伝えることができます。スライドにコメントを追加する手順は、以下の通りです。
- スライドの編集画面上部にある「コメントを追加」(吹き出しの中に+が入っているアイコン)をクリックする
- コメントを入力し、「コメント」をクリックする
コメントはリアルタイムで反映され、編集者全員が確認・返信・解決できます。
【基本編】Googleスライドでプレゼンテーション資料を編集する方法
Googleスライドは、プレゼンテーション資料が初めてという方でも使いやすいツールです。直感的に操作できるところも多く、基本的な編集方法を身につければ、誰でもクオリティの高いプレゼンテーション資料を作成できます。Googleスライドの基本的な編集方法を確認して、プレゼンテーション資料の作成に活かしましょう。
テキストを編集する
Googleスライドでは、プレゼンテーション資料の印象にあわせてフォントやテキストの色などを柔軟に変更できます。テキストを編集する方法は、以下の通りです。
フォントを変更する
- フォントを変更したいテキストをクリックする
- スライドの編集画面上部にある「フォント」(フォント名の横に「▼」がある部分)をクリックする
- 希望のフォントをクリックする
「Google Webフォント」を利用したい場合は「その他のフォント」を選択します。Google Webフォントは、Googleが提供しているクラウドベースのWebフォントで、サーバーからフォントデータが読み込まれる仕組みのため、OSや使用デバイスにかかわらずどの環境でも同じように表示できます。
フォントの大きさを変更する
- フォントの大きさを変更したいテキストをクリックする
- スライドの編集画面上部にある「フォントサイズ」(数字の左右に「+」「ー」があるもの)をクリックする
- 希望のフォントサイズをクリックする
フォントサイズは「+」もしくは「ー」をクリックすれば、より細かくサイズを調整できます。
テキストの色を変更する
- 色を変更したいテキストをクリックする
- スライドの編集画面上部にある「テキストの色」(「A」にアンダーバーがついたもの)をクリックする
- 希望の色をクリックする
Googleスライドでは、PowerPointのようにユーザー自身でカラーパレットを設定できませんが、RGBを調整して自分の希望の色を作成できます。Googleスライドのカラーパレットに自分の希望の色がない場合は、以下の手順で作成しましょう。
- 色を変更したいテキストをクリックする
- スライドの編集画面上部にある「テキストの色」(「A」にアンダーバーがついたもの)をクリックする
- 「カスタム」直下の「+」(丸の中に+が入ったもの)をクリックする
- RGBを調整して希望の色を設定する
- 「OK」をクリックする
テキストに太字・斜体・下線を適用する
- 変更を加えたいテキストをクリックする
- 「B」(太字)・「I」(斜体)・「Uにアンダーバーがついたもの」(下線)のいずれかをクリックする
適用した装飾を外したい場合は、同様のアイコンを再度クリックします。
箇条書きを設定する
Googleスライドでは、プレゼンテーション資料内のテキストを箇条書きや番号付きリストにすることで、情報を整理し、視認性を高めることができます。まずは、箇条書きの設定方法を紹介します。
- 箇条書きにしたいテキストボックスをクリックする
- スライドの編集画面上部にある「表示形式」をクリックする
- 「箇条書きと番号付きリスト」にカーソルを合わせる
- プルダウンにある「箇条書きメニュー」にカーソルを合わせる
- 希望の箇条書きを選んでクリックする
箇条書きを追加したい場合は、Enterキーで行を増やすことができます。
また、Googleスライドでは、通常の箇条書きに加えてテキストを番号付きのリストにできる機能もあります。テキストを番号付きのリストにしたい場合は、以下の手順を参考にしてください。
- 番号付きのリストにしたいテキストボックスをクリックする
- スライドの編集画面上部にある「表示形式」をクリックする
- 「箇条書きと番号付きリスト」にカーソルを合わせる
- プルダウンにある「番号付きリストメニュー」にカーソルを合わせる
- 希望の番号付きリストを選んでクリックする
箇条書きと番号付きリストを使い分けることで、情報の構造が明確になり、プレゼンテーション資料の見やすさが向上します。
画像・図形・表などを挿入する
- スライドの編集画面上部にある「挿入」をクリックする
- 追加したい項目をクリックもしくはカーソルを合わせて、希望のオブジェクトを選択する
Googleスライドでは、画像や図形、表をはじめ、線やグラフなども挿入できます。また、画像はパソコン内に保存されたものに加えて、Web上で検索した画像も挿入可能です。
【応用編】Googleスライドでプレゼンテーション資料を編集する方法
プレゼンテーション資料は、視聴する相手により伝わりやすく印象に残るよう作成する必要があります。例えば、テキストに動きを持たせたり、音声を追加したりすれば、伝えたい内容がより明確になり、視聴者を惹きつけるプレゼンテーションが実現します。
Googleスライドには、そのような演出効果を追加できる機能が備わっています。ここでは、プレゼンテーション資料の完成度を高めるために活用したい、優れた編集機能を7つ解説します。
Gemini in Googleスライドを使う
Gemini in Googleスライドとは、GoogleスライドとGemini for Google Workspaceの連携によって生まれたAI機能です。Gemini for Google Workspaceのアカウントで利用でき、この機能を活用すれば、テキストで指示を出すだけでスライドが自動で生成・追加されます。Gemini in Googleスライドを使って新しいスライドを追加する手順は、以下の通りです。
- 任意のファイルを開く
- スライドの編集画面右上ある「Ask Gemini」(Geminiに質問する)というアイコンをクリックする
- サイドパネル下部にある入力フォームに、作成したいスライドの指示を入力して送信する
- 表示された提案を確認して問題がなければ「挿入」をクリックする
音声を追加する
Googleスライドでは、スライドに音声を挿入し、発表内容にメリハリを加えることができます。ナレーションや効果音などを加えることで、より印象に残るプレゼンテーションを演出できます。
- スライドの編集画面上部にある「挿入」をクリックする
- 「音声」をクリックする
- 挿入したい音声データを選択する(Googleドライブ上の音声データが対象)
- 表示されたスピーカーのアイコンにカーソルを合わせてメニューバーを表示させる
- 必要に応じて「▶︎」をクリックし、音声を再生する
- 画面右側に表示された音声再生の設定オプションで、スライドショーでの再生方法を設定する
音声再生の設定では、音声の開始・停止のタイミング、音量、ループ再生などの細かな設定が可能です。
アニメーションを設定する
Googleスライドにおけるアニメーションとは、画像やテキストに動きを加える機能です。アニメーションによって重要なポイントを際立たせたり、資料の流れをリズミカルに見せたりすることができます。アニメーションの設定方法は、以下の通りです。
- アニメーションを追加したいオブジェクト(画像・テキストなど)を選択する
- スライドの編集画面上部にある「挿入」をクリックする
- 「アニメーション」をクリックする
- 画面右側に表示された「モーション」からアニメーションの詳細を設定する
切り替え効果を設定する
Googleスライドの切り替え効果とは、スライドの移行の際に動きを加える機能です。切り替え効果によって、強調したい箇所の印象を強めたり、話の流れにリズムを与えたりする効果があります。切り替え効果の設定方法は、以下の通りです。
- 切り替え効果を追加したいスライドを選択する
- スライドの編集画面上部の「スライド」をクリックする
- 「切り替え効果」をクリックする
- 画面右側に表示された「スライドの移行」で詳細を設定する
一括で全スライドに同じ効果を適用したい場合は、「すべてに適用」をクリックすると便利です。
縦書きの文章を挿入する
Googleスライドには、テキストを縦書きにする機能はありませんが、以下のいずれかの方法で縦書きのテキストを表現できます。
- 1文字ごとに改行する
- 縦書きテキストの画像を挿入する
- テキストボックスを横方向に縮める
テキストボックスを横方向に縮める方法は手軽ですが、折り返しの位置を細かく調整しづらく、意図した縦書きの見た目にならないこともあります。
スピーカーノートを利用する
Googleスライドには、プレゼンテーションの原稿と資料を同時に表示できる「スピーカーノート」という機能があります。スピーカーノートを使えば、自分の画面にのみ原稿を表示してプレゼンテーションを進行できるため、より高いパフォーマンスが発揮できます。スピーカーノートの利用方法は、以下の通りです。
- スライドの編集画面上部にある「表示」をクリックする
- 「スピーカーノートを表示」をクリックする
- 各スライドの下にあるメモ欄に話す内容を入力する
プレゼンテーションをする際は、スライドの編集画面右上にある「スライド」の右側の「▼」をクリックしてから「プレゼンター表示」をクリックします。
プレゼンテーション中に質問を募集・回答する
Googleスライドでは、プレゼンテーション中に視聴者から質問を集めて回答できる機能があります。その場で質問を募集して回答すれば、視聴者の興味を高めながら、満足度の高いプレゼンテーションを実現できます。Googleスライドでプレゼンテーション中に質問を募集・回答する方法は、以下の通りです。
- スライドの編集画面上部にある「スライドショー」をクリックして、プレゼンテーションを開始する
- 開いた画面の下にある「Q&A」をクリックする
- 「ユーザーツール」タブにある「新しいセッションを開始」をクリックする
- 参加者に画面上で表示された質問フォームへのリンクをクリックして、質問を投稿してもらう
- リンクを「オフ」にして質問の受け付けを終了する
- 各質問の下にある「表示」をクリックして、投稿された質問をプレゼンテーション画面に表示する
セミナーや社内説明会など、参加者との双方向コミュニケーションが求められる場面で特に有効な機能です。
Googleスライドで質の高いプレゼンテーション資料を作成しよう
Googleスライドは、プレゼンテーション資料をはじめとしたスライドショーを作成・編集できる便利なクラウドツールです。複数人での同時編集や外出先での編集・閲覧ができ、業務効率化に役立ちます。また、テンプレートが多く用意されているため、資料作成に不慣れな方やデザインに自信のない方でもクオリティの高い資料を作成できます。無料ですぐに使用できるのも大きな魅力です。
ビジネス用途でGoogleスライドを利用する場合は、Google Workspaceの導入がおすすめです。Google Workspaceには、機密情報の保護に必要なセキュリティ対策や管理機能が充実しており、Googleスライドをより安全に利用できます。
また、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシート、Google Meetなど、他のGoogleツールとも連携可能なため、チーム全体での情報共有や業務の一元管理が実現します。
電算システムでは、豊富な実績をもとに培ったノウハウで、Google Workspaceの導入支援を行なっています。Google Workspaceの導入に興味のある方は、電算システムまでお気軽にお問い合わせください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- Google プレゼンテーション