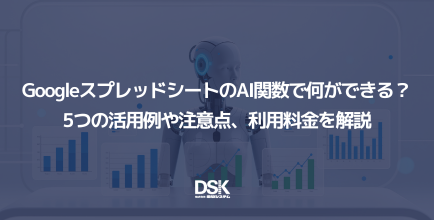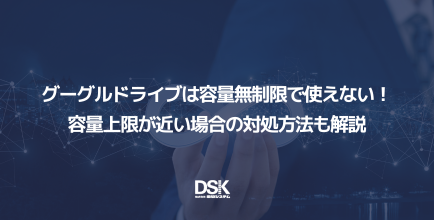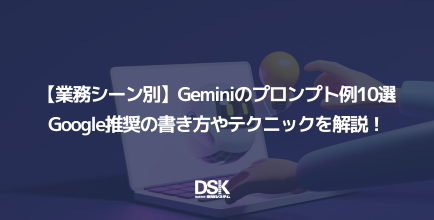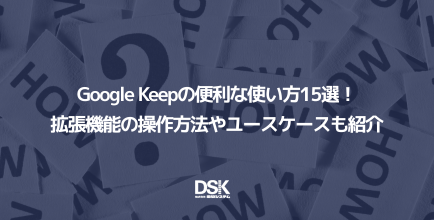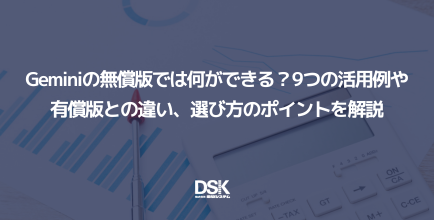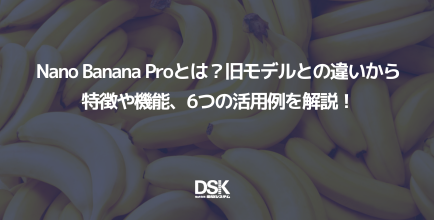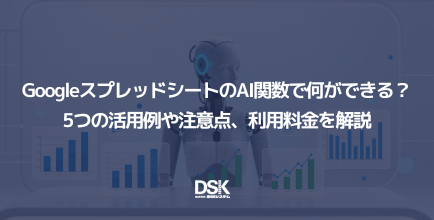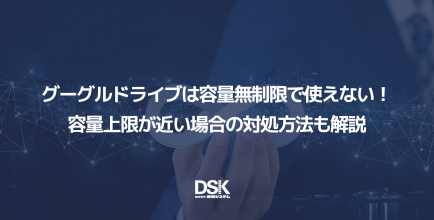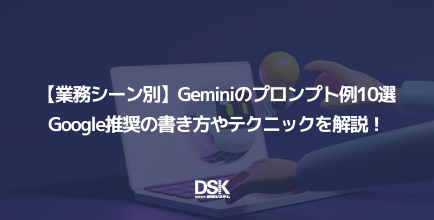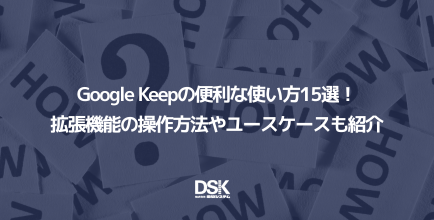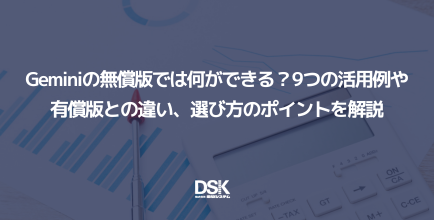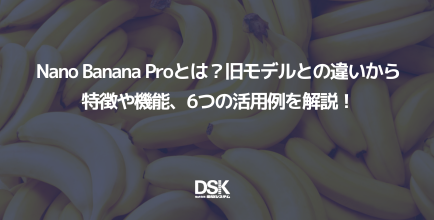生成AI技術は日々発展を遂げており、いまではさまざまな場面で活用が進んでいます。Google社が提供するGeminiアプリも同様で、ビジネスシーンでは情報収集や資料の要約、企画立案、メール作成といった形で活用できます。Geminiアプリをうまく活用することで、業務の自動化が進み、生産性の向上やコスト削減といった大きな恩恵を受けられます。
とはいえ、いままでGeminiアプリを利用したことがない方には、「生成AIはハードルが高い」と感じてしまうことも多いのではないでしょうか。しかし、Geminiアプリは生成AIサービスのなかでも手軽に利用でき、初めての方でも安心して導入を進められます。
本記事では、Geminiアプリの特徴や活用方法、導入手順などを詳しく解説します。
Geminiアプリとはマルチデバイスで生成AIを手軽に使えるサービス
まずは、Geminiアプリの特徴や仕組み、ほかのGemini関連サービスとの違いを解説します。
Geminiアプリの特徴
そもそもGeminiとは、Google社が提供しているマルチモーダルな生成AIモデルです。プロンプト(テキストによる指示)やファイルのアップロードなどでAIに指示を与えることで、その内容に沿ったアクションを自動的に実行してくれます。テキストや画像、動画、音声などに対応しており、さまざまな形式でデータを入出力できる(マルチモーダル)のも特徴です。
このようなGeminiの機能を手軽に利用できるようにしたのがGeminiアプリです。Webブラウザ上で利用できるパソコン版と、スマートフォンやタブレットからアクセスできるモバイルアプリ版があり、どちらもGeminiアプリという名称で呼ばれています。パソコン版とモバイルアプリ版を使い分けることで、オフィスで仕事を行う際もテレワークで在宅勤務をする際も、場所を選ばず生成AIを活用できるようになります。
ほかのGemini関連サービスとの違い
Geminiには、Geminiアプリ以外にも次のような関連サービスが存在します。
- Google Workspace with Gemini:
グループウェアのGoogle Workspaceには、有料版のGmailやGoogleドライブ、Google Meetなどのコミュニケーションサービスが搭載されており、それらの機能とGeminiを組み合わせて、ドキュメントやプレゼン資料の作成、ドライブ内のファイルの要約・分析などをAIが自動的に実行してくれる - Gemini for Google Cloud:
クラウドプラットフォームのGoogle Cloudには、データベースシステムや分析ツール、クラウドコンピューティングなどのサービスが搭載されており、それらの機能とGeminiを組み合わせることで、分析レポートの作成やコーディング、アプリケーション開発などをAIがサポートしてくれる - Gemini API:
Geminiが持つ生成AIの機能を、外部のツールやシステムに実装できる
上記の関連サービスは、いずれもGoogleサービスや外部システムと組み合わせて活用するのが基本です。そのため、Gemini単体で利用する場合は、Geminiアプリを活用するのが一般的です。Geminiアプリ単体でも、文章の要約やメールの作成、企画書の考案、データ分析など、さまざまなアクションを実行できます。
Geminiアプリの活用例6選
Geminiアプリでは、プロンプトを入力するだけで、その内容通りの作業をAIが遂行してくれます。テキストや画像、動画などのさまざまなコンテンツを生成できるため、活用の幅が広く、工夫次第で大幅な業務効率化につながります。
ここでは、Geminiアプリの具体的な活用例を紹介します。
情報収集・リサーチ
Geminiアプリでは、Google社に蓄積された膨大な検索データを活用できるため、情報収集やリサーチをより効率的に実行できます。使い方は簡単で、プロンプトの入力欄に調べたい情報とその指示を与えるだけで済みます。
また、「Deep Research」と呼ばれる機能を利用すると、Web上から横断的に情報を収集したうえで、その内容をレポート形式でまとめることも可能です。以下のような形で詳細な情報を出力できるのがメリットです。

Deep Researchで出力されたレポートには、それぞれの情報にデータソースが表示されています。そのリンクをクリックすると参考にしたWebサイトにアクセスできるため、情報の真偽性や鮮度を把握する場合でもスムーズに作業を進められます。
このような特徴を活かすことで、ビジネストピックの抽出や新しく導入する製品の比較など、さまざまなケースに発展できます。市場や競合製品の情報を調査したうえで、自社の理念に適ったマーケティング戦略を策定するといった高度な活用も可能です。
資料の要約
Geminiはマルチモーダルな生成AIモデルなので、PDFや画像、動画などのファイルをアップロードして、その内容をAIに要約してもらうことができます。また、Web上のURLを直接指定して要約することも可能です。学術論文や研究レポートのような複雑な資料でも、短時間で作業が完了します。
また、Deep ResearchとCanvasの機能を活用することで、要約した内容を新たな資料として再生成するといった活用も可能です。
Canvasとは、出力画面を見ながらGeminiと会話を繰り返すことで、リアルタイムに修正結果を反映できる機能です。Geminiとデジタルホワイトボードを共有しているように会話を行えるほか、Deep Researchで出力されたレポートをWebページやWebスライドとしてプレビューすることもできます。例えば、Webスライドとして出力した場合は、次のような形となります。

そのため、特定の資料を要約してプレゼン資料に落とし込みたい場合、Deep Researchで詳細情報を検索し、Canvasを使って視覚的に表現するといった使い方が可能です。
資料用の画像や動画の作成
Geminiアプリでは、画像や動画を出力することも可能です。そのため、プレゼン資料やWebサイトなどに掲載する画像や動画を短時間で作成できます。
Geminiの画像生成には「Imagen 4(※)」と呼ばれる画像生成AIモデルが採用されています。旧モデルのImagen 3に比べ、人間の肌や動物の毛皮、質感まで緻密に再現でき、解像度も1メガピクセル(1,024×1,024)から最大2K(約2,048×2,048)に対応できるようになっています。また、選択できるスタイルも、フォトリアルからアニメ調、抽象画まで幅が広がったのも特徴です。
動画生成の場合は、「Veo 3(※)」という動画生成AIモデルを活用しています。Veo 3からは音声付きの動画生成が可能になり、処理性能と生成速度も大幅に向上しました。音声は日本語にも対応しているため、資料用の動画作成以外にも、マーケティング動画の作成や教育コンテンツの強化など、さまざまな形で発展可能です。
※2025年8月時点の最新モデル
企画立案
企画立案でGeminiアプリを活用する場合は、「Gem」と呼ばれる機能が役立ちます。Gemとは、Geminiに特定の役割を与えることで、AIがその分野のエキスパートになりきって回答してくれる機能です。
例えば、アパレル関係のWebメディアを運営しており、そのコンテンツを企画する際は、Geminiに「アパレル業界に詳しい専門家」といった役割を与えられます。そして、「社会人1年目の人が参考にしたい身だしなみのコツ」といった具体的な企画テーマを指示することで、構成案の提案や見出し・本文の作成といった作業を行ってくれます。
Gemでは、入力したプロンプトに対して、「ターゲットのコンテキストを教えてください」「出力形式はどのようにしますか」といった形で質問されるのが一般的です。事前に複雑なプロンプトを用意せずとも、その質疑応答を繰り返すことで、容易に詳細な指示文が完成させることができます。
メール作成
Geminiアプリにメール作成用のプロンプトを入力すると、メールのタイトルや本文を短時間で生成できます。
例えば、「営業メールに対して相手に失礼のないように断りたい」といった指示を与えると、AIがその内容に沿ったタイトルや本文を考えてくれます。さらにGemの機能を活用すれば、定型的なメール送信をカスタム指示として登録しておくことで、次回からは「いつものメール作成」といった指示を与えるだけで、より簡単にメールを作成できるようになります。
また、メールを効率的に管理したい場合は、Google Workspace with Geminiに搭載されている「Gemini in Gmail」の機能を活用するのも一案です。Gemini in Gmailでは、GeminiとGmailを連携させて、受信メールの要約やフォルダ内から情報検索・分析、Googleカレンダーの予定を取得などを行るようになるため、活用の幅が広がります。
コーディング
Geminiにプログラミングコードを生成してもらう場合は、プロンプトの入力欄に直接指示文を入力して出力することもできますが、より作業効率を高めるには、Canvasに新たに追加された「Vibe Coding」と呼ばれる機能を活用するのがおすすめです。
Vibe Codingでは、「社内コラボレーションを活性化させるようなアプリがほしい」といった曖昧なプロンプトであっても、AIがその内容に沿った最適なプログラミングコードを生成してくれます。ReactやTailwind CSSなどの技術を活用して用途に応じた適切なプログラミングを書き上げてくれるほか、UIデザインや機能のリストなども同時に提案してくれるのが特徴です。そのため、社内にコーディングのノウハウが不足している場合でも、手軽に作業を進められるメリットがあります。
また、Gemini for Google Cloudを活用すると、Google Cloudに搭載されたデータベースシステムや分析ツールなどを組み合わせて、独自のアプリケーション開発環境を構築できます。Google Cloudにはほかにも、「Gemini Code Assist」と呼ばれるサービスが含まれており、プログラミングコードの作成やレビュー、修正といった作業をAIがサポートしてくれます。
Geminiアプリを導入する3つのメリット
Geminiアプリを導入すると、次のようなメリットが生まれます。
- 業務効率や生産性が大きく向上する
- 人手不足の解消や採用コストの削減につながる
- アイデアのきっかけを見つけやすい
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
業務効率や生産性が大きく向上する
Geminiアプリの導入によって作業の自動化が進めば、組織の業務効率化や生産性向上が期待できます。生成AI技術は年々発展が続いており、対応可能な業務の種類が増えたことから、活用範囲が広がるほどその効果も大きくなります。
例えば、営業メールの作成が苦手な方でも、取引先の名称や担当者、メッセージの方向性、訴求したい商品・サービスなどをプロンプトとして入力するだけで、AIが短時間で最適化されたメールタイトルや本文を考えてくれます。修正が必要な場合でもプロンプトを再入力するだけで済み、誤字や脱字のチェックもAIに一任できるため、ヒューマンエラーの抑制にもつながります。
そのほか、膨大なデータをAIに分析させて、顧客の購買傾向や行動パターンを正確に読み解くことも可能です。また、企業によってはコールセンターに生成AIの仕組みを導入し、会話内容の分析や自動データ入力、会話中のリアルタイム検索といった形で活用しているケースもあります。このようなケースでは、顧客ニーズの把握や問い合わせ時の待ち時間の削減につながるため、単なる業務効率化だけでなく顧客満足度の向上にも効果を発揮します。
人手不足の解消や人件費の削減につながる
ビジネスシーンにおけるほとんどの業務をAIに一任できれば、それだけ人的リソースも少なくて済みます。結果として、人手不足の解消や人件費の削減につなげられるのが利点です。
内閣府が公表した資料によると、国内の生産年齢人口は、2020年の7,406万人から2065年には4,529万人と約40%減少する見込みとなっています(※)。その内訳も、65歳以上が2020年比で10%以上増える代わりに、15~64歳は8%近く減ることが予想されています。
つまり、企業にとっては、将来的に人材を確保するのが困難になることが予想されます。人材に対する需要が高まれば人件費の高騰につながる恐れもあるため、従業員一人あたりの生産性を高めたり、人的リソースの代替策を検討したりと、いまのうちに対策を立てておく必要があります。GeminiアプリをはじめとするAIは、いままで人が行っていた作業を肩代わりする存在になり得るため、人口減少下の現状を大きく打破する画期的なソリューションといっても決して過言ではありません。
※出典:人口減少と少子高齢化|内閣府
アイデアのきっかけを見つけやすい
Geminiアプリで出力するコンテンツは、ときとしてアイデアのきっかけになることもあります。
例えば、創作分野では、新製品や広告のクリエイティブ、YouTube投稿用の動画コンテンツなどを作成する機会が多く、一から内容を創造するのは大きな手間と労力がかかります。その点、Geminiアプリであれば、プロンプトを入力するだけで、その内容に沿ったオリジナルのコンテンツを生成してくれます。たとえ、そのコンテンツをそのまま利用するのが難しい場合でも、AIのアイデアをもとに発想を広げて新たな企画や内容を考えることが可能です。
また、アイデアのきっかけを見つけやすいというメリットは、経営の現場でも活かせます。例えば、新規事業の構想を練る際、Geminiアプリであれば、プロンプトを入力するだけでアイデアを提案してもらえます。また、市場調査からビジネスプランの策定、製品開発・マーケティングの手法考案まで、さまざまな実務を任せられるのもメリットです。
【端末別】Geminiアプリの導入方法
Geminiアプリは、使用する端末によって導入方法が異なります。ここでは、パソコン版・Android版・iOS版に分け、それぞれの導入手順を解説します。
パソコン版
パソコン版の導入方法は最も簡単で、Geminiアプリの公式サイトにアクセスするだけで済みます。公式サイトにアクセスすると、Googleアカウントにログイン済みの場合は、「こんにちは、○○(アカウント名)」のメッセージが表示されます。Googleアカウントにログインしていない場合は、画面右上の[ログイン]からログインしましょう。

Geminiアプリを利用する際は、まず画面左上のドロップダウンからモデルを選択します。無料版では、コンテンツの生成速度に優れたGemini 2.5 Flashと、推論や数学などの高度な処理に対応したGemini 2.5 Proの2種類を利用できます(2025年8月15日時点)。

モデルを選択した後は、[Geminiに相談]と記載された箇所にプロンプトを入力します。また、[+]マークをクリックすると、ローカルストレージやGoogleドライブからファイルや画像などをアップロードすることも可能です。Web上から横断的に情報を調べて文章をまとめる「Deep Research」や、パネル上で直感的に文章やプログラミングコードなどを作成できる「Canvas」を活用するのも良いでしょう。

そして、しばらくすると生成結果が画面に表示される仕組みです。
なお、画面右上の[アップグレード]をクリックすると、有料プランに申し込めます。有料プランには、動画生成やNotebookLMなどの機能が利用できる「Google AI Pro」と、並列指向技術による高度な推論が可能なDeep Think機能を利用できる「Google AI Ultra」の2種類が用意されています。
Android版
AndroidのスマートフォンでGeminiアプリを利用するには、Google Playから専用のモバイルアプリをインストールします。そして、Geminiアプリを起動し、Googleアカウントにログインするとサービスを利用できます。
Android版の使い方はパソコン版とほとんど同じです。画面に表示された入力欄にプロンプトを入力するだけで、AIがその内容に沿ったアクションを実行してくれます。画像をアップロードしてその内容を解析させたり、メールや資料を作成したりすることも可能です。
また、Android版には、スマートフォンならではの音声入力機能が備わっています。マイクボタンをタップし、口頭で指示を与えるだけでプロンプトの役割を果たします。また、まるで人間と話しているようにGeminiと会話ができる、Gemini Liveの機能を利用できるのもポイントです。
iOS版
2024年11月、GeminiアプリのiOS版の提供が開始されました。これ以降、パソコンやAndroidのスマートフォンだけでなく、iPhoneやiPadでもGeminiアプリを利用できるようになりました。
iOS版のGeminiアプリはApp Storeからダウンロードが可能です。モバイルアプリのインストール後は、Googleアカウントを使ってログインします。その後の流れはAndroid版と同じで、機能にも大きな違いはありません。
Geminiアプリを活用して業務の自動化を進めよう
Geminiは、2025年5月に「Gemini 2.5 Pro」にモデルがアップデートされ、いままでよりも高精度な出力が可能になったことから、ビジネスシーンにおいても活用機会が格段に増加しています。Deep ResearchやCanvas、Gemといった便利な機能が拡充され、情報収集や画像・動画生成、メール作成、コーディングといった作業をより効率的に実行できるようになりました。このような利点を活かして業務に採り入れることで、大幅な業務効率化につながります。
また、GeminiはGoogleサービスと親和性が高いため、GmailやGoogleドライブ、Googleドキュメントなどと組み合わせて活用するのも良いでしょう。Google Workspace with Geminiを活用すれば、Gmailのメールを要約する、Googleドキュメントでの資料作成を自動化するなど、さまざまな活用が可能です。
電算システムでは、環境構築やコンサルティングなど、Googleサービスの導入支援サービスを提供しています。Geminiの活用方法や体系的な知識を学べるハンズオントレーニングやワークショップ、カスタマイズトレーニングを提供しており、Google Workspace with Geminiのスムーズな定着を支援します。Google Workspace with Geminiの特徴や機能、最新情報などに関しては、以下の資料で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。