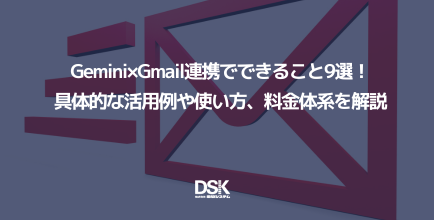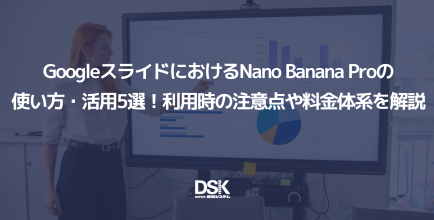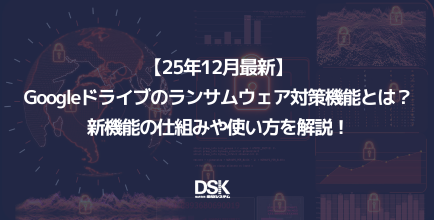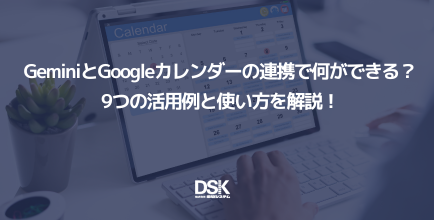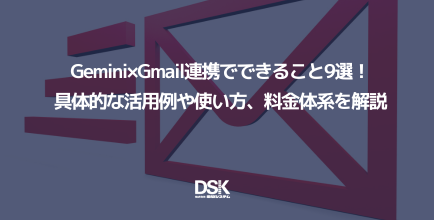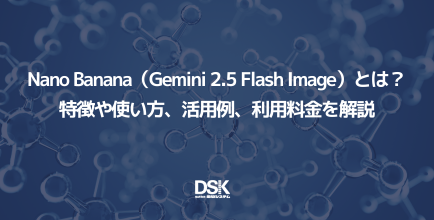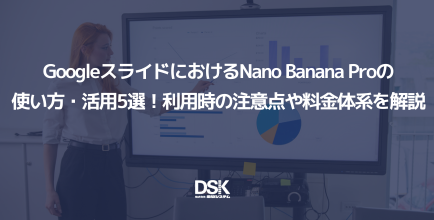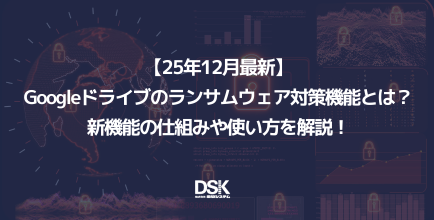DX推進が急務となっている現代において、多くの企業が生成AIの導入に注目しています。
Google でも、日々さまざまなAIツールがアップデートを繰り返しています。使いこなせば業務のスピードは著しく向上するでしょう。しかし一方で、多くのサービスや機能を前に「自分たちはどのツールを選べばいいの?」「何から考えれば良いかわからない」と悩んでしまう担当者の方も多いのではないでしょうか。細かなユースケースはたくさんあれど、まずは Google の生成AIソリューションについて全体感を掴みたいというお声も多くあります。そこで今回は、電算システムの生成AI専門チームであるProject Gen(P-Gen)チームの吉川さんに、企業が生成AIを導入する際の具体的なステップと成功の秘訣についてお伺いしました。
※今回は、Vertex AI のようにコードを用いての開発・構築が必要になるサービスについては除外しています。
聞き手は、電算システムのカスタマーサクセスチーム まなべです。
 |
電算システム 吉川さん 電算システムの生成AI専門チームであるProject Gen(P-Gen)チーム所属。主にGoogleの生成AI「Gemini」や「NotebookLM」のビジネス活用支援と「Agentspace」のプロダクト推進を担っています。五歳の娘がGemini Liveに出すプロンプト指示が上手くなってきており、生成AIネイティブの姿を日々実感中。 |
まずやるべきことは「目的と現状の明確化」
本日はよろしくお願いいたします。最初からざっくりとした質問で恐縮ですが、「これから会社で生成AIを使っていくぞ!」となった時、まず何から始めればいいですか?
吉川:
まず最初に考えるべきは、何を目的として生成AIを使いたいのか、そしてAIを活用する上で自社の環境はどうなっているのかという2点です。
生成AIの導入を検討する際、「Gemini を使い始めたい」「Agentspace を使いたい」というように特定のサービスありきの始め方をしてしまうケースがよく見られます。
しかし、そこから入ってしまうとやりたいこととズレが生じた時に修正が難しくなってしまうんです。例えば、高度で複雑なAIソリューションを希望しても、社内に技術者がいなければ開発は困難になります。
また逆に、Geminiなどの Google Workspace 内で完結できるソリューションから始めようとしたとしても、データが Google Workspace 外にあれば十分な効果が得られないこともあります。
まずは自社の目的と環境をしっかりと見つめ直すことが、成功への第一歩と言えるでしょう。
検討を進める上で注意すべきこと
ありがとうございます。「自分たちが何をしたいか、そのための環境は整っているか」を明確にしておくことが重要だとわかりました。では、その検討を進める段階で注意すべき点などはありますか
吉川:
生成AIは非常に進化が早く、私たちも日々追いつくのが大変な状況です。
そのため、明確にしておいた方がいいとは言いつつも、「今この時点でこれが100%クリア出来ないとダメ」といった基準で進めてしまうとつまづいてしまう可能性があります。
結果を100%求めるのではなく、「このくらいまで出来たらOK」という基準で成功レベルを設定し、さらにそれを成功した一部だけでなく横展開していくイメージを持つと良いのかな、と思います。
具体的には、「この部門のこの業務がこうなってほしい」というイメージでは横展開しにくいですが、「日々の定型業務を自動化したい」であれば成功パターンを横展開しやすいですよね。そういうレベル感がベストです。
確かに、特定業務で毎回同じ結果が出るように、ということであればアプリのスクラッチ開発などの方が向いていますね。その他にも注意点や、導入前に決めておくべきことはありますか?
吉川:
そうですね。事前に効果測定についても考えておくと良いですが、これには少しコツがあります。
よく言われていることなのですが、生成AIの活用ってゴールが見えにくいんですよ。
「生成AIを使えるようになったから◯時間の業務削減ができた」とか「いくら業績が上がった」とか、そういうのは出しにくいんです。
利用回数などデータで出すことはできますが、それは本質ではないですし……。
なので、そのあたりについてどう考えるかという観点も必要になってくるかなと思います。
例えば、生成AIの活用に関するアンケートをユーザーに対して実施して、その体感値を取っていただいたり、何回クエリ(検索のリクエスト)を叩いていただいたかを見ていただいたりなど、基準としていただけるものはあります。
◯時間、◯円というはっきりした数字が出せない分、そういったもので一旦のゴールを決めておくことを推奨します。
なるほど。どのように横展開していくか、どこにゴール設定をするかも進める上では重要なポイントですね。ではいよいよですが、自社にとって適しているAIツールはどれか、どのように選べばいいでしょうか?
吉川:
現在Google の生成AIを活用されている企業様の目的パターンは、ざっくりと分けて大きく4通りあります。おすすめのAIツールと合わせてご紹介しますね。
Google 生成AI活用の4つのパターン
吉川さんに話していただいた目的に応じた活用パターンを以下にまとめました。
汎用的な生成AI活用
目的:文章の要約、文章を中心としたコンテンツ生成、基礎的な分析など、基本的なAI機能を使いたい。
おすすめツール: Gemini
ポイント: Google Workspace を契約していれば、Gemini はすぐに利用可能です。特にこだわりがなければ、まずはここから始めるのが最も無難な選択肢と言えるでしょう。
しかし、Google Workspace を契約していなかったり、Google Workspace の外部のデータを使いたいというニーズがある場合は、後述する Google Agentspace が検討に入ってくる可能性もあります。
データ分析を目的とした活用
目的: 研究論文やレポート、議事録など大量のドキュメントやデータから、専門的な知見やインサイトを抽出したい。
おすすめツール: Gemini 内の Deep Research 機能、NotebookLM(Google Workspace版)
ポイント: 分析に関しては、Web上の文献をもとに高度なリサーチが可能な Gemini の Deep Research 機能や、複数のデータソースを登録してチャット形式で情報を抽出できるNotebookLM を使うのが効果的です。
もしGoogle Workspace を利用していない場合、NotebookLM Enterprise という単体で契約できるサービスを使うという手もあります。例えば、Microsoft Office を基盤としている企業であったとしても、Excel、WordといったOffice ベースの情報を入れ込んで要約したり、分析にかけることが可能になります。
データの検索やアクセスの効率化
目的: 社内のいろんな場所に散らばったデータを横断的に検索し、必要な情報をすぐに探し出したい。
おすすめツール: Agentspace
ポイント: Gmail、Google ドライブ などの Google Workspace 内のデータはもちろん、Outlook、OneDriveなど外部のデータも含め、複数のソースをコネクタでつなぎ横断的に検索することが可能です。
さまざまなSaaSに点在するデータを一つの画面で検索し、探し出すことができるため非常に便利です。
業務の自動化
目的: 反復的な手作業や複雑なワークフローを自動化したい。
おすすめツール: Agentspace、Workspace Flows(Google Workspaceの機能として後日リリース予定)
ポイント: Agentspaceの「エージェント機能」を利用することで、「あなたはこういう順番でこれをこうしてこうしてください」という指示に従って一連のタスクを自動実行するAIエージェントを構築できます。手間がかからないことはもちろん、抜け漏れの防止にもつながります。
また、将来的には Google Workspace 上で Workspace Flows という新機能も登場予定です。
Workspace Flows では、あるトリガーをもとに Google Workspace 内の様々な機能を連携させて業務を自動化することが可能になります。例えば「Gmail 上でメールを受け取る⇨Gemini が文面から感情分析⇨ Chat でそのレポートを通知する」といった連携ができるようになります。
ありがとうございます。それぞれの傾向が見えてきました。どれがどれの上位、という訳ではなく、各々の目的やニーズに適したサービスを用意しているということでしょうか。
吉川:
Agentspace は Gemini や NotebookLM の機能も含むため、上位と言えば上位ですが、Gemini や NotebookLM だけでも十分に活用できるケースは多々あります。
何でも屋さんの Gemini と、RAGのような情報源を利用した生成に特化している NotebookLM、 それらを踏まえてさらにいろいろできるのが Agentspace といった感じです。
Workspace Flows に関しては対象プランなどまだ明確にはなっていませんが、使えるようになればより強力な選択肢となるでしょう。今回は言及していませんがVertexAIを利用した開発なども含めれば、「やりたいことを実現できそうなツールが3つも4つもあって、どれを選べばいいかわからない」ということも珍しくありません。その中で、今この瞬間に出来る・出来ないという軸だけではなく、自社がやりたいことの方向性とAIツールの方向性がマッチしているか、という軸は非常に大事なポイントです!
実際に対応させていただいた「お客様のお話し」
いろんなパターンを教えていただきましたが、「このサービスに落ち着くお客様が多い!」といった傾向はありますか?

吉川:
このサービスが多い、という傾向は特に無いですが、最初に検討していたサービス・ツールとは異なるものに落ち着くケースが意外と多いです。冒頭で注意を促した「特定のサービスありきの始め方」をした場合ですね。
例えば、Agentspace のセミナーでご興味を持っていただいたお客様からお問い合わせしていただき話を進めたところ、実際にやりたいことは大量の書類データの分析だったということもあります。その時は結果的に、 Agentspace の話から始まりましたが、今既に利用が可能な NotebookLM のトレーニングの話になりました。Agentspaceでも解決できる課題でしたが、まずはあまりコストをかけずにやってみようということですね。
逆に、Gemini のようなすぐに始められるところからスタートしようと思っていたら、やりたいことは Agentspace でないとカバーできない範囲だったというケースもあります。
検討を進める中で目的や課題がより明確になったということですね。
吉川:繰り返しにはなりますが、まず目的は何なのか、現在位置はどこなのかをしっかり固めた上での検討をおすすめします。その後に、何が適しているのかを探してみたり、是非私たちに相談してみてください。
面白かった例で、Google Workspace ではなく Microsoft を使っているお客様から RAG利用の目的で NotebookLM Enterprise のお問い合わせをいただいたことがありました。
ややこしいのですが、NotebookLM は二種類あり、Google Workspace の機能のひとつであるNotebookLMと、NotebookLM の機能だけを単体で購入できる NotebookLM Enterprise があります。
Google Workspace のグループウェアの機能(GmailやGoogleドライブ)は利用しないから、 NotebookLM Enterprise がちょうどいいと考えられたわけですね。
しかし話を進めてみると、R&D業務に生成AIを利用したいというご要望もあったことがわかってきまして。Google Workspace のライセンスがあれば、NotebookLM も使えて Deep Research 機能もある Gemini が使える。値段は NotebookLM Enterprise 単体とそこまで変わらず……ということで、Microsoft を使い続けながら AIツールとして Google Workspace をご検討いただいた、という例もありました。
グループウェアとしてでなく、AIツールとして Google Workspace を使うというケースもあるんですね!
吉川:少し前までは社内に2つのグループウェアがあるのは少しもったいないイメージでしたが、他生成AIツールに比べて検索速度が優れている、調査分析業務に優れた Deep Research などそれだけでも魅力的な機能が沢山あります。「◯◯のためにGoogle のAIを併用したい!」というきちんとした意図があればそういった選択も良いかと思います。
これもまた、目的と現状を明確にした結果ですね。
目的・現状・最適なサービスがわかったら?
ここまで導入検討のためのポイントをお話いただきましたが、それらのポイントを押さえた後はどうすればいいでしょうか?
吉川:本当に生成AIを使うのが初めての企業の方であれば、まず「この会社の中では、どのツールなら使っていいですよ」「何ならしていいですよ」などの規定がまとまったガイドラインを作ることをおすすめします。
具体的な例で言うと、「他ツールに会社の情報を入れた結果学習されてしまうと困るので、会社の情報を入れるのは Gemini だけにしましょう」とか、「AIで生成された画像については問題になりやすいので、こういう場面でだけ使いましょう」とか、そういうルールを明文化することでAI活用に関するトラブルを軽減させることができます。
電算システムでご契約されていれば、そういったガイドラインのサンプルもお渡しできますので、是非お気軽にお問い合わせください。
ルールが無いと逆に使い始められないという方もいると思うので、大事なステップですね。
吉川:あとは、どのツールを使うかによってやっていただきたいことや注意点も変わってきます。
もちろん、つまづくところがあれば私たちからサポートさせていただくこともできます。
【Gemini or NotebookLM の場合】
- どんな業務で使っていくかのユースケースを考える
- ユーザー同士で活発に情報をシェアできるような環境を用意する
(Chatのスペース、ポータルサイト、社内SNSなど)
その前に使い方がわからないと……ということであれば、電算システムのセミナーにご参加いただいたり、有償でのトレーニングをご依頼いただければと思います。
【Agentspace の場合】
- より一層ユースケースが重要になるので、活用イメージを具体化させる
- Google Cloud(旧GCP)の製品なので、少しコツのいる環境構築が必要
電算システムでは、Agentspace のライセンス販売だけでなく、基本環境の構築支援やデータソースをつなげるご支援なども可能です。また、「どういったエージェントが欲しいのか」ということを深くヒアリングさせていただき、会議室などで議論しながら具体的なアイディエーションを一緒に行うセッションなどもやっています。
Gemini や NotebookLM に比べて、Agentspace は出来ることの幅がかなり広いのでかなり密接にご協力させていただいてます。
しかしどちらもやっていることとしては、以下の2つですね。
- 環境をセットする
- ユースケースをつくる
最後に
ここまでリアルなノウハウをご紹介いただきありがとうございました。P-genチームの方の持っている情報は、ただ Google から展開されたものの横流しではなく、なんだか熱がある気がします。
吉川:そうかもしれません(笑)
電算システムでは、比較的早い段階で生成AIに取り組む専門チーム Project Gen (通称P-gen)を発足しました。私がそのプロジェクトに参画したのは2024年7月からだったのですが、その頃はサイドパネルがベータ版だったり、Gemini アプリも出来ることが最低限、NotebookLM はGoogle Workspace 外のコンシューマー向け機能だったり……それが今日までにここまで目覚ましい進化を遂げました。

私たちはその進化の速さに驚かされつつ、日々情報を追いかけ続けています。
そうして得たナレッジをセミナーの形で広く共有したり、何十社もの企業に向けてご支援してきました。その中で、肌感として進化や活用方法をお客様のお隣で見続けてきたので、かなり現場感のあるリアルな情報を届けられるのかなと思います。
この1年間だけでも多くの歴史が詰まっているので、是非今後の更新もご期待ください!
執筆者紹介

<保有資格>
・Cloud Digital Leader
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- Google 生成AI 導入