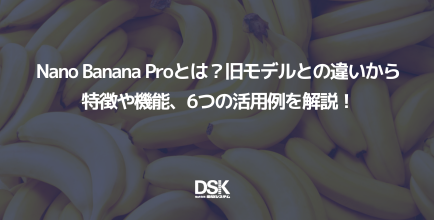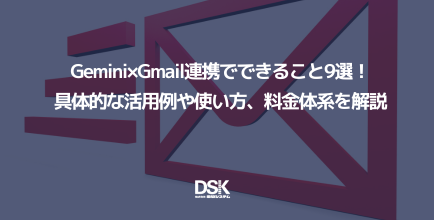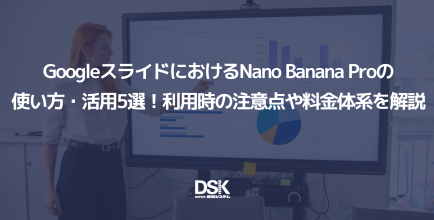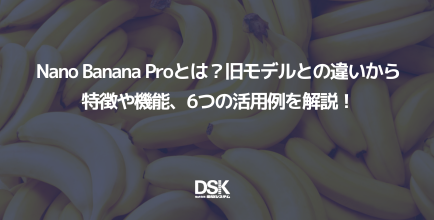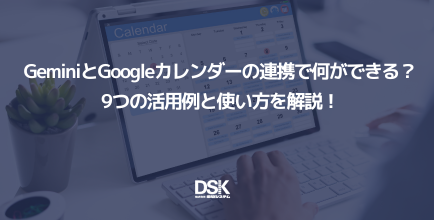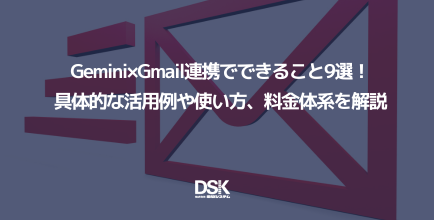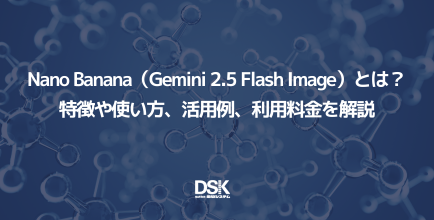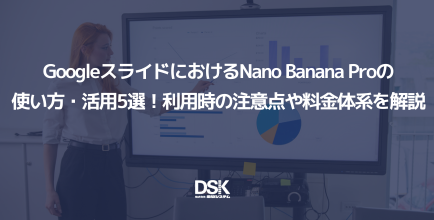Gmailを利用する際、宛先の異なる大量のメールが受信トレイに表示され、視認性や検索性が悪化するケースも多いのはないでしょうか。受信トレイが整理されていないと、メールの見落としやすくなり、取引先や顧客に迷惑をかけてしまう可能性があります。
このような事態を防ぐには、ラベル機能を活用するのがおすすめです。ラベルという専用の格納スペースを作ることで、部署やチーム、担当者ごとにメールを振り分けられます。ラベル機能をうまく活用すると確認漏れのリスクを最小限に抑えられるでしょう。
本記事では、Gmailのラベル機能の特徴や使い方、注意点などを詳しく解説します。
Gmailのラベル機能とはジャンル別にメールを分類する機能
Gmailのラベル機能は、メールを整理・管理するためのツールの一つです。取引先や案件ごとにラベルを設定することでメールを分類できます。さらにフィルタを設定すれば、特定のラベルが付いたメールのみを表示できるため、効率的なメール管理が可能になります。
一般的なメーラーに搭載されているフォルダ機能とは異なり、一つのメールに複数のラベルを付与できる点も特徴です。そのため、社内で複数の担当者がメールを共有・管理する際にも柔軟に対応しやすくなります。Gmailで膨大な量のメールを受信する際は、ラベル機能を活用してメールを整理し、受信トレイの視認性や検索性を高めましょう。
Gmailのラベル機能の特徴
Gmailのラベル機能には次のような特徴があります。
- 一つのメールに対して複数のラベルを設定できる
- 一つのラベルを階層化できる
- ワンクリックで表示・非表示を変更できる
それぞれの特徴を押さえることで、Gmailをより便利に活用できます。
一つのメールに対して複数のラベルを設定できる
Gmailのラベル機能は、一般的なメーラーのフォルダ機能と仕組みがよく似ています。どちらもテーマごとに専用の格納スペースを作成し、そのなかに複数のメールを保存する仕組みです。しかし、ラベル機能はフォルダ機能とは異なり、一つのメールに複数のラベルを付けられます。
フォルダ機能の場合、仮に「営業部」というフォルダに入れたメールは、別のフォルダに同時に分類することはできません。一方、Gmailのラベル機能を活用すれば、一つのメールを「営業部」と「マーケティング部」の両方のフォルダに格納できます。そのため、複数の部署やチームでメーラーを運用する際は、メールの分類範囲が広いラベル機能のほうが利便性が高いといえるでしょう。
一つのラベルを階層化できる
Gmailのラベル機能は、階層構造の設定が可能です。例えば、「営業部」という親ラベルを作成し、そのなかに「営業1課」や「営業2課」といった子ラベルを分類できます。そのほか、「営業案件」の親ラベルに「未処理」や「処理済み」といった子ラベルを作るのも良いでしょう。
イメージとしては、フォルダのなかに細分化されたフォルダを作るようなもので、ほぼワンクリックの簡単な操作で済むのがポイントです。このように活用方法次第でラベルの中身が整理され、より視認性や検索性が向上します。
ワンクリックで表示・非表示を変更できる
ラベルの種類や数が増えると、ラベルそのものがどこにあるかわかりにくくなります。このような場合でも、Gmailではワンクリックでラベルの表示・非表示を変更できるため、視認性が高まるようにレイアウトを調整可能です。
Gmailのトップページには、左側のメニューの下にラベル一覧が表示されます。「ラベルリストでラベルを表示しない」と設定すると、ラベル一覧からそのラベルが一時的に見えなくなる仕組みです。また、ラベルはメールリストからも非表示にできます。
Gmailのラベルを設定する5つの手順
Gmailのラベルを設定する手順は次の通りです。
- 新規ラベルの作成
- ラベルの表示・非表示設定
- ラベルの色を変更
- サブラベルの作成
- メールをラベルに格納
いずれも簡易的な操作のみで進められるため、それぞれの手順を押さえましょう。
1. 新規ラベルの作成
まずはGmailにアクセスしましょう。Gmailを利用するにはGoogleアカウントが必要なので、メールアドレスとパスワードを使ってログインします。
Gmailの管理画面にアクセスすると、左側のメニューに[ラベル]と表示されています。その隣にあるプラス(ラベル作成)マークをクリックしてください。

すると新規ラベルの設定画面が現れます。新規ラベルの名称を作成しましょう。

なお、[次のラベルの下位にネスト]にチェックを入れると、作成済みの親ラベルの下に子ラベルを設定できます。ここでは親ラベルを作成するため、チェックを入れる必要はありません。最後に[作成]をクリックすると、ラベル一覧のなかに作成したラベルが表示されるようになります。

2. ラベルの表示・非表示設定
作成したラベルは画面上に表示されるが、非表示に設定することも可能です。非表示にする際は、当該ラベルの右側にある三点リーダをクリックし、表示・非表示の項目で[表示しない]を選択しましょう。

ラベルが多すぎてラベルリストに表示されない場合は、設定画面から非表示にできます。まずは画面右上の設定アイコンから[すべての設定を表示]をクリックします。

そしてタグを[ラベル]に切り替えると、[ラベル]の項目に一覧が表示されています。表示されているラベルで[非表示]をクリックすると、一時的にそのラベルが表示されなくなる仕組みです。

非表示にしたラベルをもとに戻す場合は、同じ設定画面で[非表示]から[表示]に切り替えます。
3. ラベルの色を変更
作成したラベルは任意の色に変更できます。営業用は赤、マーケティング用は青といった形で、テーマごとに色を分けられるため、より視認性を高めたい場合におすすめです。
色を変更するには、当該ラベルの隣にある三点リーダをクリックし、[ラベルの色]から任意の色を選択しましょう。

すると、ラベルの左側のマークが該当する色に変わります。

[カスタム色を追加]をクリックすると、デフォルト以外の色を自由に設定できます。また、設定した色をもとに戻す場合は、[色をクリア]をクリックします。
4. サブラベルの作成
サブラベルとは、親ラベルに紐付く子ラベルのことです。「営業」の親ラベルに「1課」や「2課」の子ラベルを設定するといった形で、ラベルに階層構造を設定できます。
サブラベルを作成するには、親ラベルの隣にある三点リーダをクリックし、[サブラベルを追加]を選択します。

そして、サブラベルのタイトルを付けましょう。

サブラベルを作成すると、[次のラベルの下位にネスト]の項目に自動でチェックが入ります。仮にサブラベルの名称を「1課」に設定し、[次のラベルの下位にネスト]の下側の項目で「営業」を選択した場合、「営業」の親ラベルに「1課」の子ラベルが格納されるということです。
また、サブラベルはサブラベルの下層に設定し、より多層的な構造にすることもできます。例えば、親ラベルが「営業」、そのなかに含まれている中層ラベルが「1課」、中層ラベルに下層のラベルに「Aチーム」といった形で多層化が可能です。

5. メールをラベルに格納
ラベルを作成した後は、受信メールをそのラベルのなかに格納しましょう。メールを格納するには、当該メールを開き、画面上部の三点リーダをクリックします。そして、[ラベルを付ける]をクリックし、一覧のなかから格納先のラベルを選択します。

格納したラベルをクリックすると、ラベル内の受信メールが一覧で表示されます。

ラベル内のメールを削除するには、そのメールを開き、画面上部の三点リーダをクリックします。そして、[ラベルを付ける]をクリックし、一覧のなかから当該ラベルのチェックを外します。

Gmailのラベル機能を活用した自動振り分け方法
Gmailのラベル機能を活用すると、メールが受信したタイミングで自動的に特定のラベルに振り分けることも可能です。ここではGmailの自動振り分けの仕組みと設定手順を解説します。
自動振り分けの仕組み
Gmailの自動振り分け機能は、受信トレイに届くメールを自動的に特定のラベルやフォルダに分類する機能です。これによりメールの整理が簡単になり、重要なメールを見逃すリスクも減少します。
自動振り分けは、Gmailのラベル機能とフィルタ機能を利用します。フィルタとは、特定の条件を指定して受信メールを絞り込み、任意のアクションを自動的に実行する機能です。任意のアクションには自動振り分けのほか、アーカイブ化やスターの添付、自動削除などの種類があり、うまくフィルタを設定するとメール管理の効率性が高まります。
自動振り分け設定の手順
メールを特定のラベルに自動振り分けする手順は次の通りです。
1,画面上部の検索窓の右側にある検索オプションのアイコンをクリック

2,フィルタ(絞り込むメール)の条件を設定する

3,[フィルタを作成]をクリック
4,アクションの設定画面で[ラベルを付ける]にチェックを入れる

5,[ラベルを選択]をクリックし、メールを格納したいラベルを選択する
フィルタの設定画面では、[From(どこから受信したか)」や「To(誰に送信したか)」、[件名]などの条件を設定できます。
例えば、[From」の項目に「abc@gmail.com」を指定すると、そのメールアドレスから受信したメールのみを受信トレイから絞り込める仕組みです。メールを絞り込み、[ラベルを付ける]のアクションを設定することで、当該メールアドレスから受信したメールがすべてそのラベルに自動で格納されます。
自動振り分けの詳細や設定方法は、こちらの記事でより詳しく解説しています。
Gmailのラベル機能を利用する際の3つの注意点
Gmailのラベル機能を利用する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。それぞれの注意点について詳しく解説します。
ラベルリストは並び替えができない
Gmailでラベルを作成すると、画面左側のラベルリストに表示されます。複数のラベルを作成した場合、それぞれの並び順は自動的に決まります。ラベルリストの並び順は基本的に五十音順で、順番は変更できないので注意が必要です。
どうしてもラベルリストを並び替えたい場合は、各ラベルのタイトルを工夫しましょう。例えば、タイトルの前に「1」や「2」といった数字を付け加えることで、意図的にラベルリストの並びを調整できます。
作成・表示数に上限がある
一つのGmailアカウントで作成できるラベルは最大10,000個です。小規模な組織やチームでは上限に達することは少ないと思われますが、大規模な組織になると上限に達する可能性も出てくるため、受信メールの量に応じてテーマを絞り込むと良いでしょう。
また、Gmail管理画面の左側に表示できるラベルは500個までです。ラベルが500個を超える場合、ラベルリストの読み込みに時間がかかる可能性があります。そのため、ラベルの表示・非表示の機能をうまく活用して、制限を超えないようにすることが大切です。
Gmailアプリではラベルを作成できない
ラベルを作成できるのはWebブラウザ版のGmailのみです。スマートフォンやタブレットでダウンロードできるモバイルアプリでは、ラベルを作成できません。
ただし、モバイルアプリでも受信したメールをラベルに格納することは可能です。また、ラベルに保存されているメールを確認することもできます。そのため、モバイルアプリでラベル機能を活用したい場合は、一度Webブラウザ版でラベルを作成し、その後にモバイルアプリでラベルの閲覧や格納などを行うと良いでしょう。
ラベル機能を活用してGmailのメール管理効率を高めよう
Gmailのラベルは、受信トレイの膨大な量のメールを整理するための機能です。うまく活用することでラベルごとにメールを振り分けられるようになり、受信トレイの視認性や検索性が向上します。
また、フィルタ機能と組み合わせると、受信メールの自動振り分けが可能になります。メールを受信する度にラベルやフォルダに手動で格納する必要がなくなるため、メール管理の効率性につながります。両方の機能を最大限に活かし、よりスムーズにGmailを運用しましょう。
電算システムでは、環境構築やコンサルティングなど、Googleサービスの導入支援サービスを提供しています。GmailやGoogleドライブといった個別のサービスはもちろん、Google Workspaceのサポートにも対応しています。専門領域に精通した数多くのエンジニアが在籍しているので、スピーディかつ質の高いサポートを行えるのが強みです。「Googleサービスを活用したいが具体的なイメージが湧かない」といったお悩みを抱える方は、ぜひ電算システムへと気軽にお問い合わせください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- ラベル機能 / ラベル機能とは...