パブリッククラウドは個人に限らず、企業でもよく利用されるクラウドコンピューティングサービスの形態です。この記事では、パブリッククラウドのメリットやデメリット、よく比較されるプライベートクラウドとの違いについて解説します。
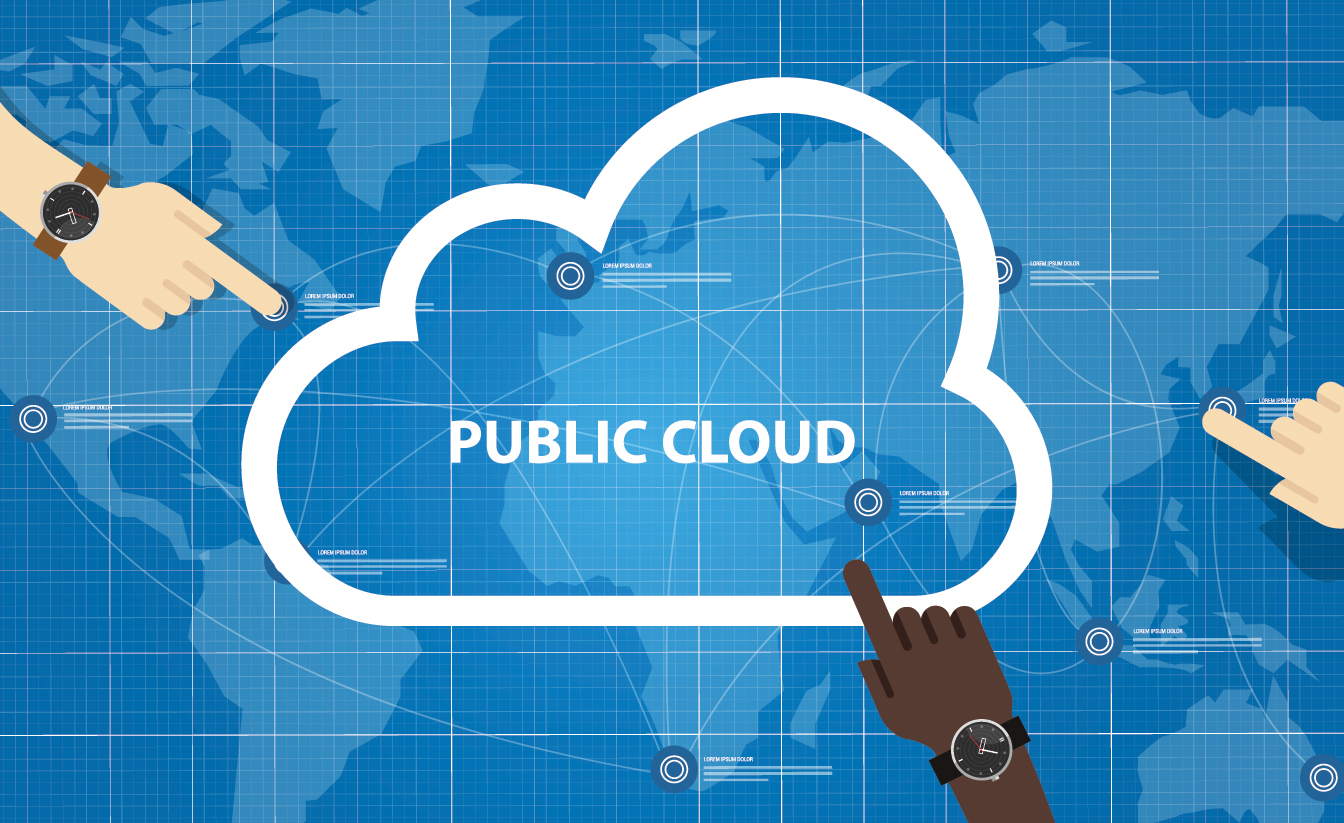
パブリッククラウドとは
パブリッククラウドとは、インターネット上で不特定多数の個人・企業に提供されるクラウドコンピューティングのサービス形態を指します。パブリッククラウドでは、サーバーやネットワーク、ソフトウェアといったクラウド上のリソースを、他のユーザーと共有して利用します。そのため比較的安価にクラウド環境が利用できるのです。
パブリッククラウドでは、一般的に必要なリソースだけ契約して利用します。利用状況にあわせてスペックを選択できるシステムです。クラウド上のハードウェアやネットワークは事業者によって構築やメンテナンスが行われるため、自社に常駐するIT管理者の負担にはなりません。
パブリッククラウドを利用するメリット
昨今では数多くの企業や個人ユーザーによりパブリッククラウドが広く活用されています。一体どのようなメリットがあってパブリッククラウドが選ばれるのでしょうか。以下で紹介します。
導入が手軽にできる
一般的にサーバーで何がしかのサービスを提供する場合、ハードウェアやソフトウェア、ネットワークを自分で調達する必要があります。それにかかる手間や時間は決して小さくありません。サーバーやネットワークを自社で構築・運用するとなれば、管理者は大きな負担を強いられることでしょう。
一方、クラウドであれば、事業者があらかじめ用意した環境を利用できます。自社で用意する必要がない分、手間が少なくて済むのです。オンラインで簡単な手続きさえ完了すれば、すぐに使えるのもメリットでしょう。サーバー・ネットワークなどの運用は事業者に任せられるため、管理者の負荷も軽減されます。このようにパブリッククラウドなら自社で用意するより、ずっと手軽にサーバー環境を導入できるわけです。
コストが抑えやすい
パブリッククラウドはコスト面で考えてもメリットが大きいです。パブリッククラウドを使えば、自社でハードウェアやネットワーク、ソフトウェアを購入・契約する必要はありません。事業者があらかじめ用意したクラウド環境を利用できるため、ほとんどの場合、初期費用もかかりません。
またクラウドコンピューティングの環境を多くのユーザーと共有して使うことから、ランニングコストも抑えられます。必要な分だけリソースを使う従量制の課金システムであるため、コストの無駄が発生することを予防しやすいのも魅力です。
さらにネットワークやハードウェア、ソフトウェアのメンテナンスを事業者に任せられる点も、コストを抑えられる理由です。自社の管理者が工数を割いたり、高い技術者をもった担当者を新しく雇用したりする必要はありません。
柔軟性が高い
自社でサーバーを運用する場合、リソースが足りなくなればハードウェアやネットワークを追加で購入する必要があります。仮に一時的なアクセス増にそなえてリソースを追加しようとすると、アクセスがおさまった際は余剰になってしまうこともあるのです。
一方、パブリッククラウドなら必要な時に必要なだけリソースを追加できます。サーバーに対する負荷がおさまった場合は、リソースを減らすのも簡単です。自社でサーバーを運用する場合に比べ、リソースの追加や削除を柔軟に行えるのは大きなメリットでしょう。
パブリッククラウドを利用するデメリット・課題
多くの企業や個人によって利用されるパブリッククラウドですが、デメリットや課題もあり、注意が必要です。
利用開始前に、このあと触れる事項についてはご確認いただくと良いかと存じます。
独自のカスタマイズは難しい
自社でサーバーを運用する場合、どのようなハードウェア構成にするかや利用するソフトウェアの種類まで自在に選択できます。自社用にリソースを占有できることから、自由なシステム構築が可能です。
一方、プライベートクラウドでは、あらかじめ利用可能なリソースの種類や範囲が、サービスによって決められています。クラウド環境を他ユーザーと共有して使うことから、自社向けに独自のカスタマイズを施すことは困難です。そのため企業独自のカスタマイズが必要なシステムを運用する場合、パブリッククラウドが環境として適さないこともあります。
トラブル対応がしにくい
自社でサーバーを構築・運用する場合、トラブルが発生した際は自社で解決を図らなくてはなりません。一方、パブリッククラウドであればサーバー環境やネットワークなどに、何がしかの問題が発生しても事業者が対応します。自社の負荷はかかりません。
この点はメリットともいえますが、トラブル解決がすべて事業者で行われるという点については注意が必要です。トラブルが発生しても、事業者から連絡がなければ詳細を把握できません。自社構築のサーバーを運営するときのように、状況をコントロールできないというのは、パブリッククラウドのデメリットと考えられます。
他のサービスとの互換性がない場合がある
一口にパブリッククラウドといっても、その環境は様々です。サードパーティーが提供する既存サービスに関しては、パブリッククラウドごとに互換性の有無に違いが生じる場合があります。各種サービスの互換性に関して、パブリッククラウドで統一された基準があるわけではないことを覚えておきましょう。
そのため利用中のサービスをクラウドに連携させたい場合は、パブリッククラウドを契約する前に互換性を必ず確認しなくてはなりません。有名なサービスでも使えない可能性があるので、慎重に下調べをすることが重要です。
パブリッククラウドとプライベートクラウドとの違い
よくパブリッククラウドと比較対象になるのがプライベートクラウドです。企業がクラウドを採用する際は、どちらを選択するとよいかきちんと検討する必要があります。
プライベートクラウドとは、自社専用のクラウド環境を指します。パブリッククラウドはその仕様上、他社ユーザーと共有して使われますが、プライベートクラウドは自社内の各部署やグループ会社内だけで共有します。
プライベートクラウドは自社で環境を構築することから、パブリッククラウドと異なり自由にカスタマイズできます。企業のポリシーにあわせたセキュリティを確保することも可能です。トラブル発生時も、パブリッククラウドのように事業者任せになってしまうことはありません。
その反面、パブリッククラウドと違い、環境を用意するための高額な初期費用がかかってきます。リソースを柔軟に追加・削除できない点も注意が必要でしょう。
パブリッククラウドの利用が向いているケース
特別なシステムを利用しているような、高いカスタマイズ性が必要な環境であればパブリッククラウドは適していません。セキュリティポリシー上、データを外部に出せないといった事情がある場合も、パブリッククラウド以外を選ぶ必要があります。
逆にいえば高いカスタマイズ性が不要で、セキュリティポリシーも許容範囲なら、パブリッククラウドが利用できます。その上でコストを抑える必要があったり、リソースの追加削除を柔軟に行う必要があったりするケースならば、さらにパブリッククラウドが適しているといえるでしょう。
パブリッククラウドサービス「Google Cloud™」について
Google Cloud(旧:GCP)は、Google社が提供するパブリッククラウドサービスです。Amazon社のAWS(Amazon Web Services)やMicrosoft社のMicrosoft Azureと並んで、高い知名度を誇ります。
Google Cloud なら、Google社のAI・機械学習・各種分析といった高品質な技術が反映されたサービスを、シンプルな料金体系で利用できます。Google検索・Gmail・YouTubeといったGoogle社の各種サービスを支えてきた実績のあるインフラを使える点もメリットといえるでしょう。
株式会社電算システム(DSK)では Google Cloud を利用したいユーザーを力強くバックアップいたします。運用から導入支援、システム開発といった、様々なメニューをご用意しています。Google Cloud 資格をもつ担当者による独自のトレーニングも利用できます。
まとめ
パブリッククラウドは、不特定多数が共有して利用するクラウドコンピューティングの提供形態です。パブリッククラウドのサービスは、インターネットを経由して利用します。
パブリッククラウドは低コストで利用できる上に、運用負荷が少なくて済むのがメリットです。状況に応じてリソースの追加削除もできます。一方で、カスタマイズできる範囲が限られる点や、トラブル対応が事業者任せになる点については注意しなくてはなりません。これらの点が問題となる場合は、プライベートクラウドの利用が選択肢に入ります。
株式会社電算システム(DSK)では、パブリッククラウドサービスのひとつであるGoogle Cloud の導入支援サービスを提供しています。導入でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- クラウド



















