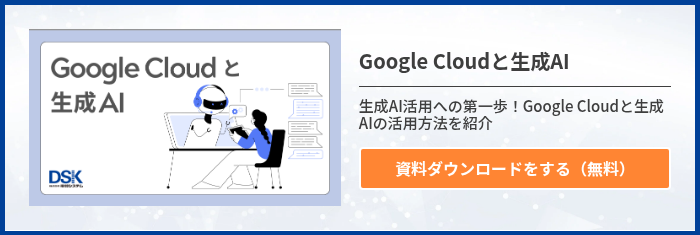生成AIとは、テキストや画像などの指示を与えることで、AIが独自のコンテンツを作成してくれる技術です。自動で独自のテキストや画像、音声などが生成されるため、クリエイティブ業務を効率化するための手段として注目を集めています。
しかし、生成AIサービスには数多くの種類があるため、「どれを選んで良いかわからない」と悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。サービスごとに強みや特徴が異なるため、目的や用途に即した適切なものを選択することが重要です。
そこで本記事では、生成AIを用いたおすすめサービスを、テキスト系・画像系・音声系の種類に分けて解説します。それぞれの特徴や強み、活用方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
【テキスト系】生成AIのおすすめサービス6選
生成AIサービスにはさまざまな種類があり、生成するコンテンツの種類によって主にテキスト系、画像系、音声系に分類されます。ここでは、まずテキスト系生成AIのおすすめサービスを紹介します。
Gemini
Geminiは、2023年12月にGoogle社が開発した高性能なテキスト系生成AIサービスです。画像、音声、動画といったさまざまな情報を使って、チャット形式で高度なタスクを手軽に指示できます。
Geminiは「マルチモーダルAIモデル」として知られています。マルチモーダルモデルとは、テキスト、画像、音声、動画など、異なる種類のデータを統合的に学習・処理できるAIモデルのことを指します。
Geminiでは、開発当初から複数の形式のデータを用いて事前学習を行い、さらに追加のマルチモーダルデータを活用してファインチューニングが施されています。これにより、多様な入力形式をスムーズに理解し、高度な推論やプログラムの生成といったタスクにも対応が可能です。
Googleは、Geminiの安全性向上にも注力しています。例えば、開発プロセスにおける安全対策の実施や、包括的な安全性評価の導入、レッドチームによるテストの実施といった取り組みが代表的です。このような施策により、倫理上の課題やバイアス、誤情報の生成などのリスクを抑えられます。
ChatGPT
ChatGPTは、OpenAI社が開発したテキスト系生成AIサービスです。膨大なテキストデータを学習した大規模言語モデル(LLM)をもとに動作しています。ユーザーが入力した文章の文脈を理解し、自然な日本語で対話を行ったり、文章の要約、翻訳、アイデアの提案、コードの生成など多様なタスクに対応できます。
OpenAI社は、2022年11月にChatGPT-3.5を発表し、その優れた性能と操作のしやすさから世界的に注目を集め、利用者数が急速に増加しました。その後もバージョンアップを重ね、2024年5月に発表されたChatGPT-4oでは、テキストに加えて音声や画像データにも同時に対応し、自然なテンポでの音声対話が可能となりました。そして、2024年12月に登場したo3-miniは推論能力が大幅に強化され、よりスピーディーな応答を実現し、創造性や生産性のさらなる向上が期待されています。
Copilot
Copilotとは、Microsoft社が提供するテキスト系生成サービスです。AIによる情報検索や文書の生成など、多彩な機能を備えており、メール作成やWord文書の作成といった作業の負担軽減にも役立ちます。
検索エンジンのMicrosoft Bingと連携しており、質問に対してインターネット上の最新かつ関連性の高い情報を検索し、回答とあわせて参照元のWebサイトの詳細を表示します。これにより、ユーザーはCopilotの回答の正確性を確認できるため、ハルシネーション(AIが誤った情報を生成してしまう現象)の防止にもつながります。
Copilotには、無料版と有料版の2種類があります。法人向けに提供されている有料版のMicrosoft 365 Copilotは、コストがかかるため導入のハードルがやや高めですが、無料版と比較してメールやWordでの文章作成支援、タスクのチャット形式での依頼など、より高度なサポートが可能です。
Catchy
Catchyは、ライティングアシスタントを得意とするテキスト系生成AIサービスです。ブログ記事やメール、キャッチコピー、Webサイトのコンテンツ作成、SNS投稿など、さまざまなニーズに応える100種類以上の文章生成機能を搭載しています。特にブログの執筆においては、SEO対策が施された見出しや本文、関連キーワードを含んだテキストの生成も可能です。
Catchyを利用することで、文章作成にかかる時間を大幅に削減できます。タイトルや見出しの作成、本文の構成、キーワードの選定、文章の文体調整など、これまで手間のかかっていた作業の効率化につながります。
また、モバイルアプリが用意されているため、外出先から利用できるのもポイントです。毎月10クレジットの範囲内であれば、無料で利用できます。
Claude
Claudeは、米国スタートアップのAnthropic社が開発したテキスト系生成AIサービスです。ほかのテキスト系生成AIサービスと同様、チャット形式での質疑応答やテキスト生成、翻訳・要約、プログラミングコード生成などに対応しています。
同サービス特有の強みは、コストパフォーマンスの高さにあります。初代モデルの「Claude Instant」や第二世代の「Claude2」は、GPT-4に匹敵する性能とされており、膨大なテキスト量でもスムーズに処理を行えるのが利点です。有料ではあるものの、比較的リーズナブルにプランが設定されており、高性能なAIモデルを低価格で利用できるのも魅力です。
最新モデルの「Claude3 Sonnet」では最大20万トークン、より上位モデルの「Claude3 Opus」は最大30万トークンのテキスト入力に対応しています。PDFファイルの読み込みも可能なので、会議資料や研究論文の要約にも活用が可能です。
Grok
Grokは、イーロン・マスク氏が創業したxAI社が開発したテキスト系生成AIサービスです。イーロン・マスク氏がかかわっているだけあり、X(旧Twitter)との互換性に優れています。
Xのアプリ内からGrokに直接アクセスでき、プロンプトで質問や指示を行うと、AIがその内容に即した回答を行ってくれます。出力される情報はSNSの強みが活かされており、リアルタイムの情報に即座にアクセスできるのが利点です。
Grokには、「Regular Mode」と「Fun Mode」の2つの動作モードが用意されています。Regular Modeでは、従来のテキスト系生成AIサービスと同様、プロンプトに沿ったテキスト生成や質疑応答、文章の要約といった作業が可能です。一方のFun Modeは、質問や指示に応じて、よりユーモアに富んだ回答を生成してくれる特徴があります。
【画像系】生成AIのおすすめサービス4選
続いて、画像作成に強みを持つ生成AIサービスを紹介します。テキストによる指示をもとに独自の画像を作成したり、既存の画像を別の画像に変換したりと、さまざまな活用が可能です。
Stable Diffusion
Stable Diffusionは、AIが膨大な画像データを学習したうえで、ユーザーが入力したテキストにもとづいて高品質な画像を生成するサービスです。
潜在拡散モデル(Latent Diffusion Model)という手法を採用しており、ノイズから画像を生成することで、完全に新しいビジュアルを作り出せます。具体的には、まずランダムなノイズから画像の生成を開始し、そこから徐々にノイズを除去していくことで、最終的にリアルな画像へと仕上げていきます。イメージとしては、最初は砂嵐のようなノイズのなかから、人物や背景が次第に浮かび上がってくるような生成プロセスです。
この際、AIはこれまでに学習してきた大量の画像データをもとに、形状や色彩を補いながら自然な画像を構築します。どのような画像ができあがるかは、プロンプトと呼ばれる指示文の内容によって大きく変わります。具体的なプロンプトを入力することで、より意図に沿った画像が出力されます。
Stable Diffusionは、オープンソースとして提供されているサービスです。ユーザーは、自分の目的に合わせてモデルを自在に調整できます。ソースコードが全世界に公開されており、Web版を使用すれば誰でも無料でStable Diffusionを使って画像を生成することが可能です。
Midjourney
Midjourneyは、テキストから画像を生成するAIサービスです。コミュニケーションアプリであるDiscordを通じて利用でき、ユーザーがDiscord上でメッセージを送信することで、そのテキスト内容にもとづいた画像を自動的に生成してくれます。Discordとは、全世界で3億5,000万人以上のユーザーが登録しているチャットツールです。
Midjourneyには高度なAIが搭載されており、精密でリアルな画像を生成することが可能です。2025年4月時点での最新バージョンはV6.1となっており、初期のV1から継続的にアップデートが行われてきました。
リリース初期のV1では、画像の一部がぼやけるなど、実用性に乏しいクオリティでしたが、V5では自然な描写が可能になり、現在のV6.1では非常に高精度な画像生成が実現されています。また、画像を超高解像度でアップスケーリングする機能が追加されたのもポイントです。それまでの出力サイズは1024×1024ピクセルに制限されていましたが、この新機能により、デフォルト設定で4倍の解像度、すなわち4Kを超える4096×4096ピクセルで出力を行えます。
DALL-E3
DALL-E3は、OpenAI社によって開発された画像系生成AIサービスです。テキストでの指示にもとづいて、リアルで高品質な画像を自動生成できます。
従来の画像生成AIサービスでは、高品質な画像を得るには複雑なプロンプトが必要でした。一方のDALL-E3は、シンプルな指示でも高精度な画像を生成できます。さらに、複雑なプロンプトにも対応しているため、細かなニュアンスの調整も可能です。生成後の画像に対しても、修正指示を出すことでイメージにより近づけた画像を再生成できます。
DALL-E3はChatGPT上に統合されており、プロンプトを入力するだけで、それにもとづいた具体的な画像を自動的に生成してくれます。ChatGPTと同じ感覚で利用できるのがメリットです。また、暴力的な表現や、ヘイトスピーチに該当するコンテンツの生成は制限されており、公人の名前を含むリクエストを拒否するなど、悪用防止のための対策も講じられています。
Canva
Canvaは、デザインに関する専門知識がなくても、誰でも手軽に高品質なデザインを作成できるツールです。プロのデザイナーによって作成された60万点以上のテンプレートや、1億点を超える素材を活用することで、ロゴやイラストをスムーズに作成できます。そのほか、ビジネス文書やメッセージカード、SNS投稿用の画像など、幅広い用途に対応したデザインに対応しています。
Canvaには、機能の一つとして画像生成AIが搭載されています。写真風やビビッド、3D、アニメ調、水彩画風など、さまざまなスタイルを選択して画像を生成できるのが特徴です。また、日本語のプロンプトにも対応しており、生成した画像をそのままCanva上で編集できます。
生成できるのは画像だけではありません。ほかにも、グラフィック素材や動画の自動生成、さらに生成した画像や動画に対して音声の追加も可能です。自身で独自のデザインを作成できるほか、AIが生成したグラフィックを活用することもできるため、クリエイティブ業務の多様な範囲をカバーできます。
【音声系】生成AIのおすすめサービス4選
音声系の生成AIサービスにも、さまざまな種類が存在します。それぞれ特徴や強みが異なるため、生成AIサービスを導入する目的に合わせて選ぶことが大切です。
NotebookLM
NotebookLMとは、Googleの生成AI「Gemini」を利用して、情報整理やリサーチを行えるアシスタントツールです。データソースをアップロードすることで、情報検索やアドバイス、テキストの要約といった作業を自動的に実行してくれます。
従来のAIアシスタントツールとの違いは、幅広いデータソースに対応している点です。NotebookLMは、Webサイトや資料などのテキストに加え、PDF・画像・音声・動画といった幅広いファイル形式にも対応しています。そのため、テキストだけでなく、音声や画像、動画でのデータ出力も可能です。
コエステーション
コエステーションは、テキストから手軽に高品質な合成音声を生成できるAIサービスです。一般ユーザーから著名人まで、幅広い音声データを取りそろえており、音質や話し方、トーンなどが異なるさまざまなオリジナル音声を出力できます。
エディターにテキストを入力するだけで、簡単に合成音声を作成可能です。喜びや怒り、悲しみといった感情表現に加え、ピッチや話速なども画面上の直感的な操作で細かく調整できます。生成した音声は、MP3やWAV形式でダウンロードして利用できます。
また、Web APIの機能を活用すると、指定した音声とセリフがクラウド上で合成され、リアルタイムで音声が生成されます。日々内容が変わる問い合わせ対応やサービス窓口での案内、天気予報の読み上げなど、あらかじめ音声を作成しておけないシーンでも活用が可能です。
ReadSpeaker
ReadSpeakerは、HOYA株式会社が提供する、テキストの自動読み上げに特化した生成AIサービスです。日本語や英語、中国語、韓国語といった需要の高い言語をはじめ、44ヶ国語に対応した多言語のラインナップをそろえており、利用シーンやユーザーの好みに応じた80種類以上の音声モデルが用意されています。2025年4月時点において88ヶ国でサービスが展開されており、導入実績は11,000社を超えます。
ReadSpeakerは、DNN(ディープニューラルネットワーク)型音声合成と、波形接続型音声合成の2種類の音声合成方式を採用しており、独自の機械学習技術によって短時間での収録を実現しています。また、顧客のニーズに応じて提供される「ORIGINAL VOICE」を利用することで、他社にはないリアルな肉声感を持った音声を出力できるのも特徴です。
Voice Space
Voice Spaceは、最先端のAI技術を活用した音声系生成AIサービスです。200種類以上の多彩な音声モデルを取りそろえ、さらに50ヶ国語を超える言語に対応しているため、ビジネスや教育、エンターテインメントなどの幅広いシーンで活用できます。
本サービスの特徴の一つは、音声バリエーションの豊富さにあります。プロのナレーター風の声からアニメ調の音声まで選択でき、リアルタイムで自然な音声を生成可能です。ユーザー自身の声をもとにAI音声をカスタマイズすることもできます。リアルタイムでの音声変換にも対応しているため、ライブ配信やラジオなどでの利用も広がっています。
加えて、PowerPointとの連携機能により、プレゼン資料のクオリティ向上にも貢献します。エンタープライズプランではAPIの提供も行っており、自社システムに生成AIの仕組みを実装できるのもポイントです。
生成AIサービスの活用方法
生成AIサービスは、種類によってビジネスでの活用方法が異なります。テキスト系、画像系、音声系に分けて、それぞれの活用方法について解説します。
テキスト系生成AIサービスの活用方法
テキスト系生成AIサービスは、プロンプト(テキストによる指示)に沿ってテキスト状のコンテンツを生成できるのが特徴です。
最もシンプルな活用方法としては、AIに対してシンプルに質問してみることです。「○○について教えてください」「○○の仕組みを説明してください」といったプロンプトを与えると、学習データやインターネット上の情報をもとに、的確な回答を行ってくれます。そのため、ビジネスシーンでは情報収集として活用が可能です。
そのほか、次のような形で発展させることもできます。
- 資料や論文の要約・翻訳
- 広告のキャッチコピーや説明文の作成
- ECサイトに出品する商品のタイトルや説明文の作成
- メールのタイトルや本文の作成
- システムを開発・導入する際の要件定義
- プログラミングコードの作成、既存コードの修正
このように文字や文章を扱う業務であれば、さまざまなケースで活用できます。ただし、テキスト系生成AIサービスを利用する際は、具体的な指示が欠かせません。AIにどのような作業をしてほしいのか、作業時に留意すべき点はあるかなど、できるだけ細かい指示を与えることで、精度の高い出力結果を得やすくなります。
画像系生成AIサービスの活用方法
画像系生成AIサービスは、プロンプトに従ってオリジナル画像を作成するのが得意です。テキストによるプロンプトを入力しても構いませんし、ラフ案や参考画像をアップロードして、それに近い画像を生成することも可能です。
画像系生成AIサービスの活用方法としては、次のようなケースが想定されます。
- 企業ロゴの作成
- 商品・サービス画像の作成
- ブログに掲載するサムネイル画像やインフォグラフィックの作成
- SNSのアイキャッチ画像やコンテンツ画像を作成
- ゲーム開発におけるグラフィックデザインのサポート
また、テキスト系生成AIサービスと組み合わせることで、プレゼン資料の作成といった活用も可能です。資料の構成や見出し、本文などをAIに考えてもらい、さらに資料内に掲載する画像もAIが出力することで、効率良くプレゼン資料を作成できます。
なかには3Dモデルの作成に特化した生成AIサービスも存在します。3Dモデルは、ゲーム業界や建築業界、医療業界など、さまざまな業種で活用されており、生成AIを使って作成することで、クリエイティブ業務の効率化につながります。
音声系生成AIサービスの活用方法
音声系生成AIサービスでは、既存のテキストや画像、動画といったデータを組み合わせて、独自の音声を作成できます。その種類はさまざまで、特定の人物の声に似せた音声を作成する音質変換や、複数の人間の声をかけ合わせて新たな音声を作成する音声合成や、低品質な音声を高品質に変換できるノイズキャンセルなど、サービスごとに強みが異なります。
ビジネスシーンで音声系生成AIサービスを利用するなら、次のような方法があげられます。
- 問い合わせ対応での自動応答システムとして活用
- ボイスボットの作成
- サービス窓口や店頭での自動案内システムとして活用
- 動画やテレビCMなどのアナウンスを作成
- 会議中の音声のリアルタイム翻訳
あらかじめ音声バリエーションが用意されているサービスであれば、プロンプトを入力するだけで即座に音質変換が完了するため、手軽に利用できます。また、サービスによっては、話し方の雰囲気やトーン、スピードなどを細かく調整できるものもあります。
生成AIサービスを選ぶ際の3つの注意点
生成AIサービスを利用する際は、次のようなポイントに注意が必要です。
- 目的を明確にする
- 適切な運用ルールを定める
- 情報の根拠や裏付けを必ず確認する
それぞれの注意点について詳しく解説します。
目的を明確にする
生成AIサービスを活用する際は、その導入目的と具体的な目標を明確にすることが重要です。単に「AIを導入したい」と考えるのではなく、業務の効率化や新たなビジネス機会の創出、顧客対応の強化、コストの最適化など、自社が抱える課題に即した活用方法を検討しましょう。
例えば、作業の自動化によって時間とコストを削減し、業務の効率化を図ることは、生成AIサービスを導入する際のよくある目的の一つです。そのほか、顧客一人ひとりに合わせたサービスを提供することで、顧客体験を向上させて満足度を高めるといった目的を設定するのも良いでしょう。
あらかじめ明確な目的を定めておくことで、ツールの選定や運用方針の決定がよりスムーズに行えます。
適切な運用ルールを定める
生成AIサービスを業務に活用する際には、セキュリティインシデントや権利侵害といったリスクが懸念されるため、適切な運用ルールの整備が非常に重要です。著作権や知的財産権の順守、個人情報の適切な取り扱い、偏見・差別的表現の排除、盗用・模倣の防止、利用部門の制限など、明確で厳格なルールを策定することで、リスクを抑えられます。
運用ルールを策定する際は、一般社団法人 日本ディープラーニング協会が公開している「生成AIの利用ガイドライン」を参考にすることをおすすめします。
情報の根拠や裏付けを必ず確認する
生成AIサービスを利用する際の留意点として、情報の正確性があげられます。コンテンツの自動生成やクリエイティブな作業の効率化など、数多くの利点を持つ生成AIですが、その出力内容が常に正確であるとは限りません。
AIが実際には存在しない情報をもとに文章を生成してしまう現象は、「ハルシネーション」と呼ばれています。これは、生成AIが情報の真偽を完全に見分けることができないために発生するものであり、特に文章生成の場面で頻繁に見られる現象です。
生成AIが出力する文章は自然で説得力があるため、つい内容を信じてしまいがちです。しかしながら、出力された情報を鵜呑みにせず、裏付けや根拠を確認したうえで活用することが重要です。
生成AIサービスを活用してクリエイティブ業務を効率化しよう
2025年1月、GoogleはGoogle Cloud上で稼働する新たな生成AIサービスの「Google Agentspace」のリリースを発表しました。同製品では、社内に蓄積されたデータ資料やメール、チャット履歴などを横断的に検索でき、カレンダーの登録やタスクの遂行などを自動的に処理できる機能が搭載されています。単なる生成AIサービスではなく、企業のDX化を促進させる強力なツールになり得るのが特徴です。
このように生成AIサービスは常に進化しており、今後もGoogle Agentspaceのような製品が増えていくことでしょう。生成AIサービスを活用することで、完全オリジナルなテキストや画像、音声といったコンテンツを効率良く作成できます。この特徴を活かせば、情報収集や資料の要約、Webコンテンツの制作、問い合わせ対応など、ビジネスシーンの各種業務へとさまざまな形で発展が可能です。
生成AIの活用方法に関しては、こちらの資料で詳しく紹介しています。無料でダウンロードできるので、生成AIの仕組みをビジネスに採り入れたい方は、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Cloud(GCP)
- キーワード:
- 生成 ai おすすめ