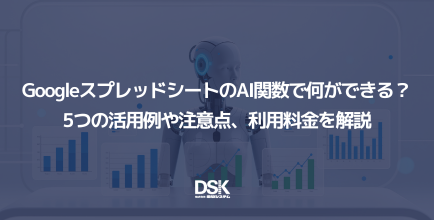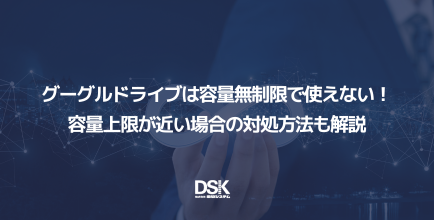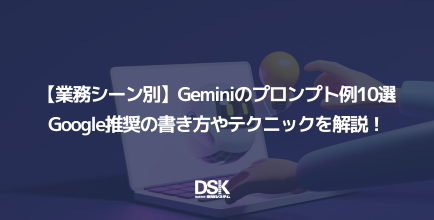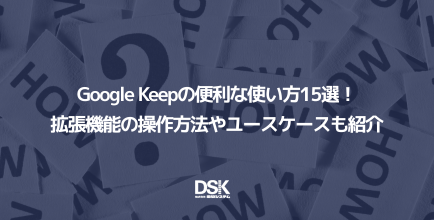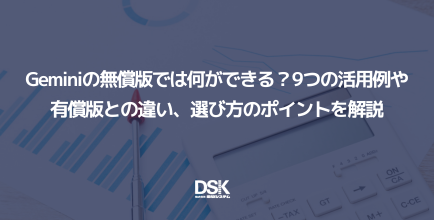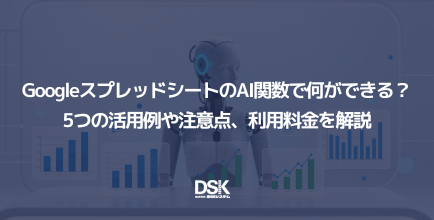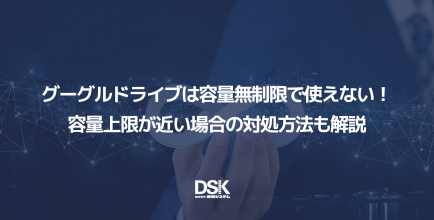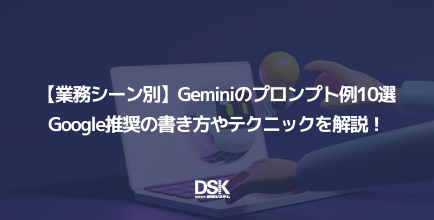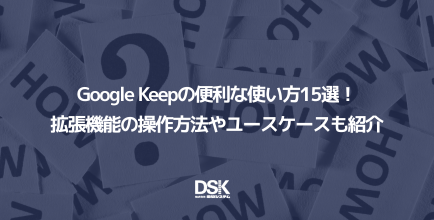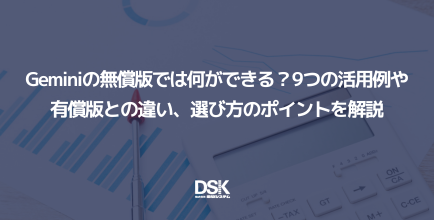BCP対策とは、自然災害をはじめとした問題が発生しても、事業を継続できるように対応をまとめた計画です。大規模な自然災害や感染症、サイバー攻撃など、事業の停止につながるさまざまな問題は、突然発生します。問題が発生しても従業員の生命や企業の資産を守り、事業を継続させるには、BCP対策が必要不可欠です。
この記事では、BCP対策の概要や目的、策定するときの手順などをわかりやすく解説しています。BCP対策の基本的な知識を網羅できる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。
BCP対策とは事業を継続できるように事前に準備しておくこと
BCP対策とは、自然災害や大事故が発生した際にも事業を継続できるように準備することや、その事業継続のための計画を意味します。Business Continuity Planの頭文字を取った用語で、日本語では「事業継続計画」と訳されます。
BCP対策の対象は、自然災害や大事故だけではありません。サイバー攻撃や大規模な感染症、国際紛争も対象になります。BCP対策を行っておくべき、事業が停止してしまうケースは以下の通りです。
- 水害や大地震といった自然災害で、機械や建物が破損
- 従業員が感染症にかかり、担当していた工程が停止
- 業務管理システムがサイバーテロの標的になりウイルスに感染し、生産ラインが停止
- 仕入先である企業の操業停止により、原材料の入荷停止
- 国際紛争の影響により、原材料が輸入不可
BCP対策には、安否確認方法や緊急時のマニュアル、データのバックアップ方法など、さまざまな対策が記されており、企業によって内容は多種多様です。従業員の生命や企業の資産を守り、事業を継続できるように綿密に計画されています。BCP対策が注目される背景や具体的なBCP対策の例を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
BCP対策に取り組む目的3選
BCP対策に取り組む目的には、以下の3つがあります。
- 緊急時に速やかに対応する
- 企業価値・信頼性を高める
- 経営戦略に役立てる
それぞれの目的を確認して、BCP対策の基礎知識を学びましょう。
緊急時に速やかに対応する
BCP対策の目的の1つは、緊急時の早期復旧に向けて企業が迅速に対応することです。BCP対策で緊急時の対応を事前に決めておけば、無駄な行動や誤った行動をすることなく、事業の継続に向けて迅速に対応できます。結果、事業の停止や縮小、企業の倒産を防ぎ、事業を継続できる可能性が高まります。
緊急時に役立つようにBCP対策を策定する以上、その計画自体が曖昧な状態では、逆に被害が拡大し、事業停止につながる恐れがあるため、効果のある綿密な計画が必要です。
企業価値を高める
BCP対策の策定は、企業価値を高める目的にも活用されます。BCP対策がしっかりと策定されていれば、緊急時でも安定した事業活動ができる企業として、取引先や顧客からの信頼を高められます。BCP対策を策定している企業は、実際に取引先として選ばれやすい傾向があるため、ビジネスの成長も期待できるでしょう。
経営戦略に役立てる
BCP対策を策定する目的には、企業の経営戦略の見直しが含まれる場合もあります。BCP対策を策定する中で、優先して復旧すべき事業が話し合われるため、事業や業務それぞれの重要度を把握できます。企業として重要度の高い事業や業務、そうでないものを洗い出せれば、何にリソースを費やして成長すべきかどうかを判断しやすくなり、経営戦略を決める重要な要素の1つになるでしょう。
BCP対策による6つのメリット
BCP対策を策定するメリットは、以下の6つです。
- リスク管理の向上
- 事業継続能力の向上
- 信頼性の向上
- 社内コミュニケーションの改善
- 経営基盤や組織体制の強化
- 社会貢献
BCP対策の策定は、緊急時の対応の明確化以外にもさまざまなメリットを企業にもたらします。それぞれのメリットを確認して、BCP対策の必要性を理解しましょう。
リスク管理の向上
BCP対策の策定は、自社のリスク管理の向上に役立つ取り組みです。BCP対策を策定する中で、事業の潜在的なリスクを明らかにでき、具体的な対策を検討できます。潜在的なリスクの洗い出しや影響度などを分析すれば、より効果的なリスク管理が可能です。自然災害やサイバー攻撃、感染症などのさまざまなリスクへの対策が立てられ、緊急時でも迅速に対応できる企業へと成長できます。
事業継続能力の向上
BCP対策の策定によって、企業の事業継続能力を向上できます。企業の事業継続能力は、事業の停止や縮小などの重大な問題が発生した際に試されますが、事前の対策がなければ、能力の向上は期待できません。BCP対策の策定をきっかけに事業継続能力が向上して、より安定した事業活動ができる企業へと成長できるでしょう。
事業継続能力を向上させるには「BCM」も重要です。BCMは、事業の継続に向けてBCPを管理・運用することを意味します。BCMが適切に行われている企業は、事業継続能力が高く、緊急時に無駄なく事業継続に向けて行動できます。BCMについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
信頼性の向上
BCP対策の策定は、投資家や取引先からの信頼性の向上につながります。投資家や取引先からの信頼は、ビジネスの成長を大きく左右する重要な要素です。
BCP対策を策定している企業は、リスク管理の意識が高く、実際の緊急時でも被害を最小限に抑えて事業を継続できるという安心感を周囲に与えます。投資家や取引先は、なるべく安定していて将来性のある企業との関わりを求めるため、BCP対策の策定によって、投資先や取引先として選ばれやすくなります。
社内コミュニケーションの改善
BCP対策の策定には、部門や部署、チーム間の連携が必要不可欠です。BCP対策の担当者がすべて決めるのではなく、各部門や部署、チームとコミュニケーションを取りながら策定する必要があるため、社内コミュニケーションを促進できます。社内コミュニケーションの減少が課題になっている企業は、BCP対策の策定に取り組めば、組織内の協力関係の強化や、組織としての一体感を生むきっかけになるため、積極的に実施を検討するとよいでしょう。
経営基盤や組織体制の強化
BCP対策の策定は、企業の経営基盤や組織体制の強化に効果的な取り組みです。BCP対策を策定すれば、緊急時に従業員が迷わず適切な対応ができるようになり、被害を最小限に抑えられます。
つまり、大きなトラブルが発生しても適切に対応できる環境づくりにつながり、組織体制の強化が可能です。BCP対策を策定する際は、自社の現状や課題、強みや弱みを洗い出す必要があるため、経営戦略の立案にも役立ち、経営基盤の強化も期待できるでしょう。
社会貢献
BCP対策の策定は、社会貢献にもなる重要な取り組みです。例えば、自然災害が発生して物資や住居に困っている人々がいる場合、自社のサービスや商品を通して援助したり、備蓄用の飲料水や食料、一時避難場所を提供したりして、人々を支援できます。BCP対策は、自社の資産を守るためだけではなく、企業としての社会的責任を果たす上でも重要な役割を担っています
BCP対策を策定するときの手順5ステップ
BCP対策を策定するときの手順は、以下の通りです。
- 自社にあった方針を選定
- 社内体制を整える
- 優先事業を決めた後、事業ごとの対策を決める
- 事業案を策定する
- BCP発動基準や体制を整備する
手順を確認して、自社でBCP対策を策定するときの参考にしてください。
1.自社にあった方針を選定
BCP対策の策定で最初に行うのは、自社にあった方針の選定です。自社がどんな目的でBCP対策を策定するのかを決めれば、具体的な内容を目的に沿って決められます。方針を検討する際は、自社の経営方針や企業理念を参考にするのも重要なポイントです。目的が決まった後は、社内全体に共有して、従業員にBCP対策の必要性を伝えます。
自社の方針を検討する際は、発生する可能性のある自然災害やサイバー攻撃、その他のリスクをリストにまとめて、発生したときの自社への影響度も含めてBCP対策の対象とするリスクを絞り込みましょう。
2.社内体制を整える
BCP対策の策定に向けて社内体制を整えます。まずは、BCP対策の策定を進めるプロジェクトチームや担当者を決めましょう。BCP対策の策定は、多くの企業がプロジェクトチームを立ち上げており、チームの作業調整を行う専門の事務局を設置するケースもあります。
次に、部門や部署を超えて社内全体の協力も必要になるため、各部門、部署でBCP対策の担当者を選びます。それぞれの部門・部署の意見を聞きながら進めることで、自社にあったBCP対策の策定が可能です。BCP対策は全従業員に情報を共有すべき取り組みなので、必要性や策定の進捗・内容の周知ができるような社内体制の整備を進めましょう。
また、社内の体制整備だけでなく、緊急時に必要な協力会社や取引先との連携も検討する必要があります。事業の継続に重要な関係先と連絡をとって、実際の緊急時にきちんと機能する計画の立案が必要です。
3.優先事業を決めた後、事業ごとの対策を決める
複数の事業を行っている企業は、緊急時に優先して復旧させる事業を決めましょう。優先度を判断する際の基準は、以下のような例が挙げられます。
- 顧客数の多さ
- 売上の高さ
- 利益の高さ
- 業務の遅延・停止によって生じる損害の大きさ
- 顧客にとっての必要性
- 自社の評判や市場シェアの維持における重要性
復旧を優先させる事業を決める際は、主観ではなく、顧客数や売上、利益などの複数の客観的視点から検討します。また、事業ごとに完全に復旧するまでの時間や必要な資金、人員配置はどうするのかも、このときに細かく確認しておきましょう。
優先して復旧する事業が決まった後にすべきことは、事業ごとの対策の策定です。対策を検討する際は、実際に発生した問題をもとに起こり得ることをまとめて、具体策を決めます。例えば、新型コロナウイルスが蔓延した際に、外出自粛の要請や緊急事態宣言があり、リモートワークを導入する必要がありました。そのときに必要だったものや見えてきた課題は何だったかなど、できる限り具体的に考えることが重要です。
4.事業案を策定する
BCP対策の事前案を作成します。事前案を作成するには、事業ごとにすべての業務を確認し、復旧に向けた優先順位を設定する必要があります。事前案を作成するときに重要なポイントは、以下の通りです。
- メイン事業が停止した際に、会社の体力がどの程度の期間まで持つのかを考慮する
- 事業継続に必要なリソースや業務、復旧までにかかる時間を把握して、さまざまなケースのシミュレーションを行う
BCP対策の事前案を策定する際は、できる限り具体的な内容にするよう意識しましょう。例えば、以下のような具体的な状況を想定して、必要なものや行動などを洗い出します。
- 自然災害による被災で事業に使う資源が手に入らない場合、資源の代替となるもの(資金や臨時の従業員など)を確保する方法を検討しなければならない
- 大規模な感染症が蔓延した場合に、リモートワークに対応できるツール(チャットやビデオ会議など)を導入する必要がある
BCP対策の事前案には、緊急時の連絡や指示の方法も忘れずに盛り込みましょう。
5.BCP発動基準や体制を整備する
BCP対策の「発動基準」と「発動時の体制」を整理します。これらが曖昧な状態では、実際に発動するときに時間がかかるため、具体的に設定しましょう。発動時の体制を検討する際は、誰が誰に対してどのように指示を出し、どのように行動するのかなどを具体的にすれば、混乱せず適切に行動できます。緊急時は冷静な判断が難しくなるため、前もってチームを組み、トップダウンで動ける体制を構築しておきます。
BCP対策を自社で策定する際は、内閣府が作成した「事業継続ガイドライン」を参考にすると良いでしょう。事業継続ガイドラインは、BCP対策の必要性を広く伝えて、策定を促す目的で作成されたもので、BCP対策の策定手順が詳しく解説されています。自然災害を対象とした内容になっていますが、大事故やサイバー攻撃、感染症などにも適用可能です。
関連ページ:事業継続ガイドライン:防災情報のページ・内閣府
BCP対策の策定・運用の3つのポイント
BCP対策の策定・運用のポイントは、以下の3つです。
- 社内・社外と連携して策定することを検討する
- 評価・改善を繰り返し精度を高める
- 社内にBCP文化を定着させる
策定・運用のポイントを確認して、自社で実践してみましょう。
社内・社外と連携して策定することを検討する
BCP対策を策定する際は、社内・社外との連携が重要です。自社の施設が利用できなくなったケースを想定して、協力会社や取引先と連携し、BCP対策を検討します。BCP対策を策定した後は、社内・社外で連携して、全従業員に周知しましょう。また、緊急時の対応をマニュアルにまとめて関係者全員に共有しておけば、BCP対策を実行できる体制を構築できます。
評価・改善を繰り返し精度を高める
BCP対策は、策定した後も内容の継続的な評価・改善を繰り返して、精度を高める動きが大切です。定期的にBCP対策のテストを行い、適切に機能するかどうかを評価した後、見えた課題を解決できるように内容を改善します。
BCP対策は、具体的かつ現実的に起こり得る問題に対応した内容でなくてはなりませんが、はじめから完璧なものにする必要はありません。内容の評価・改善を繰り返して、より効果的に機能するBCP対策を策定していきましょう。
社内にBCP文化を定着させる
BCP対策を策定した後は、社内全体にBCP文化を定着させるような取り組みが必要です。BCP対策に関わったメンバーのみが内容を理解していても、計画は実行できません。実際の緊急時にBCP対策を実行するには、普段から社内でBCPを意識できるように情報の周知や教育が必要です。
BCP対策の教育をする場合は、以下のような取り組みが効果的です。
- ディスカッション
- 社内研修
- e-ラーニングによる理解度テスト
- 社内防災訓練
- 外部の防災イベント
BCP対策にGoogle Worksapce導入をしよう
BCP対策は、事業継続を目的に、緊急時だけでなく、平常時も準備を進めていくものです。新型コロナウイルスや東日本大震災を教訓として、緊急時に備えた事前準備や対応のマニュアル化に本格的に取り組む必要があります。
BCP対策の一環として多くの企業に効果的な対策と言えるのが「Google Worksapce」をはじめとする安全性の高いクラウドストレージを活用した情報の一元管理と、リモートワーク環境の整備です。Google Workspaceは、GoogleドライブやGmailなどのGoogleの複数のアプリケーションをまとめて利用できるグループウェアです。
20種類のサービスを低コストで使用でき、パソコンやスマートフォン、タブレットでもアクセスできます。これからBCP対策の策定を予定している方や、策定中の方は、Google Workspaceの導入を検討すると良いでしょう。
電算システムでは、Google Workspaceの導入支援を行っています。導入計画の立案や、システムエンジニアによる導入時の設定サポートなど、幅広いサービスを提供しているので、導入に関して少しでも不安やお悩みがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- BCP対策とは