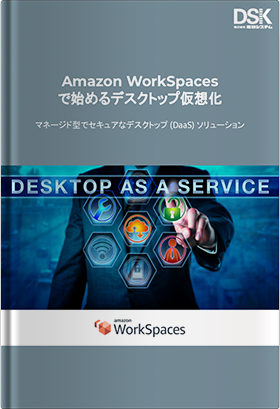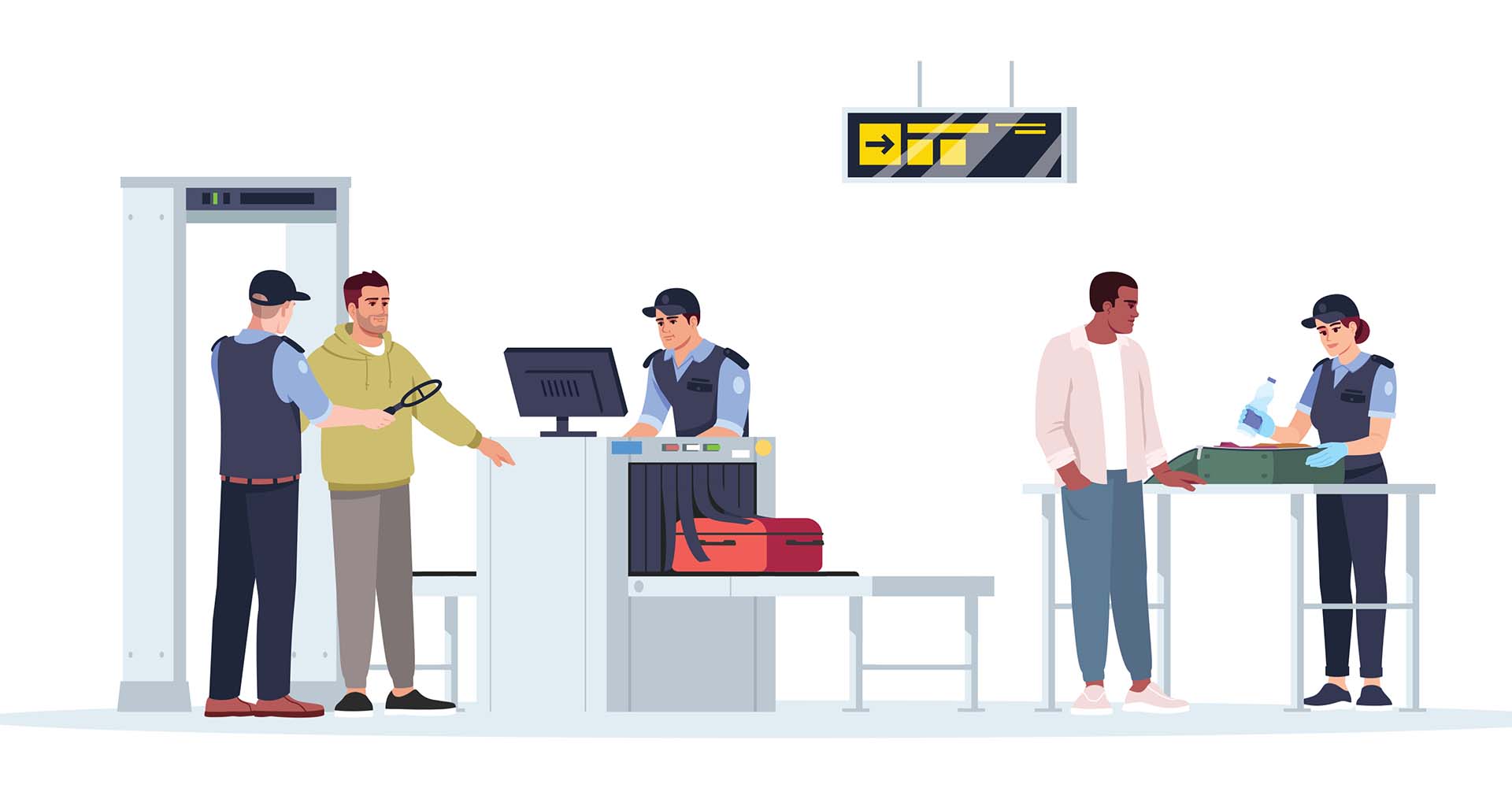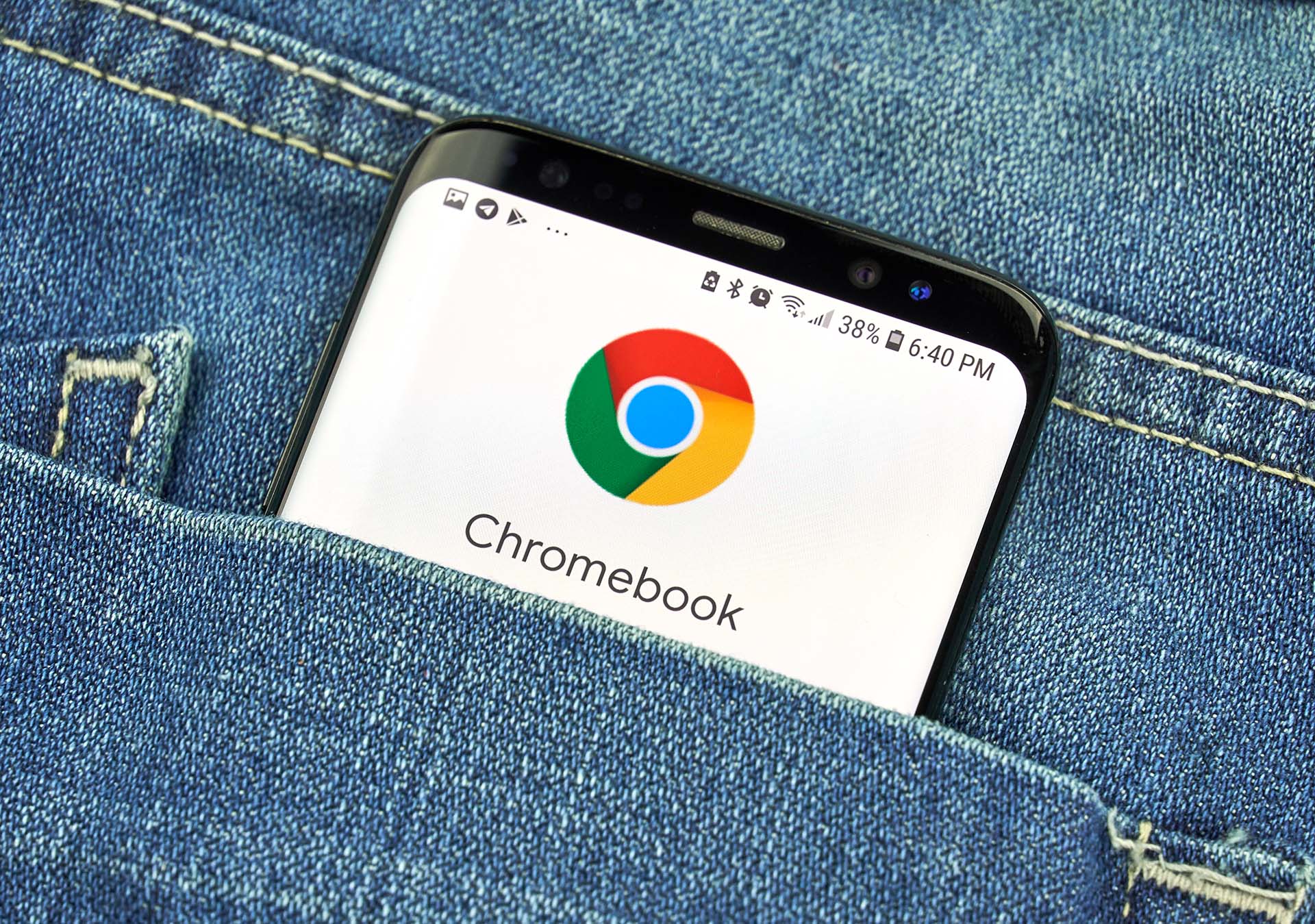多方面で注目されているリモートワークも、導入には慎重を期さなければ失敗に陥るケースがあります。まず大切なのは、メリットだけでなくリモートワークを導入するデメリットについてもしっかりと認識し、メリットを最大に引き出し、デメリットを最小限に抑える取り組みを行うことです。
本稿では、リモートワークのメリット・デメリットを整理しつつ、導入時に考慮すべきポイントについてご紹介します。
3つのリモートワークを知る
リモートワークといっても、その形態によって3つの分類があります。それが「在宅勤務型」「モバイルワーク型」「サテライトオフィス型」です。
在宅勤務型
従業員は自宅またはカフェ等、オフィス以外のスペースで仕事を行います。本社オフィスとのコミュニケーションはメール・電話・Web会議・ビジネスチャットが中心になり、私用デバイスを使用するのが一般的です。
モバイルワーク型
営業の外回りなど外出の多い従業員が、移動時間などを有効活用して仕事を行います。時には顧客企業に出向いて仕事を行うこともあり、そのための携帯用デバイスなどは会社が支給します。
サテライトオフィス型
本社オフィスの周辺や、遠く離れた土地にリモートワーク専用のオフィスを構え、従業員はそこで仕事を行います。都市部企業が地方に設置する場合もあれば、地方企業が都市部に設置する場合もあります。
このように、リモートワークを大きく3つに分類すると、それぞれにメリット・デメリットが異なるということが分かりますね。次項で各形態のメリットとデメリットをそれぞれ確認していきましょう。
リモートワークのメリットとデメリット
在宅勤務型
メリット
自宅や最寄りのカフェなどで仕事を行う在宅勤務型は、従業員が通勤にまったく時間をかけずに仕事を行えるというのが最大のメリットです。これは、企業にとっては交通費削減になり、従業員にとっては時間を有効的に活用できることに繋がります。
日本のビジネスパーソンの平均通勤時間は片道1時間なので、1日のうち2時間も余裕を持つことができれば、心身共にリラックスした状態で仕事に臨むことができます。特に都市部では、朝の通勤ラッシュで一気に疲れてしまうというビジネスパーソンがほとんどなため、在宅勤務型によるメリットは大きいでしょう。
デメリット
デメリットとしては、会社とのコミュニケーションを完全にICTに頼ることになるため、オフィス勤務よりもコミュニケーション効率が下がる点です。また、従業員の人事評価制度を変えなければいけないケースもあるため、導入に手間がかかります。
モバイルワーク型
メリット
モバイルワーク型は外出が多い従業員や企業にとって、特に大きなメリットがあります。これまでは、外出中は事務作業などを行うことができず、帰社してから処理するため残業が当たり前という企業が多かったでしょう。こうした環境にモバイルワーク型を導入すると、移動時間等を有効的に活用できるので、外出の多い従業員でも残業ゼロを目指すことができます。
デメリット
移動中でも会社のシステムにアクセスできるように、モバイルルーター等でインターネット環境を整える必要があるため、必要以上のコストがかかるというのがデメリットです。また、移動中に社用デバイスを使用するほど紛失や置き引きなどの盗難に遭うリスクが高まります。
サテライトオフィス型
メリット
サテライトオフィス型では在宅勤務ほどではないにせよ、自宅からほど近い場所にオフィスを設置することで通勤時間を短縮することができ、多様な働き方を提案することができます。それにより、仕事に対するモチベーションと会社に対するロイヤリティを向上することができ、最終的には労働生産性向上という形で会社に還元されます。
本社オフィスではないにしろオフィスに必要な機能をすべて揃えておくことができるため、在宅勤務型よりもコミュニケーション効率を上げることもできます。
また、地方自治体がサテライトオフィスの誘致活動を行っているところも多く、地方にサテライトオフィスを設置することで補助金を受けたり、オフィスを破格でレンタルすることができたり、「田舎で暮らしながら仕事がしたい」という願望を持つ従業員の離職を防ぐこともできます。
デメリット
都市部にサテライトオフィスを設置する場合は、それなりのレンタル料を支払わなければいけません。近年ではコワーキングスペースやシェアオフィスなどのレンタルオフィススペースが増えていますが、人気な場所はすぐに埋まってしまいますし、料金もやや高めです。
[RELATED_POSTS]
リモートワーク導入の注意点
このように、リモートワークには形態ごとにメリット・デメリットが異なります。それらを踏まえた上で、リモートワークを導入する際の注意点についてご紹介します。
リモートワーク導入の目的と、最適な導入形態を明確にする
リモートワークを導入するにあたりまず大切なのが、「導入の目的を明確にすること」です。実は、場当たり的なリモートワーク実施によって失敗に陥るケースが少なくありません。そのため、リモートワーク導入の目的をしっかりと明確にした上で、在宅勤務型なのかモバイルワーク型なのか、サテライトオフィス型なのか、あるいは複合型を実施するのかを選択する必要があります。
適切なコミュニケーションツールを選ぶ
リモートワークではメールと電話だけでコミュニケーションが完結する、ということは絶対にありません。Web会議やビジネスチャット、クラウドストレージなど様々なコミュニケーションツールを整えることが大切です。しかし、製品ごとに特徴も異なるので、自社にとって適切なコミュニケーションツールを選ぶ必要があります。社内調査などを実施した上で、適切な製品を選択しましょう。
私用デバイスの利用を許可するか?禁止するか?
リモートワークに私用デバイスの利用を許可することで、導入初期投資を抑えることができます。しかし、私用デバイスは社用デバイスを利用するよりもセキュリティリスクが上昇するため、その点のバランスを考慮して選択する必要があります。
許可する場合のセキュリティ対策
私用デバイスの利用を許可する場合は特別なセキュリティ対策が必要です。特に、MDM(Mobile Device Management)といった管理ツールは欠かせませんし、その他ビジネス上の利便性をプライバシーに配慮したセキュリティ対策が必要です。
リモートワーク導入にあたり人事評価制度の見直しを行う
週1日程度のリモートワーク実施ならば問題は起きませんが、週3日以上のリモートワークを実施する場合は人事評価制度の見直しを行いましょう。勤務形態が大きく変わるため、何をもって評価するのかを改めて見直し、適切な人事評価制度を導入します。
リモートワーク中の勤怠管理をどうするか?
リモートワーク中は管理職の目が届かないため、だらだらと仕事をしてしまい逆に労働生産性が下がったという事例も少なくありません。これを解決するためには、リモートワーク中の勤怠管理を徹底するために、勤怠管理システムを導入したり成果主義に切り替えたりするなど対策を考える必要があります。
まとめ
リモートワークを導入することで様々なメリットが生じますが、必ずしも導入は簡単ではありません。各注意点についてしっかりと考えた上で、自社にとって最適な形でリモートワーク制度を整備するとともに、それらを支えるためのITC環境の整備も不可欠です。
国内最大のGoogle パートナーとして豊富なGoogle 製品の導入実績をもつ電算システムでは、「Chrome Enterprise」をおすすめしています。
Chrome Enterpriseは、Chromebook をはじめとする Chrome OS 専用の管理・運用ライセンスです。1台1ライセンスの購入で複数台の端末を一元的に管理・設定がブラウザ上で出来ます。
Chrome Enterprise の設定項目は300以上あり、社内環境からモバイル、サテライト利用、在宅勤務など様々な利用シーンに合わせてプロファイルを簡単に作成することができます。
是非お気軽にご相談ください。
- カテゴリ:
- Chromebook