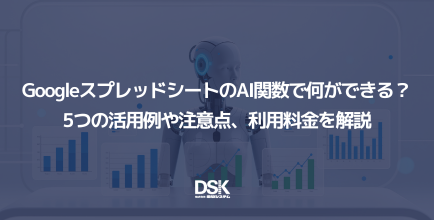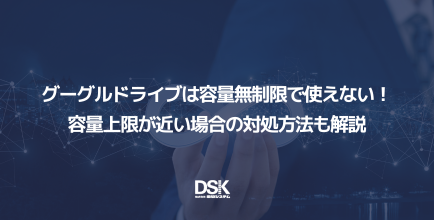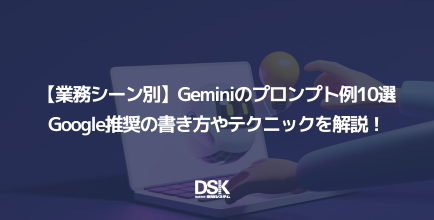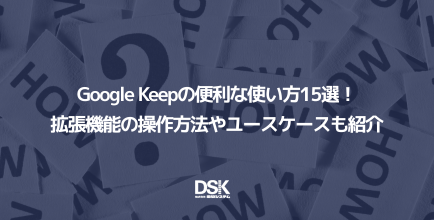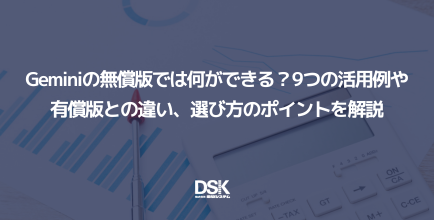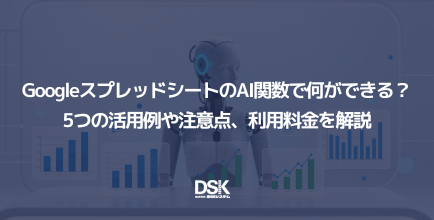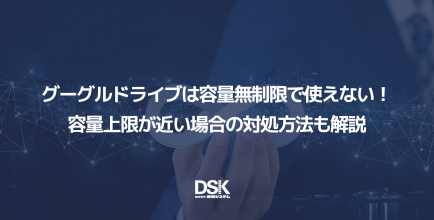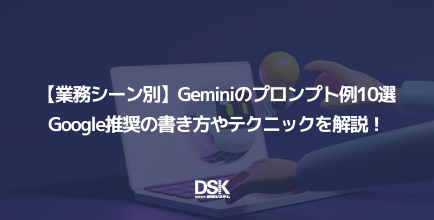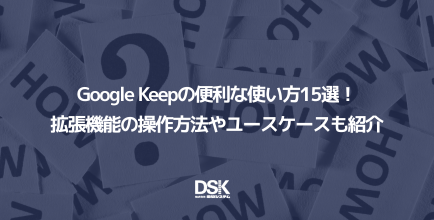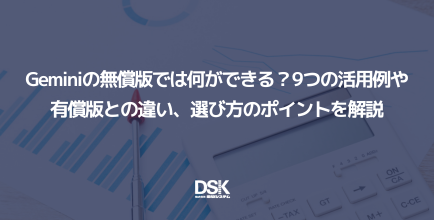ビジネスで必要不可欠な「ファイル共有」をメールやUSBメモリ上で行っていませんか。現在、IT化やDX化によって、クラウドストレージ(オンラインストレージ)やサイトを用いる企業が増えています。オンライン上で直接ファイルをやり取りできるので、メールの文面を考えたりUSBメモリを手渡したりするといった手間がかからず効率的です。
しかし、導入を検討している方や情報収集している方のなかには、「クラウド上でのファイル共有が自社にとって必要かわからない」「本当に情報の漏れはないのかセキュリティ面が気になる」といった課題に悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、クラウドファイル共有の重要性や導入メリット、選定ポイント等をご紹介します。導入の検討をしている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ファイル共有サービスとはクラウド上で蓄積・共有・管理するためのサービス
ファイル共有サービスは、テキスト、画像、動画などのファイルをクラウド上で保存・共有・管理できるサービスです。ダウンロード用のURLを送るだけで、社内外にかかわらず、共有したい相手と簡単にファイル共有が可能です。ファイル共有サービスは、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスからアクセスできて、場所や時間に制限されずに作業できます。
ファイル転送サービスと似ていますが、ファイル共有サービスとは利用目的が異なります。ファイル転送サービスの利用目的は、あくまで手軽なファイルのやり取りです。ファイル共有サービスは、セキュリティの安全性が保たれた環境でチーム内の情報共有をリアルタイムに行う目的があります。セキュリティの安全性を確保する必要があるため、ファイルを送受信する際の暗号化やアクセス権限の設定などの機能が必要不可欠です。
ファイル共有サービスが注目される2つの理由
ファイル共有サービスが企業から注目されている理由は、以下の2つです。
- テレワークの普及
- サイバー攻撃などの社会問題化
理由を把握して、サービスに関する理解を深めましょう。
テレワークの普及
ファイル共有サービスが注目されている理由の1つが、テレワークの普及です。コロナ禍により世界中でテレワークの普及が進み、オンライン上でファイルをやり取りする機会が増えました。ファイル共有サービスは、客先訪問に行けずテレワークをせざるを得なかったコロナ禍に注目が集まり、オンライン上でのファイル共有の利便性を高めたサービスです。
メールで顧客とファイル共有をする場合は、ファイルにパスワード設定をして、添付ファイルを送る作業と併せてパスワードが入力されたメールを別途送信しなければなりません。また、客先に直接足を運び、ファイルが保存されたUSBメモリを渡してデータ共有する方法もありました。しかし、コロナ禍にファイル共有サービスの利便性の高さが注目されて、テレワークが普及すると共に需要が高まりました。
サイバー攻撃などの社会問題化
企業のセキュリティ対策に対する意識が高まったことも、ファイル共有サービスが注目されている理由です。近年では、国や地方自治体、企業などをターゲットにしたサイバー攻撃が増えており、手口の巧妙化と複雑化が進んでいます。
チェック・ポイント・リサーチの調査によれば、2022年に国内組織の1つあたりが被害にあった週平均でのサイバー攻撃の数は、前年よりも29%増加しているという結果になりました。自社データを安全に保護するために、企業にとってセキュリティ対策は重要です。さまざまな脅威から自社データを守る目的で、安全性が高いファイル共有サービスを利用する企業が増えています。
参照元:「チェック・ポイント・リサーチ、2022年のサイバー攻撃数はグローバルで前年比38%増加、日本は29%増加と発表」PR TIMES
ファイル共有サービスの6つの基本機能
ファイル共有サービスの基本機能は、以下の6つです。
- ファイルの共有
- データのバックアップ
- ファイルの検索
- 暗号化によるセキュリティ
- アカウントの一元管理
- オンライン会議やチャット
基本機能を把握して、導入を検討する際の参考にしましょう。
ファイルの共有
ファイル共有サービスを導入すれば、クラウド上のストレージにファイルを保存するだけで、社内外の相手とファイル共有ができます。権限を付与した相手にのみファイルの閲覧やダウンロードができるため、不正に操作される心配がありません。
データのバックアップ
ファイル共有サービスには、ファイルを自動的にバックアップする機能があります。サービスのなかには、複数のサーバーでファイルのバックアップデータを保存するものもあるため、誤ってデータを紛失しても素早い復旧が可能です。
ファイルの検索
ファイル共有サービスには、ファイル検索機能があります。フォルダやファイルの名前、ファイル内の本文から検索可能です。検索結果が表示されるまでの時間が短いため、手間と時間をかけずに必要なファイルを探せます。
暗号化によるセキュリティ
ファイル共有サービスには、ファイル管理を暗号化して処理する機能があります。企業にとってのデータは、重要な資産です。適切なセキュリティ対策を講じて、ファイルを管理する必要があります。多くのファイル共有サービスは、ファイル管理を暗号化しており、情報漏えいの対策を施しています。
ファイル共有サービスを利用すれば、社内におけるセキュリティ対策の強化が可能です。
アカウントの一元管理
ファイル共有サービスを導入すれば、社員のアカウントを一元管理でき、プロジェクトやチームなどのカテゴリー別でグルーピングできます。アカウントによって閲覧制限の設定もできるため、一部の相手に限定してファイル共有したい場合に便利です。
オンライン会議やチャット
近年は、オンライン会議やチャットが利用できるファイル共有サービスが増加しています。テレワークや出張などで同じ場所にいない社員同士でも、手軽に打ち合わせが実施可能です。
ファイル共有サービス導入のメリット3選
ファイル共有サービスを導入するメリットは、以下の3つです。
- 社内の情報を集約できる
- 場所を問わずにファイルの共有ができる
- 複数人でも効率的に作業ができる
メリットを把握して、自社で導入する際の参考にしてください。
社内の情報を集約できる
ファイル共有サービスを導入すれば、社内で保有している情報の集約・管理が可能です。情報が一ヶ所で整理されれば、ファイル作成者や日付を一覧で確認できて、最新のファイルはどれなのか判断しやすくなります。ファイルの整理が簡単になり、チームや部署内などで円滑な情報共有が可能です。
また、情報を1つのサービスに集約する場合は、セキュリティ対策として閲覧制限の設定ができるサービスを選ぶとよいでしょう。ファイルの共有範囲を情報の重要性や利用目的などに応じて設定できるため、情報漏えいのリスクを低減できます。
場所を問わずにファイルの共有ができる
ファイル共有サービスは、複数のデバイスから利用できます。手元に自分のパソコンがなくても、タブレットやスマートフォンから簡単にアクセス可能です。移動している間や出張先にいる状況など、場所や時間の制限を受けずにファイルを共有できます。
複数人でも効率的に作業ができる
ファイル共有サービスを活用すれば、複数人でファイルの同時編集が可能です。ファイル共有サービスに保存されたデータは、クラウド上のストレージで管理されるため、複数人でアクセスしてリアルタイムで作業できます。メンバー間で円滑に編集・確認ができて、業務の効率化に役立ちます。同じ場所にいないメンバーや顧客ともファイルの編集・確認ができるため、作業時間を削減しながら素早く業務を遂行可能です。
ファイル共有サービスを選ぶ際の4つの比較ポイント
ファイル共有サービスを選ぶ際に役立つ比較ポイントは、以下の4つです。
- 十分なストレージ容量があるか
- 利用できる端末は充実しているか
- セキュリティの強化
- 社員が簡単に使いこなせるか
ポイントを確認して、サービスを選ぶ際に役立てましょう。
十分なストレージ容量があるか
ファイル共有サービスを選ぶ際は、ストレージ上に保存可能なデータ容量の大きさを確認しましょう。テキストや画像、動画などのファイルの種類を整理して、必要な容量を検討します。ストレージが容量不足になれば、ファイルの共有が円滑に進まなくなり、業務の遅延を招く恐れがあります。
サービスのなかには、有料版の利用でデータ容量が無制限になるものもあります。
セキュリティの強化
ファイル共有サービスを選ぶ際は、セキュリティ対策の内容を確認しましょう。企業は、顧客の個人情報など機密情報となる重要なデータを取り扱うため、セキュリティレベルの高いサービスを選ぶ必要があります。サービスを選ぶ際は、情報漏えいの防止につながるかどうかの確認も大切です。情報漏えいのリスク低減に役立つ機能は、以下の3つです。
- アクセス権限を設定する機能
- 利用可能なIPアドレスを制限する機能
- 通信/情報を暗号化する機能
上記以外にも、国際的なセキュリティ資格であるISO27001(ISMS)の取得があるかどうかをサービス選びの判断基準に含めれば、よりセキュリティレベルが高いサービスを絞り込めます。また、サービスのセキュリティ対策を確認すると同時に、自社のセキュリティポリシーに遵守しているかどうかも確認しましょう。
ファイル共有サービスは、インターネットを介してアクセスするため、アカウント情報の管理に注意が必要です。2要素認証や2段階認証に対応したサービスを選べば、セキュリティ対策の強化につながります。
社員が簡単に使いこなせるか
サービスの使いやすさは、自社に導入した際の運用に影響を与えます。サービスを選ぶ際は、簡単な操作でファイルが共有できて、場所や時間にかかわらずアクセス可能なものを選びましょう。機能が多く複雑な場合、操作の難しさから社内での使用率が上がらない可能性があります。サービスの使いやすさは、社内でサービスを浸透させるための重要なポイントです。
また、パソコン・スマートフォン・タブレットなどのあらゆる端末が利用できるサービスであれば、場所や時間の制限を受けずにアクセスできて便利です。入力方法が複雑で、操作画面が見にくいなど課題があると、業務効率を下げる可能性があります。サービスを選ぶ際は、使いやすさを意識しましょう。
また、ファイル共有サービスでは、利用者の属性に応じてアクセス権限を設定する必要があるため、サービスの管理業務が増えないように注意しましょう。セキュリティ面と業務負担のバランスを意識した運用が大切です。
ファイル共有サービス運用時の3つの注意点
ファイル共有サービスを運用する際の注意点は、以下の3つです。
- フォルダの構成
- ファイルの共有権限
- ファイルの保管期限
注意点を把握して、サービスを社内で円滑に利用できるよう取り組みましょう。
フォルダの構成
ファイル共有サービスを導入する際は、フォルダの取り扱いに関する運用ルールの設定が大切です。社員が個々にフォルダを作成した場合、フォルダの構成が乱雑になる可能性があります。社内共通の運用ルールを設定・周知して、フォルダが整理された状態を維持できるようにしましょう。
運用ルールの例としては「作業途中か完了かどうかを基準にフォルダを分ける」「第一階層はプロジェクトごとにフォルダを作成する」などが挙げられます。フォルダの運用ルールが設定されれば、必要なファイルを見つけやすくなります。
ファイルの共有権限
ファイル共有サービスでは「編集可能」や「閲覧のみ」などの共有権限の設定が可能です。共有権限を設定する際は、設定ミスに気をつけて作業しなければなりません。外部の人に共有するなかで誤った設定をすれば、情報漏えいが起きる可能性があります。
社内共通の運用ルールとして、ファイルの分類別に権限の種類を決めておきましょう。部署、役職別にグループを分類して、フォルダの内容に応じた適切な権限を設定する作業も重要です。
ファイルの保管期限
ファイル共有サービスを導入する際は、ファイルの保管に関するルールを設定しておきましょう。利用するサービスやプランによってデータ容量の大きさは異なりますが、基本的に利用できる容量には上限があります。使わないファイルを保管したままにすると、保存できるデータの空き容量がなくなり、一時的に業務の遅延を招く可能性があります。
対策として、ファイルもしくはフォルダ別に保管期限を設定する方法が効果的です。保管期限を過ぎたファイルやフォルダの取り扱いについても事前に決めておけば、ストレージ内のデータ容量を削減しながら、継続的にサービスを利用できます。保管してから一定期間経過したファイルは、アーカイブで保存しておく方法がおすすめです。誤って重要なファイルを紛失するリスクを低減できます。
クラウド上でのファイル共有にはGoogle Workspaceがおすすめ
Google Workspaceは、ビジネスに活用できる多種多様なアプリケーションが集約されたクラウド型グループウェアです。アプリケーションの1つである「Google Drive」は、ファイル管理機能を使ってさまざまな形式のファイルを保管できます。Googleが開発・提供しており、Googleの各種アプリケーションと連携できます。
また、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートなどで作成したファイルを、社内外の相手と共有可能です。無料プランでは、15GBまでのデータ容量を利用できて、法人向けの有料プランも提供されています。Google Driveは、ファイルの共有・管理に便利なアプリケーションですが、利用する際に注意すべきポイントがあります。
Google Driveは、フォルダを各階層ごとに管理する仕様になっており、フォルダの整理にはまとまった時間が必要です。保存するデータが多いほど、フォルダの整理に手間と時間がかかるため、利用する際は注意しなければなりません。対策としては、ファイルの種類や用途などに応じて、小まめに指定のフォルダで整理して、見やすい状態を維持する方法がおすすめです。
Google Driveは、Googleアカウントを持っていれば、無料ですぐに利用できます。無料プランの場合、ストレージのデータ容量の上限は、1人あたり15GBです。15GB以上のデータ容量が必要であれば、Google Workspaceの有料プランを購入しましょう。Google Workspaceの主な料金プランは、以下の4つです。
- Business Starter:¥680/ユーザー/月
- Business Standard:¥1,360/ユーザー/月
- Business Plus:¥2,040/ユーザー/月
- Enterprise:要問い合わせ
Google Workspaceは、部署やチーム間のやり取りを促進して、生産性の向上に役立ちます。また、Google Workspaceは、インターネットを介して利用するクラウド型ツールです。デバイスとインターネット環境があれば、場所や時間にかかわらず、ファイルを使った作業ができます。
Gmail、Googleチャット、Googleカレンダーなどのアプリケーション同士を連携できるため、円滑な情報共有が可能です。また、1つのファイルを複数人で同時編集できる機能があります。チーム間でコミュニケーションを取りながら作業できるため、社内の業務効率化に役立ちます。
関連記事はこちら
目的に合ったファイル共有方法の選択をしよう
ファイル共有サービスを活用すれば、チームメンバーやクライアントなどのさまざまな相手と手軽にファイルを共有できます。サービスによって特徴や機能、料金などが異なるため、自社に適したものを慎重に検討しましょう。無料トライアル期間を利用すれば、サービスを実際に利用して自社での運用に向いているかどうかを判断できます。
セキュリティ強化や円滑なデータ管理、業務効率化のために、ファイル共有サービスを有効活用しましょう。Google Workspace(旧G Suite)は、ファイル共有だけではなく、メール、オンライン会議などのビジネスに役立つアプリケーションが集約されたツールです。Google Workspaceを導入することで、組織内のコミュニケーション活発化や業務の効率化を促すアプリケーションを複数利用できます。
Googleのプレミアムパートナーを務める株式会社電算システムでは、中小企業などで初めてサービスを導入する企業様に対して、サポート対応を行っています。また、以下の資料では、オンプレファイルサーバーからGoogleドライブへの移行手順や運用方法について解説しています。クラウド上でのファイル共有を検討している方はぜひ参考にしてください。
「Google Workspace」の資料ダウンロードはこちら
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- 業務効率化