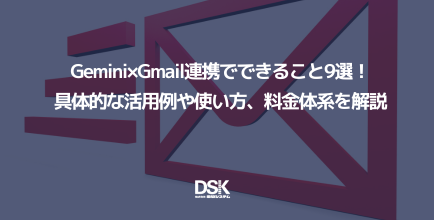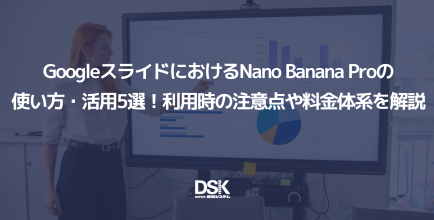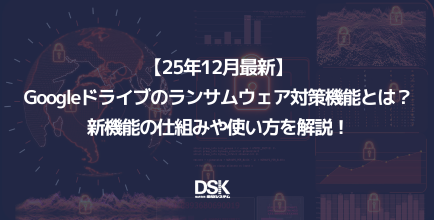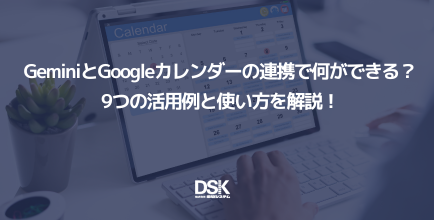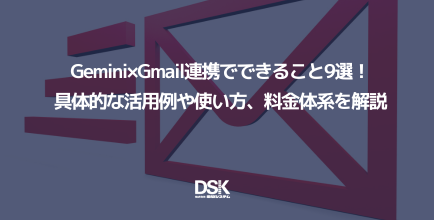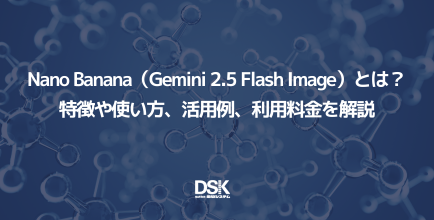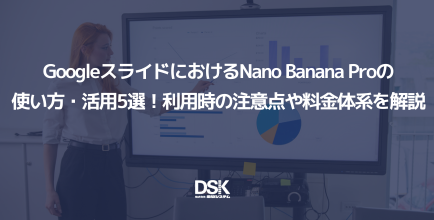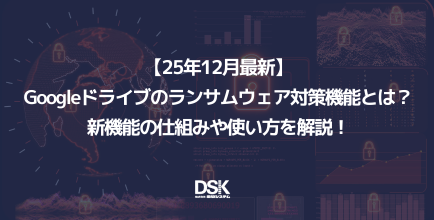組織内でファイルを共有するには、紙やストレージデバイスを用いる方法や、ファイルサーバーを構築する方法など、さまざまな選択肢が浮かびあがります。しかし、このような方法では情報共有の効率性が低下したり、情報漏えいリスクが高まったりと、深刻な課題が発生する恐れがあります。
そこで、おすすめしたいのが今回紹介するファイル共有サービスです。ファイル共有サービスは、インターネット上でファイルの閲覧や編集、アップロードなどを行えるため、従来の手法よりも手軽に情報共有が可能です。
本記事では、ファイル共有サービスの特徴や種類、導入メリットを解説します。おすすめのサービスや選び方のポイントも紹介しているので、効率的な情報共有の仕組みを構築したい方は参考にしてください。
ファイル共有サービスとはユーザー同士でデジタルデータを共有するサービス
ファイル共有サービスとは、複数のユーザー間でデジタルデータを共有し合えるサービスです。文書ファイルや画像、動画、音声など、さまざまなデジタルデータに対応しています。
従来のファイル共有は、紙やUSBメモリなどのアナログな手法を用いたり、ファイルサーバーを構築してネットワーク内でファイルをやり取りしたりするのが主流でした。ファイル共有サービスであれば、異なる端末や場所から容易にファイル共有が可能なので、情報共有の効率性を高められるほか、ストレージデバイスの紛失やサーバーへの侵入といったセキュリティリスクを抑えられます。
ファイル共有サービスの種類
ファイル共有サービスは、「ファイル転送型」と「クラウドストレージ型」の2つの種類に分類できます。それぞれの特徴や違いについて詳しく解説します。
ファイル転送型
ファイル転送型とは、送信者がインターネット上にファイルをアップロードし、受信者がそれをダウンロードすることで情報共有を行うサービスです。基本的にサービス提供事業者の公式サイト上でファイルをアップロード・ダウンロードするだけで済み、インターネット環境さえあれば手軽に情報を共有できます。
また、大容量のデータに対応しているのもポイントです。なかには数TB単位の転送に対応しているサービスもあります。メールでファイルを送信する場合、1件あたりの容量に制限が設けられているメーラーも少なくありませんが、ファイル転送型のサービスなら大容量のファイルでも問題なく送信可能です。
クラウドストレージ型
クラウドストレージ型とは、クラウド上で複数のユーザー同士でファイルを共有できるサービスです。1ヶ所にファイルを集約することで、ほかのユーザーでもファイルの閲覧や編集が可能になります。Webブラウザ上で利用できるため、サーバーやネットワーク機器を導入する必要がなく、ログイン用のIDやパスワードを使ってアクセスできます。
サービスによっては、ユーザー管理やアクセス制御、ログ監視など、さまざまなセキュリティ機能を搭載しているのも特徴です。異なる端末からはもちろん、取引先や顧客にもアクセス権を付与できるため、社内コミュニケーションや社外取引の円滑化につながります。
ファイル共有サービスを利用する3つのメリット
ファイル共有サービスを利用するメリットは次の通りです。
- スムーズに情報共有を行える
- 費用的な負担を抑えやすい
- 柔軟性や拡張性に優れる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
スムーズに情報共有を行える
ファイル共有サービスは、ほかの情報共有手段に比べてスムーズな情報共有が可能です。例えば、紙やストレージデバイスで情報を共有する場合、印刷や発送、デバイスの受け渡しなど手間がかかります。
一方のファイル共有サービスなら、インターネット上にファイルをアップロードするだけで済みます。受信者もファイルのダウンロードや共有リンクへのアクセスといった手続きだけで、ファイルの閲覧や編集が可能なので、より効率的な情報共有につながります。
また、ファイル共有サービスのなかには、ファイルにコメントを残す機能や共同編集の機能を搭載したものも存在します。そのため、ファイルの共有だけでなく、組織全体のコミュニケーションを円滑にできるのもメリットです。
費用的な負担を抑えやすい
導入コストや運用コストを最小限に抑えられるのもファイル共有サービスの利点です。アナログな手法でファイルを共有する場合、紙やストレージデバイスの購入費、印刷代、発送費などの費用がかかります。ファイルサーバーを利用する場合も、サーバーやネットワーク機器の構築費、ライセンス代、メンテナンスコストなどの費用が必要です。
その点、ファイル共有サービスは無料で利用できるケースも珍しくありません。無料版は一部の機能が制限されていることもありますが、費用的な負担を抑えられるのが特徴です。有料版にアップグレードする場合でも、初期費用が無料に設定されていることも多く、月額や年額のサービス利用料を支払うだけで済みます。
柔軟性や拡張性に優れる
ファイルを保管・共有する際は、「どの程度の容量を保管できるか」「データ使用量の増減にどの程度対応できるか」といった点が重要になります。ファイル共有サービスは、ストレージ容量の拡張や縮小に対応しやすい分、柔軟性や拡張性に優れるのがメリットです。
例えば、クラウドストレージ型のファイル共有サービスは、一般的に料金プランごとにストレージ容量が定められています。容量を変更するには料金プランやオプションを見直すだけで済むため、ハードウェアの増設や設備の取り換えといった大規模な工事は不要です。
ファイル共有サービスを利用する2つのデメリット
さまざまなメリットがあるファイル共有サービスですが、次のようなデメリットも存在します。
- セキュリティがサービス提供事業者に依存しやすい
- システムのカスタマイズが難しい
それぞれのポイントを押さえたうえで適切な対策を施しましょう。
セキュリティがサービス提供事業者に依存しやすい
ファイル共有サービスは、自社でハードウェアを用意する必要がないものの、その分サービス提供事業者のセキュリティに依存しやすいデメリットがあります。例えば、クラウドストレージ型のファイル共有サービスを利用するとしましょう。その場合、サービス提供事業者が運用するサーバー内でデータを保管するため、そのサーバーに設定されているセキュリティに則って運用する必要があります。
このような点から、仮にセキュリティレベルの低いサービスを導入すると、サイバー攻撃やマルウェア感染などの脅威を防ぎにくくなり、自社の機密情報が漏えいするリスクが高まります。そのため、信頼性の高いサービスを選定するほか、多要素認証やアクセス制御など、社内でも可能な限りセキュリティ対策を実施することが重要です。
システムのカスタマイズが難しい
セキュリティがサービス提供事業者に依存しやすいのは、ファイル共有サービスが既製品の仕様をそのまま利用する提供形態でもあるためです。既製品は自社で仕様の変更が難しいため、セキュリティはもちろん、操作性や機能性などのカスタマイズも困難です。そのため、選定するサービスによっては利便性が低下し、組織への定着を阻む恐れもあります。
システムのカスタマイズ性を重視するなら、自社で一からシステムを開発したり、オンプレミス型のファイルサーバーを導入するのがおすすめです。このようなケースでは、UIや各種機能、セキュリティなどを柔軟にカスタマイズできます。機能やセキュリティに関する要件が厳しい場合は、ファイル共有サービスよりもシステム開発やオンプレミス型ファイルサーバーを選択すると良いでしょう。
ファイル共有サービスを選ぶ際の5つのポイント
ファイル共有サービスにはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や強みが異なるため、比較時のポイントを明確にすることが重要です。比較要素としては次のような種類があります。
- データ容量
- 機能性
- セキュリティ
- 外部システムとの連携範囲
- モバイル対応の有無
それぞれ詳しく解説します。
データ容量
一般的にファイル共有サービスはデータ容量が制限されており、サービスごとに上限に差があります。そのため、利用するファイルの種類や使用量に合わせて選び分けることが重要です。
ファイル転送型のサービスでは、1回ごとにどの程度の容量のデータを転送できるかが定められています。また、1ヶ月ごとに転送可能なデータ容量を制限しているケースも珍しくありません。クラウドストレージ型のサービスは、一つのアカウントでどの程度の容量のデータを保存できるかが決まっています。
基本的に企業規模が大きくユーザー数が多くなるほど、扱うデータ量が増えます。その場合は、大容量の転送やデータ保管に対応したファイル共有サービスを選びましょう。
機能性
機能性もサービスごとに大きな差があるため、事前に比較することが重要です。ファイル共有サービスの代表的な機能には次のような種類があります。
| サービスの種類 | 主な機能 |
| ファイル転送型 |
・ファイルの送受信 |
| クラウドストレージ型 | ・ファイルの保管 ・ファイルの検索 ・ファイルの閲覧・編集 ・バージョン管理 ・自動バックアップ ・アクセス制御 ・ログ監視 など |
必要な機能を洗い出すには、ファイル共有サービスを導入する目的を明確にしましょう。現状どのような課題が発生しており、それを解決するためにどういった機能が必要なのか、あらかじめ検証することが大切です。
セキュリティ
ファイル共有サービスでは、顧客や従業員の個人情報から社内の機密情報まで、重要なデータを扱うケースも少なくありません。仮に情報が外部に流出すると、信用の失墜や損害賠償といった大きなトラブルに発展する恐れがあるため、安全性の高いファイル共有サービスを選ぶことが大切です。
代表的なセキュリティとしては、ID・パスワード・PIN・生体情報などの複数の要素で本人確認を行う「多要素認証」や、ユーザーごとのアクセス権限を設定できる「アクセス制御」、アクセスログをリアルタイムで確認できる「ログ監視」などがあげられます。また、セキュリティ機能のほかにも、セキュリティ認証資格の有無や導入実績を確認するのも良いでしょう。
外部システムとの連携範囲
ファイル共有サービスのなかでもクラウドストレージ型を利用する場合は、外部システムとの連携範囲が重要な要素となります。連携範囲が広がるほど、ほかのシステムとデータ同士を紐付けられたり、機能を拡張できたりと活用の幅が拡大します。
例えば、ファイル共有サービスと顧客管理システムを連携すると、顧客情報に紐付いたファイルを単独のシステムで一元管理できます。そのほか、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との連携により、定型的な作業の自動化が可能です。
外部システムとの連携は、業務効率化や生産性向上、コミュニケーションの促進など、さまざまな恩恵をもたらします。サービスごとに連携範囲が異なるため、あらかじめ入念に検討することが重要です。
モバイル対応の有無
モバイル端末に対応したファイル共有サービスは、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからでも利用できます。モバイル端末は場所や時間を問わずファイルを共有できるのが利点です。
出張や外出、テレワークの機会が多い場合は、モバイルアプリに対応したファイル共有サービスを選ぶのも良いでしょう。モバイルアプリはスマートフォンやタブレット用にデザインやUIが最適化されており、操作性に優れています。
【ファイル転送型】ファイル共有サービスのおすすめ3選
ファイル共有サービスにはさまざまな種類があるため、サービスごとの特徴や強みを理解することが重要です。まずはファイル転送型のおすすめサービスを紹介します。
GigaFile便
GigaFile便は、完全無料で利用できるファイル転送型のサービスです。商用利用も可能で、個人・法人にかかわらず費用はいっさい発生しません。
公式サイトにアクセスするとファイルのアップロード項目が表示されており、共有したいファイルを選択するだけで利用できます。そして、アップロード後に発行されるURLを受信者に送ることで共有が完了します。
1ファイルあたり最大300GBまでアップロードでき、個数は無制限です。また、3~100日までファイルごとに保持期限を変更できます。
| 料金プラン | 無料 |
| 主な機能 | ・ファイルの送受信 ・データの暗号化 ・メール通知 ・モバイル対応 |
| 公式サイト | https://gigafile.nu/ |
データ便
データ便は、セキュリティに強みを持つファイル転送型のサービスです。SSLやファイアウォール、データの暗号化など、幅広いセキュリティ機能が用意されています。また、セキュリティ便のオプションを利用すると、ファイルをダウンロードする際に送信者の許可が必要になるため、より安全に転送が可能です。
転送1回あたりの容量は料金プランによって違いがあります。無料で利用できるライトプランとフリープランは2~5GB、有料版のビジネスプランにアップグレードすると無制限になります。有料版では、ほかにも受取BOXやアドレス帳、再送信といった機能を利用できます。
| 料金プラン | 料金プラン ・ライトプラン:無料 ・フリープラン:無料 ・ビジネスプラン:月額330~550円 |
| 主な機能 | ・ファイルの送受信 ・データの暗号化 ・一括ダウンロード ・アドレス帳 ・ファイアウォール |
| 公式サイト | https://datadeliver.net/ |
firestorage
firestorageは、個人向けと法人向けの2種類の料金プランを選択できるファイル転送型のサービスです。
個人向けは1ユーザーで利用することを想定し、料金が最小限に抑えられています。1ファイルあたり最大2GBのアップロードが可能な無料プランのほか、有料版にアップグレードすると最大10GBまでのファイルを転送できます。また、未登録会員でもアップロード数無制限で利用できるのが特徴です。
法人向けは専用回線でファイルを転送でき、高速でアップロード・ダウンロードが可能です。加えて、独自サブドメインやロゴ挿入、電話・メールサポートといった機能も充実しています。専用のストレージが用意されており、料金プランによって1~18TBまでデータを保管できるのもポイントです。
| 料金プラン | 【個人向け】 ・無料プラン ・ライト会員:月額1,037円 ・正会員:月額2,085円 【法人向け】 ・プラン1:月額98,780円+初期費用110,000円 ・プラン3:年額999,350円 ・プラン5:月額54,780円+初期費用55,000円 |
| 主な機能 | ・ファイルの送受信 ・ストレージ ・ダウンロードページカスタマイズ ・独自サブドメイン ・ログ監視 |
| 公式サイト | https://firestorage.jp/ |
【クラウドストレージ型】ファイル共有サービスのおすすめ3選
続いて、クラウドストレージ型のおすすめサービスを紹介します。それぞれの特徴や強みを押さえたうえで、適切なサービスを導入しましょう。
Googleドライブ
Googleドライブは、Google社が提供するクラウドストレージ型のサービスです。1ユーザーあたり15GBまでデータを保存できる無料プランと、30GB~5TBの容量に対応した有料プランがあります。無料プランはGoogleアカウントを取得するだけで利用でき、Webブラウザやモバイルアプリからいつでもアクセスできます。
有料プランにアップグレードすると、共有ドライブの機能が追加されます。共有ドライブとは、組織全体で共通のファイルを一元管理できる専用の保管スペースです。共有ドライブのストレージ容量は、「1ユーザーあたりの契約容量 × 契約ユーザー数」で決まるため、組織全体の容量を共有して大容量の保管スペースを構築できます。
そのほか、有料プランでは、電子情報開示に備えて管理者側でデータを管理できる「Google Vault」や、外部アプリケーションとの安全な接続を可能にする「セキュアLDAP」など、幅広い種類のセキュリティ機能が用意されています。
| 料金プラン | ・無料プラン ・Business Starter:月額800円 ・Business Standard:月額1,600円 ・Business Plus:月額2,500円 ・Enterprise:要問い合わせ |
| 主な機能 | ・ファイルの保管 ・ファイルの検索 ・ファイルの閲覧・編集 ・Googleサービス連携 ・エンドポイント管理 |
| 公式サイト | https://workspace.google.com/intl/ja/products/drive/ |
OneDrive
OneDriveは、Microsoft社が提供するクラウドストレージ型のサービスです。1ユーザーあたり5GBまでファイルを保存できる無料プランと、1TBのストレージ容量に対応した有料プランが用意されています。
Microsoft社製のサービスだけあり、同社のさまざまなツールと連携できるのが特徴です。ExcelやWordといったOffice製品はもちろん、Microsoft TeamsやOutlook、SharePointなどとの連携にも対応しています。
また、2段階認証やリアルタイムのセキュリティ監視システム、TLS暗号化など、セキュリティ機能も豊富です。Webブラウザに加えモバイルアプリも提供しており、さまざまな場面で活用できるのも利点だといえるでしょう。
| 料金プラン | ・無料プラン ・OneDrive for Business:月額749円 ・Microsoft 365 Business Basic:月額899円 ・Microsoft 365 Business Standard:月額1,874円 |
| 主な機能 |
・ファイルの保管 |
| 公式サイト | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage |
Box
Boxは、大容量のファイル保管に向くクラウドストレージ型のサービスです。無料プランのストレージ容量は1ユーザーあたり10GBですが、有料プランにアップグレードすると無制限になります。容量を気にせずファイルをアップロードできるのは大きな強みです。
また、Web APIを実装することで、1,500種類以上の外部アプリケーションと連携できます。連携可能なアプリケーションにはGoogleサービスやMicrosoft Office、Slackなどがあり、活用次第で利便性の向上や活用範囲の拡大に結び付けられるのが利点です。
ファイルへのアクセスレベルを7段階で調整できたり、ユーザー認証時に多要素認証やSSO(シングルサインオン)をサポートしていたりと、セキュリティにも優れています。
| 料金プラン | ・無料プラン ・Business:月額1,881円 ・Business Plus:月額3,135円 ・Enterprise:月額4,620円 ・Enterprise Plus:月額6,600円 |
| 主な機能 | ・ファイルの保管 ・ファイルの検索 ・ファイルの閲覧・編集 ・ワークフロー ・Box Notes連携 |
| 公式サイト | https://www.box.com/ja-jp/home |
ファイル共有サービスを活用してスムーズな情報共有の仕組みを整えよう
ファイル共有サービスには、ファイル転送型とクラウドストレージ型の2種類の形態がありますが、いずれの場合でも、アナログな手法やファイルサーバーに比べてより円滑な情報共有が可能です。サーバーやネットワーク機器といったハードウェアを導入する必要がなく、低コストかつ場所を選ばずにファイルを共有できるのが利点です。
ただし、ファイル共有サービスにはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。そのため、現状の課題や目的を明らかにしたうえで、適切なサービスを選び分けましょう。
クラウドストレージ型のサービスを検討している場合は、Googleドライブを導入するのがおすすめです。Googleドライブでは、クラウド上でファイルを一元管理できるため、オンプレミス環境のように物理的なサーバーを用意する必要がありません。また、共有ドライブの機能を利用することで、実質的なファイルサーバーとして活用できます。
ファイルサーバーとしてGoogleドライブを活用するメリットや方法に関しては、こちらの資料で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- ファイル共有サービス