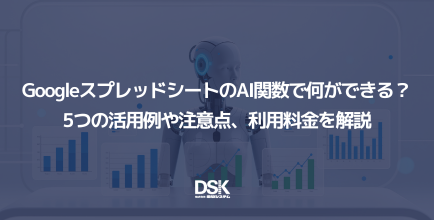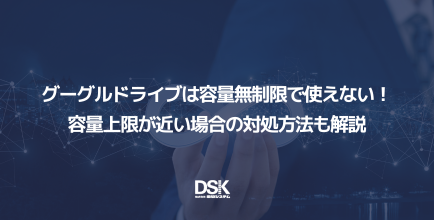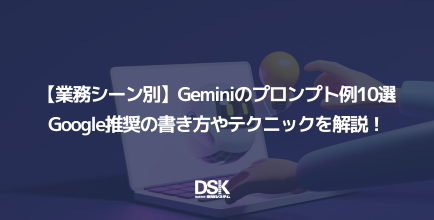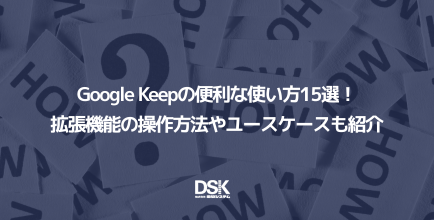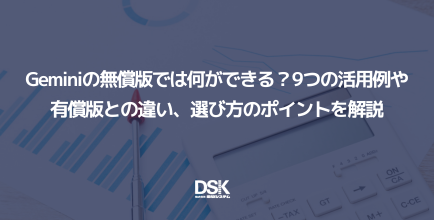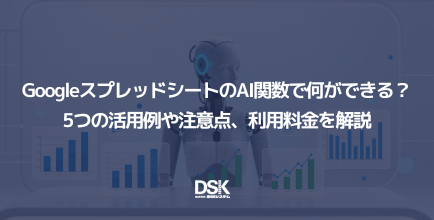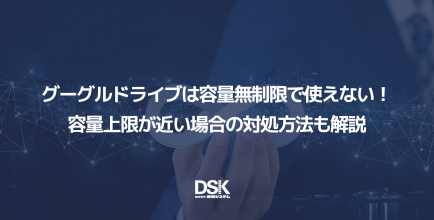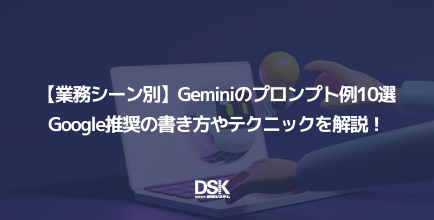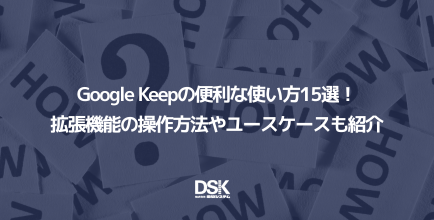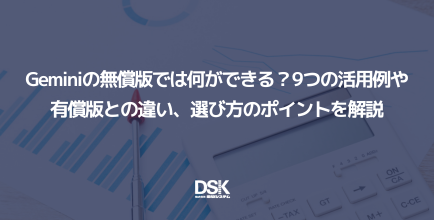紙やUSBメモリ、外付けHDDなど、アナログな方法で情報共有を行おうとすると、機器の紛失や置き忘れによってセキュリティリスクが高まったり、確認漏れなどでコミュニケーションロスが発生したりと、さまざまな問題が発生します。
このような問題を解消するには、ファイルサーバーを活用するのがおすすめです。ファイルサーバーは、ネットワーク経由で複数人でのファイル共有を可能にするため、効率的かつ安全に情報共有を行えます。ただし、効果的にファイルサーバーを活用するためにも、使い方や導入効果を押さえることが大切です。
本記事では、ファイルサーバーの特徴や種類、導入方法などを詳しく解説します。効率的な情報共有を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
ファイルサーバーとはネットワーク内でファイルを共有するための機器
ファイルサーバーとは、複数の端末同士をネットワークでつなぎ、ファイル共有を可能にする機器です。サーバーのなかにはデジタル文書や画像、動画、音声といったさまざまなデータを保管でき、ネットワーク経由で端末同士の情報共有を可能にします。
例えば、社内で従業員A用のパソコンと、従業員B用のパソコンを運用しているとしましょう。情報共有の仕組みがなければ、従業員AとBそれぞれの端末上でデータを管理しなければなりませんが、ファイルサーバーを導入すれば、どの端末からでも1ヶ所に集約されているデータへとアクセスが可能です。そのため、複数人でデータを共有する際にストレージデバイスを利用する必要がなく、効率的に業務を進められます。
ファイルサーバーの仕組みと機能
ファイルサーバーのファイル共有は、OSに搭載されている機能の一つです。この機能を利用することで、ファイルの閲覧や編集、アップロード、ダウンロードといった処理が可能になります。
また、ファイルを効率的かつ安全に共有できる仕組みも整っています。ストレージデバイスを利用してファイルを共有する場合に比べ、ファイルサーバーはより素早いデータ通信が可能です。ほかにも、ユーザー管理やアクセス制御、ログ監視などの機能が搭載されているため、情報漏えいや不正アクセスのリスクを抑えられます。
NASサーバーとの違い
ファイルサーバーとよく似た機器にNASサーバーがあります。NASサーバーもファイルサーバーと同様、ネットワーク経由で複数の端末同士のファイル共有を可能にする機器です。
ただし、NASサーバーの場合は、ネットワーク接続機能を搭載した機器を購入するだけで済み、ファイルサーバーのようにOSやプログラムを構築する必要がありません。そのため、導入時のコストや手間を抑えられるのが利点です。一方、ファイルサーバーのようなシステムを細かくカスタマイズできる柔軟性はありません。
このような点から、同じファイル共有の環境を構築する場合でも、要件を細かくシステムに反映したいならファイルサーバー、コストや工数を最小化したいならNASサーバーといった形で、目的や用途に応じて選び分ける必要があります。
ファイルサーバーの種類
ファイルサーバーは、「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類に分かれています。それぞれメリットとデメリットが存在するため、両者の特徴を理解して適切なものを選びましょう。
オンプレミス型ファイルサーバー
オンプレミス型とは、物理的なサーバーをオフィス内や施設内に設置し、自社で管理・運用を行う導入形態です。サーバーやネットワーク機器の購入費、システムの開発費などが発生するものの、一からプログラムを設計できるため、要件を反映しやすいメリットがあります。システムの仕様や機能はもちろん、セキュリティ内容も自由に決定でき、カスタマイズ性に優れるのが利点です。
一方、オンプレミス型のファイルサーバーは、導入コストが高額になりやすい傾向にあります。また、導入した機器や設備を自社で管理しなければならず、メンテナンスやOSのアップデートなどを行うためのノウハウや人材が必要です。
クラウド型ファイルサーバー
クラウド型とは、サービス提供事業者が運用するサーバーを利用できる導入形態です。ログイン用のIDやパスワードがあればWebブラウザ上でサービスを利用できるため、物理的なハードウェアを用意する必要がありません。そのほか、場所を選ばずに利用できたり、柔軟にスケールの拡張や縮小を行えたりと、さまざまなメリットがあります。
注意すべきポイントとしては、セキュリティがサービス提供事業者に依存しやすい点です。自社でサーバーを構築しない以上、サービス提供事業者が実施しているセキュリティ対策が反映されるため、安全性の低いサービスを選ぶと情報漏えいや不正アクセスのリスクが高まります。
ファイルサーバーを導入する4つのメリット
ファイルサーバーを導入すると次のようなメリットが生まれます。
- スムーズなファイル共有が実現する
- ファイル共有時のセキュリティレベルを向上できる
- バックアップや冗長化を実施できる
- ストレージ容量を拡張しやすい
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
スムーズなファイル共有が実現する
従来の情報共有の手段としては、口頭や文書でのアナログな方法や、USBメモリ・外付けHDDといったストレージデバイスを用いた方法が主流でした。しかし、このような方法では情報共有に時間や手間がかかります。
その点、ファイルサーバーの場合、ネットワーク接続環境が整っていれば、どの端末からでも必要なデータに素早くアクセスできます。また、ファイルのタイトルや形式など、条件を指定して検索できるため、従来の方法よりもスピーディに目的のファイルを探せます。従業員同士でのファイルの閲覧や編集も可能なので、スムーズなファイル共有が実現します。
ファイル共有時のセキュリティレベルを向上できる
アナログなファイル共有の場合、文書やストレージデバイスの紛失によってセキュリティリスクが高まってしまう恐れがあります。ファイルサーバーであれば、デジタル上でファイルの閲覧や編集、アップロードといった作業が完結するため、文書やストレージデバイスを紛失することもありません。
また、ファイルサーバーには、ユーザー管理やアクセス制御、ログ監視など、さまざまなセキュリティ機能が搭載されています。セキュリティ機能の活用により、不正アクセスやデータの不正利用といった脅威を防ぎ、情報漏えいリスクを抑えられます。
バックアップや冗長化を実施できる
ファイルサーバーは、バックアップ先の一つの選択肢として活用可能です。例えば、従来はストレージデバイスにデータをバックアップしていたところを、ファイルサーバーにも同じファイルをコピーすることで、データの保存場所が分散されます。仮に一方のデータが消失した場合でも、もう一方からデータを復元できるため、安全性が高まります。
また、冗長化が可能なのもファイルサーバーのメリットです。冗長化とは、障害や故障に備えて、オリジナルの機器とまったく同じシステム構成の機器を用意しておくセキュリティ対策手法です。ファイルサーバーは同じシステム構成の機器を複数台運用できるため、負荷分散や障害対策につながります。
ストレージ容量を拡張しやすい
ファイルサーバーに限らず、HDDやUSBメモリ、クラウドストレージなど、何らかの場所にデータを保管する際は、ストレージ容量が制限されます。容量を使い切ると、それ以上データを保存できません。
ただし、ファイルサーバーの場合はストレージ容量を拡張しやすいため、容量不足の問題を解消しやすいメリットがあります。オンプレミス型の場合はハードウェアの増設、クラウド型であれば料金プランの変更やオプションの追加などで拡張が可能です。特にクラウド型のファイルサーバーは、物理的な機器を再購入する必要がなく、低コストかつ省力で容量を拡張できます。
ファイルサーバーを導入する2つのデメリット
さまざまなメリットがあるファイルサーバーですが、次のようなデメリットも存在します。
- 導入コストや運用コストが高額になりやすい
- 初期設定に手間がかかる
それぞれのデメリットについて以下で解説します。事前にメリットとデメリットの両方を理解したうえで、ファイルサーバーを導入した際の費用対効果を検証しましょう。
導入コストや運用コストが高額になりやすい
ファイルサーバーを構築するには、高額な導入コストや運用コストが発生する可能性があります。オンプレミス型の場合は、ハードウェアの購入費やシステム開発費、ライセンス代、機器の保守管理費などが必要です。クラウド型は、初期費用無料で利用できることもありますが、サブスクリプションモデルを採用していることも多く、サービス利用料が継続的に発生します。
また、容量を拡張する際でも、ハードウェアの増設やオプションの追加などで費用がかさみがちです。導入時はクラウド型のほうがコストを抑えやすい傾向にありますが、利用期間が長くなるほど継続的なサービス利用料が高額になるため、長期的な目線で予算を検討することが大切です。
初期設定に手間がかかる
ファイルサーバーは、システム構築後の初期設定に時間や手間がかかります。特にユーザー数が多い場合、アクセス権限やグループ作成に手間がかかりがちです。また、設定時に専門的な知識が求められることもあるため、人材やノウハウが不足している場合は、専門会社への委託も視野に入れて計画を立てるのが良いでしょう。
ただし、手間がかかりやすい分、設定内容を細かく調整できるのはメリットだといえます。ファイルサーバーはあくまでデータ管理手法の一つの選択肢でしかないため、コストや手間に対する導入効果とのバランスを考慮し、適切な手段を検討しましょう。
ファイルサーバーの構築方法
ファイルサーバーを構築する一般的な手順は次の通りです。
- サーバーを設置する場所を決める
- OSやソフトウェア、アプリケーションなどの構成要素を比較・検討する
- 主電源や予備電源を確保する
- テスト検証を行った後、システムの構築や導入作業を進める
- サーバーの初期設定を行う
- 既存のデータをファイルサーバーに移行する
オンプレミス型の場合は上記のようなステップとなりますが、クラウド型なら工数を削減できます。クラウド型のファイルサーバーを構築する際は、サービスに契約してIDやパスワードを発行すれば、すぐに利用を開始できます。ただし、製品や料金プランを選定する際に時間や手間がかかりやすいので、注意が必要です。
このようにファイルサーバーの構築にはある程度の工数がかかるため、導入形態にかかわらず入念な計画を立てて進行しましょう。現状の課題や導入目的、各担当者の責任範囲、スケジュールなどを明確にすることで、よりスムーズに作業を進められます。
ファイルサーバーを導入する際の3つのポイント
ファイルサーバーを導入する際は、いくつか押さえるべきポイントが存在します。以下で紹介する3つのポイントを意識することで、ファイルサーバー導入後の失敗を避けられます。
導入目的や活用範囲を明確にする
ファイルサーバーを利用する際は、まず明確な導入目的を定めることが重要です。目的が明確になることで運用時の方向性が明らかになり、問題が発生した場合でも迅速な対処や軌道修正を行えます。必要な機能を特定したり、組織内で共通認識を持たせたりする場合も、明確な目的が欠かせません。
目的を明確にするには現状の課題を明らかにする必要があります。社内の情報共有に関して問題となっている箇所やボトルネックを取りあげ、ファイルサーバーによってどのように解決していくかを検討しましょう。
導入目的とあわせて活用範囲を明確にすることも大切です。ファイルサーバーの導入後はアクセス権限やグループなどを設定する必要があり、そのためには「誰が、どのような状況で、どうやって利用するか」という情報がいります。事前に導入目的や活用範囲を決めることで、ファイルサーバーのスムーズな運用が可能です。
事前にインシデントを想定しておく
ファイルサーバーを安全に稼働させるためにはセキュリティが欠かせません。しかし、現代はデジタル技術の進展やインターネットの普及により、サイバー攻撃やマルウェア感染、不正アクセスなど、さまざまなセキュリティリスクが懸念されています。そのため、複数のインシデントを想定し、必要不可欠な対策を講じることが大切です。
場合によっては、ファイルサーバーに搭載されている既存のセキュリティ対策だけでは不十分なことも考えられるでしょう。その場合は、UTM(統合脅威管理)ツールやゼロトラストネットワークツールなど、より高度なセキュリティに特化したツールを組み合わせるのも一案です。
クラウド化を検討する
スピーディな意思決定や働き方改革の推進が求められる昨今において、オンプレミス環境のみで社内システムを運用するのは無理があります。ファイルサーバーも同様、オンプレミス型はカスタマイズ性に優れる一方、物理的な機器を管理しなければならない、ユーザー数が増えると管理が煩雑化しやすいといった難点があります。そのため、オンプレミス環境のみでシステムを構築すると、組織内の柔軟性が低下し、スムーズな情報共有を妨げる恐れもあります。
このような課題を解消するには、クラウド主体の環境を構築したり、オンプレミスとクラウドの両方を組み合わせたりといった対策が必要です。クラウドはインターネット環境があれば即座に利用でき、ハードウェアを購入・管理する必要がありません。場所を問わず、いつでも必要なデータにアクセスできるため、組織内の柔軟性や情報共有のスピードを向上できるのが利点です。
クラウド上でのファイル共有ならGoogleドライブがおすすめ
ファイルサーバーのクラウド化を検討する際、まずはクラウドストレージの導入から検討してみてはいかがでしょうか。クラウドストレージとは、クラウド上でファイルの閲覧や編集、アップロードなどを行えるサービスです。なかでもGoogleドライブは無料で利用でき、Googleアカウントを保有するユーザー同士でファイル共有を行えます。
また、有料版にアップグレードすると、共有ドライブの機能を利用できます。共有ドライブにファイルを格納すると、組織全体でそのファイルを共有できるため、クラウド上のファイルサーバーとして活用可能です。共有ドライブのストレージ容量は「ユーザー1人あたりの容量 × ユーザー数」で計算され、組織全体で容量を共有できるのも利点だといえるでしょう。
有料版のストレージ容量は、料金プランによって1ユーザー30GB~5TBに分かれています。Enterpriseエディションでは、ストレージ容量の拡張も可能なので、規模の大きい企業でも安心して利用できます。
Googleドライブの特徴や機能、料金体系については、こちらの記事で詳しく解説しています。
自社にとって最適なファイル共有の環境を構築しよう
ファイルサーバーは、ネットワークを介して効率的にファイル共有を行えるメリットがあります。紙やストレージデバイスで情報共有する場合に比べ、データ転送速度や検索性、安全性に優れています。
ただし、ファイル共有の手段は、ファイルサーバーのほかにもさまざまな選択肢があります。そのため、手法ごとの特徴や導入効果を理解したうえで、自社にとって最適な環境を構築することが大切です。
クラウドでのファイル共有を行うなら、Googleドライブを導入するのがおすすめです。Googleドライブでは、クラウド上でファイルを一元管理できるため、オンプレミス環境のように物理的なサーバーを用意する必要がありません。また、共有ドライブの機能を利用することで、実質的なファイルサーバーとして活用できます。
ファイルサーバーとしてGoogleドライブを活用するメリットや方法に関しては、こちらの資料で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- カテゴリ:
- Google Workspace
- キーワード:
- ファイルサーバー