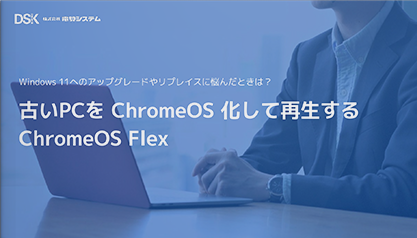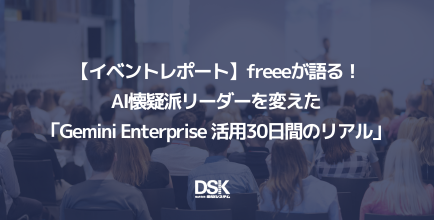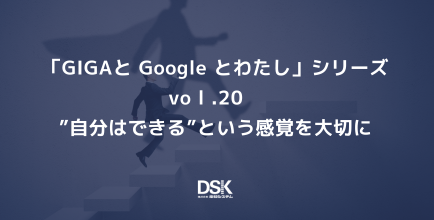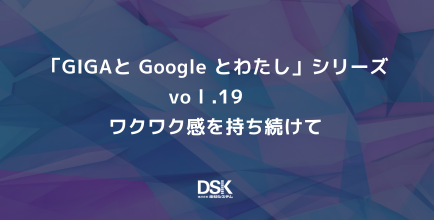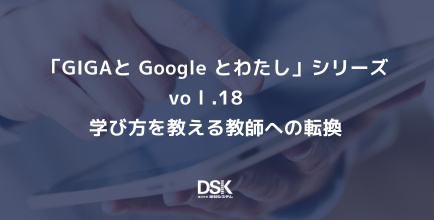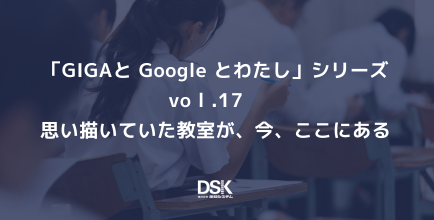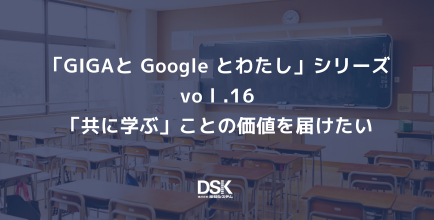GIGAスクール構想によって、全国の小中学校に1人1台の端末が導入され、ICTを活用した取り組みが始まりつつあります。しかし、学校現場からは、端末をどのように活用したらよいかわからないといった声を多く聞きます。そこで今回は、導入初期をどう捉え、乗り越えていけばよいか、ご紹介していきます。
1人1台への変化をしっかり捉える
これまでにも教育の情報化が叫ばれて久しかったわけですが、地方財政措置で投じられていた予算には見向きもされないまま長い時間が過ぎてきたことを思えば、昨年度の実質1年であっという間に1人1台の環境自体が整ったことは、極めて異例なことと言えるでしょう。
GIGAスクール構想と新型コロナウイルスの影響はそれほど大きく、世の中を一気に変えるだけのインパクトがあったことの証左でもあります。
この間、「全国一斉休校」「オンライン授業」「学びを止めない」などいろいろなキーワードが取り沙汰されましたが、実際に1人1台の端末が届いた学校の職員室からは、こんな声も聞こえてきているようです。
「今までもコンピューター教室で授業はしていたし、そんなに変わらないよね」
「コンピュータ教室の授業と何が違うの?」
「1人1台の使い方が全然わからない」
しかしながら、GIGAスクール構想が立案された経緯や、新しい学習指導要領を丁寧に確認していけば、日常にICTの革新の大きな波がやってきているからこその1人1台の端末活用であり、常時接続・常時利用であり、これまで以上にICTを使いこなす資質・能力の育成が急務だということに気がつくと思います。(GIGAスクール構想の立案経緯や新学習指導要領などは以前のブログでご紹介しています)
今回の1人1台の端末整備によって、これまでICT活用の中心だったコンピューター室は空き教室やスタジオ、オンライン会議室などに変貌を遂げ、各教室には端末とともにアクセスポイントや充電保管庫など、新しいICT機器が導入されることになりました。
わざわざコンピュータ教室に移動してICTを活用していた状況から、いつでも机の中から端末を取り出して学べる状況ができあがりました。また、端末はクラウドにつながることが前提のため、共同作業や情報共有がスムーズに進み、教授スタイルは革新され、学習形態は大きく変わることになるでしょう。
1人1台の端末整備とは、そうした大きな変革のうねりのなかにいるということを、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
活用に前向きなマインドを醸成する
とはいえ、全国には多様な学校があり、これまでに学校の情報化の知見の蓄積がある地域かどうか、ICTに詳しい教師が複数在籍している学校かどうかなど、正に千差万別です。
学校のICT化度合いにばらつきがあるように、1人1台の本当の意味を理解できている教師がいれば、そうでない教師もいるでしょう。また、ICTが得意な教師もいれば、苦手意識を持っている教師もいるでしょう。
そう考えると、すべての学校が同じように足並みを揃えていくことは現実的にはかなり難しい部分があります。やはり、各学校ごとにしっかりと現在の課題を捉え、スモールステップで考えていく必要があるでしょう。
校内の意思疎通が取れないとか、研修がうまく捗らないとか、スムーズに進まないことも多々あるとは思いますが、導入初期にはそうした抵抗や足かせが生じるのはICTに限った話ではありませんから、ある種の割り切りと寛容さで受け入れて、みんなで一歩ずつ前に進んで行くような働きかけが大切になります。
その意味では、特に管理職や情報教育担当者は、教員間の目線を揃え、活用してみようとするマインドを醸成し、それをバックアップする精神を持つことが何より大切です。
1人1台の端末活用を進めれば、きっと子どもたちがあっと驚くような学びや成長や足跡を残してくれます。確かに最初は苦難や苦労は伴うでしょうが、使いこなした先にある便利さや可能性はきっと教師をワクワクさせるに違いありません。
前向きな気持ちで導入初期をみんなで乗り切っていくことが肝心でしょう。
教師もクラウドに慣れる
活用をスタートさせて、一足飛びに使えるようになる魔法はありません。生徒たちがICT機器を文房具のように使うことが大事だとするならば、文房具の最低限の使い方やマスターするための練習期間が必要です。そのことは教師も生徒も同じです。
1人1台端末の活用は、個別最適な学習や協働的な学びに生かすために使うものですが、初期段階で理想ばかり見て難解な使い方になったりして、利活用が進まないことこそ、一番避けなければなりません。
ですから、初期指導のステップについては、以前のブログでご紹介していますが、やはり最初は教師も1人1台の環境に慣れることが何より大切でしょう。
今回のGIGAスクール構想では、生徒は1人1台の端末を利用して、クラウドを活用して学習していくことが前提となっています。クラウドを利用すれば、いつでもどこからでもデータにアクセスすることができ、パソコンやタブレット、スマートフォンなど端末の種類も選びません。データ共有が容易であることから、クラウド上のデータを複数人で共同編集するといった使い方もできます。
ドキュメントやスプレッドシート、スライドを共同編集する、カレンダーを共有する、ドライブのデータを共有するといった一般的な使い方で十分です。Google Workspace for Education で提供されているアプリを使えば、瞬時にこうしたことを実現できるほか、たんに共有するだけでなく、修正・コメントしたり、そのことが自動的に相手にメールで送信されるので、共有や共同作業がとてもスムーズに運びます。
例えば、議事録作成を Google ドキュメントでやってみましょう。事前に参加者に共有しておけば、会議次第を事前に把握でき、会議がスムーズに進行できます。また、同時に編集できるので、発言者以外の人たちで議事録に書き込みをすれば、会議中に議事録は完成し、改めて議事録作成の時間を取る必要がありません。加えて、すでに共有できているので、議事録の印刷や配付、保管といった手間の軽減につなげることができます。
また、日々のICT活用シーンを スプレッドシート に入力すれば、校内のミニ実践のデータとして蓄積して活用することができます。
あるいは、紙で実施している毎日の検温記録の確認を、Google フォーム を使って入力をさせることで、データ化して確認や転記のミスを減らすことができるのほか、フォームに回答したデータはスプレッドシートに出力することもできるので、数日間の経過観察も容易にするでしょう。
このほか Google Chat も情報共有のスピードを迅速化し、学年間・部活間など必要な教員間での業務の効率化を後押しします。
このように教師がクラウドに慣れる場数を踏むことで、はじめてわかることがたくさんありますし、もっとこういう使い方の方が便利に使えるのではないか、ああいった方法は試せないかなど、アイデアがどんどん湧いてくるものです。普段使いをすることで見えてきた便利さを授業に転化させることで、活用もより効果的なものになるでしょう。
まとめ
今回のブログでは1人1台の導入初期の捉え方や乗り越え方をご紹介しました。
多くの人にとって初めての環境となる1人1台の端末。わからないことや疑問もたくさん生まれてくるとは思いますが、たくさんのトライ&エラーを繰り返しながら、それぞれの学校に合った使い方を見つけていっていただければと思います。
電算システム(DSK)では、ドキュメントやスライド、Classroom などのツールが一体になった教育機関向けのグループウェア「Google Workspace for Education」や Chromebook の学校現場への販売・トレーニングなどを行っています。学校現場での豊富な導入実績もありますので、導入やその後のサポートを検討してみてはいかがでしょうか。
また、先生向けのセミナー・イベントなどで、Google Workspace for Education の使い方などをご紹介していますので、ぜひ、ご活用いただければと思います。
- カテゴリ:
- Google for Education
- キーワード:
- Google Workspace
- Chromebook
- Classroom