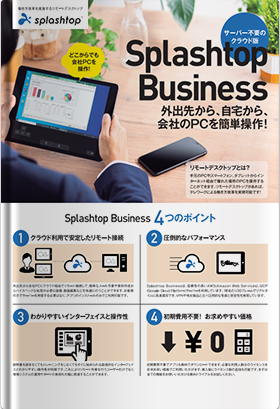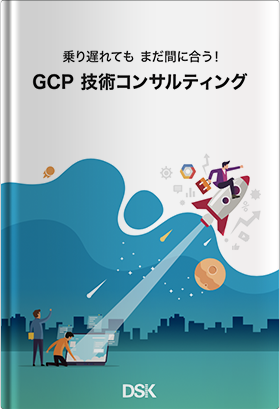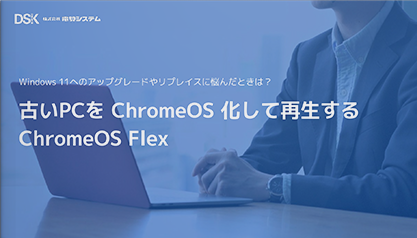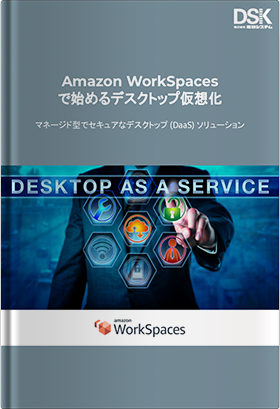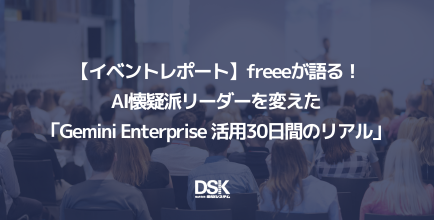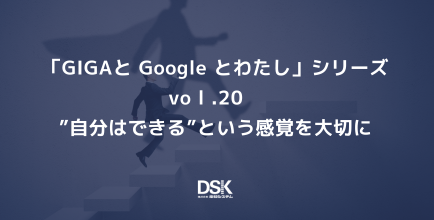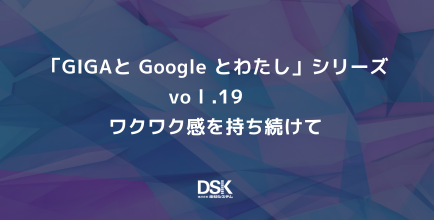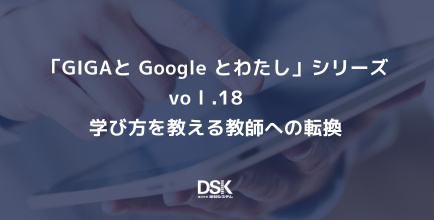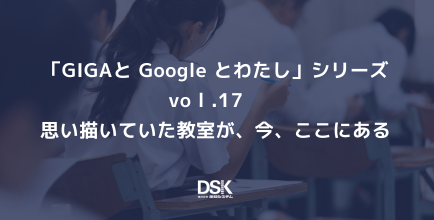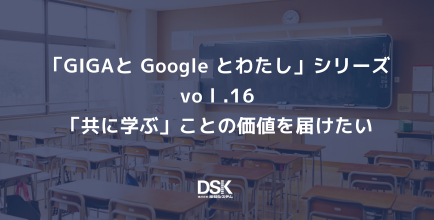FAXではなくメールやライン、会議ではなく Meet や Zoom など、日常のさまざまな場面でデジタル化が進められています。デジタル化の波は学校教育の場にも進出しており、さらに新型コロナウイルスの影響もあってその流れはより速くなっています。
学校で教育用に使うタブレットの導入を急いで検討しているところもあるかと思いますが、その際にいくつか考慮すべきポイントがあるのも事実です。教育用タブレットを導入する前に検討した方が良いこと、導入に向けた課題などを詳しくみてみましょう。
学校へのタブレット導入は急務
政府による「GIGAスクール構想」が進められていることから、学校へのタブレット端末導入を急いで検討しているところも多いのではないでしょうか。デジタル端末に触れることが当たり前とも呼べる今、紙の教科書による教育ではなく、タブレット端末を用いた教育の必要性が叫ばれています。
GIGAスクール構想による学校へのタブレット導入促進
まず、GIGAスクール構想について見てみましょう。GIGAスクール構想とは、文部科学省によって進められている教育の「デジタル化」に向けた取り組みのことで、学校におけるタブレット導入が促進されている大きな要因です。
そもそも、世界各国ではすでにタブレット端末を用いた授業が積極的に進められているなか、日本は先進国の中で普及率が最下位という結果になっています。さらに、新型コロナウイルスの影響によって学校に行くのではなく、自宅からリモート授業を受けることが推奨されたところ、対応できない学校がほとんどだったことで、日本の教育現場でのデジタル化が遅れていると感じる人も多くいたのではないでしょうか。
GIGAスクール構想では、生徒1人につき1台のタブレット端末導入を目指し、2024年には教科書の本格的な電子化を予定していることにも注目が集まっています。
現場への導入は進んでいない現状
では、教育の現場となる小学校、中学校や高校で、今の時点ではどれくらいの割合でタブレット端末の導入が進んでいるのでしょうか。
現状では、決して端末導入が進んでいるとは言い難く、政府が掲げた端末導入率の基準に及んでいません。「3クラスに1クラス分程度以上整備を進める」という目標について、その達成率は2020年7月時点で1割にも満たないことがわかっています。
この結果と同様に、新型コロナウイルスの影響によってリモート授業の必要性が高まりましたが、実際にリモート授業を実施できた学校も1割に満たなかったことがわかっています。まだまだ現場へのタブレット導入が進んでいないことが浮き彫りになり、GIGAスクール構想の実現には課題が山積みだと言えるでしょう。
学校へのタブレット導入時に考慮すべきポイント
それでは、ここからはタブレット端末を導入する際に、どのようなことを考慮すべきなのかを考えてみましょう。
子どもたちはもちろん、現場で実際に教育をしていく教師、導入に際して学校にかかる負担について、それぞれの面で考えられるポイントをご紹介します。
タブレット導入後の利用イメージの明確化
まず、タブレット端末を導入した際に、子どもたちがどのようにして端末を利用していくでしょうか。1人につき1台ずつタブレットなどの端末が与えられると、多くの場合は子どもたちが積極的に端末に触れ、使い方を次第にマスターしていくでしょう。
しかし、端末を漠然と導入しても「持ち腐れ」になることが懸念されるケースもあります。
教育用として利用されるのはもちろんですが、生徒のプライベートな時間になったとき、どのような使われ方をするのか、教育内容と運用の両面でどうやって利用していくかのイメージ・目的を明確化する必要があります。
学校でのタブレット端末の導入を考えると、子どもたちの学習への取り組み方にもばらつきがあらわれることが懸念され、より手厚いサポートが必要になるかもしれません。
予算の確保
学校側として大きな懸念になっているのが、タブレット端末の導入時にかかる予算についてです。「1人1台ずつ」という目標を掲げているGIGAスクール構想ですが、現実的には膨大な費用がかかってしまいます。
特に、多くの生徒を抱える学校であればあるほどその負担は大きくなることが予想されます。
また、端末導入時に政府や自治体から補助金が出たとしても、その後の運用にも費用がかかることに留意しなくてはなりません。もし、生徒が利用するタブレット端末を各家庭で購入してもらう場合には、納得感のある価格と十分な説明が必要なのは言うまでもありません。
保護者、生徒、学校でそれぞれ納得してタブレット端末を利用できるよう、事前に入念な説明が必要です。
通信環境の整備
タブレット端末を用いた教育は、端末があれば解決というわけではなく、通信環境を整備しなくてはなりません。インターネット接続ができる環境作りに取り組む必要がありますが、1人につき1台ずつ、一度に数百人以上という大人数が同じ場所で通信する場合には大規模な環境整備が必要です。
校内に十分なWi-Fi環境を準備しなければ、タブレットが機能しないでしょう。生徒が一斉に使った場合においても、遅延などの問題なくタブレットが利用できるのかどうかが重要なポイントになります。
さらに、タブレットを用いた学習は学校だけでなく、充実したリモート授業を行うために、自宅でのネットワーク環境整備も必要となります。学校にWi-Fiを整備するのも大切ですが、それだけでは生徒の自宅での学習を支援しきれないため、生徒の自宅ネットワーク環境を整備するために、LTEを用いることも含めて検討される学校もあります。
セキュリティの保全
タブレット端末を1人ずつ用いる際の大きな課題として挙げられるのが、「セキュリティ」の問題です。
企業はもちろんですが、学校でも流出させてはならない情報がたくさんあります。特に、生徒や保護者、教員に関する個人情報については、万全のセキュリティ対策が必要です。すでに稼働している学校内での既存システムとの連携にも注意を図りながら、どのような体制でセキュリティレベルを保つかが課題となっています。
さらに、生徒や教員に向けたITリテラシーの向上も急務です。
Webサイト利用時にフィッシングサイトを利用してしまったり、メール利用時に何らかの情報をうっかり洩らしてしまったりなど、さまざまな経路でセキュリティ事故が起こり得るでしょう。こうした事故が起こらないよう、端末導入やネットワーク環境整備だけでなく、利用者に向けたセキュリティ対策の周知も行う必要があります。
生徒による利用の管理
1人1台ずつ付与されるタブレット端末は、基本的に生徒に持たせておくことが多いでしょう。そのため、授業で使うとき以外の時間はどうするか、本来の目的以外での端末利用をどう制限するかが課題となっています。
タブレット端末を使うための条件やルールを設けること、ネットにはさまざまな脅威が潜んでいることを周知させるためのITリテラシー教育など、タブレット端末導入を急ぐ前にやっておくべきことが多くあるのが現状です。
自宅に持ち帰ってリモート授業を受ける場面が増える一方、学校の外など教員・保護者のあずかり知らぬところでタブレットが破損したり、その際にかかる費用だったり、保護者の不安・負担も大きくなります。生徒自身が自分の端末の管理を行う場合については、トラブル防止のためにも厳格なルールを設ける必要があるでしょう。
クラウドとの親和性
最後に考慮すべきポイントとして挙げられるのが、クラウドとの親和性です。
クラウドとは、パソコンやタブレット端末の中にデータを保存しておくのではなく、オンラインでデータを保管できるサービスのことです。タブレット端末を用いた授業では、教材などもクラウドによる配信・配布が前提となり、クラウドサービスをまず利用するのが原則という意味の「クラウドバイデフォルト」と呼ばれています。
クラウドとのシームレスな接続は、タブレット端末を導入した学習において、ひとつの課題となっています。クラウドバイデフォルトは学校教育だけでなく、民間企業や政府においても主流の方針になっているのが特徴です。
まとめ
学校教育におけるオンライン化は、生徒や教員にとってこれまでとは学習環境が大きく変化するため、負担になる面も見られるでしょう。そこで、Google Workspace for Educationのようなソリューションの導入が重視されています。
生徒のアカウント管理を一元化でき、資料配布やリモート授業が行いやすいというメリットがあるのが特徴です。
電算システム(DSK)では、Google Classroom やタブレットの導入サポートなどを行っており、さまざまな相談も受け付けています。教育現場のデジタル化が進むにつれて発生する課題解決のため、まずは気軽に相談してみてください。
- カテゴリ:
- Google for Education
- キーワード:
- Google for Education
- GIGAスクール