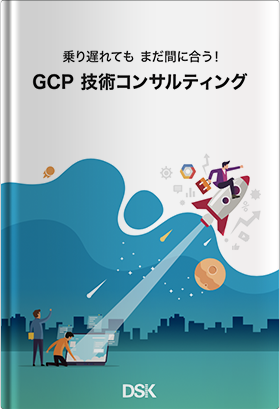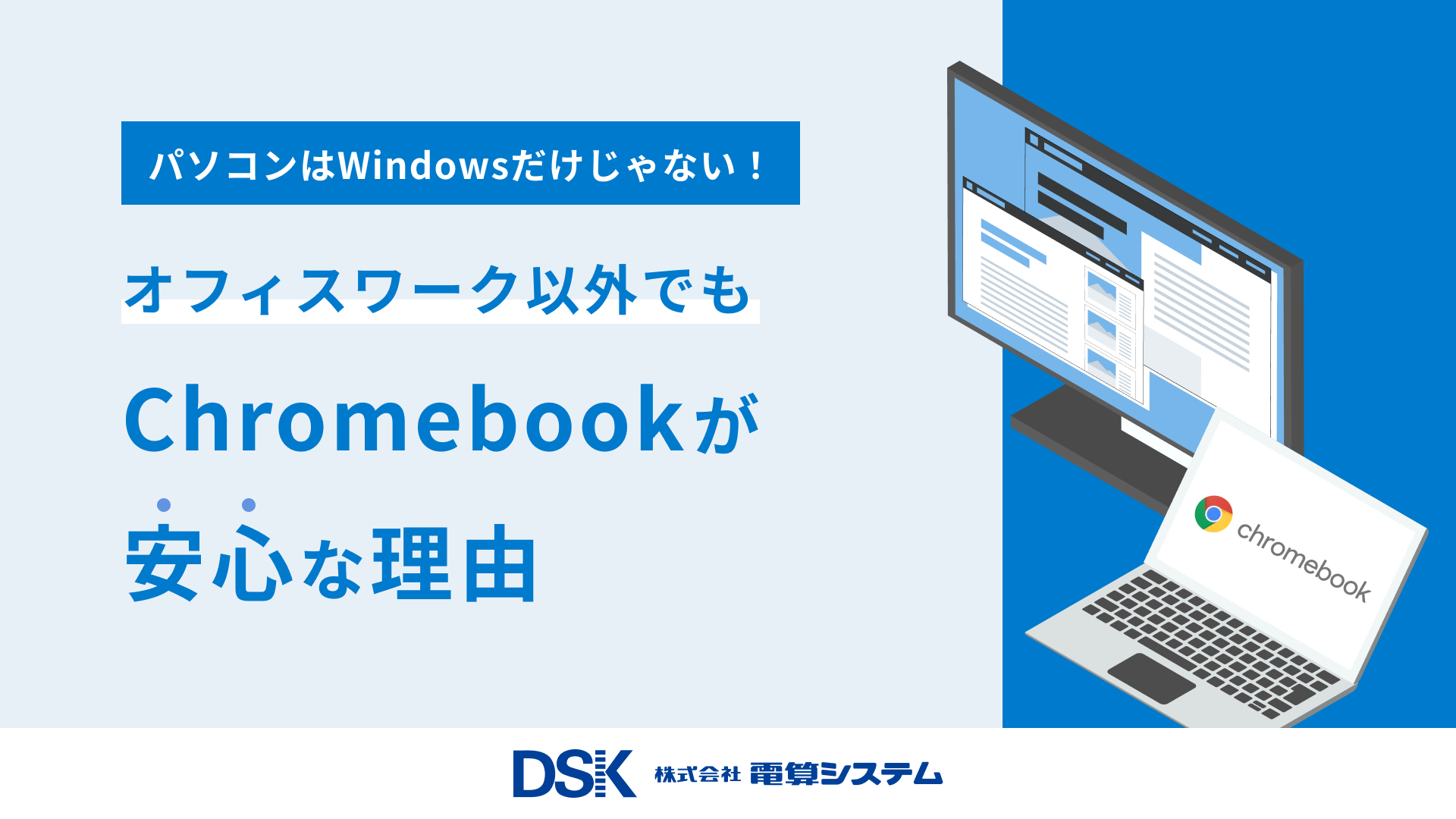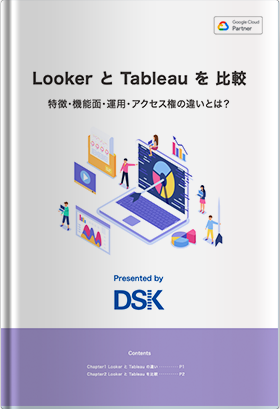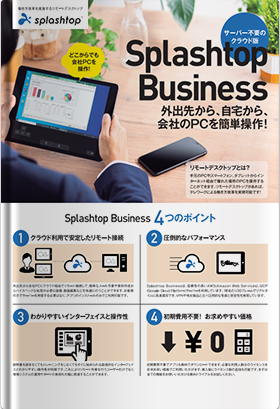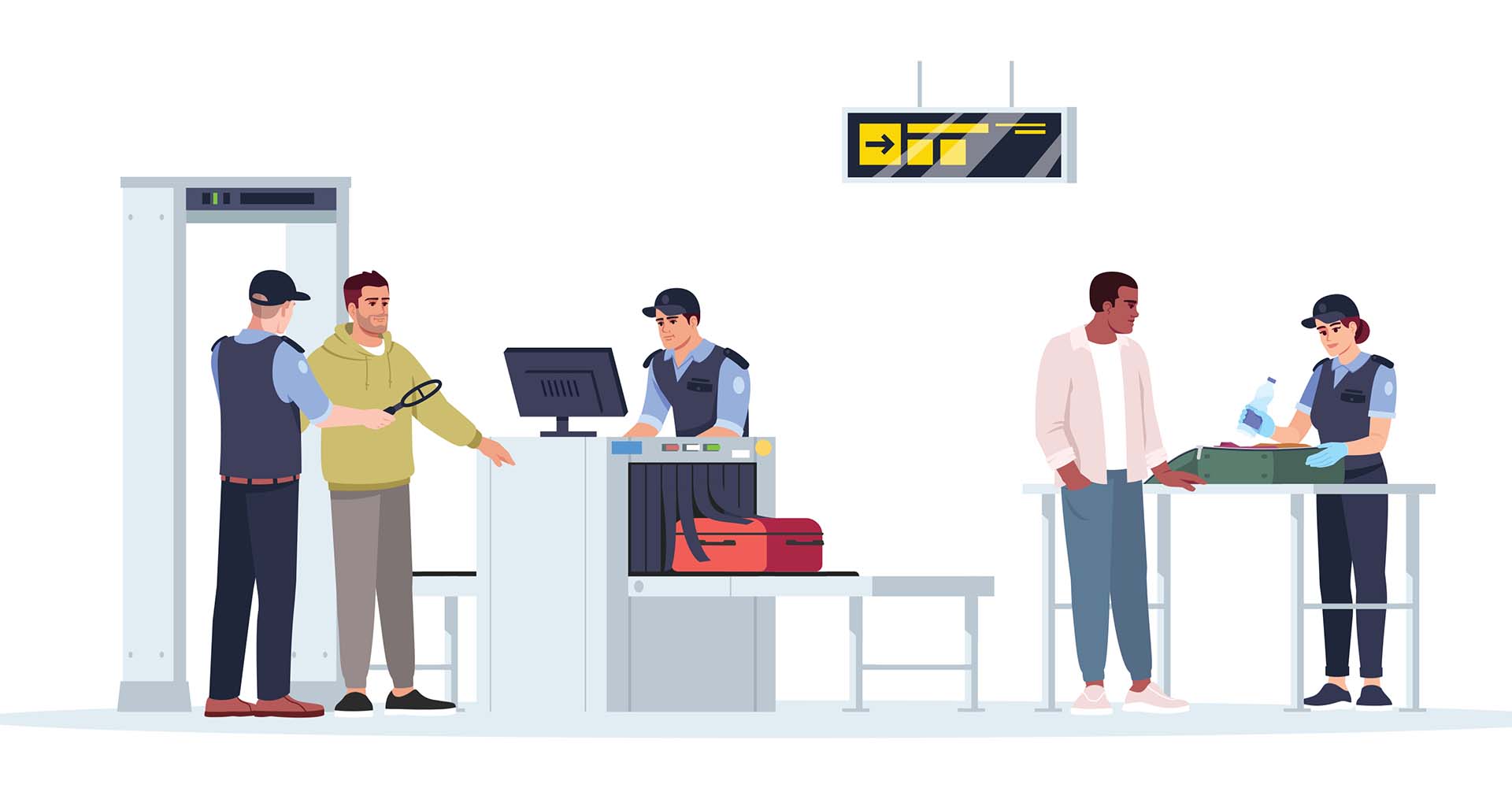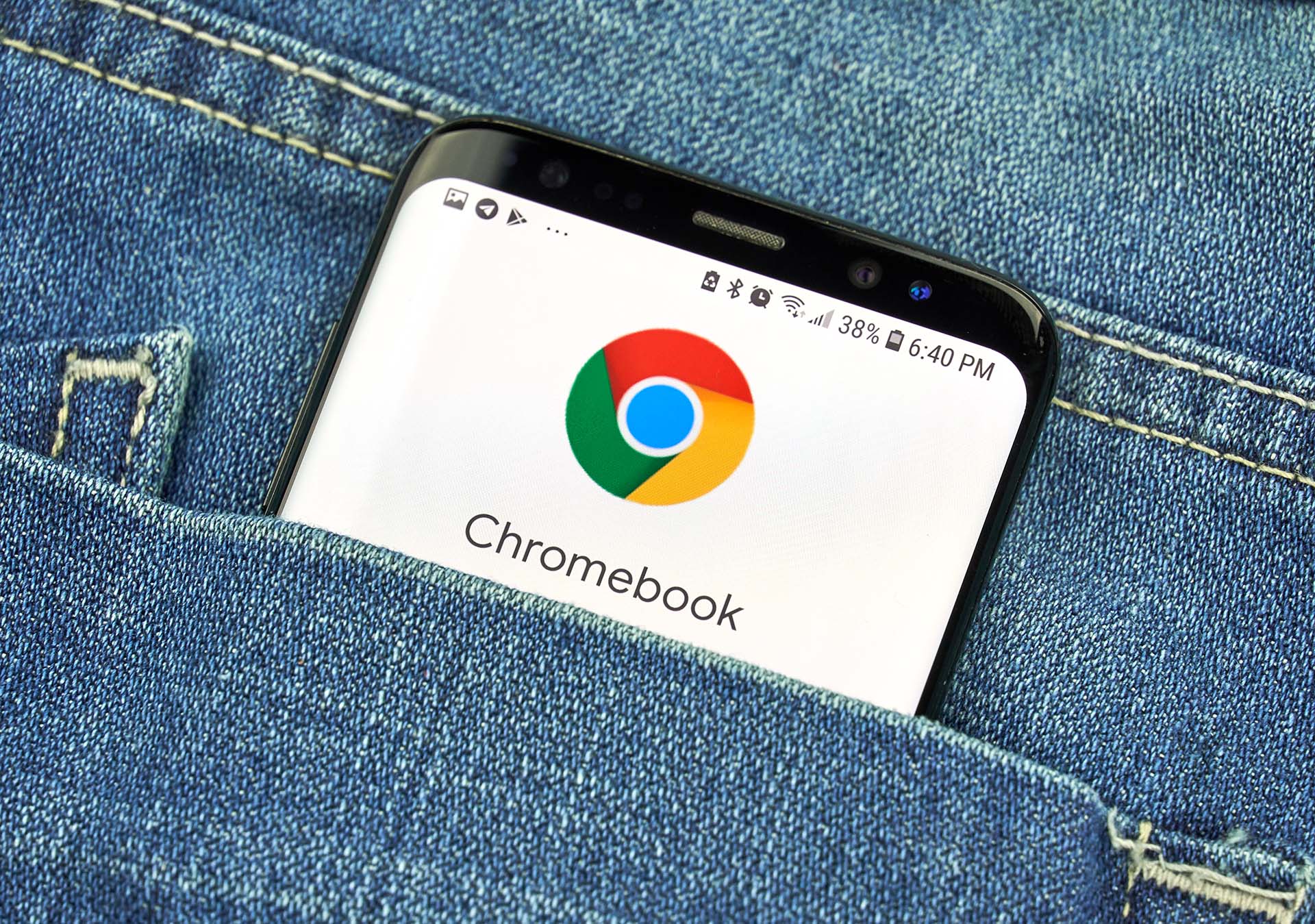多くの企業で利用が進んでいるテレワークやリモートワークですが、PCやスマートフォンなどのデバイスから業務に支障ないレベルで自由に社内環境にアクセスすることが可能となっています。
この遠隔(リモート)からの端末操作で、社内と同様に業務を遂行するために用いられる技術が、「シンクライアント(Thin Client)」と言われるテクノロジーです。
シンクライアントとは、ユーザーが使用するクライアントPCの機能を必要最低限のものに留め、OSやアプリケーションをサーバー側に集約管理し、データ処理に関してもサーバーが一括して行う仕組みのことです。
サーバー側で処理された結果はRDP(Remote Desktop Protocol)などの画面転送プロトコルに従って、画面のみをクライアントPCに出力します。従ってクライアントPC内にデータは保管されないため、情報漏洩対策やその他セキュリティ強化としても非常に注目されています。
本稿では再び注目を集めるシンクライアントについて、その歴史から現代の活用方法について解説していきます。
シンクライアントの歴史
シン(Thin)は日本語で「薄い」という意味で、クライアント(Client)はサーバー/クライアントシステムにおけるクライアントPCのことです。つまりシンクライアントとは「クライアントPCとしての機能を限りなくそぎ落とした端末」を意味します。ちなみにOSやアプリケーション、データが端末内にある一般的なクライアントPCはシンクライアントと対比して「Fat Client(太ったクライアント)」と呼ばれています。
近年シンクライアントによるメリットが多方面で注目されていますが、決して新しい技術ではありません。シンクライアントの歴史は1990年代半ばまでさかのぼり、すでにシンクライアントを実現するための概念と技術は確立していました。
当時の代表的なシンクライアントといえば、ディスクレス設計と廉価部品やソフトウェアを利用することで、一般的なPCより安価に出荷することを狙った「Network Computer(Oracle社)」や、Javaアプリケーションを実行することだけを目的として「Java Station(Sun Microsystems社)」などがあります。
「シンクライアント」という言葉がまだ一般的ではなかった1990年代初頭にはMicrosoft社のWindows OSをマルチユーザーで利用することを目的にした、Windows上で動作する「WinFrame」および「Independent Computing Architecture」というアーキテクチャをCitrix社が開発しています。
そこから10年以上の時間が経過し、2008年頃からはサーバー仮想化のリーディングカンパニーとなっていたVMware社がリリースした「VMware VDM」やCitrix社の「XenDesktop」などの製品を筆頭に、サーバー上に構築した複数の仮想マシンで仮想デスクトップ環境を実行し、ユーザーの接続先を自動的に振り分けるVDI(Virtual Desktop Infrastructure)が注目を浴びるようになりました。これが、現在のシンクライアントブームの原点だと言えます。
シンクライアントの接続方式
現代のシンクライアントでは一般的に4つの接続方式があります。
- ネットブート方式
- 画面転送方式
- ブレードサーバー方式
- SBC(Server Base Computer)方式
それぞれのメリット/デメリットがあるため、どの接続方式が最適かはシステム環境によって異なるでしょう。
大まかに分類すると、1台のサーバーに対し1台のクライアントPCを接続する「ネットブート方式」と、1台のサーバーに対し複数台のクライアントPCを接続する「画面転送方式」があります。
さらに、画面転送方式は「ブレードサーバー方式」「SBC(Server Base Computer)方式」「VDI(Virtual Desktop Infrastructure)」方式」に分類されます。
通常サーバーには1台につき1つの環境しか構築できませんが、仮想化技術によってリソースを分割することで実現できます。1台のサーバー上に複数のマシンを作り、各マシンにOSやアプリケーションをインストールすることで、1台のサーバーで複数の環境を動かすことができます。
ただし、VDI方式では仮想化ソフトウェアを使用するためのライセンスが必要になります。また、通常のシンクライアント実現方式とは違う技術/知識を要するため、新しいIT教育が必要になることもあります。
シンクライアント環境構築時のサーバー構成について興味のある方は、こちらの記事で詳しく紹介しています。『シンクライアント環境の種類と違い』
[RELATED_POSTS]
シンクライアントとしての Google Chromebookの可能性
Googleはスマートフォン向けOSとしてAndroidを開発していますが、実はPC向けOSも開発しているということを知らない方は多いでしょう。名称を「Chrome OS」と呼び、同じくGoogleが開発しているデスクトップPCの「Chrome Box」やノートPCの「Chromebook」に搭載されています。
その中で、従来のシンクライアント環境の代替として大注目されているのがChromebook(クロームブック)です。Chromebookの特徴は端末内に必要最低限の機能しか備わっていないことです。
ChromeBookはGoogleが提供するブラウザであるChromeに接続することを前提としており、他のブラウザは使用できません。データ保管に関してもクラウドストレージのGoogle Driveを使用することで、端末自体のストレージ容量は16GB/32GBと極めて少量に抑えられています。
一方で、端末の起動にかかる時間は8秒程度と非常に短かったり、データが自然とクラウドストレージに保管されるため、万が一端末がクラッシュしても、新しいChromebookまたはその他の端末から保管されたデータにすぐにアクセスして利用することができます。
Chromebookは他のPCよりもクラウド化されたPCであることから多くの企業がChromebookをシンクライアントとして採用しており、電算システムでもAmazon WorkSpacesやEricom AccessNowなどのサービスと合わせてお客様の課題を解決しています。
現代では、多くのアプリケーションやインフラがクラウド化したことで、サーバーリソースの使用方法やセキュリティー設定(特にユーザ認証方法)なども変化しています。単に「シンクライアント」としてシステム導入を検討するのでなく、従業員の方が快適で安全に業務を遂行するためにツールとして、端末の選定や環境構築の検討を進めることが求められます。
まとめ
シンクライアントの歴史は、サーバー側のシステム構築方法やデスクトップ側のツールの進化などで方式が変わってきました。
現在では、フリーアドレスやサテライトオフィスのエリアなど、自席以外の場所で仕事をすることも多く、Chromebookは、単に外出専用の端末としてだけでなく、機動的に業務を進めるビジネスパーソンにうってつけの一台と言えます。
Chromebookは、従来のシンクライアントとはまったく異なるPCではあるものの、クラウド環境に適合しながら、必要な機能に特化することで非常にシンプルな使い勝手使用が可能となり、企業で使用するクライアントPCとしても注目されています。
Windows 7のサポート期限や、バッテリーを長時間使用するテレワークの普及など、企業様端末を見直す良いタイミングを迎えています。皆さんもシンクライアント導入の選択肢として、Chromebookをぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
- カテゴリ:
- Chromebook
- キーワード:
- Chromebook
- OS
- PC